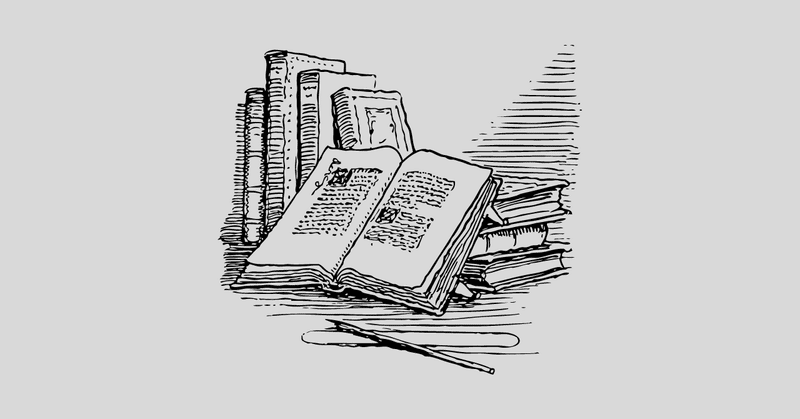
ジェンダーとメンタルヘルスのこと~ハンドメイズテイルの考察~【#11】
セリーナから読み解く、ハンドメイズテイルに描かれる希望の在処
(※ドラマのネタバレがかなり含まれる記事です)
前回の記事でゆうきさんは、「その人にとっての救いとは何か?」というテーマから、ハンドメイズテイルに描かれる様々なエピソードを通じて見えてくる人物たちの生き方、そしてそこに映し出される「尊厳」と「希望」と、彼らの「生きる力」の源になるものについてを考察してくださいました。
次の第6シーズンが最終回であると告知されているハンドメイズテイル。ゆうきさんが前述ブログで触れていたように、クライマックス前章のシーズン5では、少子化がさらに加速し世界情勢の悪化が背景に垣間見える中で、主人公ジューンと、ギリアド時代からの宿敵・司令官の妻セリーナの関係に大きな変化が待っていました。そして、それが最終シーズンの物語の結末を大きく左右する要になっていきそうな予感がしています。
シーズン5は特に、マーサのリタやモイラなどのサブキャラクターのストーリーが極端に省かれ、物語は主人公ジューンと司令官の妻セリーナの二人に軸が絞られて、彼女らが相対的に描かれながら場面が進行していったのがとても印象でした。
元ハンドメイドであり、我が子をギリアド共和国に奪われた被害者であるジューンは、ギリアドから逃れた先のカナダで待っていた夫ルークと共に子供の奪還を目指す中で、カナダの情勢悪化や出生率で成果を出すギリアドへの傾倒化といった政治的な力の変動に巻き込まれていきます。そこには、カナダ国民によるアメリカからの難民(ギリアドを逃げてきた人)への風当たりが強くなり、ヘイトクライムが起きている様子も描かれました。
一方で、ジューンの宿敵であり高官の妻であるセリーナにも、劇的な変化が待っています。子供を身籠ったセリーナは、神のご加護を受けた神聖な存在として、ギリアド共和国に受け入れられるものの、母親として思い描いていた理想の母子の生活と、実際に身をもって経験するギリアド的な母子の在り方のギャップに、彼女の中で違和感が強くなっていく、見ていた世界がちょっとずつ不協和音を奏で始めるような…そんなズレが特に顕著に描かれていました。
主人公ジューンが悲劇のヒロインとして観る側にすんなり受け止めやすい一方で、セリーナは加害者でもあり被害者でもあり、様々な顔・立場を持ったキャラクターとして物語に存在しています。
そこで、この記事では、ゆうきさんの次のバトンのテーマ、ジューンとセリーナの関係について、セリーナという人物の置かれた立場を辿りながら、彼女がどういう人物であるのかを一人の人間として見てみた時に改めて感じることを、そしてハンドメイズテイルのディストピアな世界に微かに感じる『希望』の在処を探ってみたいと思います。
セリーナとハンドメイズテイル
セリーナ・ジョイは、主人公ジューンをあてがわれる司令官フレッドの妻として登場します。
以前フレッドを特集した記事でも触れていますが、ギリアド建国前の彼女は、ギリアド建国を積極的に支持する活動家として著作活動やメディア露出をする学者評論家をしていました。
少子化の原因となっている環境汚染を食い止めるための自然回帰の生活の実現や、信仰を通じて混沌とする社会情勢に希望を見出すようなメッセージを発信する立場にあり、そのカリスマ性と強い理想主義的、急進的な宗教思想から、ギリアドの反対勢力に命を狙われたこともあります。
しかし、念願のギリアド建国後以降は、彼女のアイデアは採用されることはあるものの評価や功績は夫にのみ与えられ、『女性』である彼女の活躍の場は著しく制限されることとなります。本を読むことも、文章を書くことも、議会で発表する場も持てなくなった彼女は、毎日つまらなそうにタバコをぷかぷか、奥様方の集まりに心半分に参加しているのでした。そんな彼女の救いは、いつか子供を持つこと。そこに全ての気持ちを注ぐことが、彼女にとっての希望となるのでした。
そのような状況に現れたのが、子供を作る役割を与えれたハンドメイドである主人公ジューン。ここからセリーナとジューンのハンドメイズテイルが始まっていきます。
特権を利用した加害者であるセリーナ
ゆうきさんの記事にもありましたが、気持ちが極端に抑圧されたギリアドの世界では、心の中を話すような機会は一切与えられず、鬱憤や苦しみは、全て自分より立場の低い者へ投射され、それが八つ当たりや虐待という形で現れていきます。
セリーナも例に洩れず、子供がなかなか授かれないイライラを自身よりも階級の低いジューンやマーサのリタにぶつけていきます。暴力を加えたり、懲罰を加えたり…。特に、ジューンに関しては、なんとしてでも妊娠させたい一心で、儀式という名のレイプ幇助以外にも、ニックとの性交渉を強要するなど、「子供を作るため」という名目で、かなりひどい仕打ちを主導的に行なっています。
高官の妻という特権を利用した彼女のそのような姿は、とても恐ろしく映ります。
しかし、ジューンに至れり尽せりの暴力の末に手に入れた子供ニコール(ジューンが産んだ子供)は、ジューンとマーサ達の斡旋のもと、自分の特権が効かないカナダに行ってしまいます。
ニコールにどうしても会いたいセリーナは、カナダとの交渉がなかなか上手くいかないギリアド政府に我慢を切らし、カナダに拠点を置くアメリカ政府と裏で手を組み、フレッドを騙して彼を戦犯としてカナダに引き渡すのと引き換えにニコールと再会する約束を取り付けてしまいます。
このような状況があってカナダにやってきたセリーナはそのままカナダに留まり続け、時を同じくカナダに亡命を果たしたジューンと再度関わっていくのです。
これだけ読むと、セリーナってマニピュラティブ(操作的)で特権を振りかざす、とっても高慢で自己中な人。なんて極悪非道な人物なんだろうかと感じてしまいますが、彼女の心の中には、ギリアドという理不尽な社会に触れながら常に大きな心の揺らぎと葛藤が見えることが、このドラマではとても丁寧に描写されています。
自己心理学のコフートは、共感をしにくい人に対して共感力を得るにはどうすればいいのかという問いに対して、その人を一見理解し難い行為・言動に突き動かす根底にある文脈を理解することこそが共感であると言えるだろう、と共感力について話しています。
確かに、彼女がなぜそのような行為に突き動かされたのか…?という問いかけをしてみると、現代社会を生きる私達とも通じるような等身大の女性としての葛藤が見えるように思います。彼女の今までの行いを、彼女にそうさせる動機とは何なのか?文脈を追いながら振り返ってみたいと思います。
ジューンにあってセリーナに無いもの
ジューンとセリーナの相対的な描写が特徴的だったシーズン5において、わたしの中で特に強く心に残ったのがセリーナの孤独さでした。
常に気にかけてくれる誰かがいるジューンに対して、セリーナは終始とても孤独です。
パートナーであったフレッドは、ギリアド共和国が出来てからホモソーシャルな社会に飲まれ、彼女の相棒ではなくなっていきました。彼女には、自分と立場の同じ政府上層部高官の妻達のコミュニティがありますが、ギリアドの指示通りに妻としての役割を全うすることを受け入れた彼女達とは話が合いません。
せっかく仲良くなりかけたジューンに対しては、プライドや特権意識が邪魔してなかなか対等になれない。
上下関係や性別役割を重視するギリアドは、彼女をどんどん孤独にしていきます。これは、ホモソーシャルな価値観を内在した男性の生き方にとても似ています。しかしながら、彼女は女性なので、ホモソーシャル社会からは受け入れられることは一切無く、ギリアド幹部達のボーイズクラブに良いアイデアを提案して受け入れてもらおうとしても、何度も拒絶を経験させられることになります。むしろそれがミソジニーとなって跳ね返ってくることも。(ミソジニーとは、男性の望む女性観から外れた女性達に対して罰則的な意味合いの攻撃を与えることを指す、とする専門家もいます。セリーナは実際に小指の切断という罰を受けました。)
特にシーズン3に遡ると、フレッドとの関係に苦しむセリーナが助けを求めに母親のところを訪ねるシーンでは、彼女と母親とのとても冷たい関係性が見て取れます。フレッドとの関係に心が折れてしまったセリーナが涙を流しながら行き場所が無いと助けを求めに逃げ帰った実家で待っていたのは、「ここにあなたの居場所はない、フレッドのところに戻りなさい」という母親からの拒絶でした。
ジューンの母親が、娘の幸せを第一に、自分が娘から嫌われるのを覚悟でルークとの結婚を反対する場面があるのとは打って変わって、世間体や地位にこだわることを優先するセリーナの母親の様子から、セリーナは、ありのままの自分を見て受け入れてもらった、そのような自己承認を受けた経験がないのではないかということを思い起こさせます。むしろ、母親の建前や社会的ステータスが重んじられる環境で、「良い子」、「自慢の娘」、としてのプレッシャーを受けながら生きてきた様子がありありと浮かんできます。そして、親の期待に応えられない「悪い子」になった途端に、手のひらを返したような対応が待っていたのはとても居た堪れなかったです。
セリーナのギリアドでの人間関係を振り返ると、様々な場面でプッシュバック(自ら歩み寄るも押し出される感覚)に遭っているのが感じられます。そして、彼女自身も、プライドと力に塗れたフレッドにふっかけられて、仲良くなりかけたジューンを押し返す場面もあり、ホモソーシャルな価値観の有害性を感じずにはいられません。
人怖じしない自信家の彼女を尊敬し愛してくれていたフレッドをギリアドの世界で失い、ありのままの自分を出せない環境で、本当の自分の姿を見てくれる人が誰もいない世界において、彼女を孤独から救ってくれる唯一の希望が、『自分を誰よりも必要としてくれる』我が子を持つことであったことは、想像に難しくありません。
セリーナの人生に連続する喪失感
彼女の孤独感と共に強調されるのが、喪失感。セリーナの人生を振り返ると、『喪失感/loss and grief』が大きなテーマとして浮かび上がってきます。
自分のキャリアを果敢に歩んでいたセリーナを待っていたのは、性別分業がはっきりした世界。ギリアドにおいて妻の役割は「主人に仕え、子供を産み育てること」、自身の存在意義がそこにのみあることが強調されています。それは、彼女にとってどのような意味を持っていたのでしょうか。
社会的アイデンティティのシフト:
性別分業を押し付けられたセリーナがまず最初に経験したこと。それは、自身のキャリアを手放すことでした。自らの考えを自らの声で主張する、そんな提唱者的な立場にいた彼女にとって、ギリアドで与えられた「夫に尽くす」役割は、自身が自ら築き上げてきた社会的地位や社会的アイデンティティの喪失を意味しています。
そして、それはイコール、対等なパートナーシップの終わりも示していました。
これは、現代日本社会において、結婚という形にこだわりたくない、と考える、結婚を選ばないカップルや、夫婦別姓を求めるカップルが感じる懸念に共通するものであると見て取れるでしょう。
制度的な結婚によって、特に相手姓を名乗ることが多くなる女性側に大きなアイデンティティの変化がもたらされること。自分の呼び名が変わるだけでも十分な違和感ですが、自分の今までの生き方とは違う、社会的に期待される新たな役割が与えられる、というアイデンティティの変化は、今まで自身が築き上げてきたアイデンティティを一部、もしくは全て手放すことも意味しています。(男性が女性側の姓を名乗る場合に、大きな抵抗や葛藤が見受けられることを考えると、婚姻制度によって名前が変わる、というのは当たり前の事情にされていますが、実は性別問わず個人にとってとても大きな出来事なのです。)
日本ではあからさまに結婚を機に苗字が変わりますし、母親になった暁にはパートナーや周囲から「お母さん」「〇〇ちゃんのお母さん」と役割で呼ばれることも増えます。そのため立場の変化がとても分かりやすい。一方、アメリカなど欧米では、下の名前で呼ばれる機会が多いので、結婚して姓を変えたとしても普段そのような変化はあまり感じられません。しかしながら、ギリアドの世界では、日本と同じように、既婚者はMr/Mrs.苗字と呼ばれるようになり夫婦間で力関係の差が現れた表現が使われることがわかります。日本にも、ギリアドにも共通するこの性別分業は、家父長制を強く表す一場面です。
不妊と喪失感:
自分の存在が、主人の付属物となり子供を産み育てることにしか意味を見出さない存在となってしまった。そんなセリーナを次に襲うのは、子供を産めない自分、自身の子を持てないことへの喪失感です。
彼女の回想の中には、演説の最中に腹部を撃たれたことや、ハンドメイズを受け入れるまでに夫婦で子作りに挑戦している期間があったことが示唆されています。不妊期があったこと、その結果、子供の産める身体のハンドメイドを受け入れるに至ったことから、彼女自身、自身の身体のこと(もしかしたらフレッドとの子供を持てないこと)に対する喪失感を常に経験していたかもしれません。
ハンドメイズテイルは、ハンドメイズたちの置かれた立場の苦しみに焦点が当たるものの、そもそもなぜハンドメイズというシステムが成立しているのか、というところを見ていくと、高官の妻達の不妊の苦しみが垣間見える場面があります。例えば、ローレンスの妻エレノアが、「子供が欲しかったけど出来なかった…」とポロッとジューンに吐露する場面や、ハンドメイズが主人と色恋中になり捨てられてコロニーに送られた元妻もちらっと登場する回もあります。
出来ることならハンドメイドは受け入れたくない、自分たちで子供が出来ればどんなに良いだろうか…。そのような妻達の葛藤がある上でのハンドメイズの制度がある。夫婦の間で不妊という現実を受け入れることはとても辛いことですし、そこには大きな喪失感が存在することも。
ハンドメイドを携える全ての妻が経験しているであろうこの共通する喪失感を妻同士が皆、腹を割って話せるような場所が無い。社会における女性の存在価値が子を産むことに重きが置かれていることが、不妊の女性に対してどのような精神的打撃を与えているのか…。妻の中には、ひょっとしたら夫の不妊が明らかな原因による不妊症の方もいるでしょう。しかしそんなことはギリアドでは一切話せません。不妊に対する気持ちの行き場が無い妻達はどこに気持ちの行き場を求めるのか。それは、ハンドメイズシステムの肯定化や、「子供」という存在をファンタジー的に扱う子供の極端な理想化、そして自分が一番母親に相応しいと思いこむ虚偽の優越感やハンドメイズへの虐待(怒りの気持ちの投射)、現実逃避につながっているのかもしれません。ハンドメイズが出産する様子を隣で模倣しハンドメイズが産んだ子供を「私の子だ」と容赦無く言い切る妻達の心理には、不妊という出来事をとにかく塗りつぶしたい、事実を受け止めたくない否認の気持ちももしかしたらあるのかもしれません。
母親になれなかった喪失感:
セリーナは、喪失感という苦しさや自身の経験している気持ちと向き合うよりも、システム・制度の肯定に走る妻達を目の当たりにして、同じように感じている時もありました。しかし、セリーナには、それを疑問に思うような機会が何度か訪れます。
パトナム夫妻の子として育てられた、ハンドメイドのジャニーンの産んだ子供が原因不明の瀕死になった時、ジャニーンの温もりで赤ちゃんが元気になったシーンがありました。
そして、セリーナ自身、自身が受けた洗礼やイーデンの経験を目の当たりにして、『女性』としてギリアドで生きることがどのような意味を持つのか、現実を見ざるを得なくなっていきます。そして、ジューンの言っている「娘をギリアドから解放したい」願いとその理由がうっすら輪郭を徐々にはっきり理解できるようになってくるのです(本当は分かっていたけれども目を背けていたのかもしれません。)
シーズン2で、ジューンがニコールをカナダに逃そうとする際、それを見つけてしまったセリーナは、自らの意志でニコールをジューンに託す選択をします。ずっと「わたしがニコールの母親だ」と言い切っていたあのセリーナが、「あなたが本当のお母さんだから」とジューンに言ったあのセリフのシーンは、とても悲しそうな顔をしていて、とても切なく感じました。
この母親になれなかった喪失感やどこかで親子の絆がハンドメイズには勝てないと思っている気持ち、それはきっとどの妻も本当はどこかで感じているのだろうと思います。でも、それを何十にも蓋をして抑圧している。認めたく無いけれどもそこにある現実が目の前にある。そんな葛藤をセリーナも感じている様子がとても伝わります。
自身の信じた理論が間違っていたことを認める勇気…プライドの喪失感:
セリーナがニコールを手放した理由であるギリアドの家父長制は、セリーナにとってとても苦しい存在です。それもそのはず、彼女はギリアド建国を圧倒的に支持してきた支援者の一人、少子化を食い止めるための答えがここ(ギリアド)にあると信じてきました。
学者にとって、自身の理論が間違っていたかもしれない恐怖はとても大きなものです。そして、彼女と一緒に戦ってきたギリアド建国者(男性)たちによる、裏切りもありました。
信仰心がとても強いセリーナは、神様の教えがギリアドの制度であると捉えて、必死でギリアドで行われる非業を信じようとします。それが、時には都合よく自身の欲求や満たされない気持ちにピタリとハマるところもあるからこそ、なかなかその矛盾を正していくことが難しい。
現実を見るのが怖い否定の気持ちと、ありありと感じられるギリアドのおかしな部分。この責任が自分にも一端あるという事実を直視することがセリーナにはなかなか出来ない。ジューンが何度も何度も、セリーナに現実を見るよう仕向けても、それがなかなか出来ない…。むしろ認めてしまったら、彼女の築き上げてきたキャリアは本当になくなってしまう。そんなセリーナの弱さ、怖さ、辛さ、切なさが彼女を一転二転の行動へと向けさせていきます。このアンビバレント(相反する)な感覚は、彼女の自分軸をぶれさせ、彼女を大きく不安にさせ、また、スタック(立ち往生)させ思考停止させてしまいます。この大きな否定の力動も、裏を返せば、セリーナが大切にしていたプライドを失う喪失感への恐怖とも言えるかもしれません。
喪失感との向き合い方
人が何か大切なものを失くした・亡くした時、そこには様々な感情が生まれます。
アメリカのキューブラー・ロスが提唱する悲しみの5段階モデルでは、人は喪失をこのような感情を行ったり来たり巡りながら対処すると話しています。
否認:現実を受け止められない
怒り:なぜ?と言う気持ちから、周囲に当たりたくなる
取引:もしかしたら…と何かに縋りたくなる
抑うつ:絶望感で何も手につかなくなる
受容:現実を受け止め、心の平穏がくる
この悲しみの5段階モデルは、死を意識した時に人が辿る心の過程を観察したものであるものの、この喪失への向き合い方(グリービング)のプロセスは、大切な何か(誰か)を失(亡)くした時や、別離を迎えた時、思い描いていた将来の夢が絶たれた時にも経験するとされています。
受容に向かうには、これら様々巡る気持ちと向き合いながら、自分の思うこと・感じることを内に溜め込まず、外に開放して(mourning)いく必要があります。自身がどのような気持ちを抱えているのか内省していくことはもちろん、誰かと気持ちを共有し合いながら孤独感を解消していくことも大きな手助けになっていきます。
果たして、ギリアド共和国では、数々の喪失に対して、このような気持ちの向き合い方が行われている機会はあるのでしょうか。わたしには、ギリアドでまかり通る様々な暴力や加害性が、喪失感への未熟な向き合い方による反動に思えてしまいます。
宗教と家父長制はイコールなのか?
ところで、ギリアドの基盤となるキリスト教原理主義が内包する家父長制度は、セリーナの望む生き方に沿っているのでしょうか?
神の存在を信じ、その教えに忠実に生きようとするセリーナは、宗教の教えるエンパワメントを力の糧に、表舞台に出ていき提唱活動を精力的に行ってきました。
しかし一方で、その宗教の教えを巧みに社会構造のシステムに都合よく解釈し取り入れたギリアド政府により、自身(女性)を支配するための道具に使われてしまいます。
ゆうきさんが前回の記事で触れていたように、宗教や信仰、スピリチュアリティは、個人にとって心の支えや、レジリエンスや逆境力、癒しの源となるものである一方、宗教という名のもと、それが権力者による悪用、支配のツールに使われてきた歴史が人類にはあります。
セリーナは、この相反する顔を抱えるギリアドの『宗教』に対して、理不尽や矛盾に気づきながらも、彼女自身のインセキュリティ(自信の無い部分)を重ねて、時には自らも悪用、支配の道具に利用していきます。
セリーナと宗教の関係をみると、ギリアドの教えに近づけば近づくほど、彼女自身は自分を失うことになっていき、そこから離れようとすればするほど、自分の所属先を失うような疎外感を味わう、どちらの側にたっても苦しみが付きまとう立場にあったように思います。
セリーナとジューンのやりとりを見ていると、ジューンが聖書の言葉をレファレンス(参照しながら)にセリーナと話す場面が頻繁にあります。その様子はまるで、ギリアドの宗教の中で自身の信仰先を見失ったセリーナが、本当に自分の立つべき場所を見つけるための指針のような役割を果たしているようにさえ思えます。
ジューンが信じる信仰は、女性の権利のために命を捧げた産科医である母親から受け継いだ、自分を大切にすること、その権利と自身の存在意義を誰もが持っていることを信じるエンパワメントの信仰です。
母親となったセリーナに訪れた変化
セリーナはとても勝気なキャラクターで、好きになれないと感じる人も多い人物かと思います。実はわたしもそうでした!しかし、一人の女性として見た時に感じるのは、どちらかというと、支配的な社会構造に翻弄された、大きな苦しみを一人で抱え孤独を彷徨う、とてもか弱い人物にも見えます。
そんな彼女が、男の子を産んだことは、とても大きな出来事だったのかな、とわたしは感じています。
ジューンが、ギリアドの将来の被害者となりうる娘たちを持つ母親である一方で、ギリアド建国に加担したセリーナが、将来の加害者となりうる男の子の母親となったことは、彼女の中で、何か大きな使命を見つけるきっかけになったように思います。
ジューンとセリーナは、持っている特権も、経験してきた出来事も大きく異なります。しかし、この二人が本当に真から信じるものが、同じ方向を向いている限り、被害者・加害者といった分離ではなく、結託に繋がっていく可能性はあるのではないか、そのような希望を感じる展開で、シーズン5は終わりました。
物語が託す希望のメッセージとは
得体の知れないコロナウィルスが襲ったパンデミックを機に、世界は転機を迎えました。不安が不安を呼び、内と外の境目が色強くなり、排除も進みました。加速した二極化が社会を本当に分断し、人種、ジェンダー、思想など、自らとは違うものの排除や疎外を目的にしたヘイトクライムも増えました。
そんな分断が進む社会において、ハンドメイズテイルが描くセリーナとジューンの姿は、本来であれば決別してておかしくない立場や境遇の違うもの同士による結託や団結が生まれる可能性、そしてそこに生まれるかも知れない人類の和解や平和への解決策に向けた希望を描こうとしているのではないか。そんなことを思います。
分断は、相手を知らないことから始まります。理解し難い相手を排除することは簡単で、特に過去に何度も拒絶を経験し傷ついた思いをした者なら尚更、相手に歩み寄ることはとても勇気がいることですし、ついつい傷つく前に相手を拒絶してしまいたくなることもあるかも知れません。しかし、相手を知ること、それは相手の痛みや苦しさ、思いを想像することからも生まれるかも知れないし、ただ訊いてみるだけでもいいのかもしれない。そんなスタンスを持って目の前の相手をただ見てみて、自分の何かを重ね合わせることが出来た時に初めて、何か暖かく特別な心強さを人は感じることが出来るのかもしれません。共同体を形成しながら厳しい自然界を生き延びてきた人間だからこそ、人との結束感や団結を感じられることが、生きる糧に、そして未来に生を繋ぐための戦いを厭わない勇気をくれるのではないでしょうか。
何度も何度も拒絶を経験してきたセリーナが、ジューンにどれだけ心を開いて歩み寄っていけるだろうか、わたしはシーズン6、そこにとても注目しています。
今回の記事では、そんなことを思いながら、なかなか共感できないセリーナにちょっと近づいてみる感じで彼女の経験を振り返ってみました。
バトンタッチ
今回の記事では、ゆうきさんから引き継いだバトン『ジューンとセリーナの関係性』を、共感がなかなか難しいセリーナの視点から考察してみました。
そこから見えてきた『分断・統合』というテーマの、分断が起きるメカニズムは、実は、ゆうきさんが以前書いてくださったリディア叔母の記事でもあった、個人の中に起こる『スプリッティング』という現象に通じており、それは、個人の心の中だけでなく対人関係、または集団やグループとの間の関係性にも起きることを示しています。
一般的に、スプリッティングは、心の防衛機能の一つと言われており、是も非もある存在の対象物をそのままの姿で見るのではなく、無意識のうちに信じたくない・受け入れたくない現実(要は自分にとって痛みを伴う部分)を見ないで済むよう自分にとって都合の悪い部分を否定することで、極端な美化や、極端な卑下による拒絶を起こしてしまう現象を指します。そしてそれは、感情への向き合い方が未熟な環境で多く起こります。ギリアドのような、心の内を表立って表現し処理することができない環境では、スプリッティング(分断)の可能性はより一層多くなります。
そこで、ハンドメイズテイルで描かれる痛みの数々を登場人物たちはどう受け止めていけば良いのだろうか。次の記事では、分断から統合へ向かうには何が必要なのか。痛みへの向き合い方を振り返りながら、物語に隠される統合のヒントをゆうきさんに聞いてみたい、と思います!
参照:
・Hulu ハンドメイズテイル 〜侍女の物語〜 シーズン1−5
・江原由美子 (2001) ジェンダー秩序 平文社
・荻本快 (2022)哀しむことができない 社会と深層のダイナミクス 木立の文庫
・くどうみやこ(2018) 誰も教えてくれなかった子どものいない人生の歩き方 主婦の友社
・キューブラー・ロスの死の受容過程(悲しみの5段階モデル)by ITカウンセリングLab
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
