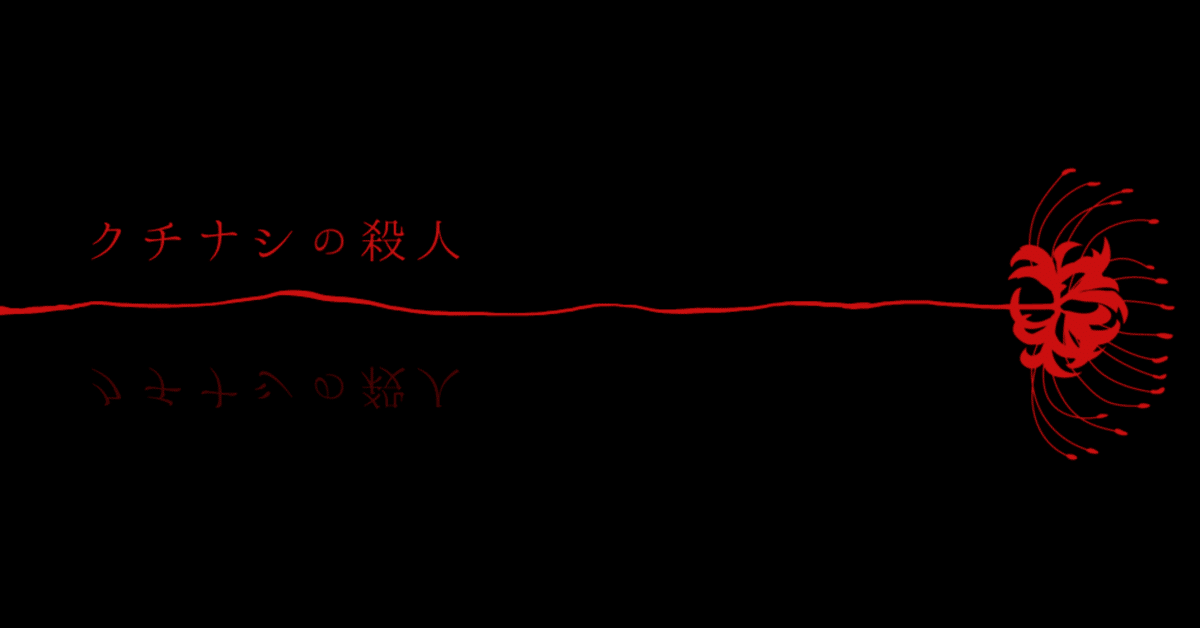
クチナシの殺人 第4幕
第4幕
天清瞳子が殺害されてから10日、花見堂周が殺害されてから3日が経過した日の午前7時45分。久地那警察署前。
愛車を駐車場に停め、出勤用の鞄を提げた小西が署に向かっていると、背後から耳慣れたパンプスの足音が近付いてきた。
「おっはよーう小西」
ぽんと後ろから小西の肩を叩いて声をかけたのは南だった。微かに煙草の匂いが漂うのはいつものことである。
「おはよう南。早いね」
小西が挨拶を返すと、南はサングラスを外しながら声を潜めて言う。
「さすがに連続殺人の捜査の最中ともなれば早番出勤しないとね」
そう話しつつ、2人は署の玄関口でIDを端末にかざして署内のセキュリティーチェックを抜ける。ロビーに入り、エレベーターホールでボタンを押してエレベーターが降りてくるのを待つ。
ポン、と軽やかな電子音と共に照明が光り、エレベーターの訪れを知らせる。降りてきたエレベーターの扉が開くと、中から笹村が現れた。いつもの上質なジャケットではなく薄手の黒いカーディガンを肩に羽織っている。
「あ、おはようございます笹村さん」
「おはよう」
眠そうな声音で応える笹村。
「随分早いですね。これから始業前の一服ですか?」
南が訊ねると、笹村は首を横に振った。
「いや、ちょっと外の空気を吸いにね」
笹村は欠伸を噛み殺しながらそう答え、そのまま南の横を通り過ぎようとしてふと足を止めた。
「あァ、そうだ。私、朝のミーティングが終わったら2時間仮眠とるから」
そう言って気の抜けた声音とは裏腹に、笹村は割としっかりした足取りでロビーの出口へと歩き去っていった。ちなみに笹村の言う仮眠での2時間は4時間に相当する。
「…さてはあの人、昨夜帰らなかったな」
笹村の背中を見送りつつ、南はスラックスのポケットに手を突っ込みながら呟く。
「だろうね。徹夜で調べ物してたか、もしくは道場か射撃じゃないかな」
久地那警察署には仮眠室の他、剣道と柔道の道場、射撃練習場、トレーニングジムが併設されており、その兼ね合いでシャワールームも整備されている。そのため、署に泊まり込んで仕事をする捜査官が稀に存在する。笹村もその1人だった。捜査が停滞すれば、気分転換に稽古へ赴く職員は多い。
「私もそろそろ射撃練習したいな」
エレベーターに乗り込みながら小西がそう零すと、南も頷いて同意した。
「わかる。定期的にやらないと腕鈍るしね」
「とは言っても、この国はアメリカほどの銃社会じゃないから、現場で拳銃を構えて発砲することなんてそうそうないけど」
「それな」
世の中、アメリカの警察ドラマのように、銃撃戦!カーチェイス!爆発!といった刺激的な展開は滅多に起こり得ないのである。そういった異常事態は起こらないに越したことはないし、平穏であることが一番ではあるが。
刑事1課のオフィスがある階に止まり、エレベーターの扉が開く。2人はエレベーターを降り、通路を曲がってすぐ右手にあるオフィスのドアを押し開いた。
「おはよう…って、どうした際田」
オフィスに入ると、そこにはデスクの上に突っ伏している際田の姿があった。
「あ、おはようございます先輩…」
2人の出勤に気づいた際田がのろのろと顔を上げる。
「おはよう。…具合悪いの?」
タイムカードの端末にIDをかざしてから小西が心配そうに際田の顔を覗き込むと、際田はどこか疲れを滲ませた表情で答える。
「いや、体調が悪いわけではなく…実はさっきまで1時間ほど笹村さんに剣道の稽古のお相手をしていただいていたんですけど」
そこまで聞いて、小西と南は同時に「あァ…」とすべてを察したように声を洩らした。
「なァんでまたこんな朝早くから」
「久しぶりに身体を動かしたくなりまして…7時前に道場に行ったら、偶然徹夜明けの笹村さんがいて」
折角なら一本どう? と誘われ、稽古をつけてもらっていたのだという。
「笹村さんって何段だっけ」
南が首を傾げながら言うと、際田が「六段って言ってました」と答える。
「じゃあ13の頃に初段に合格して、そこから順調に昇段してきたってことか」
「剣道は六段からハードル高くなるよね」
剣道の段位制は一級受有者かつ満13歳以上で初段の昇段審査を受けられ、段位が上がるごとに1年ずつ修行期間が延びる。つまり六段の有段者は、五段受有後5年以上修行したことになる。ちなみに、合格率は六段で約10%、七段で約8〜10%、八段ともなれば1%未満と言われる。
「なんというか、笹村さんの集中力といい技量といい、諸々すべてに圧倒されて力が抜けました。『徹夜明けで疲れてる』なんて言ってましたけど、じゃあ本調子ならどうなってしまうんだろう…と思って」
「成程。それでこんな萎びた葉っぱみたいにへにょへにょなわけ」
弱々しく呟く際田の跳ねた髪を南がちょんちょんと突きながら納得したように零す。
「でも、際田だって段持ちでしょ?」
小西が鞄をデスクに置きながら言うと、「一応…三段です」と答える際田。
「私もだよ。南は四段だっけ?」
「そ。近々、昇段審査受けるつもりではある」
椅子に座り、鞄から取り出したチョコレートバーを齧りながら南が応える。
「私も今度久しぶりに笹村さんに稽古つけてもらおっかなァ」
「その前に事件解決が先でしょ」
「ご尤も」
南はチョコレートバーを飲み込んで、ふと際田に目を向ける。
「そういえば、笹村さんが泊まり込みで何してたか聞いた?」
机の上で溶けていた際田は気怠げに上体を起こしながら言う。
「野暮用って言ってました」
「あァ…そう…」
野暮用。笹村が多用しがちな単語のひとつである。本来の意味である「仕事の上のつまらない用事」といった意味合いだけではなく、主に笹村にとって面倒かつ厄介な用件を指す。上層部からの呼び出しや捜査上の諸々の手続き、また、笹村が秘密裏に抱えている仕事も含まれる。
そのため、笹村の野暮用については詮索しないのが1課の暗黙のルールなのだが、際田がそれを知るのはしばらく経ってからのことである。際田はただ、「他に抱えている仕事があるのかな」程度にしか捉えておらず、詮索するという行動には出なかったので。
南はチョコレートバーの包装袋をゴミ箱に捨て、椅子の背もたれに背を預けて両手を頭の後ろに当てる。先程の際田とのやりとりで南は確信していた。
際田は嘘を吐いている──と。
・
「目昏摩の所轄に捜査協力を要請し、染浦絃の失踪に関する捜査資料を取り寄せました」
朝のミーティングにて。オフィスのミーティングルームで、小西が捜査資料のデータをモニターに表示する。
「携帯端末、クレジットカード、口座は失踪する前に解約済み。車も売却されており、現在の行方を追うのは困難かと」
「染浦夫人の話通りだね。染浦絃は自ら意図的に姿を消した」
南が腕を組みながら呟く。その横で、際田が手を挙げて報告する。
「染浦絃が勤務していた葬儀会社に話を聞いたところ、彼女は失踪する直前、退職願を申し出て退職していたとのことです。当時の彼女の上司によると、退職する1ヶ月ほど前から婚約指輪を身につけていたことから婚約相手がおり、結婚を機に退職した、と」
「その婚約相手については?」
笹村の問いかけに南が答える。
「染浦絃の同僚たちや上司は詳しくは聞いていないそうです。仕事の話はするものの、プライベートのことはほとんど話さなかったようで。ただ、仕事はそつなく丁寧にこなすタイプで人柄も穏やか。職場での評判は非常に良く、皆から慕われている魅力的な人物だったと」
ふむ、と笹村は顎を撫でながら目を細める。絃は仕事とプライベートをきっちり分けるタイプの人間だったようだ。おまけに職場では誰からも評判が良かったともなれば、ある種のカリスマ性を備えていたのだろう。
「婚約相手がいたのなら、家族に紹介くらいはしていたはず。染浦夫妻に聞いたらわかるかも」
笹村の言葉に、南と際田が頷く。
「この後、連絡を取って確認します」
「頼んだ」
3人のやりとりを見ていた小西が、ふと思い出したように口を開いた。
「笹村さん。檀さんから何か聞いてませんか?」
小西の問いかけに笹村が振り向いて「檀から?」と首を傾げる。
「はい。花見堂周の殺害現場の証拠品の分析で何かわかり次第連絡するよう頼んでいたんですけど、音沙汰がないので」
笹村は先日、檀から個別で連絡を受けていたが、小西には伝えていなかった。情報共有するにはまだ早く、確実な証拠として扱うにはもう少し調べを進めてからの方が良いと判断したからだ。
笹村はまだ捜査班の班長に就く前、担当した事件で情報共有をすっ飛ばし、協力体制を怠り1人で犯人を勝手に捕え、自白を引き出して粗方解決してしまったことが何度かある。優秀で実績はあるものの、自身が「間違っていない」と思える指示でない限り上司には従わない。危ない橋を渡ったことも数え切れない程ある。それを見兼ねた上層部に咎められ、こってり絞られた経験もある。そんな問題児だった笹村も、班長になってからは部下を指揮する立場になったため、そういった自分勝手な行動はかなり減った。
減ったが、確実になくなったわけではない。
笹村が「必要である」と判断した場合、その悪癖は今も尚発動する。
「…質量分析計とお茶会してるうちに忘れたんでしょう。檀には後で私から確認しておく」
「…わかりました。よろしくお願いします」
「あ、そうだ」
そこで笹村が顔を上げて小西に呼びかける。
「小西、染浦絃が借りていたマンションの一室を家宅捜査した時の資料はある?」
「こちらに。先程データが届いたのでまだ確認はできていません」
「じゃあ先にその確認をお願い。仮眠取ったらここに戻るから、それまでに各自、報告内容をまとめておいて」
「了解」
南と際田は席を立ち、小西は資料を広げて早速内容の確認を始める。笹村は椅子の背もたれに掛けていたカーディガンを肩に羽織ると、デスクの一番下の抽斗を開けた。そして徐に抽斗の中から取り出したのは、化繊素材の仮眠用枕と、『触るな危険』とゴシック体で書かれたアイマスクだった。
「じゃ、あとはよろしく」
そう言い残し、笹村は愛用の仮眠セットを携えてオフィスを出て行った。
「笹村さんのあのアイマスク、どこで売ってるんですかね」
聞き込みの支度をしながら際田が南に耳打ちして訊ねると、南は肩を竦めて小声で答える。
「さァ…一時期忙しすぎてやばかった時は、Fワードが書かれたアイマスク付けてミーティングルームのソファで寝てたこともあったけど」
Fワードが書かれたアイマスクって何だ。どこに売っているんだそんなもの。
際田はそう突っ込みたくなったが、あまり詳細は触れない方がコンプライアンス的に良さそうな気がしたので、そこは敢えて流すことにした。
「アイマスクが笹村さんの精神状況の指標を示してるんですか?」
「そう。『触るな危険』の時は『緊急時以外は絶対起こすな』って意味だから、そのつもりで」
「成程…」
後々、際田が笹村の愉快で治安の宜しくないアイマスクコレクションを目にする機会が増えることになるのは、また別の話である。
・
際田の運転するカローラの車中。窓を開け放した助手席で煙草を咥えていた南は、スラックスのポケットに手を突っ込み、中に入っていた物を取り出す。
それは小さな白い紙切れだった。今朝、出勤時に署のエレベーター前で笹村とすれ違った時、笹村が南のポケットにこっそり捻じ込んだものだ。南は最初、あまりに自然だった笹村の挙動に違和感を持たず、ポケットに何かを仕込まれたことに全く気づかなかった。しかし、別れ際のほんの一瞬。笹村からのさりげないアイコンタクトでなんとか気づいたのである。
「何です? それ」
気になったのか、運転中の際田が前を見たまま南に訊ねる。南は紙切れに記されたアルファベットの文字列を眺めたまま、紫煙を燻らせながら表情を変えずに答える。
「今朝コンビニで煙草買った時のレシート。ポケットに突っ込んだまま捨てるの忘れてた」
息をするように嘘を吐いた。
「近々また煙草値上がりするみたいですよ」
「あァ、ニュースで見たわ。さすがに禁煙しよっかな」
「それ笹村さんも言ってました」
「うわ無理なやつじゃん。諦めよ」
赤信号。際田はブレーキを踏み、車を停止させる。
南は紙切れを小さく折り畳むと、ジャケットの胸ポケットから黒革が巻かれた円筒状のアッシュシリンダーを取り出し、そこに仕舞い込んだ。それは南がいつも使っている携帯灰皿とは色が違った。いつもはキャメルの皮が巻かれたものを使っている。
その合図を、際田は見逃さなかった。
「そうえばさァ」
南は煙草を車内に備え付けられているアッシュトレイに押し付けて火を消しながら言う。
「今度ばあちゃんがこっちに遊びに来るって言うから、昨日部屋の掃除してたら聖書が出てきたんだよ。昔、親からもらったんだけど」
唐突に脈絡のない話を始めながら、再び煙草を取り出して口に咥え、ジッポライターで火をつける南。南はこうして時折、思い出したようにその場とは一切関係ない斜め上の話題を振ってくることがある。しかしそれは最終的にかなり重要なオチへと終着することを際田は知っているので、「始まった」と思いながら聞き逃さないよう相槌を打つ。
際田は南に試されているのだ。
「ユダってわかる?」
南が紫煙と共に口にした問いかけに、際田は過去に聞きかじった記憶を掘り起こす。
「えっと確か、イエス・キリストの13人の弟子の1人で、イエスを裏切った人物でしたっけ」
「そう。ユダは祭司長たちにイエスを引き渡し、結果イエスは処刑された。このことから、裏切り者の代名詞としてユダの名前が使われることもある」
南はフィルターに口をつけ、深く吸い込む。口の中で煙を燻らせてから、ゆっくりと吐き出した。
「けど、数年前に見つかった古文書によれば、ユダは真面目で篤実な性格で、律法学者に騙されて捕縛者をイエスのところへ導いてしまった、なんてユダを擁護する新説も出てきた」
南の言わんとしていることを、際田は徐々に読み取れてきた。その一方で戸惑いを隠せない様子の際田を横目でじっと観察していた南は、ふっと口元を緩めて左手の人差し指を唇に当てる。余計なことは何も言うな、のサインだ。つまり当たり障りのないリアクションと会話をしろ、と。
「新発見がある度に次から次へと解釈が変わる。諸行無常だなと思うわけよ」
「…そうですね」
「今回の事件だってそう。相次ぐ殺人、増える容疑者、新たに判明した事実──キリがないね」
『新たに判明した事実』という単語に、際田は目を見開く。
南は頷いてみせた。
「…南先輩のおばあさんって、確か紅瑠峰(くるぶ)に住んでるんでしたっけ」
青信号。アクセルを踏みながら、際田は物は試しと質問を投げかける。南は肩を竦めて答えた。
「そ。辺境も辺境。でも長閑で良いとこだよ。自然豊かだし、星は綺麗だし。狐、狸、野兎、野鳥がいっぱいなメルヘンワールド。猪が畑を荒らすから厄介だけど」
ジジ、と煙草が燃える音。煙を吸い込み、吐き出しながら南は目を細めて意味深に付け加えた。
「あと、"鼠"もね」
・
一方、小西は鑑識課のラボのスペースを借り、目昏摩の所轄から取り寄せた染浦絃の失踪時の捜査資料と、テーブルの上に並べた押収品の数々を確認していた。
絃が借りていたマンションの一室に残されていた押収品一覧を眺め、めぼしいものがないか見ているのだった。
「気になるものはあったかい?」
珈琲を飲みながら小西の様子を眺めていた檀が問いかける。
「気になるものなら、これでしょうか」
小西は檀に指し示しながら答える。一覧で目に留まったのは、『40.鍵/錠前』という項目。備考欄を見ると、それは特注のウォード錠らしく、絃が借りていた部屋のものではなく、どこか別の用途で使われていたものとのことだった。
どれどれ、と言いながら、テーブルの上に並べられた押収品の中から、40の番号ラベルが貼られた物を見つけ、檀が手袋をはめてから袋に入れられたそれを手に取る。よくよく観察してみると、鍵の持ち手と差し込む部分の形状が花と葉を模ったデザインになっている。
「これは…梔子の花だね。見事な鍵だ」
ウォード錠とは、古代ローマでその原型が作られたという錠前である。現在でも、南京錠や簡単な鞄などの錠に使われている。
構造としては、錠の内部にウォードと呼ばれる障害が設けられており、正規の鍵はその障害に当たらずに回転できるような形状になっている。原理自体は単純であるため、簡単な物であればすぐに解錠でき、合鍵も容易に作れてしまう。しかし、ウォードの形状を複雑にすれば解錠や鍵の複製は困難になる。そのデザインの多様性から、芸術品とさえ称される。
絃の部屋から見つかったのはかなり複雑なウォード錠で、特注品であることは想像に難くない。だが目昏摩の所轄は、何のために彼女がそのようなものを持っていたのかまでは見当がつかなかったようだ。
「この鍵の製造メーカーと年代、購入履歴を調べれば何かわかるかもしれません」
「おやすいご用さ。調べるとしようか」
檀は鍵と錠前を袋から取り出し、作業台に載せる。小西は「よろしくお願いします」とその様子を見届け、押収品一覧に目を戻した。
・
再び染浦夫妻の家へと訪れた南と際田。此度も染浦夫人が2人を出迎えた。絃の養父にあたるご主人は、仕事で遠方に出張中とのことだった。
「再度お邪魔してすみません。お時間は然程取らせませんので」
リビングに通され、ソファに座った南は早速本題に入る。
「娘さんについてお聞きしたいことがございまして。単刀直入にお尋ねしますが、娘さんには婚約者がおられたとか」
南の質問に、染浦夫人がやや間を置いてから首肯した。
「ええ。ですが彼は娘の失踪には直接的に関与していないだろうと、目昏摩の警察の方が仰っていて」
やはり染浦夫人は察しが良い。絃の失踪に婚約者が関わっている可能性を探ろうとしたことを見抜いた夫人の言葉に、南がぴくりと片眉を吊り上げる。
「と言いますと?」
「娘が失踪した時期、彼は仕事でアメリカにいました。アリバイの裏付けも取れたと聞いています」
成程、と際田は手帳にメモを取る。これは天清瞳子と懇意にしていたというモデルの絹川と同じパターンか。
南の脳内に一瞬、絃が婚約者を頼って渡米した可能性が過ったが、すぐにその推測を否定した。
絃の婚約者の存在は、目昏摩の所轄も把握していた。その婚約者が仕事でアメリカにいたことを知っていたのなら、絃がアメリカに高飛びした可能性も真っ先に浮かんだはず。空港の税関のセキュリティーはそう甘くない。その辺りの監視記録も調べているはずだ。それでも尚見つかっていないということは、つまりそういうことだろう。
加えて、ひと昔前なら戸籍謄本さえ取れればパスポートの偽造は至って容易だったものの、ここ数年は個人情報の問題で簡単には取れなくなった。絃がパスポートを偽造して海外に高飛びした可能性は低い。
「彼は今でも時折、うちに様子を伺いに来てくれます。あの娘が姿を消した理由はわかりませんけれど、それでもまだあの娘のことや私たちを気にかけてくれる存在が1人でもいるというだけで、心の支えになっています」
そこで初めて、染浦夫人の声が僅かに揺れた。それは、行方をくらました娘を案ずる母の顔だった。
「その婚約者の方のお名前をお教えいただいても?」
南が静かな声音で訊ねると、染浦夫人は鼻を啜り、やや涙ぐみながらもはっきりとした口調で答えた。南と際田はその返答に目を瞠ることになる。
「丹羽万純さんという方です。職業は写真家だと聞きました」
・
「どういうことか説明してもらおうか」
取調室にて。持参したファイルを机の上に置き、ドサッと椅子に腰を下ろした南の正面。そこには丹羽が落ち着かない様子で身を縮めて座っている。その横には無愛想な顔つきの弁護士が控えていた。
実際のところ、警察側の人間にとって弁護士の存在は非常に厄介である。弁護士はまず容疑者に黙秘を推奨し、警察側に伝える情報を制限する。容疑者にとって不利となる証言はしなくて良いという権限だ。そのおかげで捜査がスムーズに進まなくなるため、弁護士がつく前にいかに情報を引き出せるかが鍵となるのだが、今回は弁護士の目があるため少々面倒になる。
しかし南は弁護士には目もくれず、丹羽だけを真っ直ぐに見据えていた。
「あなたには婚約者がいた。染浦絃、28歳。1年前に姿を消して、失踪届が出されてる」
南は染浦絃の顔写真を机の上に置き、トントンと人差し指でその写真を指し示す。丹羽の表情が俄かに曇った。
「この事件に彼女は関係ないはずですが」
「丹羽さん」
弁護士が口を挟み、発言を制そうとする。丹羽はしまったと言いたげに口を噤んだ。内心舌打ちを零したくなる気分を抑え、南は続ける。
「以前にも何度かお話ししましたが、今回の事件、かつて被害者たちとアートグループを結成し制作活動をしていた芸術家である艶島由綺という人物の自殺の現場と、いくつか共通点があるんですよ」
南はファイルから資料と写真を取り出し、机の上に広げる。
「殺害現場を再現したと見られる絵画。これは艶島由綺の自殺の現場にも見られたもの。遺体の口内に詰められたドグセリの花。これは艶島由綺が自殺に用いたもの。これらはメディアには公開されていない情報です。つまり、一連の事件は艶島由綺の自殺について詳しく知る人物による犯行と見ています」
「…その艶島由綺という人物と丹羽さんにどういう関係があると?」
弁護士が問いかけると、南は間を置かずに淡々とした口調で答えた。
「直接的な関係性はない。けど、丹羽さんの婚約者だったという染浦絃は、艶島由綺の実の娘です。実母にあたる艶島由綺の死の詳細を知っていてもおかしくない」
その返答に弁護士は眉を顰める。一方で、丹羽は呆気に取られた様子で固まった。丹羽の挙動を見て、彼がその事実を本当に知らなかったということを察すると共に、これまで第一容疑者として疑っていた丹羽が黒幕ではないことを南は即座に理解した。
「…その様子だと、ご存知なかったみたいですね」
南は椅子の背もたれに背を預ける。丹羽は何か言おうとして口を開き、何を言って良いかわからず口を閉じる。南は少し黙考し、身を乗り出して机の上に両腕を置き、覗き込むようにして丹羽を見つめた。
「丹羽さん。あなたは染浦絃に利用された。彼女があなたに近づいたのは、天清瞳子と花見堂周と接点を得るため。我々は、彼らが艶島由綺の自殺の要因であると見てる。実の母親を死へ追いやった2人への復讐である可能性が極めて高い」
「待ってください。資料によると艶島由綺の死因は確か、精神疾患を患っていたことによる自殺だったはずです。精神を病んだ要因に被害者たちが関係しているという証拠は? 仮にその染浦絃という人物が今回の事件の真犯人だとして、被害者たちを殺害した明確な動機を示す物的証拠がない以上、あなた方の要求には応えられない」
またしても間に割って入る弁護士。南はちらりと弁護士に目を向け、「物的証拠、ね」と呟く。そして取調室の壁に取り付けられている鏡を一瞥した。
すると程なくして、際田が取調室のドアを開いて中に入ってきた。鏡越しに隣の部屋で待機していたのである。手にはクリップで留められた紙の束を持っている。南はそれを受け取ると、机の上の資料を端に寄せてからクリップを外し、新たな資料を広げた。弁護士は怪訝そうに南を見遣る。
「…これは?」
「あなたが今求めた物的証拠ってやつですよ。ご覧になっていただいて構いません」
それは、事前に檀から笹村伝に知らされた内容をまとめたものだった。
厳密に言えば、殺害現場で見つかった犯人のものと思しき毛髪のDNA鑑定結果と、絃の生い立ちの調査結果である。
そこには、絃が特別養子縁組に出された記録、艶島由綺の診療記録、担当医だった常盤みどりの証言の記録のほか、犯人の毛髪のDNAが、データベースに登録されていた艶島由綺のDNAと一致したこと。
それに加え、"花見堂周のDNAとも一致したこと"が記されていた。
つまり、犯人は艶島由綺の実子である染浦絃であり、その父親は花見堂周であることが判明していたのだ。
天清瞳子を殺害した動機は未だ不明ではあるものの、絃が実父を明確な殺意を持って殺害したことは一目瞭然であった。
結果報告書を見た弁護士の表情が、だんだん険しくなっていく。弁護士は丹羽に資料を見せ、内容をかいつまんで説明した。その様子を、南と際田は優勢を確信しながら見ていた。そこで畳み掛けるように南は口を開く。
「丹羽さん。あなたは連続殺人事件の証拠隠滅を図ったとして証拠隠滅罪の容疑がかかってる。染浦絃についてあなたが知っていることをすべて話すなら、情状酌量の余地ありとみなして減刑の手助けをする」
これは取引だ。
丹羽はしばし呆然とした後、微かに口を動かして何かしら呟いた。南は眉根を寄せる。聞き返そうとしたその瞬間。
「そんなはずない! 何かの間違いだ! あなたに彼女の何がわかる!? 彼女は…!」
バンッと音を立てて丹羽が机を叩いた。これまでの柔和で穏やかで、緊張で怯えるような態度を示していた丹羽の口から飛び出たとは思えないほどの怒鳴り声だった。弁護士が諌めるのも構わず、丹羽は南に罵声を浴びせた。
あァ、とうとうボロが出た。
南は冷めた目で丹羽を一瞥すると何も言わず椅子から立ち上がり、際田を連れて取調室を後にした。
ああなった人間は、しばらく時間を置いて落ち着かせなければ話にならないと経験上わかっているからだ。
愛していた婚約者に犯罪に利用された挙句、用済みと判断され捨てられたという事実を受け止めるには、それ相応の時間を要するに決まっているのであった。
・
検死室にて。
九十九はにこにこといつもの笑みを湛えながら、検死室にある3台のうち、一番奥の検死台の上で枕を抱えて寝転ぶアイマスクの女を見下ろしていた。
「笹村女史。あなたはいつから死体に転職したので?」
「……仮眠中は起こさないでって言わなかった?」
「あなたが指定した2時間ならとうに過ぎています」
「私の体内時計はまだ12分しか経過してない」
「それだけ口答えできるなら目も覚めているでしょう。起きなさい。そもそもここは仮眠室ではない」
至極真っ当な指摘である。何故このかつての養い子がわざわざ検死室の検死台で眠るのか、その理由が「静かで九十九以外誰も邪魔しに来ないから」というものであることは知っているとはいえ、だ。過去にも何度か咎めたが、笹村は懲りなかった。
「私が偶に仮眠で使うからって、余程のことがない限りこの検死台は使わないようにしてるの知ってるんだよ」
「………」
九十九の笑顔がぴしりと固まる。堪忍袋の緒が切れた。図星であるが故だった。
「起きなさい」
「やる気が出ない」
「では、やる気が出るように頭蓋を割って神経回路を弄って差し上げよう」
「怒らないでよグランパ」
笹村はアイマスクを上にずらし、やっとのことでのろのろと上体を起こす。寝起きが悪いのはいつものことである。
「先程からあなたの携帯端末からひっきりなしに通知音が鳴っています。仮眠後に報告するよう指示したのでしょう。みんな待っていますよ」
九十九はヒーター式のホットプレートの上に置いていたビーカーを笹村に手渡す。ビーカーにはティーバッグが浮いたままの紅茶が入っている。ちなみにこのビーカーはきちんとドリンク専用である。
笹村は寝惚け眼でビーカーを受け取り、程よく温かい紅茶を啜る。枕元、もとい作業台の上に置かれていたステンレス鋼/チタン合金製の医療用トレイに律儀に載せていた仕事用の携帯端末を手に取って新規の通知を確認すれば、メールが6件、着信が3件。いずれも親愛なる部下たちからだった。
「…………」
黙ったままちまちまと紅茶を飲みながらメールの内容を確認すること数分。笹村は携帯端末をポケットに仕舞う。
この時、既に笹村は仕事スイッチがオンになっていた。
「そろそろ潮時、か」
小さく呟き、笹村は紅茶を飲み干すと検死台から降りて立ち上がる。
「ご馳走様。邪魔したわね」
そう言ってビーカーを九十九に返すと、アイマスクを外して枕を抱え、そのまま検死室を出て行った。
「まったく、世話の焼ける」
九十九は笹村の後ろ姿を見送りながら肩を竦めるのだった。
・
ようやくオフィスに舞い戻った笹村を迎え、1課の面々はミーティングルームに揃って報告を始めた。
「染浦夫人の証言により、染浦絃の婚約者は丹羽万純だったことがわかりました。彼は染浦絃に利用され、証拠隠滅の幇助をしたものと見ています。染浦絃に関して知っていることをすべて話せば減刑するとの取引に応じ、現在供述調書の作成中です」
南の報告に、笹村は把握した意を示して頷く。続いて小西が口を開く。
「染浦絃の失踪時の捜査資料及び証拠品に、特注のウォード錠がありました。檀さんに調べてもらったところ、製造メーカーと購入者を特定できました」
小西がモニターにPC画面を共有し、結果画面を表示する。
「手光(てびか)ロック株式会社。ウォード錠の特注品の受注は6年前に廃止しているため、数が限られるとのことですぐに注文依頼者が判明しました」
画面に表示された注文依頼者の氏名は──
"艶島由綺"
「では、染浦絃の部屋に残されていた鍵は、もともと艶島由綺の所有物だったってことですか?」
際田が訊ねると、小西は「その可能性が高い」と首肯する。南がモニター画面を睨みながら両手を頭の後ろに当てて椅子に背を預ける。
「疑問点が2つ。1つ、その鍵は何の鍵か? 2つ、染浦絃はどうやってその鍵を入手したか?」
それには小西が答える。
「1つめの疑問点なら判明してる。艶島由綺はウォード錠の発注と一緒に、錠前の取り付けも依頼していた。場所はここ」
そう言って小西は地図を表示する。住所だけではわからなかったものの、ストリートビュー機能で表示された景色及び建物を見た面々は、そこがどういう場所かすぐに察した。
「艶島由綺の自宅…!」
際田が閃いたように呟くと、「厳密にはアトリエの出入口の鍵だった」と小西が言う。
「艶島由綺の、アトリエって…」
南がはっとした表情で小西を見る。
「艶島由綺の自殺現場だね」
小西の代わりに、笹村が目を細めて答えた。
「かつて艶島由綺が発注して取り付けまで依頼した錠前を染浦絃が保管していたなら、かつての艶島由綺のアトリエにあたる建物の鍵は、当然今は別の物に取り替えられてるだろうね。おそらく染浦絃の手によって」
「わざわざ鍵を交換した理由は何でしょう? 見たところ、壊れた様子はなかったみたいですけど」
際田が疑問を口にする。際田の言うように、ウォード錠は壊れているわけではなかった。しかし、際田以外のメンバーはウォード錠の実物を見た瞬間、当然のようにその理由を察していた。南が代わりに答える。
「ピッキングの形跡を一時的に隠すためだよ」
「ピッキングの形跡…?」
小西がウォード錠の画像を拡大して表示する。
「見て。鍵の差し込み口にうっすら傷が入ってるでしょ。ピッキングの跡だよ」
小西の言う通り、錠前には細い傷がついていた。
誰が何のために艶島由綺のアトリエの鍵をピッキングしたのか。言うまでもなく、染浦絃がアトリエに入るためだろう。
「かつての艶島由綺の自宅及びアトリエにあたる建物は、今は個人管理になっています。管理者を特定して何度か問い合わせてみましたが、連絡が取れず…」
小西の報告に、はァと南が頭を掻く。
「そんなの、染浦絃の息がかかってるとしか考えらんないでしょ」
「もしくは管理者の権限を何らかの手段で染浦絃が引き継いだ可能性もある。艶島由綺の血縁者であると名乗れば話は早いだろうしね。防犯上の理由をこじつければ、鍵交換だって容易だし。隠れ家として拠点にしてるかも」
そう言って笹村は椅子から立ち上がった。
「艶島由綺の自宅及びアトリエに突入する。令状の発行請求してくるから、各自家宅捜索の準備」
「了解」
・
久地那市郊外の高級住宅地。
かつての艶島由綺の自宅前に到着した1課の面々は、緊張した面持ちで門扉の前に立った。
防弾チョッキに拳銃を携え、完全武装の出で立ちである。何しろ相手は残忍な殺害手段に抵抗のない連続殺人犯。何が起きるかわからない。家宅捜索とは名ばかりの、突入と犯人確保が主たる目的となる作戦だ。
突入するのは笹村、南の他、突入部隊の捜査員が13名。小西は万が一被疑者が逃走を図った際の逃走経路追跡のため、機材を載せた車両で待機。際田も現場への突入経験がまだ少ないため、小西と共に車内待機である。
先行していた捜査員からの情報では、電気、ガス、水道のメーターに動きは見られず、建物内に人の気配はない。近所への聞き込みでも絃と思しき人物の目撃情報は得られなかった。アトリエの様子に関しては、カーテンが閉まっているため中の様子は伺えないとのことだった。
絃がこの場所を拠点にしていると仮定した場合、深夜に外出していたとしたら目撃される可能性は低い。この辺りはひとつひとつの土地が一般的に比べて広く、閑静な住宅地だ。治安が良すぎるが故に、却って深夜に外を出歩く者は少ない。
懐中電灯、ライター、蝋燭、ガスコンロの確保と、飲料水の無料提供を利用すればある程度隠れて生活はできる。もしくはまだ見つけられていないだけで、他にも拠点があるかもしれないが──
笹村は令状を携え、突入部隊の前に立ち合図を送る。
「これより、被疑者・染浦絃の拠点と見られる建物に突入する」
令状の読み上げを始める笹村。周囲に緊張が走る。
「──総員、突入!」
瞬間、一斉に門扉を開いて押し入った。
まず南と突入部隊の過半数は家宅へ、笹村と残りの部隊はアトリエへ向かう。
足音を立てぬよう、気配を消して建物の玄関口に立つ。南は玄関のドアの鍵が閉まっていることを確認し、強行突破の合図を送る。ドアを蹴破り、隊員たちは次々と屋内へ突入した。
「A班は1階、B班は2階へ」
「了解」
南の指示で、隊員たちはそれぞれ任された範囲を捜索し始める。
屋内は薄暗く、埃の匂いがした。南は拳銃を構えつつ、1階の廊下を進んでドアを開く。そこは広々とした居間となっており、家具や家電といった類はひとつもなかった。誰かが生活していたような気配は見受けられない。裏庭に面した窓を開けて庭に出てみるも、やはり気になるものは見当たらず、誰もいなかった。
『こちらA班。家宅1階オールクリア。異常なし』
『こちらB班。家宅2階オールクリア。異常なしであります』
各隊員たちからトランシーバーで報告が上がる。南は拳銃を下ろし、腰に装着していたホルダーに仕舞い込む。
「やっぱり本命はアトリエだったかな」
南はちらりとアトリエに目を向けてから屋内に戻ると、隊員たちに念の為現場保全の準備をするよう指示を出そうとした、その時だった。
笹村からトランシーバー越しに全体へ向けた報告が入った。
『こちら笹村。アトリエにて女性の遺体を発見。突入部隊総員、至急アトリエへ』
・
アトリエの出入口の鍵が開いていた時点で、嫌な予感はしていた。
音を立てず、そっと扉を引いて開く。拳銃を構え、部隊を率いてアトリエに突入した笹村だったが、目の前に広がる光景を見て僅かに瞠目した。
窓から差し込む黄昏の気配。
空間に長年染みついているのであろう、木材と画材の匂い。
床一面に所狭しと敷き詰められた赤い彼岸花。
窓際のテーブルに置かれた真白なティーセットと、硝子の器に盛られた白い花。
その奥には、壁に凭れ掛かるようにして俯き、座り込んだ女の姿。
部屋の一角に配置されたイーゼルには、その現場をそっくり再現した絵画が飾られていた。
この現場には見覚えがあった。
1年前、証拠品保管庫から何者かにより持ち出され紛失したという、艶島由綺の自殺現場に残されていた絵画に描かれていた景色と、そっくり同じだったのだ。
思わずその異様な空間に圧倒され、数秒の間何も言えずに立ち尽くしてしまう程だった。
まるで、絵画の中に入り込んでしまったような──
笹村は我に返ると、床に座り込んで微動だにしない女のもとへ歩み寄った。
肩口あたりで切り揃えられた艶やかな黒髪が女の顔に垂れかかっている。目は閉じていたが、色を失った女の唇の端からは吐瀉物が溢れていた。喉元には掻き毟った痕がある。かなり苦しんだのだろう。しかし、死臭はしない。
まだ間に合うかもしれないと僅かな期待を胸に、笹村は女の首筋に指先を当て、脈を測る。だが、その微かな望みは呆気なく打ち砕かれた。
──ひと足遅かったか。
指先を伝う冷え切った皮膚の感触に笹村は目を細め、下唇を噛み締めた。
視界の端にちらりと映った何かが気になり、そちらに視線を向ける。床の上に投げ出された女の白魚のような華奢な左手の近く。赤い彼岸花の群れに紛れるようにして、真白なティーカップが落ちていることに気がつく。
中に入っていたのであろう紅茶は飲み干されて空っぽだった。そのティーカップの底に何やら赤い文字が記されているのが垣間見えた。笹村は目を凝らしてその文字列を読み取ろうと身を屈めた。
そこには、"The curtain fell."──閉幕、と筆記体で記されていた。
笹村はゆっくりと立ち上がるとトランシーバーを手に取り、全体に向けて女の遺体を発見した旨を報告したのだった。
・
DNA鑑定の結果、発見された遺体の身元は染浦絃であると断定された。
久地那市内で起きた画家連続殺人事件の真犯人は、警察を翻弄し、世間を騒がせ、市民を恐怖の渦に陥れた後、嘲笑うかのように自ら命を絶ち、事件の幕引きとしたのである。
犯人を捕え、法のもとに裁くことが叶わなかったのは警察としてかなりの痛手だった。マスコミからは痛烈な批判を受け、評論家や専門家を気取った人間たちの間では突拍子もない憶測が飛び交い、根も葉もない言葉を吐かれた。メディア様々である。
丹羽はといえば、絃の死を聞かされ、ひどく取り乱した。以降、抜け殻のように変わり果てた結果、医師の診断により入院することが決まった。
絃が自ら命を絶った、かつての艶島由綺のアトリエの本棚には、ノートが1冊置かれており、そこには綿密な殺害計画と日記のような走り書きが乱雑に綴られていた。
その内容からは、一連の事件の現場に残されていた絵画について、絃が被害者たちに「自らが思う、絵になる最期を描いてほしい」と秘密裏に依頼して描かせたものであったことが判明した。
天清瞳子は、赤い花が散りばめられたような血染めの最期を。
花見堂周は、蔦が這い風化した彫像のような冷たい最期を。
絃は被害者たちがそれぞれ描いた"最期"を再現し、その通りに被害者たちを殺害したのだ。
遺体の口内にドクゼリを詰めて口を赤い糸で縫ったのは、絃にとっては芸術家が自身の作品の最後の仕上げに施すサインのようなものだったらしく(由綺が自殺に用いた"ドクゼリ"、由綺の自殺現場で印象的だった彼岸花の"赤"、自身の名に因んだ"糸")、芸術家ではなく、あくまでエンバーマーとしてのアイデンティティを縫合技術でもって表現していたようだ。
また、絃の自殺現場に残されていた絵画は、1年前に証拠品保管庫から消えた艶島由綺の自殺現場にあった絵画と特徴が一致した。絃がその絵を入手した経路と方法は現在調査中である──
「と、表向きはそうなってるけど」
署の屋上。笹村は柵に背を預け、両肘を柵の上に置いた姿勢で飴玉を口の中で転がしながら呟く。その隣には、缶コーヒーを啜る小西がいた。
午後の小休憩。小西はいつも屋上で外の景色を眺める。長時間PC画面と睨めっこしていた目を休ませるためである。そこに笹村が先客として景色を眺めていたのだった。
「1年前、証拠品保管庫から証拠品が消えた件について監察の捜査が入ったにも関わらず、進展もなければ周知の報告もなかった。おかしいと思わない? 監察が聞いて呆れる」
笹村はガリッと飴玉を噛み砕く。小西はどこを見るでもなく、ただ遠くの空に視線を向けていた。
「だから監察に直談判してきた」
「え?」
笹村の唐突な告白に、小西は思わず声を洩らして笹村を見た。
監察とは、所謂『警察の中の警察』と呼ばれる部署で、警察庁、警視庁及び各都道府県警察本部に設置される役職である。警察不祥事の捜査や服務規定違反など内部罰則を犯した警察官への質疑、さらには会計監査業務に携わる。
そんな役職の人間に直接会うのはかなり難しい。況してや所轄の人間がそう簡単にお目にかかれるような存在ではないのだ。小西が驚くのも無理はなかった。
「一体どうやって」
「企業秘密」
小西からの質問を予測していたかのように即答する笹村。しかし、笹村は小西の方にちらりと流し目を向けて肩を竦め、ヒントを与えた。
「小西には教えたはずでしょ。私には情報屋がいる」
笹村と小西の間をビル風が吹き抜ける。
小西は考えた。
もしや情報屋を利用して、艶島由綺の自殺現場の証拠品紛失の件を担当した監察官が1人でいる時間を割り出し、直接会いに行ったというのか。いつだ? この半月、そんな時間を取れる余裕は──
『ちょっと野暮用』
そう言って、笹村が時折オフィスを抜けていたことを小西は思い出す。小西が把握していないだけで、笹村の野暮用はおそらく時間外労働の範囲にも及ぶ。
「直接会った監察官からは大した情報は得られなかった。『君には知る権利がある。だが、監査業務の詳細を、私の口から話すことはできない』って言われてね。要は知りたいなら勝手にしろ、ってお許しが出たわけ。ただし監察の目の届かないところで調べるようにって忠告を頂戴したけど、それはそれ。だから好きに調べさせてもらった。目星はついてたからね」
一際強い風が吹き、陽が翳る。厚い雲が午後の穏やかな太陽を覆い隠した。
笹村は小西の方を向き、一切の感情を削ぎ落とした顔で言った。
「内通者は君でしょう──小西」
・
「内通者? 私が?」
小西は心外だと言いたげに眉を顰めた。しかし、笹村は表情を変えずにはっきりと言った。
「とぼけても構わないけど、私の推測は大方合ってるはずだよ」
笹村の目に平常時と違ったものが映れば、それは違和感、バグとして処理され、エラーが生じる。
一番最初の違和感は、天清瞳子が殺害された事件が起きた朝のことだ。
いつもなら担当案件の捜査資料の確認やら書類対応やらで、朝はPC画面と向き合っている小西が、現代美術の月刊誌を読んでいた。
『艶島由綺っていう画家の回顧展が久地那現代美術館で近々開催されるらしくて』
当初は誰もが些細なこととして気に留めなかった。笹村でさえ、「そういえば小西の趣味は美術館巡りだったっけ」程度に捉えていた。
だが、小西は趣味やプライベートに関わるものをオフィスに持ち込むことは、それまで一度もなかった。仕事中に気が散らないようにと、仕事とプライベートはきっちり分けていたはずなのだ。
その点に思い至ったのは、小西からの「1年前、証拠品保管庫から艶島由綺の自殺現場の証拠品が消えた」という報告を聞いてからだった。
他にも違和感はあった。小西は艶島由綺の担当医だった常盤みどりの存在を見落としていた。小西が意図的に報告しなかった可能性を笹村は疑ったのだ。
そこからの笹村の動きは早かった。
1課の面々が帰宅した後、笹村は小西が2課から取り寄せた当時の艶島由綺の自殺に関する捜査資料に片っ端から目を通した。そしてわかったことがあった。
「紛失したのは絵だけじゃなかった」
話している内容とは相反するように、笹村は詰まらなそうに自身の爪並びを眺めながら呟く。小西は何とも形容し難い表情で笹村の横顔を見据える。
「記録と実物を照合してみたら、一致しないものがあった。記録上あるはずのものがなかった。絵画という重要証拠品の影に隠れるように、別の証拠品も消えていた」
小西は「重要証拠品である絵画が紛失した」としか報告していない。他にも消えた証拠品があるとは、一言も伝えていなかった。単なる見落としならあり得ないことではない。
「持ち去られたもうひとつの証拠品は、一見何の変哲もない1冊のノート。そして、そのノートに挟まれていた1枚の写真。記録には"被害者の日記帳と思われるもの"との記載があった。なぜ日記帳であると断定できなかったか。その理由は至って単純──解読できなかったから」
小西は黙ったまま何も言わない。笹村は淡々とした口調で続ける。
「当時の艶島由綺の精神疾患の病状は軽度とされていたけれど、実際はそうじゃなかった。誰にも見せることのない自身の内面を吐き出す手段に遠慮なんて不要。たとえ見られたとしても、誰かに理解してもらうつもりなんて毛頭なかったんでしょう。けど、書かれてある内容は相当重要なものだったはず。たとえば──艶島由綺が自ら命を絶つことを選択した理由、及び精神疾患を患った原因について書き連ねていたとすれば話は変わってくる」
「……何が言いたいんです?」
小西が険しい表情で笹村を見て訊ねれば、笹村はさも当然のように答えた。
「絵画はフェイク。少なくとも本命ではなかった。本命はノートの方。艶島由綺の死の真相を知りたいと望む人間による犯行。ノートが本命であることを見抜かれないよう、あえて重要証拠品である絵画も持ち出した。小西──君ほどの優秀な捜査官なら、この程度、見落とすはずがない」
──あァ、そういうこと
小西は唇を歪めた。
優秀な部下であると信用されていたが故に、真っ先に疑いを向けられたのか。皮肉なことだ。
「人間、誰だってミスは犯しますよ」
そう小西が反論すれば、笹村はふっと笑った。
「そうくると思った。でも残念。君のPCに染浦絃とやりとりをしていたログが残ってるのはわかってる」
「なっ」
直球でそう言われてしまえば、小西はさすがに狼狽えた。
そんなはずない。バレるはずがない。そこに関しては、それだけの自信があった。
小西の反応に、笹村は目を細めて言った。
「その反応、図星? カマかけただけのつもりだったんだけど」
──やられた
南が"話術"に長けているとすれば、笹村はこうして相手の不意を衝くのが巧い。
「まァ確信がなければさすがにこんなカマはかけない」
笹村は手をひらひらと振りながら言う。
確信があったのか。どこで見破られた?
そんな小西の様子を見遣り、笹村はどこか愉しげな気配を纏わせる。
「いつバレたのかって顔してるね。その答えなら、君が丹羽万純の経歴を調べていた時、と言えばわかる?」
小西はオフィスにひとりでいた時、PCで丹羽の経歴を調べていた。丹羽が卒業したアメリカの教育機関に連絡を取る件で唸っていた時、突如笹村が背後から現れた。
PCの画面には丹羽のホームページとアメリカの教育機関のホームページを開いていた。実はそれらの背後のタブには、小西が作成した暗号チャットアプリを最小化した状態で開いていたのだ。
あの時、PCのタブを見られたのか。
しばらく誰も戻って来ないだろうとたかを括り、1人でいたため油断していた。
「見慣れないアイコンだったから調べたら、公式には配信されていないアプリだった。妙だとは思ったけど、まァその程度の認識だっただけ」
笹村の観察眼と瞬間記憶力は常人の比ではない。小西はそのことを当然知っていたが、改めて思い知らされる。
ここまで来れば一層のこと、笹村の推理をすべて聞きたくなってくる。
「では、染浦絃はどうやって証拠品保管庫から証拠品を持ち出したんです? 入手経路はまだ判明してないですよね」
「あァ、それならとっくにわかってる」
なんてことはない、と言うように笹村はあっさりと述べる。
「監視カメラのクラッキング元のIDと住所が君のものであることは特定済み。クラッキングされる前の元データの映像まではさすがに追いきれなかったけど、手段は大方予想がつく」
小西はごくりと固唾を呑む。笹村は続けた。
「あの絵画を持ち出すには複数の人手がいる。まとまった人数が怪しまれずに保管庫に立ち入るなら、設備の業者を装うのが手っ取り早い。来客用IDが使えるからね。そして、なんやかんや理由をつけて証拠品や棚の移動を要求する。その際、絵画は人目のつかない廊下の隅──エレベーター、台車置き場など倉庫の近くに移動させ、パーテーションを模したケースに収納。それを業者に変装した仲間たちに運搬用エレベーターで運び出させる。地下1階まで降りてしまえば地下駐車場に直通してるから、後は車に載せて運び出すだけ」
──やはり、この人を欺き通すのは不可能だったか
小西は乾いた笑いを零す。見抜かれていた。見抜かれていた上で泳がされていたのだ。
「染浦絃が艶島由綺と花見堂周の間にできた娘だとわかった時は肝が冷えたよ」
檀からその報告を受けた時、笹村はすべて理解してしまった。全容を理解してしまったが故に、これからの動き方で結末が大きく左右されることも。
「君が内通者だと勘づいてから、君にバレないよう1課の関係者に根回しするのにどれだけ苦労したか。檀にはすぐ君を警戒するよう伝えたけど、南と際田は君と距離が近すぎる。だから私に直接入ってきた情報についてはギリギリまで共有を制限してた」
際田は表情に出やすく、嘘が下手である。際田に小西を警戒するよう伝えるか悩んだが、先日、笹村が徹夜明けにシャワーを浴びようと署内のトレーニングジムに併設されているシャワールームへ向かう途中、早朝に道場へ来ていた際田を見つけた時、考えを改めた。
この道場で2人きりのタイミングであれば、小西に盗聴される可能性はないと踏んだのだ。
「君、至るところに盗聴器仕掛けてたでしょ。オフィスのデスク裏、ミーティングルームの椅子の座面裏、機材裏のコンセント──挙げ出したらキリがないから省略するけど」
笹村が際田に伝えたのはこうだ。
"近頃、内部がきな臭い"
担当している事件の犯人と同じ部署の人間に繋がりがあるとストレートに伝えれば、際田の挙動はきっと平常を装えなくなる。だから、あえてぼやかして伝えたのだ。証拠品が内部の人間により持ち出され紛失した件が揉み消されたことを例に挙げ、説得力を持たせれば簡単だった。
そして南にはその直後、エレベーターホールで偶然出会した風に装い、スリの要領で暗号メモをスラックスのポケットに仕込み、小西が内通者であること、いつどこで盗聴されているかわからないこと、際田も把握していることを伝えた。本当は喫煙所で手渡すつもりだったのだが、予期せぬタイミングと場所で南と鉢合わせてしまった。おまけにすぐ近くに小西がいた。想定外だったので、内心ひやりとした。
色々あったものの、裏であれこれ手を回した結果、最終的に黒幕を捕らえることは叶わなかった。最後の最後で逃げ切られてしまった。
この事件は、染浦絃の描いた精緻な絵図の通りに結末を迎えたのであった。
「君がいつどこでどうやって染浦絃と繋がったのかは知らない。そこまでは興味が湧かなかった。正直ぶっちゃけると、ここ数年担当した事件で一番キツかったし、疲れてたから、調べる気にならなかった」
ふとどこか気が抜けたような声音でそう言って、笹村は両手をスラックスのポケットに突っ込み、柵から背を離した。そのまま歩き去ろうとした後ろ姿を、小西は思わず呼び止める。
「私を逮捕しないんですか」
小西の言葉に、笹村は立ち止まる。そして小西を振り返ると、呆れた様子で言った。
「君、檀に言ったそうじゃない。『物的証拠がなければ裁判で罪を立証できないのも事実だろう』って」
風が吹く。雲が流れる。午後の穏やかな太陽が顔を覗かせた。
「君が連続殺人鬼と繋がっていた、という点に関して私が持っているのは、裏の手口で情報屋を使って得た証拠。裁判で提出しても信憑性を疑われるだけ。保管庫から証拠品を持ち出した手段も、憶測に過ぎないと一蹴されてお終いなのは目に見えてる。君があちこちに仕掛けていた盗聴器も、気づいたらなくなってたし」
事件が収束した後、小西がすぐに回収したからだ。笹村はそれもわかっている。気づいたらなくなっていたというのは方便だ。
小西は下唇を噛む。笹村は、あァそれと、と付け加えた。
「おまけに君、警察本部の上層部に親戚がいるでしょう」
保管庫から証拠品が消えた件が揉み消されたのは、つまりそういうことだ。
上層部の身内の不祥事が揉み消されるのは、何もドラマの中の話に限ったことではない。実際に現実で起こり得るのだ。
だが、小西は本部の上層部に身内がいることは誰にも話していなかった。
なぜそれを、と言おうとして、やめた。笹村にそんなことを訊ねるのは、それこそ野暮だ。代わりに小西は別の質問を投げかけた。
「そこまでわかっていて、どうして今この場で私を追及したんです?」
小西がそう訊ねれば、笹村はただ一言。
「答え合わせがしたかった。それだけ」
そう言い残し、小西を1人屋上に置いて歩き去っていった。
小西はしばらくの間その場に立ち尽くし、深々と溜め息を吐いて空を見上げた。
「……やっぱりあの人、大ッ嫌い」
心の奥底から湧いて出た本音は、風の音に掻き消された。
・
小西が絃と出会ったのは、1年半前。場所は美術館だった。
休日、日本画の展覧会を観に訪れた日のことだった。館内で近くを通り過ぎた若い女が展覧会のチケットを落としたのを目の当たりにしたので、拾って渡した。その相手が絃だった。
「宜しかったら、お茶でもご一緒にいかが? お礼をさせてほしいの」
初めは辞退したのだが、どうしてもと言われ、館内に併設されていたカフェに入り、話をした。
絃は聡明だった。チケットの差し出し方で、小西が警察関係者であることを見抜いた。
絃と話をしているうちに、その人となりに惹かれた。思いがけず話は弾み、初対面であることを忘れて楽しい時間を過ごした。
連絡先を交換し、以降休みが合えばお茶を飲みに出かける間柄にまで進展した。
絃から、自身が艶島由綺の娘であると告白されたのは、知り合って3ヶ月ほど経った頃だった。
絃は艶島由綺のこと自体を詳しく知るわけではなかった。特別養子縁組に出され、実母である由綺とは一度も会ったことがなかったという。だが、芸術家としての艶島由綺のことを誰よりも愛していた。
「私、実母が死を選んだ本当の理由が知りたいの。あなたならきっと力になってくれると思って」
この頃既に、小西は絃に心酔していると言っていい程の状態に近しかった。すっかり絆されてしまっていたのだ。
小西は絃に協力することを約束してしまった。
由綺の自殺を取り扱ったのは、幸いにも自身の職場の他部署だった。調べるのは容易だった。現場の詳細を絃に伝えれば、彼女はこう言った。
「現場にあったっていう、その絵。私、欲しいわ」
絃の要求がエスカレートしてきたのはこの頃からだった。
「あとは、そうね。日記帳。これが気になる。本命はこっちね。絵はフェイクとして持ち出せないかしら」
言われるがまま、小西は保管庫から由綺の手記と現場に残されていた絵画を持ち出す作戦を立案し、実行した。人手は絃の伝手を頼った。
作戦は成功した。
監察の捜査が入ったものの、思惑通り、重要証拠品として扱われていた絵画にばかり目が向けられ、本命だったノートは見向きもされなかった。
絵画とノートを手に入れた絃は大層喜んだ。小西に何度も感謝を述べた。これでやっと由綺の死の真相がわかるかもしれないと。
しかし、絃の上機嫌は長くは続かなかった。
由綺の手記は、一見しただけでは解読不能な程筆跡が荒れていたのだ。
軽度の精神疾患を患っていたという捜査資料の記録は間違っていた。末期に近い状態だったことが見て取れる程だった。
それでも絃は、なんとか解読しようと試みた。その結果、筆跡には規則性があることが判明した。
すべて鏡文字だったのだ。しかもドイツ語だった。鏡文字の手稿を残したとされるレオナルド・ダ・ヴィンチを彷彿とさせた。
ドイツ語だと気づいたのは、絃が仕事で医療関係者と話す機会が度々あったからだった。医者はカルテをドイツ語で書き込む。その知識が頭の片隅になければ気づけなかった。
そして、絃は由綺の秘密を知った。
かつて29年前、花見堂という男が由綺に性的暴行をはたらき、妊娠させてしまった。しかし、花見堂が犯した罪の証拠はなく、由綺自身はこのことを誰にも知られたくないという思いから事を公にせず、行動を起こさなかった。瞳子はそれに勘づいていながら、由綺に手を差し伸べようとしなかった。
天清瞳子と花見堂周。この2人の存在が絃の復讐対象となると同時に、自身も由綺の人生を狂わせた要因であることを知った絃は、2人への復讐を遂げたのち、自身も命を絶つ決意をしたのだ。
「艶島由綺が生きていれば見られたかもしれない未来の作品を奪う権利なんて、あの2人にも、私にもない。それなのに私たちは、艶島由綺の可能性の芽を摘み取ってしまったのよ。罰を受けるべきだと思わない?」
そう言って忌々しげに微笑んだ絃の顔を、小西は忘れられなかった。
・
笹村を完璧に欺くのは無理だろうと、小西は初めからわかっていた。伊達に長い付き合いはしていない。あくまで仕事の上でだが。
わかっていたから、捜査の進展を一時的に滞らせるため、報告すべきだった内容を一部伏せて時間稼ぎをすることにしたのだ。見落としていたと言い訳が罷り通るギリギリの範囲内で。他にも、花見堂が殺害された後には一時的に丹羽が第一容疑者として疑われるよう仕向けることで捜査を妨害した。盗聴器についても、設置すると周囲の電波に影響が出るため、電話でのやりとりに支障をきたす恐れがあった。気づかれることのないよう、時と場合に応じて拾う周波数を調整するのに苦労したのだ。どのタイミングで笹村が盗聴器に気づいたのかはわからなかったが。
何はともあれ、全体的に見れば妨害工作は成功したと言える。最終的に、絃の目的は、願いは、復讐は果たされた。
なのに、この虚無感は何だ。
試合に勝って勝負に負ける、と言う言葉があるが、まさしくその状態が近い。
笹村のあの様子を見るに、このことは上にも報告していないだろう。
つまり、試されている。
小休憩の時間はとっくに過ぎていた。
オフィスに戻らなければ。頭ではそう思うが、足は一歩も前に進まない。
これからどんな顔をして笹村の下で働けというのか。内心、退職も割と本気で考えていた。
南と際田のことは好きでもなければ嫌いでもない。ただの職場の同僚と後輩としか捉えていなかった。檀との話は面白かったが、その程度だ。九十九は何を考えているかわからないあの笑顔が不気味でどうも苦手だった。
要するに、刑事部刑事1課を離れることに抵抗は全くと言っていい程なかったのである。
途方に暮れる。追及するなら、せめて終業後にしてくれれば良かったものを。上司を恨めしく思いつつ、小西は持っていた缶コーヒーを飲み干した。
ふと、笹村が度々口にしていた言葉が蘇る。
── 条件次第でなんでも調べてくれる知り合いがいるんだ
──私には情報屋がいる
そこで、小西にとって最悪の考えが浮かんでしまった。
自分でもなぜこんな思考に至ってしまったのかわからなかった。小西は笹村のことを心の底から嫌っている。それなのに──
"笹村の情報屋になる"という選択肢が、頭に浮かんでしまったのである。
「………まさか」
笹村が小西にだけ情報屋の存在を仄めかしていたのは不思議に思っていた。
小西の行動を怪しんで警戒していながら、わざわざ手の内を見せていたようなものだ。笹村は理由もなくそんなことをするような人間ではない。
小西は笹村から情報屋の存在を明かされたあの日の夜、笹村の所持している端末にハッキングし、情報屋について何かわからないだろうかとログを漁った。
彼らは小西と同等、あるいはそれ以上の能力を持つ天才ハッカーたちばかりで、なかなか尻尾を掴ませてはくれなかった。しかし、やっとの思いで何人か正体を暴くことができた。
笹村の情報屋は、過去のサイバー犯罪事件に関わった"現在も指名手配中のハッカーたちである"という情報を手に入れたのだ。
笹村は指名手配犯を匿い、代わりに情報屋として働かせているというのである。
実のところ、その情報はあらかじめ小西からのハッキングを予測していた笹村の機転により
、真秀という若き天才ハッカーが小西にわざと盗ませたフェイクの情報で、事実は「笹村が過去にサイバー犯罪対策室からの要請で捜査の協力に応じたとあるサイバー犯罪事件で、自身が検挙したハッカーたち数名と"取引"の下で協力関係を結んでいる」が正しい。
笹村がフェイクの情報を盗ませたのは、ハッカーたちの身元を明かさないためと、警察の目を掻い潜り逃亡中の身であるハッカーたちを匿っていると思わせることで、行き場をなくした小西が笹村の情報屋になる道を選ぶ確率を少しでも上げるためだった。
小西はそれを知る由もなかったが。
──兎に角、その情報を得た小西は、物好きな人だな、としか思わなかったが、今なら理解できなくもなかった。
行き場のない犯罪者を拾い、隠れ蓑まで与えているのは、彼らの能力を無駄にすることなく役立て、社会に貢献させるためなのだろう。
アメリカでは、罪を犯したにも関わらずその能力を買われ、政府お抱えのハッカーとして雇われた者もいると聞く。
わざわざ笹村が情報屋の存在を小西に打ち明けたのは、"小西が自ら笹村の情報屋になる選択肢を視野に入れる"よう仕向けるためか。
敵に塩を送るとは、まさにこのことだろう。
本気で吐き気がする程嫌ではあるが、背に腹はかえられない。行き場がないのだから、開き直るしかなかった。
小西は携帯端末を取り出し、笹村の番号に発信した。
笹村はスリーコール後に着信に応じた。
『はい』
小西は開口一番に言った。
「笹村さん。私、捜査官辞めます」
『……そう。それで?』
仮にも"優秀な部下"と評した相手に対して、この反応である。お世辞でも「残念だわ」とは言わない辺り、笹村はこのタイミングで小西から電話がかかってきた時点で、何を言われるかわかっているのだろう。小西は一周回って苛立ちすら覚えなかった。寧ろ感動するレベルだ。
笹村の思い通りに転がされるのは心底癪だったが。小西は深く息を吸い込み、意を決してはっきりと告げた。
「あなたの情報屋になります。責任持って再就職先くらいは面倒見てください」
・
──1ヶ月後。
久地那警察署刑事部刑事1課のオフィス。南と際田はそれぞれのデスクに座り、始業前のルーティンワークをこなしていた。
そこに小西の姿はなかった。
かつて小西が使っていたデスクの上には、備え付けのPCだけがぽつんと置いてあった。
秀でた情報収集能力を買われ、本部のサイバー犯罪対策室に引き抜かれたとかなんとか。数ヶ月前から打診があったらしく、担当している仕事をすべて片付けたらという条件で異動を決意したらしい。
「──と、表向きはそうなってるけどさァ」
書面確認に飽きた南が口を開く。
「どうも納得いかないんだよ。笹村さんがそう易々と部下を他所に引き渡すかね」
椅子の背もたれに凭れ掛かり、両手を頭の後ろに遣りながら零す。
「小西先輩の意志を尊重したんじゃないですか? もしくは、小西先輩の能力が存分に発揮できる場所に行った方が、本人のためになると判断したとか」
「いや、そこじゃない」
際田の言葉を、南はチョコレートバーを齧りながら否定する。そして、今まで表立って話すことを意図的に避けていた事実を一言。
「だって、内通者は小西だったじゃん」
南が口にしたその発言の意味を、際田は一瞬理解できずフリーズした。
内通者? 小西先輩が? 何の?
きょとんと目を見開いて固まる際田を見て、今度は南が首を傾げる。
「え? だから、1年前に艶島由綺の自殺現場の証拠品が保管庫から消えたってやつ。あれ、手引きしたの小西だったって。え、もしかして聞いてないの?」
会話が噛み合っていないことを察した南は、際田と答え合わせをするように話を進めた。
「2回目に染浦夫妻の家に行った時、車でユダの話したでしょ。あと、うちのばあちゃんの地元の話。"鼠"が厄介だって」
「え、はい。…ん? 猪が畑を荒らすから厄介って言ってませんでした?」
「鼠もって付け加えたよ私は」
「そうでしたっけ…?」
あ、駄目だ。南は頭を抱えた。
「ユダは裏切り者の代名詞として使われるって話は覚えてる?」
「はい」
「じゃあ、ユダの新説の解釈云々の話は?」
「なんとなく…ユダを擁護する内容だったような」
「オーケイ。じゃあここでクイズ。鼠は英語で?」
「え? マ、マウス…」
「もう1個あるでしょ」
「もう1個?」
際田は訳もわからず南の質問に答えていたが、鼠は英語で、なんて、マウスしか知らない。なぞなぞか何かだろうか。
南は耐えかねたのか、溜め息混じりに言った。
「正解は"rat"」
「ラット…? あァ! 言われてみれば…」
確かに聞き覚えのある単語だ。そこでようやく、際田は気づいた。
「もしかして、裏切り者…つまり、内通者ってことですか?」
「そう。私、あの時ずっと裏切り者に関する話をしてたんだよ。ユダもそうだし、鼠──特にラットは裏切り者を意味する言い回し。ついでに言うとマウスはコンピュータの入力装置。要はコンピュータの扱いに長けた奴、つまり小西が裏切り者だっていう『新たに判明した事実』ってこと。我ながら秀逸な言い回ししてたって自負してたんだけど、伝わってなかったのか…」
伝わるわけないだろ、と際田は突っ込みたくなったが、成程、こうして解説してもらうとよくわかる。笹村であれば、解説がなくとも見抜いていたかもしれないが。
「私、笹村さんから渡されたメモで、際田も把握してるから安心しろって言われてたから、てっきり伝わってると思ってたんだけど…」
南に渡された笹村からのメモは、英文のシーザー暗号で書かれていた。解読すると以下の通りになる。
"We have a RAT!
The walls have ears.
Probie got it.
Keep your eyes open."
和訳するとこうだ。
『仲間に裏切り者がいる。
常に盗聴されていると思え。
新米は把握済み。
気を抜かないこと。』
盗聴の恐れがあったため、南はあの場で回りくどい言い方を選んだのだ。
「確かに笹村さんと道場で稽古つけてもらった時、そんな感じの話はしましたけど……僕が言われたのは、『近頃、内部がきな臭いから警戒しろ』とだけ…」
「それだけ?」
「それだけです」
南は納得した。あァ、と。
笹村は、小西が裏切り者だと知ることで際田の挙動がおかしくなることを危惧したのだろう。それを南にさえ伏せていた辺り、流石というか何というか。
「……そっか。小西先輩が、内通者だったんですね」
際田が噛み締めるように呟く。その表情は哀しいとも寂しいとも受け取れるものだった。
「……際田」
南が口を開きかけた時、際田は言った。
「南先輩が丹羽万純の取り調べを担当していたのを、小西先輩と隣の部屋で見学してた時、南先輩は笹村さんをめちゃくちゃ尊敬してるって話になって」
「え? 真剣な取り調べ中に裏でそんな話してたの? 聴取内容の考察とかではなく?」
思わず南は突っ込んだ。口にしようとした気遣いの言葉が引っ込む程の衝撃だった。際田は気にも留めず続ける。
「僕、訊いたんです。小西先輩も笹村さんを尊敬してるんですかって。そしたら小西先輩、笹村さんのことは『尊敬に値する人だと思ってる』とは言ってたんですたけど、『尊敬している』とは言わなかったんですよね」
それを聞いた南は、思わず口を噤んだ。
小西が笹村を嫌っていたのはなんとなく察していたが、小西自身ははっきりと口にはしなかった。よくよく観察してみればわかる程度に言動や行動には表れていたが。
笹村相手に限らず、小西は他者に対して深く踏み込まず一定の距離を保つところがあった。
その小西が、染浦絃という1人の女の駒になっていたのだから驚きである。
それほど、染浦絃という人間は他者を惹きつける何かを持っていたのだろう。
「口は禍の元」
「うぉっ」
南は唐突に耳元で声がしたことに思わず飛び上がる。南のすぐ背後に、いつの間にか笹村が立っていた。
「お、おはようございます笹村さん」
「おはよう。朝から無駄話をする元気な口はどの口?」
「仕事します」
南は姿勢を正し、書面に向き合う。際田も慌てて書類整理に戻った。
結局、笹村が小西の異動を認めた本当の理由について、南と際田が推測を交わす機会は失われたが。
こうして、今日も久地那警察署刑事部刑事1課の朝は始まったのであった。
・
《久地那市画家連続殺人事件に関する捜査記録》
─中略─
染浦絃の自殺現場には1点だけ、艶島由綺の自殺現場と違った箇所が見られた。
艶島由綺の自殺現場では、アトリエの棚に、中身のないフォトフレームが置かれていた。
しかし、染浦絃の自殺現場にあったのは、写真が入れられたフォトフレームだった。
それは若い女性が赤ん坊を抱いた写真で、女性は艶島由綺であることがわかった。彼女が抱いている赤ん坊は、おそらく染浦絃だろうと推測される。
また、その写真は、1年前に証拠品保管庫から絵画と共に持ち出され紛失した、艶島由綺の自殺現場の押収品である日記帳と見られるノートに挟まれていたものであることが当時の記録から判明した。
・

不定期で映像配信・作品展示を行うアートグループ〈ケイケイ〉が1年2ヶ月ぶりに繰り出す新基軸。 インスタレーション/映像表現/絵画世界が渾然一体となって紡がれる“クチナシの惨劇”を貴方は目撃する!計7名の作家が織りなす衝撃の問題作。(※全ての会期を終了しました)
ケイケイ主催企画{糸を引く}
2023年 5/5(金)〜5/7(日)
Design Festa Gallery West 2-A
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3丁目20-18
💐
当記事、および企画で取り扱っている事件はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。
ケイケイTwitter
ケイケイInstagram
ケイケイYouTube
Yuki_Tsuyashima
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
