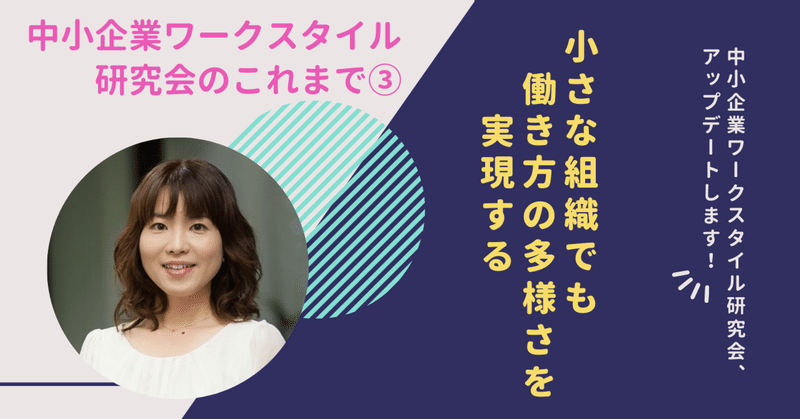
『会社を辞める人』は減らすことができますか?/中小企業ワークスタイル研究会のこれまで③
ちょうど10年前の2014年2月5日、サイボウズ株式会社ソーシャルコミュニケーション部(当時の部署、現在)に在籍しておられた渡辺清美さんにお越しいただき、中小企業ワークスタイル研究会のオープン講座を開催しました。
テーマは「ここが成功企業のターニングポイント!『会社を辞める人』って減らすことができますか?」
当時のサイボウズ株式会社は社員数488名、中小企業枠から少しずつ拡大中のフェーズでしたが、そこに至る前の組織の葛藤と変化についてお話をお聞きしました。
1.サイボウズ株式会社・渡辺清美さんをスピーカーにお呼びした理由
ArrowArrowは今まで中小企業とそこで働く人々と関わりながらさまざまなプロジェクトを進めてきましたが、そんな中で多くの課題にぶつかってきました。
「中小企業で女性が働き続けることは難しいでしょう」
「うちの会社は長時間労働が当たり前だから働き方は変わらないよ」
「現場では人がどんどん辞めてしまっているのに経営者にその問題が伝わらない」
企業にとって「これからのワーク・ライフ・バランス」の概念が「経営戦略」になっていく今、働く人と企業双方にとっての「働くこと」の最適解を見つけながら前進していくことは必須になってきています。
現場では社員が疲弊して辞めてしまっているのに、それを変えようとしない組織の状況が続くとしたら、個人が苦しいのは疑いようもありませんが、組織も結果的に持続可能ではなくなってしまい、双方苦しい状況に陥っていきます。
サイボウズ株式会社は「働く仲間がどんどん辞めていってしまう…
3年、5年たったら皆辞めてしまう…」と、一時は社員の1/3に近いほどが辞めてしまったという高い離職率が課題としてありました。
現在は離職率が1/7に低下、退職者がぐっと減り定着率が増えているという転換が起きています。
そしてそのような荒波の中で、妊娠・出産・子育てというライフイベントを迎えながら復職している渡辺さんからみた働き方の多様さや両立支援の状況について尋ねてみようと思いました。

サイボウズ株式会社が抱えていた課題をどのように解決していったか。その具体的な施策や働き方、そしてワーキングマザーでもある渡辺様から見た当事者の意識などから紐解いていきます。
2.会社を辞める人を減らすための施策①
渡辺さんのお話をお聞きしてサイボウズが離職率を少なくすることができたきっかけが見えました。
それは、まず社員の「離職した理由」をまっすぐに問いかけ、それを可視化していることでした。社員が辞めるきっかけは大きく6つあり、そのうちの3つが「ライフイベントに関すること」で、結婚・妊娠・出産ということが見えてきました。
そこで組織側は具体な両立支援に乗り出していきます。(以下2006年当時)
育児休業は最大6年間取得可能
男性、女性を問わない
妊娠が判明したらいつでも産休をスタート
これによって出産で辞める社員は0%になったとのこと。課題から施策を打ったことで結果をだしている状況が読み取れます。
3.会社を辞める人を減らすための施策②
「働き方を柔軟に」その言葉通りの施策として選択型人事制度を2007年から開始されています。ライフイベントに沿って働き方を変更できるための経路を3つ提示されていました。
PS2-ワーク重視型/時間に関係なく働く
PS-バランス型/少し残業して働く
DS-ライフ重視型/定時・短時間で働く
これによって離職率が4%にまで下がり、女性社員の比率がグンと高まりました。また、東日本大震災以降、全員在宅勤務で決算発表をおこなったことによって、場所を選ばずに働くことの実体験と難しさも模索していました。結果、社員同士の信頼関係構築にも力を注ぐプロセスがあったと渡辺さんが教えてくれました。
サイボウズの働き方としてその当時トピックスにあがっていて「ウルトラワーク」についてもシェアいただきました。2012年より、時間・場所の制限の有無を選べる働き方も本格導入に踏み切っています。

両立支援として組織から離れる選択肢だけではなく、働き方の多様さを選べるような仕組みを創造してきた過去を教えていただきました。
4.会社を辞める人を減らすための施策③
最後は組織内のマインドセットの話に繋がっていきました。
会社で働くにおいて説明責任・質問責任があるという考えでした。
気になることは質問をすること。
質問を受けた側は説明する必要があること。
一見当たり前に聞こえますが、自立と議論を生み出すために、社員同士が建設機に議論して問題を解決していこうとする土台作りに値しています。
「人事制度は会社から与えられるものじゃないんですよね」
渡辺さんははっきりとそう明言してくださいました。
説明責任・質問責任の考え方をもって社員が意見や提案をし、社内でワークショップを繰り返しながら草案を策定し、最終的に社長が意思決定するというプロセスがあるということでした。
必要なものを自分たちで創っていく、そのためには互いへの質問・互いへの説明を伴うことは当然であるというマインドを社内に行きわたらせている様子がうかがえました。
5. 会社のことを社員も一緒に考える
「会社を辞めていく人がいる=本人の選択だから」
確かにその考えも間違ってはいないかもしれません。
ただ、サイボウズ株式会社のこれまでをお聞きしてみると、その考えに辿り着くまでにはプロセスがあることが分かります。
課題にとことん向き合い、どうして辞めていってしまうのか、その理由を真正面から見つめる
回避できる課題があるならば組織が変わっていく
そのための施策を模索しながらトライしていく
これらの実践を繰り返しているからこそ、社員のマインドが自律し、組織の風土や文化が出来上がったからこそ、会社を辞めることについて、本人の選択だと捉えられるのかもしれません。
6.2024年の今、ふりかえって
現在のサイボウズ株式会社は1000人を超えるIT大企業として、「働き方」においてお名前を聞かない日はないくらいご活躍されている企業の印象を受けられる方が多いと思います。
10年前の当時に、サイボウズ株式会社の働き方の多様さをつくるにあたっての痛みや葛藤、そしてその変化の渦中に触れられる機会があったことを学びに受け取っております。
改めて、この度の場にご協力いただきましたサイボウズ株式会社・渡辺清美さんに御礼申し上げます。
最後にお知らせ
働き方の変化を生み出したい、創りたい....!そんな社会の変化が起こっていた最中から年数を経た今、「小さな組織の働き方を学び合うコミュニティ」として場を再構築していきます。皆さんと共に小さな組織の多様な働き方を、その挑戦や模索や継続を学び合える場所を創っていきたいと思います。
小さな組織の働き方を学び合うコミュニティ CAMPFIREコミュニティ (camp-fire.jp)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
