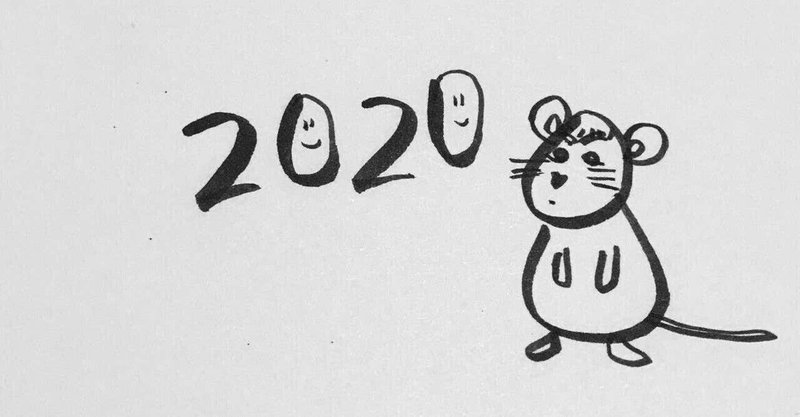
2020記事まとめ(2/5):汎用ビジネススキルのまとめ
みなさま、新年あけましておめでとうございます。
年が明けてしまいましたが、2020年の記事の総まとめの第二弾です。第二弾では、汎用ビジネススキル関係の記事をまとめておきます。
はじめに:アップルが書いてきたビジネススキル
記事に書いたことを振り返りながら括ってみると、大きく3つのテーマで書いてきたことがわかりました。
1.会議術
・会議の生産性を上げるための要諦やtips
・ファシリテーションやレビューで押さえるべきポイント
2.資料作成術
・そもそも資料作成において心得ておくべきこと
-資料作成がうまい人と下手な人の差はどこか?
・ストーリーラインを作る上でのノウハウ
-ストーリーのいくつかのパターン など
3.プロマネ術
・アップル自身の経験を踏まえたプロマネのコツ
この3つがビジネススキルをMECEに押さえているわけではありません。例えば、調査・情報収集もある程度汎用的なビジネススキルですが、アップルはそこにフォーカスした記事を現時点では書いていません。
ですが、この3つは、非定型業務(企画、マーケ、営業等)に従事するビジネスパーソンに共通して求められる重要なスキルであると思います。
以降、この3つのカテゴリでアップルが書いた記事をまとめておきますので、ぜひご覧の上参考にしていただければ幸いです!
1.会議術
日本の特に大企業は会議が下手くそなところが多いです。目的が曖昧だったり、やたらと時間はかかるが何も決まらない会議があふれています。一方で戦略ファームでは、「会議のお作法」が徹底され、それを全員が心得ているため、比較的有効な会議が行われています。
では、会議の生産性を上げるためには具体的にどうしたらよいのかという押さえるべきポイントやtipsをまとめたのがこちらの記事になります(前編、後編の2回にわたってまとめてあります)。
さて、会議の生産性を上げるために重要な存在が、ファシリテーターやレビュアーです。これらの役回りの人の力量がいかほどかによって、会議の生産性やアウトプットの質はとても大きく変わります。
まずファシリテーションか。社内外の会議のファシリテーションは戦略コンサルタントの重要な業務であり、腕の見せ所でもあります。議論を活性化させるために具体的にどのようなテクニックを駆使しているのかについてまとめたのがこちらのエントリーになります。
次にレビュー。会議に何らかのアウトプット(調査分析結果や、資料の素案)が持ち込まれたときには、それに対して適確にレビューすることが大事になります。戦略ファーム内でも、パートナーやマネージャーは日々メンバーのアウトプットをレビューしています。事業会社においても、管理職以上であれば部下の作成した資料に対してレビューする機会も多いでしょう。
レビュアーが本質を突かずに重箱の隅をつつくようなコメントばかりしていては、そのレビューの生産性は極めて低いと言わざるを得ません。往々にして、レビュアーの意識の低さが問題であることが多いため、レビュアーはどういう心構えでレビューしないといけないかということをこちらのエントリーにまとめました。
2.資料作成術
ビジネスパーソンであれば何らかの資料(報告資料や議論用資料)を日々作っています。総務、経理などの定型的な業務であれば、既に資料のひな型が決まっており、それを埋めるだけでよいかもしれませんが、経営企画、営業、マーケティング、技術開発など非定型業務の職種では、その時々の目的や説明相手に応じてわかりやすく説得力ある資料を作成する能力は極めて大事です。
資料を作る際の起点となるのが「ストーリー」です。パワーポイントで30枚くらいの資料を作る場合、その30枚をどういうお話の流れで組み立てるか。これを考えるのがストーリーづくりです。
ビジネスドキュメントのストーリーには、いくつかのパターンや型があります。これらを頭に入れておくことでストーリーを効率的に作ることができます。以下のエントリーに基本的な型をまとめました。
こうしたパターン・型をベースにストーリーの大きな構成を作った上で、それをより訴求力・説得力あるストーリーにブラッシュアップしていく必要があります。ここは暗黙知の世界なので、ともかくたくさんストーリーを書くことによって暗黙的にできるようになっていくものですが、鍵となる心構えは「徹底して相手目線に立つ」ということです。
相手目線に立った時、どういうストーリー展開で説明されると、理解が進むか?腹落ちするか?
このように相手にいわば「憑依」しながらストーリーを磨くのが大事であるということを、こちらのエントリーに書きました。
ストーリーが出来たらスライドライティングに進んでいきます。ここでポイントになるのは「いきなりパワポをさわらない」ということです。スライドの構成やアウトラインもイメージできていないのに、いきなりパワポで作業を始めるのは「負けパターン」です。結果的に1枚のスライドを作るのに時間がかかり、ひいては長時間労働になります。
上級者は、手書きとPC作業とをうまく組み合わせで資料を効率的に仕上げます。スライドの構成やアウトラインは手書きで作り、それを清書する段階になったらパワポで作業する。これがセオリーです。
こうしたアナログ(手書き)とデジタル(PC作業)の組み合わせは、漫画やアニメの作成プロセスと極めて類似しています。こちらの記事に、漫画とコンサルの資料作成の類似性と、踏まえた資料作成のセオリーについてまとめました。
これができないコンサルタントのことをアップルは「パワポ中毒者」と呼んでいます。残念ながら、パワポ中毒者は増加傾向にあります。コロナ禍でさらにデジタルデバイスへの依存度が高まっているため、今後パワポ中毒者はさらに増加する可能性があるでしょう。
こうした懸念をまとめたのがこちらの記事。戦略コンサルタントに限らず、事業会社で企画系の業務に携わる方は、資料作成において「パワポ中毒者」にならないことを意識されるのが大事ではないかと思います。
3.プロマネ術
戦略ファームの仕事は全てプロジェクトで遂行されます。そしてプロジェクトをリードするプロマネの力量がプロジェクトの成否を大きく左右します。
事業環境変化のスピードが高まる中、今後は事業会社でもプロジェクト形式の仕事(目的、期間、アウトプットを定めた仕事)が増えてくると思われます(実際に、クライアントとして接する大企業でも、様々なプロジェクトやタスクフォースが走っているのを見かけます)。
プロマネ力は、今後事業会社においても一つの重要なケイパビリティになっていくでしょう。
アップル自身数々のプロジェクトのプロマネをやってきました。その経験も踏まえたプロマネのコツについてこちらの記事にまとめています。
業務の中でプロマネをされている方、今後する可能性がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
以上、会議術、資料作成術、プロマネ術について関連記事をまとめてみました。
その他の記事も含め、こちらのマガジンに仕事術に関する記事をまとめていますので、興味のある方はご覧いただければと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
