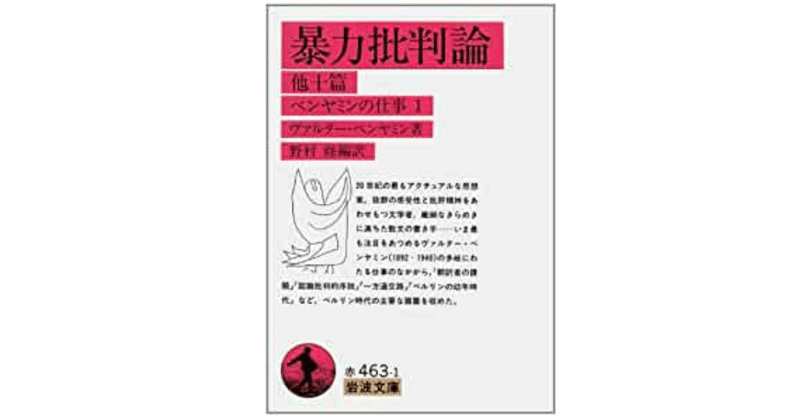
破滅のあとに天使が降りてきたコトバたち
『暴力批判論 他十篇: ベンヤミンの仕事 1 』ヴァルター ベンヤミン , 野村修 (編さん, 翻訳)(岩波文庫)
二○世紀の最もアクチュアルな思想家,抜群の感受性と批評精神をあわせもつ文学者,繊細なきらめきに満ちた散文の書き手……いま最も注目をあつめるヴァルター・ベンヤミン(一八九二―一九四〇)の多岐にわたる仕事のなかから「翻訳者の課題」「認識批判的序説」「一方通交路」「ベルリンの幼年時代」など,亡命以前の主要な諸篇を収める.
ベンヤミンの哲学的草稿からエッセイまでの11編の文章。一番好きなのは最後の『1900年前後のベルリン幼年時代』。これはプルースト『失われた時を求めて』のベンヤミン版だった。『翻訳者の課題』でドイツ語を翻訳語に逐語訳するのではなく、ドイツ語が翻訳語化する変革を促している。それはドイツを閉じられた精神とするのではなく開かれた世界に誘う試みだった。哲学から批評へ、さらにエッセイへと天使が降りてくるようなそんなベンヤミンのコトバたち。
運命と性格
アリストテレス『悲劇』によって理知的に運命づけられた性格の主人公は、悲劇から逃れ得ないのは、それが神によって運命づけられているからでも、主人公の性格によるものでもなく、始めから「悲劇」という枠内のストーリーに過ぎずその枠を超えれば「幸福」なのだろうと述べる。
奇しくもベンヤミンが被った運命を予感させるエッセイ(批評)だが、ユダヤ人がキリスト教徒から異教徒して運命づけられるから「悲劇」になるのであって、ユダヤ人的性格(ずる賢いとか一般的に言われるイメージ)は「悲劇」を形作る要素になりさえしても、その外へ出れば、例えばキリスト教世界の枠外に出れば違う運命を得られるのではないか?むしろそうした悲劇よりも、モリエールの喜劇に登場する愛されるべき人物に見られる行為の自由さを評価する。
運命が、罪を負わされた人格の複雑な縺れを、その罪と縺れの絡まりを、繰り広げて見せるとすれば、性格は、罪関連の中にある人格のこのような神話的隷属化に対して、ゲーニウスの答えを与える。複雑は簡明となり、宿命は自由となる。というのも、喜劇の人物のもつ性格は、決定論者によるこけおどしではなく、その人物の自由さを照らしだす灯台なのだから。
暴力批判論
暴力と、法と正義との関係をえがくこと。ここで暴力は、目的の領域ではなく手段の領域に見いだされる。暴力が手段だとすれば、暴力が正しい目的とされるものを問えばいいのである。
自然法の暴力は生存という正しい目的の為に(無闇に殺されるよりも抵抗するだろう)自明なことされている(法哲学一般の潮流)。
この自然法の暴力と対極にあるのが、歴史的暴力の中にある実定法だとする。実定法は目的の正しさよりは手段としての正しさ(国家権力や警察の暴力か?)を保証しようとする。ここでは「正義」の判断は除外して考察していく。
実定法はその枠内での根拠であって、枠外では適用されない。法的暴力は支配権力の無抵抗の現れとして服従や隷属を意味する。目的の欠如、ある特定の法的権力機関の手段でしかなく、外部の世界や自然法の原理からは外れる。
ヨーロッパ世界では個人の持つ権利主体の目的は法秩序の中で、個人の自然目的と対立する。大犯罪者が称賛されうるのは、個人の自然目的(欲望)と合致するので、大衆にとってはそれを制限する権力のアンチヒーローとなるのだ。
戦争権の可能性は、生存権の目的のためだが、略奪目的へと向かう矛盾である。原始状態に於いて、所有権を講和する儀式はどうしても必要なものである(カント『永遠平和のために』)。
死刑については、違法を罰するよりも新たな法を確立すること、それは法そのものを強化する。この暴力は警察権力の中で保存される。この非道さは、権力の代理人として警察の暴力が無法に許されてしまうからだ。議会がそれを取り締まれる保証はなく、議会の没落が独裁者の存在を許す。
紛争の非暴力な調停は可能だろうか?勿論可能だという。それは異文化が互いに手を結び合っていく交流姿を描く。人間の対立はものを媒介にすることによって和解を得られるのか?
翻訳者の課題
他文化の古典や死者と向き合うことで同世代や次世代に伝えようとしたこと、単に伝達ではなく、ベンヤミンと異文化(死者の文化も含む)との交流。この時期なのか『失われた時を求めて』の翻訳にかかわったのは。
翻訳は可能だとするが、ベンヤミンは原文に自国語を合わす逐語訳ではなく、むしろ自国語の方を原文によって変容させるような翻訳を望んでいた。それは、二葉亭四迷ら明治の文学者が外国語から日本語を変容させたような文学の力だった。聖書の翻訳は行間を読むことにある(逐語訳だけでは理解できないものがある)。ヘルダーリンの翻訳への批判は、ドイツ語の中に閉じ込められいるという。
「ドイツ語の諸翻訳は、最良のものすら、誤った原則から出発している。それはインド語やギリシア語や英語をドイツ語化しようとしていて、ドイツ語をインド語化・ギリシア語化・英語化しようとはしていない。それらは、多言語の精神にたいしてよりも、自身の言語習慣にたいして、畏敬を払いすぎている。」
暴力批判論』の頃はまだ哲学(啓蒙)ということに期待があったのだと思う。カント『永久平和のために』と同じような論理だ。ただ状況的にそれでは済まされないので文学に向かったのかと。
雑誌『新しい天使』の予告
実際にはこの雑誌は出版されなかったという。ベンヤミンが新しい雑誌に期待したのは新聞報道のような事実性だけではなく、アクチャリティということ。変容していく精神というものか?ドイツ語だけの創作だけではなく、翻訳に力を入れたいというような。世界的な同時代性。
天使は──毎瞬に新しく無数のむれをなして──創出され、神の前で讃歌をうたいおえると、存在をやめ、無の中に溶け込んでゆく。
認識批判的序説
『ドイツ哀悼劇の根源』の序論で非常に難解。フランクフルト大学に提出した教授資格論文だから難しいはずだ。結局、受理されなかった。ベンヤミン前期の思想の決算ということらしい。
今までアリストテレス『詩学』を批判しているのかと思っていたが、ドイツで翻訳された受容に対して、それがドイツ哀悼劇の擁護に使われたことに対して批判していた。だから、訳者である野村修は「悲劇」ではなく「哀悼劇」と訳している。悲劇だと単に物語だけど「哀悼劇」になると敬う感じなのか?
バロック古典にしてもシェイクスピアにしても批判の鋒先はドイツ語に変容させられたものに対しての批判。それが認識不足だった。そのぐらいはわかったんだけど、実際の中味は哲学論文だから難解。
一方通行路
大学教授になれなかったベンヤミンが生活の為に書いたエッセイ。エッセイでも難しい。路上観察日記のたぐいだがそこに思想性を込めるという後のパッサージュ論につながるのかもしれない。一方通行路と言っているように一方通行のようだ(読解力なくてすまん)。
シュルレアリスム
ベンヤミンのシュルレアリスム理解が表現されたのが『一方通行路』だと思う。思想的なものをサッとスケッチするような。フランスのシュルレアリスムのアクチュアルな描写。
ベルト・ブレヒト
ブレヒト劇讃歌のエッセイ。ブレヒトの登場人物のアンチヒーロー性について、悪人だけど反体制だから愛されるという。アメリカン・ニューシネマのアンチヒーロー像に近いのかな。日本だと清水次郎長とか任侠ヤクザの健さんとか。
破壊的性格
前述のアンチヒーロー像の内面的なエッセイ。
文学史と文芸学
文学評論の神学的な言い回しについて批判的であるような。ベンヤミンはやっぱ論理学(哲学)の人なんだと感じる。文学全般に述べるよりも個人の作家について論じよという。
1900年前後のベルリン幼年時代
ほとんどベンヤミンの『失われた時を求めて』だ。亡命生活からの内面への回想。ベンヤミンのブルジョアジーの時代の夢。プルースト的な回想文。エッセイ文学とも言えそうなベンヤミンの文章のなかではこれが一番良かった。「せむしの子供」は「新しい天使」の原風景。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
