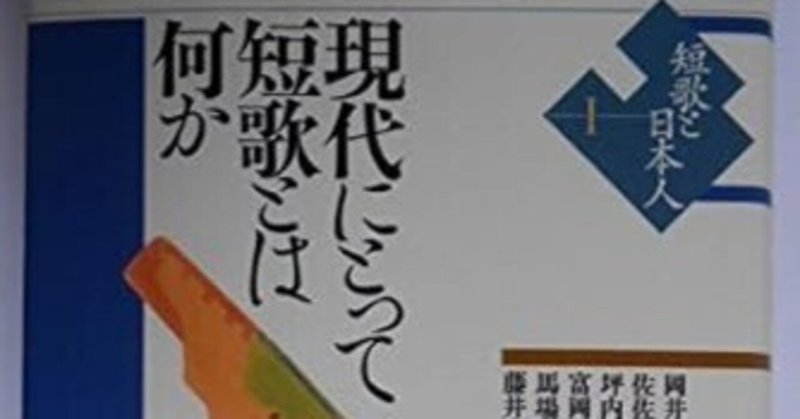
短歌にとってリズムとは何か
『短歌と日本人〈1〉現代にとって短歌とは何か』
日本語にとって短歌とは何か,日本人にとって短歌とは何か-日本文学史からあえて短歌という衣を引き剥がし,現代文化における短歌の重要性を探究する試み.全編集委員による共同討議と力作評論によって,短歌の発生からその展開,文学的意味,海外での受容に到るまで,縦横に短歌と日本人の問題を考え,短歌の本質に迫る.
目次
〈共同討議〉現代にとって短歌とは何か…全編集委員/
〈評論〉呪言から呪歌へ…谷川健一/
短歌と真言・陀羅尼…栗田勇/
拘束・リズム・散文…平出隆/
短歌の輪郭…小池光/
実用の言葉としての短歌…高柳蕗子
/田中綾/吉屋敬
和歌の呪術的な面と恋文のような相聞的な面は、ハレ(天皇の歌)とケ(恋文の歌)のように和歌の二面性を発展させていく。ハレ(公用的な)部分が強すぎると権力者に利用されたりもする。そして戦後に「第二芸術論」が出て和歌のリズムが奴隷の旋律と言われたりする中で、戦後は七五調のリズムをどう崩したりしていくかでモノローグ的な短歌も増えていくのだが、一方で俵万智が口語・句跨りという独自な短歌もブームになっていく。さらにそれはコピー化という経済にも利用されていく。
「日本語に取って短歌とは何か」
まだ短歌ブームの時代ではなく、俳句の方が勢力があったのかな。俵万智&穂村弘という2大スターが登場する以前の考察で、藤井貞和「日本語にとって短歌とはなにか」は、短歌史の外部からの振り返りだと思うが、ちょっと違っていた。
短歌の内輪化という今ある問題が出てこない。それは批評性の欠如だけど、例えば藤井貞和のこの批評では、沖縄の琉歌についての考察がなされているが、今はまったく忘却の彼方に追いやられているという。非日本語としての短歌はますます中央集権化されてきている。
その中で面白いと思ったのが文語を第二国語として捉え方るという。それがナショナルのものとして内輪での、例えば大学の短歌会とかで仲間の内輪言葉として存在する。その一方で口語短歌はますますコピーライト化して、アメリカナイズされた資本主義社会を形成している。そこで問題とされ良くない方向に進んでいるわけだった。
何よりも批評性の欠如で、経済至上主義の売れればいいという方向性と内輪化という保守的ナショナリズム的傾向が強い。今は短歌ブームであるから、そういう批評性も必要としないのかもしれない。またAIと短歌という問題も出てくるだろう。俳句の方はかなりAIに脅かされている感じだが。
佐佐木幸綱「日本人に取って短歌とは何か」
天皇の歌は読み方があり、そこに国見というような民にお告げというような。言霊で言えば庶民に知らしめる上から目線。また自然に対しては仰ぐような大きな歌を歌ったという。興味深い。そんな天皇もハレの歌ばかりではなくケの歌も歌うときは、女になって歌ったというのは始めて聞いた。
ハレとケということ。聖と俗。それで庶民が恋文とか詠むのはケになる(天皇が女として歌うのは恋の歌か?)。日本の短歌的な韻律は、「ハレとケ」とで考えるとわかりやすいという。
例えば桑原武夫が否定した「俳句第二芸術論」は、俳句よりも短歌の方で問題意識が強く、それは戦後公的な短歌(ハレの歌)を否定して、個人的な短歌(ケの歌)が詠まれていく。それがリズムの問題として、例えば七五調は奴隷の旋律と小野十三なんかが言ったのだ。
塚本邦雄などはそれを受けて句跨りで表現していく。戦後世代は七五調を崩して自身のリズムで読んでいくのだが、戦後短歌はその模索ということだったかもしれない。その中で、口語で句跨りを使ったのが俵万智だという。それは口語短歌は文語のリズムに合わないからだった。平安短歌でも実は句跨りが使われているのだが、それは口語的なものだったという。
だから公(ハレ)としての和歌と俗(ケ)としての和歌があり、短歌でもケの方が生き残った。俳句は和歌のハレの中にケを混じらせたので、最初から第二芸術論でけっこうだという主張がある。またそれは、俳句や短歌だけではなく、詩(近代詩)や小説の中にもある。ポイントは公的な言葉と私的な言葉の区別ということになるのか?
辞世の句などは、軍人も死刑囚も右翼も左翼も個を捨て公のために命を犠牲にするという歌が多い。俳句でも坪内稔典が「辞世の句」という死のパターンが面白いと思ったのだが、続けているうちにみな同じような句になるという。つまり個を消して自然に還るといような。
それは自己否定が仏教によってもたらされ、神道的な公と一体となる精神が否定されていくのは、仏教によってなのだ。そこで出家とか解脱とかなるのだが、人間何かに帰属してないのはやりきれないので死後の世界というものが出てくるとまた一緒になってしまうようだ。
それと日本人が和歌で文字を持たない人まで共通言語として五七調の型で上から下までコミュニケーションが出来たという。それが外国人が新聞投稿欄に短歌や俳句が掲載されるのが不思議で、一億総詩人なのかと疑問を呈したりするのは、外国では詩というのは極めてインテリ(知識が高い者)が詠むもので庶民は詩などは詠まないという。それは中世から日本では共通言語として貴族から卑俗まで歌を詠んだということらしい。
それで例えば白拍子などの芸能の人たちの存在、そうした歌(民謡的)なものが庶民から貴族まで伝えられたのだろう。それは仏教でも和讃という文字を読めないものでも節で覚えるとか、また芸能の歌が庶民に広まるとか七五調という定形は覚えるのに適していた。
それが鎌倉時代になって武士が出てくるとケの方は消されてハレの公ばかりになっていくという解釈もあるようだ。だから平安時代はハレとケが混じり合っていた。それは『源氏物語』でも一番ハレの歌を歌うのは光源氏なのだが、ケの女たちと共通言語として和歌が使われる。そして女で一番上手いのは明石の君だが、浮船などは最初は下手な詠み手だったが、最後は素晴らしい歌を残す。そのように階級が下のものでも和歌に通じるということが出来る。
最近の短歌は自己批評がなくてまた公的な翼賛体制になりはしないかというのが、富岡多恵子の俵万智批判だった。俵万智は佐佐木幸綱の教え子だった。だから短歌の知識があり、それを上手く口語で宝塚のようなファンタジーを少女漫画のように作ったということなのだろう。教師というのもある。
呪言から呪歌へ(「言問ふ」世界へ)
自然や動物を擬人化して語るのは『ユーカラ』でも見られたが、それは元々日本人の中にもあったものであるとする。例えば火を見てそれを火の舌とか言うとか風が悪さをするとか。
「呪言」とはそうした擬人化した自然を沈めるために使うまじないの言葉でアニメ『呪術廻戦』はそれを現代風に拡大した話なのである。『万葉集』は日本に天皇中心の律令国家が形成される過程を描いた和歌集で、まだ地方部族らの「呪言」や巫女的な葬送の晩歌などにその傾向が見られる。柿本人麻呂はそういう役割を担った歌人であったとされ、貴族だけではなくそれ以外の事故死した者たちにも歌を捧げていたりしている。
和歌がそうした呪言から呪歌へと辿っていく中で言問ひ歌(歌垣)などはお互いに歌でもって戦い屈服させていたものと言われている。そこで呪言が言霊となって作用していくのが民謡から和歌に伝えられていく。例えば巫女的な歌人が天皇の代わり和歌を読み行動を決めていく。持統天皇は、天武天皇が亡き後に夢見で占って(言問ひ)天皇になったという。まだ巫女的なものが残っていた姿だという。
短歌とリズム
平出隆「拘束・リズム・散文」、小池光「短歌の輪郭」は短歌によるリズム論で、桑原武夫「第二芸術」論から小野十三「奴隷の韻律」を受けて戦後の短歌では七五調に従属しないで短歌を詠む前衛短歌運動なのどが起きた。
小池光「短歌の輪郭」はその分析をしている。例えば「万葉集」にある人麻呂の石見相聞歌にある長歌の息苦しさについて、通常の五七調は五音と七音の間に一泊空白(ブレス)が入ることで楽に読めるのだ。
人麻呂の五七調は十二音で一つのセンテンスを作っていき、空白が入るのは五音の先頭であり、それはそこで溜めて一気に吐き出すというような緊張を強いられるリズムだという。十二音は人が一気に言葉を吐き出す限界であり、通常は五音と七音の間にブレスすることで楽に長歌が発生出来ているとする。それで五七調は延々に繋がっていくのだが、終わりを七七で繰り返すことによって打ち止めにするという和歌のリズム論はわかりやすい。
またそれは反歌として、前の長歌に対する相聞として短歌が存在するのだという。短歌の元にある相聞性はそういうことだった。
その短歌のリズムを見ていくと歌人が様々な試みをしていたことがわかるという。
数学のつもりになりて考へしに五目ならべに勝ちにけるかも 斎藤茂吉
普通に見ればタダゴト歌なのだが、「考えしに」が字余りになり、そこで中断される。「考えし」で五音だと下の句に流れるようなリズムでそれこどタタゴト歌なのだが、上句と下句を繋ぐところで考える時間の「に」があることによって熟考した結果五目ならべに勝ったという句なのである。字余りの上手い使い方だという。
醫師は安樂死を語れども逆光の自轉車屋の宙吊りの自轉車 塚本邦雄
この歌も通常の短歌のリズムではなく、句跨りに始まって、後半のリフレインは非シンメトリー(同一ではない)構造を自然のリズムではなく、あえて人工的に崩しているのだ。
ホメロスを読まばや春の潮騒のとどろく窓ゆ光あつめて 岡井隆
二句目の七音は断絶させる句割れを使っている。その句割れが下の句で統一された美を見出すという。
晩夏光おとろへし夕 酢は立てり一本の壜の中にて 葛原妙子
3句目がまるまる欠損しているのだが、空白から一気に下の句を読み上げる。
大鉢を引き摺りにつつ薔薇の繁りを連れて敷き瓦のところにきたり 森岡貞香
五七七九七というリズムで詠んでいる。そのように戦後短歌はリズムに対して敏感に反応していたのだ。その成果として俵万智の口語短歌があるのだった。
「嫁さんになれよ」だなんてカンチューハイ二本で言ってしまっていいの 俵万智
しかし、それは短歌のコピー化という経済戦略として短歌が売れるということを証明したのだった。そこから短歌のCM化のようなものが出始めて今日に至る。
平出隆は現代詩から定形詩(俳句・短歌)を論じる。
その昔、定形の短歌や俳句に対して自由詩と言っていたのは定形にこだわらなかったからだ。ただその枷をはずして本当に自由に表現できるのかというそうでもないと言う。自由詩には自由詩なりの枷があるのだ。それは現代性ということなのか?今では現代詩と呼ばれていたりする。短歌でも俳句でも現代のものであるのに、なにゆえ詩だけがそうなのか?やっぱそこにモダニズムの問題があるのではないか?
芥川龍之介は、古典の韻文はその詩形が存在していて、古典の詩を読むことはその韻文の詩形を呼び覚ますことであるから興味深く、さらにそれを新たに目覚めさせることはなおさらである、というようなことを言っている。芥川の文学が古典から近代文学を照らしたものだからだろうか?また芥川は俳句にも興味を示した。
その一方、詩人の側から萩原朔太郎は『詩の原理』でポー『詩論』に影響を受けて西欧の象徴詩であるボードレールやヴァレリーから多く得ようとしていた。
「三種の詩器」という言葉があるという。「詩」「俳句」「短歌」の敷居が語られて、それらの断絶が言われる。吉本隆明はその断絶を、単なる差異ではなく近代の断層(モダニズム問題か?)と見た。このへんは吉本の「言語にとって美とはなにか」とか詩論に詳しいと思うのだが忘れてしまった。日本人論でもあるのかな?これは課題ということで先に進む。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
