あとがき/雨月日記
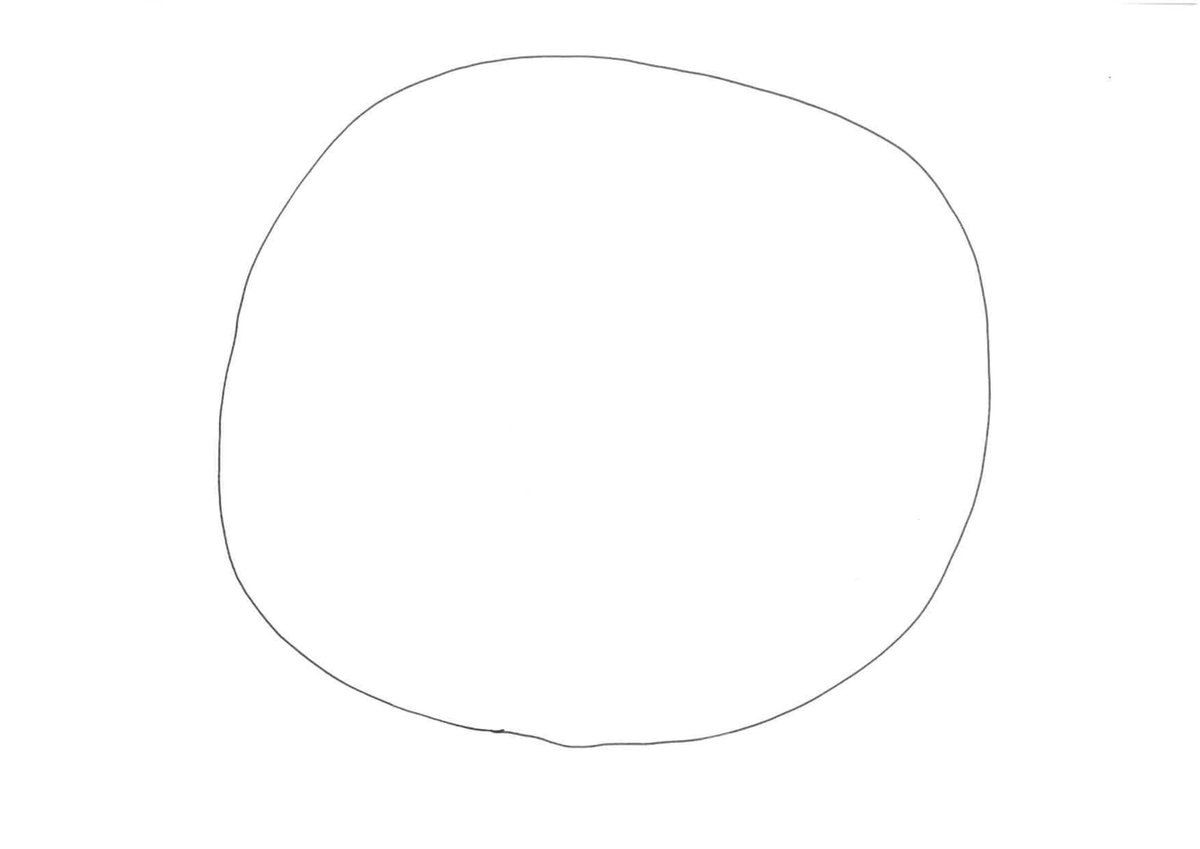
あとがき
梅雨の間に詩文集を出すなどと気まぐれのように思い付いたのが、六月二十五日のこと。体感的な暦の上では、もう梅雨も終わって欲しい時期になっていたのに、詩文集を編むという、日常生活においてあんまり大それたことでもない事の不言実行の為に、梅雨がいつまでも終わらずのびのびに伸びて、季節を征服してしまえば良いと思ったりもした。けれども、それではいつまでも夏が来ないじゃないか、と気付いて最初に書いた「序文」の三行目に差しかかったぐらいで、その思想を捨てた。結局、胃腸風邪をこじらせたりで梅雨は過ぎてしまい、何としてでもと意気込む前に締切りは行ってしまった。今更ながら振り返れば、識者には読んでも、損得もない集になってしまったかもしれない。ただ、こんな言葉のままごとが、奇妙な魔法のような意味合いを持つこともあるのだということを、今更ながら胸の中で思ってもらえたら、僕としては幸いなのかもしれない。人間の言葉というのは、特に日本語ではその機微が、その人の感情だったり性格だったり威厳だったりを決めてしまう。それは気付かなければ気付かない内に、相手の心に、長引くいやな風邪のように、なんとなく残り続けるものだ。僕はそういったレッテルを貼られることがいやなので、なんとなく色んな方向から見た、ある意味でうそっぱちの、多色な言葉で自分の意見の帳尻を合わせてしまう。人間が他種にはない『言葉』を進化させてきたことの思いがけない弊害ではあるが、人間として生きていきたいならば、それを捨てることは出来ない。まったく、いつまで経っても僕たちは、言葉に捕われ縛られ続け、それを捨てない限りは人間であり続けなければいけないのか。詩人は言葉で戦う人間であり、言葉で逃げる人間である。僕は、この詩文集で後者の方法を取った。言うまでもなくそれは、逃走による戦争なのだということを、少なくともこの未熟な駄文集に最後まで付き合ってくれた、識者の貴方には、何となく知っておいて欲しいことなのである。梅雨の終わりはMojitoの良く似合う季節である。と僕は、幼馴染みの恋人にふとした時に教えてもらったが、それだから僕はMojitoを飲みながら、このあとがきを書いている。これを飲み終わることで、僕の詩文集と、僕の陰鬱な梅雨の季節とをお終いにしてしまいたい。よって、これを書き終える瞬間から僕は、新しい顔をして生きていってしまいたい。ここまで付き合ってくれた識者を、置いてけぼりにしていくような気がしなくもないが、そもそも、気分が悪くなったので吐き出したいのだ、と言わさしてもらった。それで勘弁してもらいたい。ただ、僕は明日からその顔で街を歩くのだが、つまりは、書いてしまったとそういう顔で歩いているのだから、識者の貴方も僕の詩文集を読んでしまったとそういう顔をして、街を歩いていて欲しい。それに気付いたら僕は、すれ違った後にためらってから、貴方の肩を叩いてみたいと思っている。そうしたら、被っていた帽子で顔を隠しながら「やあ、こんにちは…。」と言うから、その後に出来れば、喫茶店にでも連れ立って欲しいとそう思っている。
二〇一二年 夏
青田宗助

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
