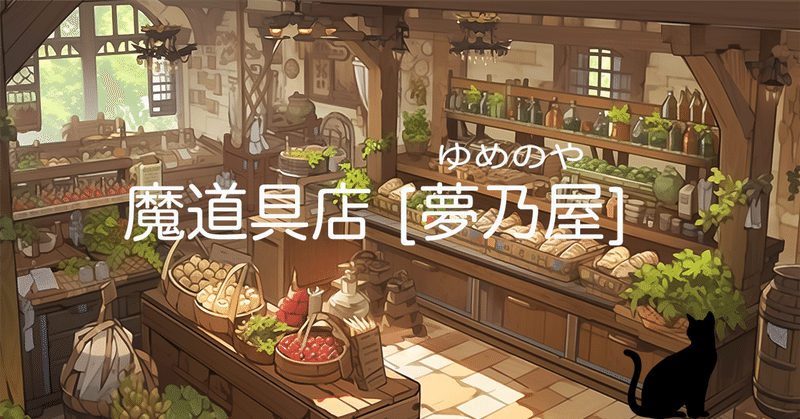
No,3「伯爵様ご来店」
営業初日の午後、ドアベルの音が響くと同時に私は椅子から飛び上がっていた。
初めてのお客様だ。
「い、いらっしゃいませ!」
緊張している私とは裏腹に、その人は静かなゆったりとした足取りでカウンターに歩み寄ってきた。グレイのスーツを上品に着こなしているインテリっぽい感じの男性だ。年齢は私の父親と同じぐらいだろうか。有名私大の教授か、上場企業の管理職か。こめかみから側頭部にかけて髪に少しばかり白いものが混じっているけど、なぜかそれすらも上品に見える。
店内を見回すようすもなく慣れた雰囲気だから常連客かもしれないと思っていたら案の定、私が何か言うより先に、隣にいたクロが挨拶と共にうやうやしく頭を垂れた。
「これは伯爵、ようこそおいでくださいました」
「久方ぶりだね。息災で何よりだ」
猫がしゃべってもノーリアクション。やっぱり常連さんだ。
だとしても、お客さんをあだ名で呼ぶなんてと思ったけど、言葉遣いが上流階級の人っぽいので伯爵という呼び名は確かにピッタリかもしれない。
「実は昨日、店主が代替わりいたしまして」
「ああ、聞いているよ。風の噂でね。彼女はまた旅に出たのだろう?」
「はい」
またってことは、あのマダムよっぽど旅行好きなのね。
「しかし、こんなに若くて可愛らしいお嬢さんが後継ぎとは驚いた」
紳士がカウンター越しに私を見つめて、にこりと微笑んだ。
途端にピンと背筋が伸びる。
「は、初めまして! 雫川と申します。あの……未熟者ですが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」
「はは、堅苦しい挨拶はいいよ」
「……どうも」
容姿に関してはもちろんお世辞だと分かっているけど、やっぱり初対面の人に言われるとそれなりに嬉しい。それに何より、怖くない人でよかった。本当によかった。物腰が落ち着いているし、ちゃんとした普通の人だ。最初のお客さんがこういう人で助かったと、ほっと胸を撫で下ろす。
「ところで伯爵、本日はどういったご用件で?」
「うん、実はね」
クロの問いかけに小さく笑みを浮かべた紳士は懐に右手を差し入れ、何かを取り出すと、私に向かってスッと拳を突き出してきた。
「これを買い取ってもらえないかと思って」
「えっ? あっ……」
思わずこちらもつられてカウンター越しに両手を差し出し、ぽとりと落とされた物を手のひらで受け止める。それは澄んだ青紫色の美しい石だった。
「わぁ、とってもきれいな石ですね」
「そうだろう? 我が領地で新たな鉱脈が見つかったのでね。採掘地から掘り出したばかりの魔石だ。こちらで価値を見極めてもらえるとありがたい」
(魔石ってつまり、パワーストーンのことかな? どことなくアメジストっぽいけど)
アメジストの実物を見たことがないので宝石については何も断言できないけど、普通とは明らかに違う点が一つ。
(なんか、これ…………光ってる、よね)
比喩ではなく、石そのものが淡く光を放っている。
すごくきれいだけど、やっぱりコレは普通じゃない気がする。
「お、お預かりします」
私はやや引きつりながらも、何とか笑みを浮かべて初めての接客を行うことにした。
買い取りの場合、まず店主が品物を預かってカウンターに置く。すると内容に合った金額が表示されるらしい。それをお客様に伝えて、オーケーならそのまま買い取りになるという話なんだけど。
(でも金額の表示ってどこに!?)
カウンターの天板は木目がきれいな一枚板で、幅およそ240cm、奥行き70cm。表面はツヤツヤピカピカ。もちろん板の上はきれいに片付いていて、秤とか鑑定道具らしき物も一切置いていない。
仕方がないので、傷つけないように注意しながら、ひとまず預かった石をカウンターの中央にそっと置いてみた。すると驚いたことに、デジタルのキッチンスケールに載せたときみたいに、たちまちカウンターの木目の上に数字が表れたのだ。0という数字が。
「えーと…………ゼロと表示されています」
金額0円。
これって、言って大丈夫なやつ?
「ふむ」
「あ、あのっ……すみません! もしかすると私が何か間違えたのかも」
「それでは、今度はこちらを」
紳士は別段不機嫌になることなく石を懐にしまうと、もう一つ別の石を取り出した。
今度は先程よりもやや小粒で、色も濃く、どちらかというと紺色に近い感じかもしれない。瑠璃色というやつだろうか。ラピスラズリを思い出す色合いだけど、これも普通の石と違って内側からうっすら淡く光っているように見える。
「は、はい」
その石も受け取ってカウンターに載せた。
現れた数字は――――
「……80万、です」
(高っっっ!!!)
ラピスラズリってそんなに高くない石だと思うんだけど、本当に大丈夫なのかなと不安になってくる。紳士はというと、当然、今度は満足そうに頷いた。
「うん、いいだろう。買い取りをお願いする」
「は、はい」
私は事前にクロに聞いていた通り、まずはカウンターの下に設置されている金庫の扉を開けた。その中に買い取り品の石を納めて、一旦扉を閉める。
(1、2、3……)
5つ数えてから再び扉を開けるとアラ不思議、中に入れたはずの石は消えていて、代わりにずっしりと中身の詰まった革の袋が入っていた。それを取り出し、お客様に手渡す。
「どうぞ、お確かめください」
中身をチラリと覗いた紳士が、確かに、と答えた。
どう考えても札束が入っている感触じゃなかったので、どこかの世界の金貨が入っているんでしょうかね。今さらツッコミませんけど。自動換金システム完備か!?
「ありがとう。では、今日はこれで失礼するよ」
立ち去ろうとする客の背中をクロが呼び止める。
「伯爵、新しい店主を試しましたね」
その言葉に再び足を止めた紳士は、振り向くとニヤリと目を細め、大きく口角を持ち上げた。一瞬にして、まるで別人のような冷徹な気配を纏わせて。
――――否、穏やかな紳士の仮面がわずかに外れて、その内側を垣間見たような……
ぞくりと背筋に悪寒が走った。
「なぁに、そう大層なことでもあるまい。ほんの挨拶代わりだよ」
「それで? お眼鏡に適いましたか?」
「ああ」
「では、またのお越しをお待ちしております」
「うむ」
クロとの意味深な会話の後、紳士は入ってきたときと同様、ゆったりとした足取りで店を出ていった。最後まで紳士然とした態度のまま。
「……試したって、私を?」
「うん。この店の主に相応しいかどうか、採点しに来たってところじゃないかな」
「最後ちょっと怖い感じの笑顔だったんだけど……どういう人?」
「伯爵様だよ」
「だから、それはあだ名でしょ?」
「まさか。お客様をあだ名で呼ぶわけないじゃないか。正式な階級だよ。魔王軍の団長を務めているビフロンス伯爵」
「…………まおうぐん?」
「そう、魔王軍の団長。とても厳しくて怖い存在ではあるんだけど、薬草とか石に関する知識が豊富で、昔からこの店のお得意様なんだ。新しい薬品の開発とかに使用する魔道具なんかもよく購入されているから、一度帳簿を覗いておくといいかもね」
「…………はぁ」
ダメだ、脳がバグって受け付けない。無理。
ファンタジーノベルズはあんまり読んだことがないのよ、私。転生もしてないし。
「あのさ。昔からってクロ……今、何歳なの?」
とりあえず真っ先に浮かんだ疑問点をぶつけてみる。
確か動物病院で診てもらったときは、生まれて半年ぐらいって聞いたはずなんだけど。
「さあ? 何年生きてるかなんて、もう忘れちゃったよ」
「……そう」
まぁ人間と会話してる段階で普通の猫とは違うんだから、それもそうか。
「でもボクに名前をつけた店主はキミが二人目だよ」
それは果たして良いことなのか、悪いことなのか。
全然分からん。
「ここには各界からいろいろな立場のお客様が来店されるけど、基本的には店主には何もしない決まりになっているし、そもそも店内でキミに危害を加えることは不可能だから、琴音は何も心配しなくていいよ」
「それはどうも」
店内に限定してるってことは一歩店の外に出たら危険な相手もいるってことですかねとか、各界ってどこらへんですかとか、そもそもお客さんに普通の人間っているのとか、新たな疑問や不安が次々に浮かんできてぐるぐるしている私に、クロはさらりと付け足した。
ただまぁ、さっきみたいに少しばかり試されることはあるかもしれないけど、と。
(なんか……不穏な響き……)
「試されるって、さっきもそれ言ってたけど、私は何をどう試されたの?」
尋ねると、クロはスッと姿勢を正して厳かに告げた。
「この店の主たる資質――――それは、魔に惑わされないことだ。初めてこの店に来たとき、キミにそう教えただろう?」
そうだ。確か、クロはこう言ったのだ。私がピッタリの人材だと。
『この店ではさまざまな魔道具を扱うからね。よほど強い魔力の持ち主か、あるいはどんな魔法にもまったく影響を受けない魔力ゼロのまっさらな人間か。そのどちらかしかできないんだ』
「うん。私は魔力ゼロで影響を受けないってことだったよね」
それはごくごく普通のことのような気がするんですけど。
クロは違うと言う。
「キミたちは知らないだろうけど、多くの人間は日頃から天界や魔界の影響を少しずつ受けているんだ。鋭敏な感覚の持ち主は無意識にそれをキャッチしていたりするし、欲望や嫉妬、疑念、不安などが小さな魔を呼び寄せたりもする。特別な人間じゃなくても。いや、むしろ普通の人間の方が影響は受けやすいだろうね。だからキミたちはよく『魔が差す』という言葉を使うじゃないか」
「なるほど」
「ひとくちに魔道具と言っても用途はさまざまなんだ。祈祷や召喚のための品もあれば、呪詛に用いる物、護身用、退魔用。お守り程度の代物から武器として使用可能な逸品まで、ランクも多岐にわたっている。そういう品が集まっている場所では影響力も大きいからね。惑わされやすい人はすぐに自分を見失ってしまう」
そう聞くと、なんだか恐ろしいな。
私は軽くこめかみを押さえた。
「魔石ってパワーストーンのことかと思ってたわ。ネットでそう表現しているのを見かけたことあるし。魔道具っていうのも、単に占いとかおまじないに使うような物だと思ってたんだけど……」
「人が、人のために造っている物はだいたいそうだよ」
「…………」
人ではないものが、人ではないもののために造る道具もある、と?
私は店内の品々に視線を移して、長く、ゆっくり息を吐き出した。
まぁ確かに魔王軍を率いる伯爵とやらに、占いやおまじないの道具は必要なさそうだ。
あまりにも現実味がなさすぎてピンとこない内容ばっかりだったけど、ようやくじわじわ怖さが出てきましたよ。
けれど、クロは頓着せずに話を続ける。
「伯爵が最初に見せた石には人を惑わす呪いが掛けてあったんだ。石そのものは普通の宝石だったけど、伯爵が魔力を込めて作ったんだと思う。普通の人間だったら、目にした瞬間クラッときちゃったかもしれない」
「そういえばどこかの国に、持ち主が次々に不幸に見舞われることで有名な宝石があったような」
「それは余程強力な呪詛がかかっているんだろうね」
「しかも不吉なことで有名なのに、めちゃくちゃ高額だったはず」
「不幸になると分かっていても、魅入られてしまった者はそれを手に入れたいと願ってしまうんだよ」
「じゃあ私がさっきの石に惑わされていたら不幸まっしぐらだったわけね」
「そうだね。だから、そうならない人材を選んだ。それがキミだよ、琴音」
「……それは、どうも」
ありがたいのか、ちっともありがたくないのか。
なんかもう訳が分かんなくなってきた。
「この仕事、勤まるかな」
ぽつりと漏らしたつぶやきに、大丈夫だよとクロが事もなげに返した。
よろしければサポートお願いいたします。いただいたサポートはありがたくリラックスタイムのコーヒーに使わせていただき、今後も創作活動を頑張る原動力といたします。

