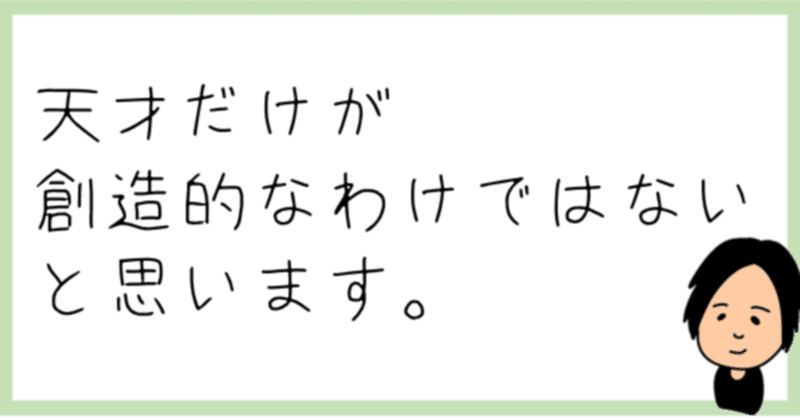
創造性ってなんすか?
この記事は創造性について知りたい方におすすめです!
こんちは、あおきです。先ほどNewsPicksを見ていたらこんな記事が。
先行き不透明で不安にもなりますし、どう動いたらいいかわからなくて、動きが鈍ったりすることがあると思います。この記事の中では、そんなときに、創造性(クリエイティビティ)が重要と述べられていました。
思考法については最近考えを怠ってましたので、今日は、創造性について考えていきたいと思います(ノリで言ったはいいが、いけるか?あおき笑)。
創造性のイメージ
みなさんは創造性と聞いて、どんなものをイメージしますか??
ピカソの芸術作品を見たり、近代アートを見たりするときに、創造性を感じたりしますよね。このような創造性の側面はたしかにあって、成果物から逆算して創造的かどうかを判断しています。それから、ピカソのような人は「卓越した創造性」を持つ側に分類されます(そのほか、ダーウィンとか、アインシュタイン、フロイトとかもこの分類に入るようです)。
こう考えると、創造性って天才的な発明とか発想をするものにだけあるようにも見えます。経済産業省の定義だと、「新しい価値を生み出す力」と言われているようで、研究の世界だと独自性や新奇性と言われている次元です。
普段使いの創造性
あおきに限って言うと、天才でもないし、新しいすごい物作れるわけでもないし、なにかとても秀でているものもないですが、凡人=創造性がないわけではありません。というのも、「卓越した創造性」だけが創造性なのではなく、「普段使いの創造性」(誰しもがもちうる創造性であり、その能力値が人によって異なる)というのもあるためです。ここからは、天才的な創造性ではなく、誰しもが持つ創造性について考えていきますね。
創造性のプロセス
創造性と聞くとあまりに大きくて対応しきれないので、そういうときには細切れにして、考えていきましょう。いくつか有名な心理学者(だと思う)の定義を挙げていきます。
問題や知識とのギャップを感知し、仮説または命題を開発し、仮説検証し、最終的に結果を共有するプロセス(トーランス,1977)。
問題への感受性、流暢さ、柔軟性、独創性、合成、分析、再編成または再定義、複雑さおよび評価を含む創造性の変化を解釈するための要因(ギルフォード,1955)
拡散的思考が創造的思考と関連している(ギルフォード,1975)
言いたいことはよくわかりますよ。心理学の言葉ってマジで難しいんすよ…。これから必死で読み解いていきま…(いけるか?)。
①拡散的思考
思考法は大きく分けて2つあり、拡散的思考と収束的思考というのがあります。収束的思考というのは、手持ちの情報から1つの答えをみちびく思考方法で、じゃがいも、にんじん、豚バラ肉、カレー粉がある状況で、夜ご飯はカレーにしよう!というような思考法です(これについては後日の記事)。
反対に、拡散的思考が創造性と関連していて、情報を様々な方向性に巡らせ、新しいアイディアを生み出す思考方法です。晩ご飯何食べようかなあ、焼き肉もええな、お寿司もいいな、しゃぶしゃぶもいいな、いや、外食するか、バーベキューするか、カレー食うか、そもそも食べない?、北海道いってジンギスカン食べちゃう?みたいに色々な発想を出していきます。
②ワラスの創造性のプロセスモデル
ワラス(1924)では、創造性を4つの段階で説明しました。
準備 → あたため(孵化) → ひらめき(啓示) → 検証
簡単に言うと、なんらかの課題についてのアイデアを出すときに、アイデアに対しての情報を集め、時間を置いたあとにひらめきが起こって、そのひらめきについて実際にやってみて仮説検証するというのが創造性の過程であるというものです。
準備は、なんらかのアイデアに対する情報収集したり、過去の経験や知識と照らし合わせて、考える段階です。同じ視点だけではなく、いろいろな角度からそのことについて検討して、新しい着想はないかなど色々な角度から考えます。拡散的思考がとくに生きてくるのは個々の段階です。
あたため (incubation)は、準備段階で考えていると、だんだん煮詰まってきますよね(あたまのなかスパークする感じになる)。そんなときに気分転換しようーとかなんかちがうことしよーってしているときです。あおきは休日は、このあたためを目的として、リフレッシュして温泉行って、うまいもん食って、お酒飲んであたためしてます(遊びたくて遊んでるわけじゃないんですよ)。
ひらめき (illumination)は、アイデアがふっと出てくる瞬間です。わたしの場合は、家でボケーっとしてるときとか、それこそお風呂に入ってるときとかにふっとアイデアがわいてきます。そのことについて考えているときは全然思いつかないんすけど、ほかのことをしてるときにひらめきってでてきやすいんですね(なんかトイレで便器に座ってるときにいろいろとおもいつくのはなんなんだろか…)。
検証 (verification)についてはまた後日!(めんどくさくなったわけじゃないよ)
まとめるとこんな感じ!

あおきの小言
ここからはエビデンスもなにもなくて、ただわたしが思うことです。
こういう創造性とか発散的思考って、本来みんな持ってるものだと思うんですよ。ただ、周りに同調したり、意見を制される経験とか、これが正しいって教え込まれたりすると、思っていても言えないってことになると思うんすよね。いま考えていることって、ひととはもしかしたらちがうかもしれないけど、間違ったことじゃないと思うし、あなたらしくかんがえられることのほうがわたしはだいじだと思います。否定されても、バカにされても、それでいいと思う。あなたがあなたらしくかんがえられることのほうが、バカにされずに生きることよりもよっぽどだいじだと思います。
アイデアはたくさんあったほうがいいです。1つの方法に決め打ちしていたら、あたらしいことはできないし、より良いものなんてできないっす。そこで、次回は、アイデアをたくさん出すための練習や経験方法について考えていきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
