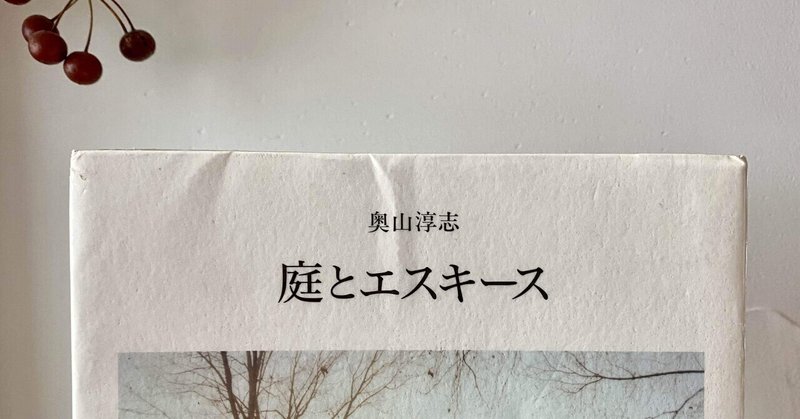
写真を撮る人が書く文章 「庭とエスキース」奥山淳志
「庭とエスキース」という本を図書館で借りて読んでいる。
借りる期限を何度か更新してもまだ読み終えることができていない。ひとつの章を読み終えては本を閉じ、余韻の中に佇む時間が必要だからだ。
本屋に平置きされた表紙をみて惹かれたのが最初だった。
どこかの冬の森だろうか。逆光に浮かぶ葉を落とした木々と、落ち葉の上に佇む狼のような犬のシルエット。光とそこに存在しているものの境界があいまいで美しかった。本のジャケ買い?には自信がある。この本もきっと間違いないと確信を持ったけど値段をみて躊躇。(←スイマセン...)
この場合の選択は図書館一択となる。帰ってから早速図書館サイトで取り寄せの申し込みをした。
この本は、奥山淳志さんという写真家が、北海道の原野に自給自足を目指した生活を送り、独り丸太小屋で暮らす”弁造さん”という老人と出会い、彼が亡くなるまでの十四年間を撮り続けた記録の随想だ。
詳しい本の内容についてはこれから読まれる方もいらっしゃるので割愛するが、私がこの本で深く感化を受けているのは、写真を撮る人が持つ、「観る視線」の奥深さについてだ。加えて奥山さんが綴る文章が素晴らしく、書くことを学びたいと思っている私に様々な刺激を与えてくれる。
偉そうなことを言っているが、私は写真についても、文章についても素人だ。でも結局、素人が何を受け取ったかっていうのが直球の感想になるのではないか。そう思ってこの本について思う事を書いている。
***
写真家の人は一枚の写真のため、大切にシャッターを押すのだろう。
iPhoneメモリのギリギリまで撮りまくる私とは次元が違う。こういう写真を前にすると、私は記録したことに安堵してその場で感じる事を、考える事をしていないのだと思い知る。
奥山さんが撮った写真からは、その場を包んでいた空気や思想、写真家が受け取つた全てをすくった跡のようなものが伝わって来る。写真家としてこちら側に立っていた奥山さんの存在も見える。そして、奥山さんはその「場」のことを言葉にする能力もお持ちだ。
写真家が情景を綴る言葉は、透過する光まで目の前に浮かび上がらせる。文章を読んでから、丁度その場面と思われる写真をみる。すると最初に写真だけを見た時には、私が数々の情景を見落としていた事に気づいた。
奥山さんが撮りたいと思った全体像が奥行きを持って迫ってくる。
ああこれは写真家の目のままなのだと何度も感じ入った。
弁造さんが何らかの覚悟を抱いて、震える指でキャンバスに向かう情景がある。それは私に自分の祖父の姿を思い起こさせた。
私にも、逆光の中で老いた背中がキャンバスに向かう姿をみた記憶がある。自分の祖父も同じように、体の自由がきかなくなるまで頑なに独りで暮らし、孤独の中キャンバスに向かっていた。
覚えておきたいと思ってそのことをnoteの記事にも書いた。
書けるだけ、思い出すだせるだけ向き合って書いたつもりだったけれど、「庭とエスキース」を読み進めていくと、それだけじゃなかったなと気づく。本から目を離して立ち止まる事で、あの時祖父の陰の周りに埃のようなものが舞っていたことを思い出したりもする。
それに私は当時、祖父を包んでいた空気や、キャンバスに向かわせた祖父の意志のようなものまで、受け取っていたはずなのだ。
それを言葉にできていない。自分が文章を書きながら、目の奥で見ていた光景を言葉にしていないのだと。
奥山さんが書く弁造さんの描写は、こんな風にして私をいちいち立ち止まらせる。想起させる文章の力を考えずにいられない。
私も、観て捉えたい。そして書いてみたい。そんな欲が湧いて来る。
庭とエスキース以外にも、また別の写真家が書いた名エッセイがある。それはまた別の機会に感想を書いてみたい。
興味をもって下さり有難うございます!サポート頂けたら嬉しいです。 頂いたサポートは、執筆を勉強していく為や子供の書籍購入に使わせて頂きます。
