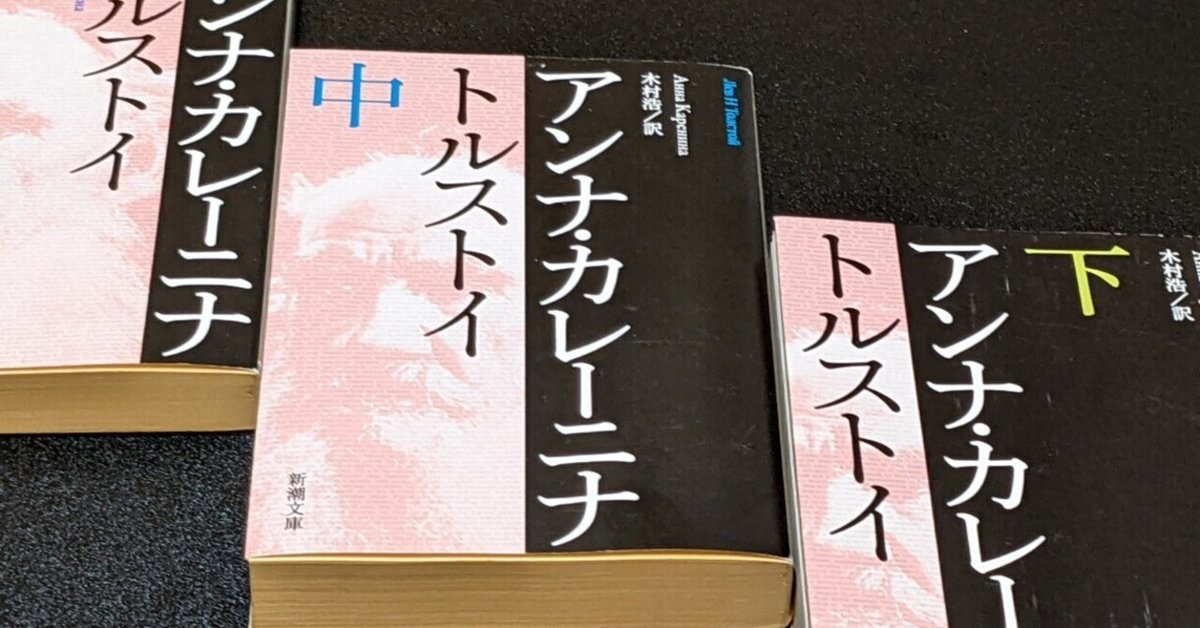
『アンナ・カレーニナ』を読んだ、華麗にな。
まず初めに言いたいのは、登場人物が多すぎる!
そして長すぎる!
でも面白すぎる!
完
――と言いたいところだがそんな単純な小説ではない。
ドストエフスキーなんかもそうだけど、帝国ロシアではロシアのデカさを象徴するがごとくに長い小説を書かないといけない使命みたいなのを感じてしまうのだろうか。あるいは寒いから引きこもってやたら長い小説をひたすら書く以外にすることがないのか。しかも面白いのがすごい。
僕は全然アンナ・カレーニナがどんな話か知らなかった。文庫本の裏に書いてあるあらすじを読んでアンナ・カレーニナが不倫する話と書いていて、そんな話だったの? と驚いた。そして読み始めたら100ページ以上アンナ・カレーニナは登場しない。驚いた。
以下、感想のようななにかである。
※もちろん物語の核心に迫るネタバレを含みます。当たり前ですが。
登場人物が多すぎる!!!
やはり登場人物が多すぎる。登場人物が多すぎる小説を読むと、登場人物が多すぎる! と思わざるをえない。去年読んだ島崎藤村の『家』もそうだった。
『アンナ・カレーニナ』には150人ぐらい登場人物がいる。もっとかもしれない。200人ぐらい? 正確な数はわからない。とにかく多い。
――なぜか。
①召使いたち
ロシア帝国の貴族の話なので、それぞれの家に雇っている人々がいる。召使いやら使用人やら女中や下男や下女やなんと呼ぼうが構わないがそういう人々が大勢いる。御者だったり玄関番だったりばあやだったり家政婦や家庭教師もいる。当時のロシア帝国の階級制度がどうなっているか全く知らないので彼らの立場もよくわからない。貴族に限った話じゃなくても、同じ家に住み込みでか通いでかは知らないが一緒にいる人々という感覚がわからない。そういう人たちも皆含めて一つの家族という価値観なんだろうか? それとも昔のアメリカが舞台の小説なり映画なりに出てくる黒人奴隷みたいな感じだろうか? いや、でもそれも奴隷だと見下している感覚もあれば同じ家族だという感覚でも描かれることもあるので一概に結論は出せない。現代日本に生きる庶民の我々にはわからない世界。
ともかく、そういう人々が大勢いる。
②貴族社会
ロシア帝国の貴族の話なので、社交界にて人々との交流が描かれる。そこではなんちゃら公爵やなんちゃら公爵夫人、なんちゃら伯爵、伯爵夫人が大勢出てきて誰が誰かわからなくなる。忠実に訳すと「~公爵夫人」となってしまうのはわかるがやたらと出てくるので混乱がすごい。貴族に限った話じゃなくても、翻訳小説だったらMr.を「~氏」とかMrs.を「~夫人」、Missを「~嬢」と訳すこともあって独特の語感が生まれてしまう。初登場ならそれでもいいが、原文にはいつもMrs.と書いてあるから事あるごとになんちゃら夫人が登場してもう省略しても(日本人的には)ええやんと思ってしまう。日本人が日本語の小説を書く場合いちいちなんちゃら夫人と毎度は書かないと思うから奇妙な感覚に陥ってしまう。もちろんあらたまった場とか敬意を表してというのはわかる。それにしてもひたすら出てきすぎである。しかも「公爵夫人」とだけの表記のときもあってそれはこの人でいいんだよね? と混乱する。
ともかく、そういう人々が大勢いる。
③世間話が描かれる
ロシア帝国の貴族の話なので(?)、世間話も多い。社交界で、もちろん別の場所でも。そしてその世間話に出てくる固有名詞はその会話の中でしか出てこなかったりする。「三丁目の中川さんがどうたらこうたら」という話の中に出てきた中川さんは今後小説に二度と登場しない。そういう描き方。たしかにその方が人間としてはリアルだ。そういう世間話だってあるだろう。でもそんなリアリティは追求しなくてよかった。ていうかそこに固有名詞を出さないでほしかった。その人物が今後重要人物となって現れるのかもしれないと思うと同時に、どうせこの会話の中にだけ存在しているんでしょう? と思ったりする。ていうか誰だよってなって困る。もしかして今までに出てきた? と戸惑わされる。
ともかく、そういう人々が大勢いる。
だから僕はその日読んだ分をルーズリーフにメモしておいた。小説は第一編から第八編まであるが、それぞれのパートで出てきた最初のページ数とともに記録していった。それが以下の写真である。



最初はぐちゃぐちゃだし、丁寧な字で書いていたり汚い字で書いていたりもする。途中からとにかく一列に書いていくスタイルにしたり、結局定まらなかった。でもこのおかげで、数百ページ前に出てきた人物が誰だっけこいつってなってもすぐに該当の箇所を調べることができた。
名前が多すぎる!!!
現代日本人には全然わからないことだが、この小説では登場人物の呼び名が色々ある。
――なぜか。
①愛称
これは海外小説ではよくあることだが、愛称で呼ぶことがある。というか本名で呼ぶことのほうが少ない。そんなことはもちろんわかっていることだし今更戸惑いもしない。でも呼び方統一してほしいとは思う。もちろん地の文と誰かのセリフとでは呼び方が違うのは当然で、その人物同士の距離感をつかむこともできるので愛称で呼ぶのは別にかまわない。しかし説明無しでいきなり出てくることもあって、この人のことでいいんだよね? と戸惑わざるをえない。しかも同じ人物なのに途中から違う愛称も出てきたりして混乱が激しい。
②ヴィチ、ヴナ
これはロシア文学ではよくあることだが、人名に「~ヴィチ」「~ヴナ」とつくことがある。「ヴィチ」は男性に「ヴナ」は女性につく。日本語でいうと「~男」や「~子」のようなもの、ではない。これはミドルネームのようなもので、父称とか日本語では呼ばれるらしい。父親の名前の後ろにつけて呼ぶことにより父親の名前がわかる。
たとえば、「キリル(キリール)」の息子だから「キリーロヴィチ」、「アルカージイ」の娘だから「アルカージエヴナ」
それはいい。
でも、さっきまで(数百ページ)そんな呼び方で呼んでなかったやん、いきなり父称が出てきても誰の話? と戸惑わざるをえない。あらたまった場とか状況によって変わるのはわかるけど混乱が激しい。
そして僕はそんなことはなんとなくしか知らなかった。でも読んでいくうちに、「~ヴィチ」は「~の息子」って意味なんっだっけ? て思い出した。なら「~ヴナ」は女性バージョンかと気づいた。あと、「カレーニン」の妻だから「カレーニナ」。そこも性別によって呼び方変わるんだって知った。
③同名
これは現実ではよくあることだが、メジャーな名前だと同じ姓や名のものを見る/知ることがよくある。同じ職場に(親戚でもないのに)「高橋さん」が3人いたりする。そしてこの小説では、「ワシーリイ」や「ニコライ」が複数人出てきて、明らかな別人の場合もあるけれど、これはあのワシーリイと同じ人なの? となることもある。
あと、アレクセイ・カレーニンとアレクセイ・ヴロンスキーが出てきて、これはアンナ・カレーニナの旦那と愛人で二人のアレクセイの間で苦しむ話だからわざと同じ名前にしているのでそれは物語的にそれでいい。
でも、(スチーヴァ・)オブロンスキーが最初から主要キャラとして出てきているのに、いきなり終盤にピョートル・オブロンスキーが出てきて、どういう関係なの? ただ同じ苗字なだけ? と戸惑わざるをえない。しかも前者は「オブロンスキー」と表記されているのに後者は「ピョートル・オブロンスキー」と表記されていて、「オブロンスキーはピョートル・オブロンスキーに尋ねた」みたいな文章で出てくるから混乱がすごい。別人だということは文脈からわかるし、血縁関係はなさそう(あっても少し離れている)なこともなんとなくわかる。でもそれなら違う名前で良かったやん。あるいは「ピョートル」だけで良かったやん。
僕はそう思う。
あと、もちろん「伯爵」やら「公爵夫人」やらが多いから、それだけで出てくると誰のことを指しているのか混乱が激しい。
現代日本人にはわからないけれど、昔の日本人も「なんちゃら三郎なにがし」とか呼んでたし(実際に呼称としてどこまで使われていたかは知らないけど)、幼名は違ったりするし元服して名前が変わるし、養子にもなる。死後は戒名がついたりする。中国なんかでも、字や諱の概念があったりする。
そういう概念は全部わかるけど、小説なんだからそこは便宜上統一してくれた方が読みやすいぜ。
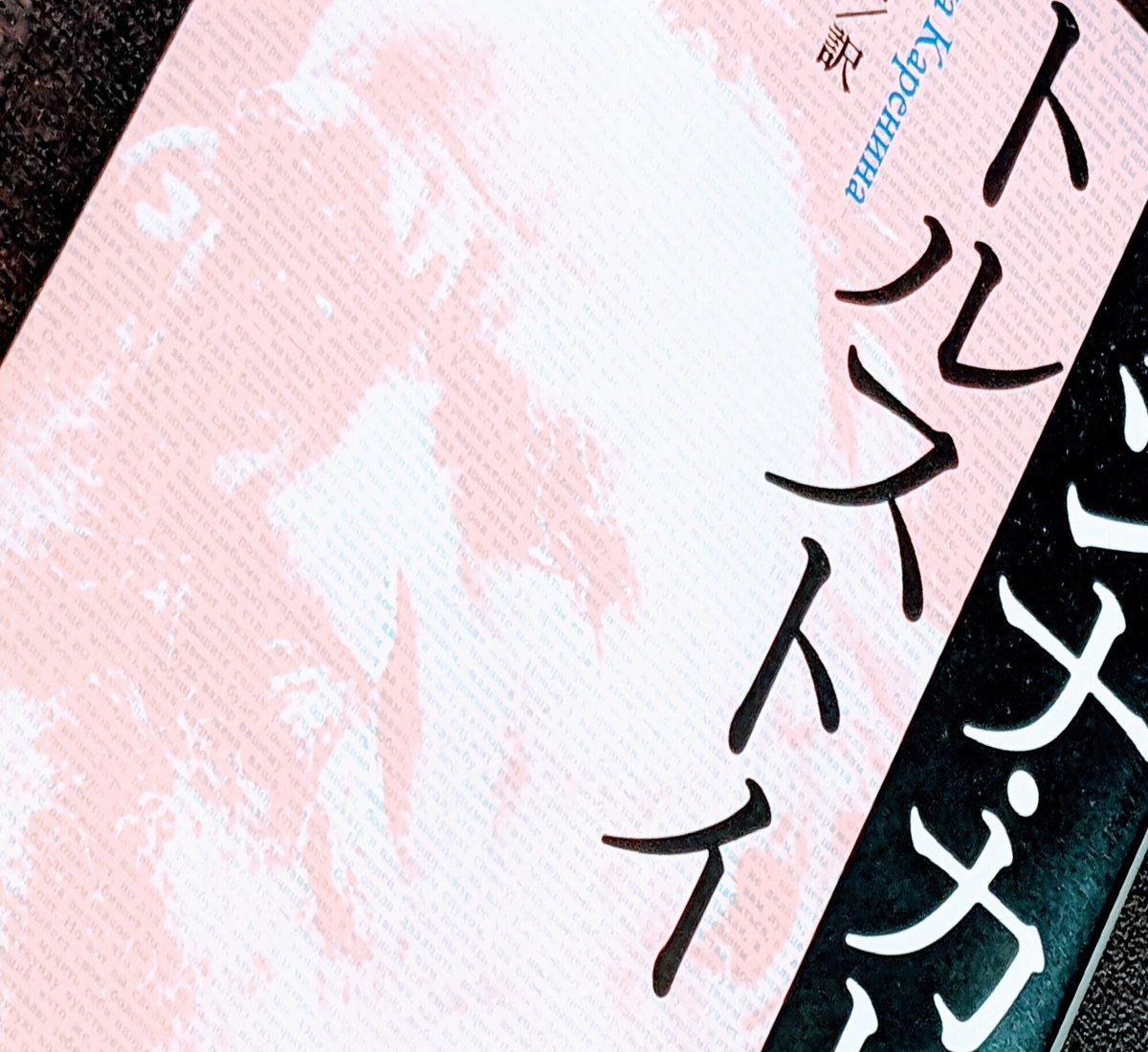
主要登場人物
だから一旦主要登場人物をまとめる。
メモしている範囲内で。
()は愛称。太字は作中での主な呼び名。
①主役
アンナ・アルカージエヴナ・カレーニナ
アレクセイ・キリーロヴィチ・ヴロンスキー[伯爵]
コンスタンチン・リョーヴィン (コスチャ)
エカテリーナ (キチイ)(カーチェンカ)(カーチャ)
上2人と下2人のカップルが対比的に描かれるから、主人公はアンナ・カレーニナ1人ではない。というか群像劇的描き方である。表の主人公がアンナなら裏の主人公はリョーヴィンという感じか。
本物の愛に出会えたけどそれは不倫で、道から外れた恋で、しかもだんだんその愛すら信じられなくて破滅していくアンナ。それに対して、幸せな家庭を築こうとしてはいるがそこには不安が入り交じり、でもそれは自分が幸福でそれが本当なのか信じられない戸惑いで……という新婚のリョーヴィン。アンナの悲劇性を描くために対比させるために登場させられたリョーヴィンだが、物語の半分ぐらいは彼の物語といってもいいぐらいに描かれる。だからこそ境遇の違いを浮かび上がらせることに成功している。
主役力を10が最大とすると、リョーヴィンが10、アンナが9、ヴロンスキーが8、キチイが6ぐらいだろうか。キチイは他の3人に比べて描写は少なめだった。どこからが助演女優賞なのかみたいな問題だからそんなに気にすることではない。
②準主役
アレクセイ・アレクサンドロヴィチ・カレーニン
ステパン・アルカージッチ・オブロンスキー (スチーヴァ)
ダーリヤ・アレクサンドロヴナ (ドリイ)(ダーシェンカ)(ドーリンカ)
主役の2組とは違うという意味で準主役だが、カレーニンとオブロンスキーはかなり出てくる。オブロンスキーに至っては最初の130ページぐらいはこの人が主人公かなと思わせる語られっぷりだった。この人も主人公の1人というとらえ方もある。というか視点人物全員主人公みたいな感覚でもある。オブロンスキーは妹のアンナが家にやってくるとか言っておきながらアンナ・カレーニナは130ページぐらい出て来ない。なんだこいつってアンナ・カレーニナに思ったものである。しかもこの、兄が家庭教師に手を出していたというところから物語は始まるのである。妹が不倫する伏線みたいな、この兄にしてこの妹ありということかと誰しも思ったはずだ。
オブロンスキーはおおらかな人で面倒見がよくいつも笑顔なムードメーカーみたいな人で、カレーニンは仕事はできるけど堅苦しい役人みたいな人で、ここでも対比が描かれる。
そしてドリイは浮気した旦那が信じられないもう他人だ、みたいなことを最初は思っていたのに、段々、自分の気持ちに正直に生きているアンナを羨ましく思い始める。自分を持って気高く生きているその生き様にアンナは立派だと憧れみたいなものを感じ始める。ドリイは子だくさんで、家庭のために生きていて、自分のために生きているように見えるアンナとの対比がここでも用意されている。
※ 作中では表記されていなかった(と思う)けど、上の項で書いた法則に従ってフルネームを記す。
◇キチイ→エカテリーナ・アレクサンドロヴナ・シチェルバツカヤ
ドリイの妹なのでアレクサンドロヴナは同じ父称。
シチェルバツキー公爵の家の女性なのでシチェルバツカヤ。
ついでに、キチイと呼ばれることがほとんどだけど、終盤はカーチャと呼ばれだす。
◇ドリイ→ダーリヤ・アレクサンドロヴナ・オブロンスカヤ
オブロンスキーの家の女性なので。
愛称が複数出てきて、実際の生活ではそうかもしれないけど小説だからそこはひとつでええやんと思ってしまう。でも違う愛称で呼ぶ人は1人だけとかで他の人と距離感が違うことを描けているという点ではいいのかもしれない。
とりあえずこれらメインの7人の関係は下図になる。わかりやすく描くと。最初はキチイを巡ってリョーヴィンとヴロンスキーがライバル関係だったけどそれは最初だけなので記さない。

これぐらいのシンプルな図でいいから載せておいてほしかった。あるいは箇条書きで登場人物一覧とか。
③その他脇役
コズヌイシェフ :リョーヴィンの異父兄
ニコライ :リョーヴィンの兄
リジヤ伯爵夫人
ベッチイ・トヴェルスコイ公爵夫人 :ヴロンスキーの従兄妹
セルゲイ・アレクセーヴィチ (セリョージャ)(クーチック) :アンナとカレーニンの息子
シチェルバツキー老公爵 :ドリイやキチイの父
アガーフィヤ :リョーヴィンの家の家政婦
ヤーシュヴィン :大尉。ヴロンスキーの親友
スヴィヤジュスキー :貴族団長
リヴォフ (アルセーニイ) :キチイの姉ナタリイの夫
もちろんもっと大量に名のあるキャラクターは存在する。老犬ラスカとか、犬にも名前は存在する。
ということで(?)、他のキャラクタも交えた相関図というか家系図を描く。血縁関係や婚姻関係にあるもののみで。
(兄弟姉妹では左が年上。青が男性。赤が女性。点線は事実婚です)

※オブロンスキーとドリイの子どもたちだが、長女がターニャで末子がグリーシャなのは最初の方に出てくる。途中で1人生まれるからそのリリイ(で合っていると思う)がその下なのはわかる。でも真ん中の3人(7人子供がいて2人亡くしていると最初の方に書いてある)の名がわからない。おそらくアリョーシャとニコーレンカと誰か。名前がそれで合っているのかわからないし年齢もわからない。そして途中で生まれたリリイも結局死んでしまったような気がする。細く設定を作って大量の人物が出てくるのに子どもたちは曖昧なんだと思った。
そしてとりあえずこれだけわかればだいたい理解できる。と思いたいがそんな単純な小説ではない。
リョーヴィンの農園の話の中には関係者が20人ぐらいは出てくるし、アンナの社交界での話には、リジヤやベッチイを中心とした人物が20人ぐらいは出てくるし、ヴロンスキーの競馬の話にも20人ぐらい出てくるし、カレーニンの政治の話にも20人ぐらい出てくるし、といった感じで大勢の人間が出てくる。20人ぐらいというのはあくまで感覚で、実際はもっと多いかもしれないし少ないかもしれない。感覚的にそう感じたということ。
価値観
これはこの小説の面白いところだと思うんだけれど、様々な価値観が描かれていて良いという話。
シチェルバツキー家の末娘であるキチイが誰と結婚するかというのが序盤の話題である。
キチイの姉ドリイの夫、オブロンスキーは自身の昔からの親友リョーヴィンを推している。本人もキチイにメロメロである。リョーヴィンは地方の役人だったけれどそれを辞めて田舎で農園を経営している。
もう一人の候補として現れるのがエリート軍人ヴロンスキーである。一見好青年でキチイの心も彼に傾いている。そしてキチイの母親(老公爵夫人)もヴロンスキー推しである。
田舎者でどっちかっていうと線の細いリョーヴィンよりも、いけ好かないけど男前で軍人のヴロンスキーと結婚しろってキチイをけしかける。そしてキチイもその気になっている。それは親が言うからであって、キチイ本人の意志ではない。後にあのときは間違っていたというようなことを述懐するシーンもある。
ここが面白いポイントだった。
ただの三角関係ではなく、その背後に親の感情がある。でも世間では、親の言う結婚相手と結婚するなんてダサい、時代遅れ、みたいなことが囁かれている。19世紀の帝国ロシアでは。意外だった。そんな価値観だったのか。当時の日本だと、親の言う相手以外と結婚するなんてありえないだろう。それに反対するなら駆け落ちしかない。明治から昭和初期の日本の小説なんかでありそうな世界観。それなのにロシアでは自由恋愛の時代! いつまでも親の言いなりではいけない! (意訳)という感じで驚いた。
そしてその価値観はアンナ・カレーニナにも当てはまるわけで、アンナも20歳ぐらい年上のカレーニンとやむなく結婚したみたいなところがある。この結婚に愛はない。息子だけが生きるよすが、というアンナの心境が描かれる。だからこそヴロンスキーと出会って最初は否定していたけれど、これが本物の愛だと気づく。
本物の愛だとかいう都合のいい言葉で自分の恋愛を正当化していたアンナは愛に溺れて苦しんでいく。でもそこには気高さを感じてちょっとだけかっこよかった。社交界の人々の中にはアンナと同じように愛人と不倫をしている人もいる。そしてキリスト教社会ではそんなことは許されない。離婚なんてもってのほか。だからこそ簡単に離婚できない状態に苦しむさまを描く。アンナの行動が正しいか正しくないかとかそういう話ではない。自由に好きな相手と結婚したかった後悔や嘆きは時代のせい? でもしかたない。それが人生なのだ。と僕なんかは思う。と同時に自分の生き様で生きるアンナを羨ましくも思う。それが茨の道になろうとも。

アンナ・カレーニナ
アンナ・カレーニナとは主人公の名である。もちろんそうだと思っていた。でも読んでみると彼女は主人公格の人物の1人にすぎない。リョーヴィンが一番主人公感を出している。アンナ・カレーニナのことを語るために、その取り巻く世界観を描く。周りの人々をより濃く描くことでアンナ・カレーニナという存在、事象を浮き彫りにする。最序盤から登場するわけじゃないから読者はやきもきする。そして去ったあとも最終章が用意されていて、アンナが与えた影響ももちろん描かれるわけだけれど、アンナについて直接言及されるのはいつなんだと思って文字を追っていくから、登場しないことでアンナ・カレーニナが読者の頭の片隅に居座り続ける。
だからタイトルは『アンナ・カレーニナ』で何も問題はない。内容としては19世紀のロシア貴族の生活を描いて、そこに存在するある種普遍的な感情の話だけれど。『アンナ・カレーニナ』というタイトルにすることによってより読者はアンナのことを意識するという狙いもあるかもしれない。ていうかそもそもはアンナ・カレーニナの話を書こうとしていて、そのために結果として周りの人物たちが創られたらしいので、トルストイ的には初めからアンナ・カレーニナ一筋だったわけだ。群像劇でアンナは主人公の1人なので『アンナ・カレーニナ』ってタイトルでいいの? と疑問を抱くことはお門違いである。トルストイは意図的にそうしている。アンナ・カレーニナを描くのにより効果的な方法を取ったらこの形になったのだ。天才かよ。
さて、タイトルの話はまだ続く。
アンナ・カレーニナは中盤以降、アンナ・アルカージエヴナと呼称される。あらたまった場だからとかそういう理由もある。けれどそれ以上に、アンナはもうカレーニンの妻ではないからだ。実際には離婚はまだ成立していないので、法的にはアンナ・カレーニナで間違いはない。でも誰も彼女をアンナ・カレーニナとは呼ばない。実際に離婚しているかいないかはともかく、もはやだれもカレーニンの妻だと思っていないからだろう。でもヴロンスキーと結婚してはいないからヴロンスカヤとも呼べない。だから「アンナ・アルカージエヴナ」と呼ぶのだろう、と思った。そういう意味で描いているのかは知らない。しかもほとんど説明もなく「アンナ・アルカージエヴナは~」と出てくるから一瞬戸惑う。アンナ・カレーニナのことだという説明がない。他のシーンで、アルカージエヴナという父称が出てきたことはなかったように思う。仮に出てきていたとしてもそんな数百ページ前のことなど細かく覚えていないと思う。
でもタイトルは『アンナ・カレーニナ』なのだ。ここからは第二部『アンナ・アルカージエヴナ』です、とはならない。それはカレーニンが離婚に同意しないからであって、それによって苦しんでいるのがアンナ・カレーニナだからだ。「アンナ・カレーニナ」という呪いに縛られている。彼女は「アンナ・カレーニナ」から逃れられない。カレーニンは政府高官で「カレーニナ」を名乗るのはその地位の象徴であったはずで、その夫を捨てたアンナへの罰として彼女は「アンナ・カレーニナ」であり続けなければいけない。
思想
農園を経営しているリョーヴィンが雇っている百姓たちが働かないと嘆いているシーンが現代でも通じるシーンだと思って面白かった。なんで誰も理解してくれないんだ、作物が取れなくて最終的に苦しむのは自分たちじゃないのかってリョーヴィンは1人で悩んでいるけど百姓たちは一向に真面目に働いてくれない。かといって全員クビにするわけにも行かない。企業経営の難しさよ。経営陣と現場で働いている人との意識の違いが描かれる。
いっそのこと自分も一緒になって耕す、と力仕事をしようとすると貴族のあんたにそんなことされると俺たちの働く場所がなくなる的なことを言われたりする。リョーヴィンはことあるごとに百姓の地位向上みたいな話を展開するがその意識の違いがある。百姓たちのことを思ってリョーヴィンは考えているのに、百姓たちは百姓たちでその生き様で生きているんだからそれでいいと思っていたりする。その両方の面から人々の心情を描いていたのが面白い。そしてその経営哲学はトルストイ自身の経験に基づいているとかなんとか。自分の思想を作中にうまく描いていて抜け目がない。
というか主人公力の高いリョーヴィンは作者の分身的側面がある。
リョーヴィンは信仰を持たない人だけれど、子供が生まれるというシーンに際して、神に祈り始める。母子ともに健康に、無事に生まれますようにと。そしてハッとなって俺は神なんて信じていないのに、神とはいったい……。俺は何に祈っていたのだ。祈りとは。という哲学的問いを自分と読者に投げかける。神なんて信じていないけど、祈りという行為そのものは自然と起こったことだ。信仰なんてなくても。でもその祈りの対象がわからない。これが神なのか。これが信仰なのか。そして生とは死とは……。兄ニコライそしてアンナの死を目の当たりにして、人生ってなんだ、なぜ人は生きているのだと最終章でひたすら考え続けている。それはトルストイから読者への投げかけであって、それを問いたいがために長々と小説を書いてきたんじゃないかと思わせる。そのための装置としてアンナ・カレーニナを創造した。
だからやっぱり『アンナ・カレーニナ』がタイトルなんだと納得する。
終盤のアンナはかなり追い詰められていて、被害妄想が激しく、幻聴こそ聴こえないものの統合失調症の症状のようだった。この時代に統合失調症についてどれほど解明されていたのか、そしてトルストイがどこまで理解をしていたのかはわからない。そんな時代にそこまでの精神の状態を描くのだから凄まじい。圧倒される。だんだんアンナが壊れていって、もう少し真剣に周りがアンナの声に耳を傾けていたら、あるいはカレーニンが離婚に同意していたら……なんて思うけど、それも夫を裏切ったアンナに対する罰なのかなと納得してしまえる。それだけ人々の中で信仰というものの占める割合が大きかったのかなと感じる。そしてきっとそれはアンナ自身が一番感じていて、夫を裏切って情夫と暮らしている自分は罰を与えられるべきだと心のどこかで思っていただろうし、それと同時に自分は幸福を手に入れる権利があると思っている自分もいて、そのせめぎあいが気づかぬうちにアンナの精神を引き裂いてしまったのではないか。「アンナ・アルカージエヴナ」とみんなは気を遣って呼ぶけれど、その笑顔の下でアンナを憐れみ見世物を見るような目で見ている。自分はそっち側の人間にならなくてよかったと。実際にそう書いていたかは忘れたけれど、そう感じた。アンナも同じような被害妄想を勝手に抱いていたことだろう。と勝手に思う。
キッカケ
最後に、僕が『アンナ・カレーニナ』を読もうと思ったキッカケを書く。
数年前に村上春樹の『眠り』という傑作短編を読んだ。その短編では眠れない主人公が寝ずにひたすら『アンナ・カレーニナ』を読む。めちゃくちゃ面白くて一気に読んでしまったという展開で、そんな馬鹿な、さすがに笑うわ、という感想を抱く。そして『アンナ・カレーニナ』に興味を抱いてしまう。でもめちゃくちゃ長いし躊躇してしまう。その思いが心の中にある。常にあるのはわかっているけれど、その気にはなかなかなれない。湖の底の方に沈んでいる。普段の水量では、地上からは到底見ることができない。水が減っていかないと。そして水が減っているということは水が必要になっているということで、それだけ飢えないと手にとることができなかった。それほど飢えていたのだろうか。そんなに読書欲が高まったキッカケはなんだろうと考えた。今年読んだ本を思い返してみたら、そこには『月と六ペンス』があった。とても面白かった。世界的名作は世界的名作だった。史上最高の小説の一つだと思った。それと同時にまだまだ読んでいない世界的名作があることを思った。ふと見ると『アンナ・カレーニナ』が顔を出している。手の届くところにある。まずはこれを読まなければ。という具合だ。
一つ忠告しておきたいのは、『眠り』には『アンナ・カレーニナ』のネタバレが書いてあるので注意ということだが、ここまで僕のこの文章を読んだ人はすでに『アンナ・カレーニナ』のネタバレをされているので問題はないのである。そういう性質があるから安易に短編で面白いからと『眠り』を薦めることができないし、『アンナ・カレーニナ』も超長編だから薦めることができない。
さて、『アンナ・カレーニナ』を読んで僕は、もうどんな長編でも読める気になってしまう。これをキッカケにいろんな未読の世界的名作も世界的駄作も読めたらいいんじゃないかな。読むために生まれてきたのだから。読まれるために書かれたのだから。
終
この記事が参加している募集
もっと本が読みたい。
