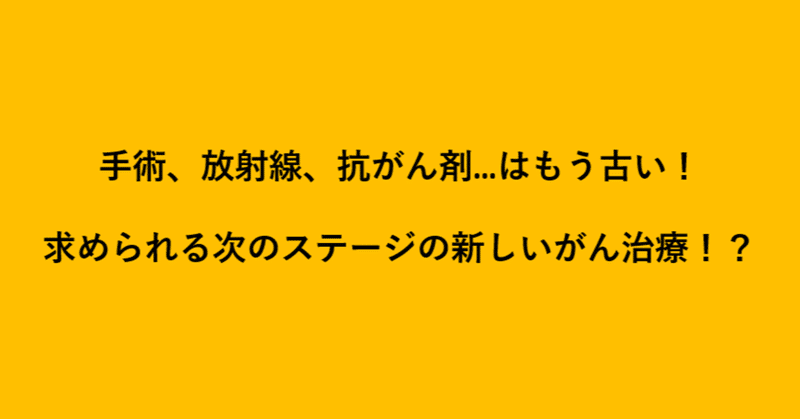
「がんと共に生きる」21世紀型の新しいがん治療の提言
疾患によりあまりに異なる終末期医療
現代の日本における死因の2大疾患は「がん」と「心不全」である。終末期医療に携わっていると当然、このふたつの疾患の患者さんを多く診ることになるわけであるが、実は同じ「看取り」を主眼に置いた治療でも、このふたつの疾患では治療方針を決定する考え方は180度異なるのだ。
「倒す」がん治療
まず「がん」であるが、近年の診断技術と治療法の両面からの目覚ましい進歩により、より早期に発見しより効果の強い治療を行うことによって救える命は年々増えてきている。がんの治療法は外科治療、放射線治療、内科治療(化学療法)の大きく3種類に分けられるが、これらはいずれも、がんを取り除くことを目指す治療である。すなわちがんを切り取ったり、がん細胞を殺したりするわけであるから、当然多かれ少なかれ侵襲や副作用が必ずついてまわる。であるから、残念ながら早期発見がかなわずすでに遠隔転移をきたしてしまっている症例(どこの臓器のがんでもステージⅣに分類される)に関しては、現在の治療法では救命はほぼ100%不可能であると判断され、副作用に耐えるよりも、症状を最小限に抑えて残りの時間をできる限り安楽に過ごして頂く「緩和医療」に移行する訳である。
がんの根治療法は必ず侵襲または副作用を伴う、すなわち短期的には患者さんを「苦しめる」介入であるため、緩和医療との両立は成立し得ないわけである。なのでこの根治療法を行うか、緩和医療を行うかで明確な線引きがなされ、根治療法を専門とする医師はステージⅣに至ると途端に患者への興味が薄れるし、緩和医療を専門にする医師は、それ以降患者の体内の状況把握には全く意識を向けないわけである。
「付き合う」心不全治療
次に「心不全」の方はどうであろうか。こちらも目覚ましい医学の進歩によりおびただしい数の新薬が開発され使用可能となってきている。しかし、驚くべきことに心不全患者の予後はなんとこの20年、全く延びていないのである。つまり、心不全患者さんに我々が用いる薬剤は、ほぼ全てが患者さんの寿命を延ばすためではなく、患者さんの症状を軽減して生活の質、いわゆるQuality of Life = QOLを向上させるために用いられるのだ。それでは心不全患者さんのQOLを落とす症状は何かというと、「うっ血」と「組織灌流低下」というふたつの異常によるものに大別される。
心不全は極言してしまえば、心臓というポンプの機能低下によって全身の水分循環が滞る病気である。水が前に流れず後ろに溜まる「うっ血」の方からは、足に溜まれば「浮腫」、肺に溜まれば溺れたような状態なって「呼吸困難」が引き起こされる。そして水が前に流れず臓器に届けられない「組織灌流低下」の方からは、全身のあらゆる内臓の機能不全が起こって、「倦怠感」や「身の置き所のない感覚」といった、抽象的ではあるが確かな苦痛が引き起こされるのだ。これらの症状を抑えるために、今の患者さんの苦痛が主に「うっ血」から来ていると判断されれば、水を抜く利尿薬を用いたり、「組織灌流低下」から来ていると判断されれば、心臓のポンプの力を一時的に上げて臓器への血流を底上げする強心薬を用いたりする。しかし利尿薬には前に流れる水分をさらに減らして臓器への血流を余計に減少させる副作用や、強心薬には心臓の動きを空回りさせて不整脈を誘発したりといった副作用もあるため、その使用は慎重に判断されなければならない。
苦しみを伴う根治療法と、苦しみは取るががん自体には何の影響も及ぼさない緩和医療の線引きがクリアであるがんに対して、心不全は全ての治療手段に症状緩和の作用と副作用の両方が存在するのだ。乱暴な表現だが、がんの治療は、ある時点までは「がんを倒す」ことに全力を尽くすが、敗色濃厚になった時点で突然戦線放棄をする感じ、一方の心不全の治療は、最初から倒すつもりはなく、手をかえ品をかえ、なんとか「心不全と付き合う」ことを目指す治療と言えるだろうか。
感染症治療から始まった20世紀の「病を倒す」医療
このようながん治療と心不全治療の治療概念の違いは、がんは異常な塊が体内に発生して増殖するという「目に見える」病気であるのに対して、心不全は体内の循環の異常という相対的なバランスの崩れによる「目に見えない」病気であるという、そもそもの病気の性質の違いによるところが大きいであろう。そして「目に見える」病気のがんの治療は、先んじて人間が直面してきたもうひとつの「目に見える」病気、感染症の治療の背中を追うようにして発展してきた。
感染症はもはや言うまでもなく、「細菌」や「ウイルス」といった、本来は我々の体の外に存在していた別の生物、いわゆる「非自己」が何らかの経路から我々の体内に侵入し、増殖して我々の体を蝕むことによって生じる病気の総称である。しかしこの概念、証明されたのはなんとほんの百数十年前なのである。人類はこれまで数千年の歴史の中で、ペスト、天然痘、インフルエンザ、そしてCOVID…と数えきれない種類の伝染性疾患の脅威にさらされてきたわけであるが、その原因としては悪い空気が媒介するといった「瘴気説」なるものが、なんと二千年以上もの長きにわたり世界中で信じられていた。それが17世紀に顕微鏡の発明によって微生物が確認され、さらに19世紀に細菌の培養方法が確立されて微生物と疾患との因果関係が証明されるようになって初めて、感染症が微生物病であることが認識され、そこからこの微生物を「殺す」抗菌薬の開発が劇的に進歩することになる(感染症学)。時を同じくして、牛痘に感染した者は天然痘を発症しないという事実から、人間にはもともと微生物を排除する機能が備わっている(=免疫)ことが明らかとなり、この機能を利用して自分自身に微生物を「殺させる」ワクチンの開発・普及も爆発的に進んだのである(免疫学)。
「非自己」を殺す感染症治療を踏襲したがん治療
感染症とがんは、自分自身(宿主)がコントロールできない細胞の増殖によって自分の組織が破壊されるという点において、極めてよく似た疾患である。違うのは、感染症はその細胞がもとから「非自己」であり体外から侵入してくるものであるのに対して、がんはもともと自分の体内にあった正常な細胞が、遺伝子の突然変異を経て「非自己」に変貌するという点である。似ている疾患であるから、おのずと治療哲学もそのまま感染症からがんに引き継がれた、つまり非自己を「殺す」治療である。先述の、外科治療、放射線治療、内科治療(化学療法)、いずれもがんを取り除く、殺すことを目的としているが、もとはと言えばがんも「自己」であるため、その細胞に傷害を加えるからには多かれ少なかれ必ず正常な細胞にも傷害がおよび、それが副作用につながるわけである。そして近年、こちらも感染症治療に踏襲して「がん免疫療法」なるものが急速な発展を遂げている。我々の免疫機能は病原微生物に対してだけでなく、非自己に変わったがんに対しても積極的に機能していることが次々と明らかとなり、これを人為的に促すことで、自分自身にがんを「殺させる」治療法である。これは感染症での「ワクチン」の治療哲学にそったものである。しかしこちらも、「免疫」を惹起させると必ず自分自身にとって有害な「炎症」も惹起してしまうというジレンマから逃れることは不可能であり、やはり副作用をゼロにすることは不可能であろう。先ごろノーベル賞を受賞した免疫チェックポイント阻害薬などの新規のがん免疫療法の治療薬は、自己免疫の機序による副作用が少なからず報告されてきている。
心不全治療に倣って「がんと共に生きる」医療を
ここまで述べてきたように、20世紀の西洋医学を引っ張ってきた感染症治療の「非自己を殺す」という治療哲学をそのまま踏襲して発展してきたがん治療であるが、その非自己ももともとは自己であるというジレンマから深刻な副作用を克服できず、これが根治療法と緩和医療の分断化を招いてしまっているわけである。予後を改善できない現在の心不全医療にも課題は山積しているが、それでも「疾患とうまく付き合う」という治療哲学は、がん治療にも応用できる点が多々あるように思う。
そもそもなぜ人ががんで死ぬかというと、その直接的な原因は以下の四つに大別される。
①正常な組織を「こわす」:がんは無秩序に周囲の正常組織を破壊することによりその機能を低下させたり、血管を破壊して大出血を起こさせることにより命を奪う(臓器不全、出血)
②脈管を「ふさぐ」:がんは血管やリンパ管といった重要な脈管の中にまで侵入してふさぐことにより、重要な体液の循環を滞らせ命を奪う(腫瘍塞栓、がん性リンパ管症)
③栄養素を「うばう」:がんは正常細胞よりエネルギー消費が亢進しているため、優先的に栄養を奪い栄養失調に陥らせて命を奪う(悪液質)
④有害な物質を「だす」:がんは炎症を惹起したり、血液の固まり具合のバランスを崩させるような物質を分泌することで、全身の生命維持のバランスを崩し命を奪う(がん性腹膜炎、播種性血管内凝固症候群)
このように、がんは実に多様なメカニズムで以て私たちの肉体を蝕み命を奪うわけであるが、しかしよく考えてみて欲しい。がんはそこに存在し拡大するだけなら、決して私たちの命は奪わないのである。これは感染症にも言えることである。病原微生物は、決して我々を殺すために感染してくるわけではない。彼らも「生きたい」のである、そして彼らが生きるためには、感染される宿主にはむしろ死んでもらっては困るのである。我々が抗生物質やワクチンを使って、必死に微生物を「殺そう」としている一方で、微生物側は必死に我々と「共に生きよう」としているのである。そしてそのせめぎ合いは、たいてい共に生きようとする側の勝利に終わっている。COVID-19でも、抗ウイルス薬の開発よりも、ワクチンの開発普及よりも、ウイルス側の弱毒化した遺伝子変異によってこそ、死亡率の急落が得られたのである。またしても、ウイルスを「殺す」ことしか考えなかった人類は、人間と「共に生きる」努力に徹したウイルスに敗北したのである。
「病を排除する」20世紀型医療から「病と共生する」21世紀型医療への転換
この教訓を、いい加減がん治療にも活かそう。がんを「殺す」ことに躍起になって副作用の呪縛から逃れられないでいるのではなく、がんを敢えて殺さず、しかし周囲の組織を破壊したり有害物質を産生したりといった、がん細胞に特異的な機能は抑えることによって、がんに「静かにそこで生きていて」いただく治療を模索しようではないか。「抗がん剤」から「静がん剤」へのパラダイムシフトである。がん細胞を殺さない「静がん剤」が実用できれば、より体力の落ちた高齢者にも使用しやすく、また副作用がなければ、よりステージの進んだ患者であっても緩和医療に併用しても患者のQOLを損なわず末期でもまだまだ予後を改善させることができるであろう。
社会の在り方に対し大きな問題提起をしてくれたCOVID-19のパンデミック。こと医学の世界においては、隔離政策、抗ウイルス薬開発、ワクチン開発といった従来通りの感染症医療の延長線上での反省しかなされていないように思うが、私はこの敗北の経験からウイルスに学び、「病を排除する」ことを主眼に置いた20世紀型医療から、「病と共生する」ことを目指す21世紀型医療へのパラダイムシフトの必要性を強く訴えたい。特にこの概念が欠落しているのが、感染症に類似した疾患であるがんに対する治療だと思う。一歩先を行く心不全治療に学び、がん治療においても副作用のない「静がん薬」をうまく用いることで、体内からがんを排除せずその「悪性性」だけを抑えることによって「がんと共に生きる」という治療のオプションが確立できれば、人類と疾患との関係性は、これまでの200年から次の200年へ、新たなステージへと移行することができるのではないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
