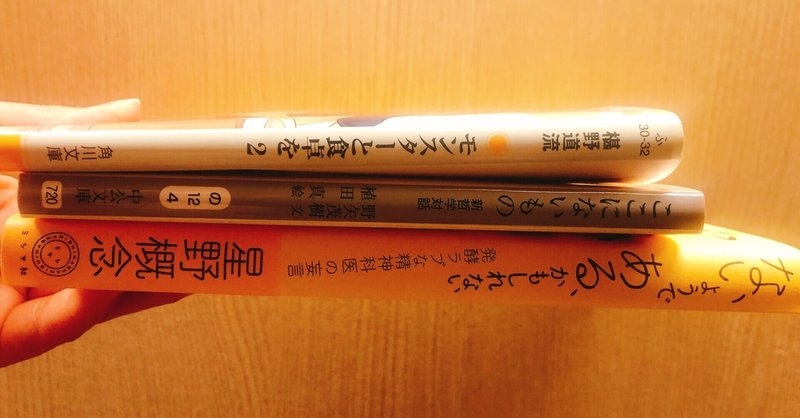
ほん(さんがつ に)
ひらがなってアホっぽいけどまるみがかわいくて好き。
前回(うえのやつ)、とある1冊について書きすぎてしまったので、3月に読んだ残りの本について書いていく。
『モンスターと食卓を 2』椹野道流、角川
先月(というか下書きに入れている間に、先々月になってた)1巻を読んだので、続きをば。
この小説、本編にはそんなに興味がないかもしれない(笑)単純にごはんものの話が好きっていうものはあるのだが、この小説に関しては、エピローグが健康的で好きだ。エピローグはわりと本編の内容に関係がない。ただただ有とシリカが仲睦まじくごはんを食べているだけ。その様子が心地いい。誰かとごはんを食べるのっていい。誰かとご飯やお茶をしながら他愛もない話がしたくなった。
「HUNTER×HUNTER」冨樫義博、集英社
ネイリストさんとハンタの話をした。ネイリストさんはグロいのがダメらしく、カイトがうわーってなるところから読めていないとのことだった。蟻編はラストがめちゃいいから読んだ方がいいと推した。そういう流れもあって蟻編を読み返した。やっぱめちゃめちゃ好きだ。王とコムギのラストがとてもいい。
ラストがいいんだが、このラストが素敵、好ましい、圧倒的だというのは結構伝えづらいなとも思っている。唐突だけど、小学校国語で習う「ごんぎつね」を思い出してほしい(大体の教科書に採用されてたはず)。そのラストをよかったよね、と言ってしまうこととたぶん近しい。
大学院にいた時「ラストの扱い方には注意しろ」となにかで聞いた。きつねのごんは、後ろめたさから善行をしていたのに、悪さをしてると勘違いされて兵十に撃たれて死ぬ。が、勘違いされたまま終わるのではなく、「ごん、お前だったのか」という兵十のセリフにあるように、誤解はとける。だから、このラストについて「ごんはよかった」「死んでよかった」というオチにするのは違って、そうならないように授業では気をつけなきゃいけないという話だった。はず。
ここまで書いて、ちょっとわかってきた。死んでよかったとか、死ぬこと自体の良し悪しはわかんない。でも死に際が潔いとか綺麗とかっていうのはあるんじゃないだろうか。王とコムギの最期は、死ぬこと自体が良いか悪いかなんてわかんないんだけど、圧倒的に美しくはある。物語としても綺麗な終わり方だと思う。「良かった」っていう表現が、微妙というか誤解を生むというか。そこがいけない気がする。
で、なんで王とコムギの最期の美しいと感じるのかを考えてみたい。なんとなく、種別を超えたとか人間愛とかみたいなものと切り離せない気がしている。ペットが飼い主の危機を救うと、それが生命がかかわるものだと尚更、感動したりするじゃないですか。言葉は通じないけど何かわかったんだな、伝わったんだなって思う。メルエムという人ではないものとコムギという人間が、およそ分かり合えないだろうふたり(?)が、軍儀を通して何か通じ合ったからこそ、あのラストは胸に来るものがあるんだと思う。
一方で、枠組みや境界線とかなにかの線引きが溶けてしまうことは、恐ろしくもある。それを感じたのが、ドラマ「MIU404」だった。所謂刑事もののドラマ。野木亜希子脚本で、ストーリーが抜群に面白く、綾野剛の藍ちゃんがめちゃくめちゃ可愛いので未視聴の方は是非!!(隙あらば推す)
物語の後半、SNSを使ったフェイクニュースやデマに、警察側の人間は翻弄される。その際「#MIU404」というハッシュタグが、ドラマで使われるのだが、この仕掛けがすごかった。だってそのハッシュタグは、ドラマを見ている私たちも感想をつぶやくために使っていたものだから。『千と千尋』のトンネルとかここではない世界への扉のように、「#MIU404」というハッシュタグを通して、ドラマの世界と私たちがいる現実が繋がってしまった。ゾッとした。画面の向こうだと切り離していたものが、全然向こう側なんかじゃなかった。
だから、人間じゃないと思っていた生き物が、実は自分たち人間と変わらないと知ってしまったとき、それはすごく怖いんじゃないだろうか。画面の向こうだと思っていた世界がこちらと地続きだと気づいてしまったときみたいに。何かの境界線や枠組み、たとえば「常識」とか、それが溶けたり崩れたり反転することは、今まで信じていた世界や前提が壊れることであり、とても不安で怖いことだ。ここまでドラマを例に挙げたけど、コロナ以前以後の世界を考えれば早かったね(笑)
境界線を越えることは、王とコムギのように感動もする。感動もするけど、実際目の前で起こったら受け入れられないかもしれないなあ。ネテロやじっちゃんも面食らうし、パームも戸惑って取り乱していた。男も女も関係なくとかいうとき、そこにはある意味想定している人たちがいる。その想定から漏れてしまっている人は本当にいないのか。この言葉、気軽に口にできないかもしれない。目指していくべきではあるけれど。
あ、あと読み返して、思ったことをふたつ。キルアってよくあの家庭環境でグレなかったなと(笑)いいお兄ちゃんだし、仲間思いだし、本当にいい子だ。もひとつは、蟻編って、アニメにするとナレーションにあたる部分がやたらと多い!それも本人が自覚してない感覚の部分をちょー言ってくるから、町屋良平の小説みたいだった。
『ここにないもの』野矢茂樹、中央公論新社
国語の教科書って、とくに授業で触れられないけど、巻頭に詩とか短い文章載っていませんでしたか?導入的な感じで。高校の国語の教科書には、その部分に野矢茂樹の文章が載っていた。見るものがいなくなったときにも夕焼けは赤いのか、という文章だった(講談社現代新書の「哲学の謎」という本だ)。素敵で不思議でとても惹かれた。それからというもの、野矢茂樹のことは何となく好き。
本書は、内容は難しいけど文章は平易なので、読みやすい。カバーとか挿絵とかがとてもかわいくて素敵。登場人物のミューもエプちゃんもとってもかわいい。
ミューとエプちゃんは、不思議に思うことをとつとつと話す。それをふたりで考えて、思ったことを伝えて、不思議の輪郭を探っていく。ミューとエプちゃんのように、誰かと語り合えたらとっても素敵。そんな風に誰かとお話したいなあ。
関係ないけど、よくカバーむいちゃって、表紙の状態にして本を持ち歩いて読む。で、全然見たことない表紙出てきた。あー中公の文庫って全然買ったことなかったんだなーって。思い出?が増えた。
『ないようである、かもしれない』星野概念、ミシマ社
坂本真綾のライブに行くときに、乗り換えで渋谷を使った。時間に余裕があったので、以前から気になってた青山ブックセンターに行ってみた。ツイッターでちょくちょく見かけていた本書が売っていた。最初の方だけ読んだらもうこりゃ好きなやつだーって買ってた。そんなことばっかりしている。
タイトル通り「ないようである」ことに目を向けながらいろんな話がされていく。なので、はっきりすっきりするような本ではない。しばしば、ふごふごもごもごしていたりする。その分とっても優しい本だ。誰かの何かを認めなかったり否定したりということがない。
自由を手にした僕らはグレー(「大人の掟」より)
情報が溢れすぎて、どれが正解か、なかなかわからない。白黒つけられることばかりじゃない。自分で決めること考えることに疲れてしまう。誰かに決めてほしくなる。委ねたくなる。だから、わかりやすいものが好まれる世界だと思う。だけど、やっぱり世界はそんなにわかりやすくはないし、わかりやすくしていくと零れ落ちていくもの、ないことにしてしまうものがたくさん出てくる。
その場をとりあえず笑ってやり過ごすことも多い。それだって立派な生きる術だ。いちいち突っかかってもいられない。これを捨てることはできないと思う。でも、やり過ごしたときに感じた気持ちまでなかったことにしては、たぶん自分を大切にしなくなってしまう。なんとなく、をもっと大切に扱っていきたい。なんとなく感じたこと、それは「ない」のではなく、「ある」なのだから。
楽しいことや好きなこともなんとなくを尊重したい。誰に責められるわけでもないのに、どうしてもその理由を言葉にしようとしてしまう。それを言えないとダメな気がしてしまう。そんなわかりやすいことばかりじゃないから全部言語化できるわけじゃないのに。なんとなく好きをもっと堂々と言いたい。
余談だが、坂本真綾のライブはとってもよかった。あんまり喋っている姿を見たことがなくって、お茶目で可愛くて、とても綺麗な人だと知った。坂本真綾や朴璐美のように素敵に歳を重ねたい。憧れる。
MCで、歌詞にその時の気持ちをそっと忍ばせる、というお話をしていた。曲を聴く私たちもまた、同じことしているんじゃないだろうか。ある曲のある歌詞に励まされる。またいつの日かその曲を聴いたとき、「ああ、あの時も励ましてもらったな。またがんばろ」とかそうやって繋がっていくものがあると思う。全部を忘れずに持っていられるわけじゃない。曲に持ってもらっているのかなーなんてことを思った。MCもお歌も素敵で、真綾さんのことがさらに好きになった日だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
