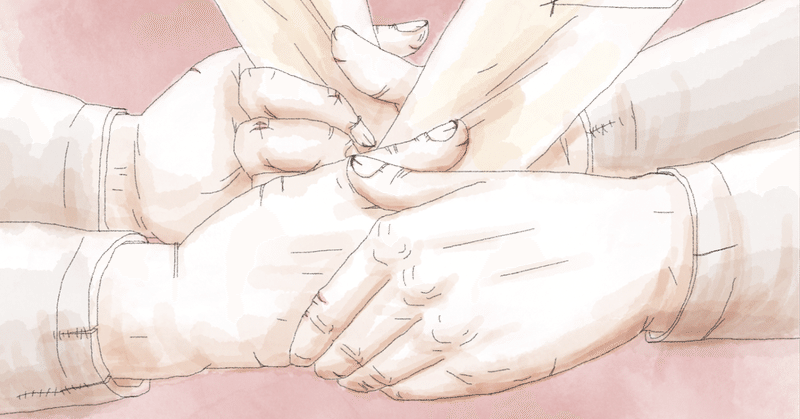
文房具屋のおじいさん
2015年の春のこと。
わたしはまだ青木杏樹ではなく、ただ趣味で小説を書いている人でした。毎日毎日、400字詰め原稿用紙を20枚ワンセットを消費しては、文房具屋に買いに行きました。帰宅するとまた明け方まで20枚消費し、日が高くなる頃には買い足しに行く日々が続きました。
小説とは応募するもの、小説とは他人に読んでもらうもの、という考えがわたしにはありませんでした。
わたしの中には小さな世界がごまんとあり、その世界で生きている人たちはたえず呼吸をしていて、畑を耕し、水を飲み、作物を売ったり買ったりしていました。ときには殺し合って世界は消えてしまうこともありました。そうした流動する世界線がいくつも走り、絡み、まじり、繰り返す、衝動にも近い意識と妄想がするすると動くものですから、歴史をつむぐように彼らの証をのちのちまで残せないものかと考えたのがどうもわたしの執筆の原点のようです。つまり応募する、評価される、そういった考えには至らなかったわけです。
さてその2015年の春に、わたしを呼び止める人がいました。文房具屋の店主さんでした。髪の毛は真っ白でぶあつい眼鏡をかけたしわくちゃのおじいさんでした。いつも難しい顔をしていて、お釣りを「ん」と言って渡してくる気難しい雰囲気の店主さんなので、わたしも臆病なものですから、買うだけ買ってお礼のひとつも言わずに出ていくわけで、もちろん滞在時間はものの1分。いえ1分もなかったかもしれません。無愛想。ぶっきらぼう。文房具屋は万引きが多いというけれど万引きなんて恐ろしくて考えることすらできない、商品を触るだけでも緊張するお店でした。従業員はおじいさんただひとりでした。他の人を見かけたことはありません。万年筆のショーケースに囲まれたレジカウンターの内側でいつも戦争の本を読んでいました。なぜ戦争の本だとわかるのかといいますと、わたしは文房具屋に通うのと同様に本屋にも毎日通っていたからです。なにか面白い本はないかなとぐるりと店の中をまわり、カバーの写真やイラストを眺めるのが日課でした。戦争の本は戦争の本だと書いてなくても見ただけでわかるのです。おおかた赤みを帯びた茶色か灰色なのです。もしかしたら店主のおじいさんは戦争経験者なのかもしれません。青春を戦争で過ごし、戦争の中に友達がいたのかもしれません。だからいつも読んでいるのは戦争の本で、つまり青春小説なのかもしれないなどとわたしは思っていたのでした。
戦争の本を読みながら怖い顔のおじいさんがどかりと腰掛けている文房具屋。まぁなんとも入りづらいではありませんか。しかしわたしが頑なにその文房具屋で原稿用紙を買う理由はふたつありました。
ひとつは、スタンプカードです。買い物をするごとにポコンと「松」のスタンプが押してもらえて、50個たまると500円の割引券になるのです。どうして「松」なのかはのちほど。
もうひとつは原稿用紙の種類が豊富だったからです。原稿用紙といっても何種類かあります。レポート用紙のように綴られているもの。これは筆がのりにのったときに良いものでした。それから二つ折りにされて袋に入っているもの。これは紙の質も良くなによりサイズが大きいので字を書いている感覚が長く続き、筆が遅いときに良いものでした。すこしクリーム色が強い原稿用紙もありました。これは目が疲れたときに良いものでした。サイズの小さいもの、これは出先でさらっと書けて携帯用でした。覚えているだけでも四種類。原稿用紙をここまで揃えている文房具屋さんはそうないでしょう。その日の気分で原稿用紙が変えられました。
「なに書いてんだい」
わたしは驚いてお釣りを取り落としそうになりました。
「小説でも書いてんのか」
しわだらけの顔が難しそうに歪み、わたしをぎろぎろと睨んで言うものですから、返事ができませんでした。その日は逃げるように帰りました。
帰宅したわたしは、ちゃぶ台に突っ伏し、ばくばく鳴り続けている心臓をぎゅうぎゅう押し付け、自分の中でたえず流れ走っている世界線に指を引っ掛けられた気持ちでした。恥ずかしいという気持ちでした。恋文を書いているわけでもなしに、なにを恥ずかしがることがあるのでしょう。まぁ当時のわたしはシャイだったのです。せっかく原稿用紙を買って帰ったのに、その日は一枚も書けませんでした。わたしの中の小さな世界はどくどくと波打ってしまい、形にならなかったのです。
目を開けると朝でした。
書きためた小さな世界はおそろしいほど巨大な塊となっていました。わたしの背後には実にさまざまな種類の原稿用紙で紡がれた物語がめちゃくちゃに積まれていて、ばらばらになっていて、部屋の中で銀河になっていました。
わたしはその中から戦争ものを取り出しました。養父から伝え聞いていた戦地で焼いて食べた青いバナナの話でした。おいしかった、養父は生前、思い出してはきいてもいないのに言っていました。なのに第一線で失った戦友の話はひとつもしませんでした。わたしがいまも大切に持っている養父の遺品、血染めの日の丸の話も、尋ねても答えてもらえませんでした。
きりで穴をあけ、紐でくくり、わたしは青いバナナの短編を持って文房具屋に行きました。
なぜ持っていったのか。わかりません。たぶん、恥ずかしかったけれど、嬉しかったのかもしれません。わたしの筆に興味を持ってくれる人に、初めて出会えたからかもしれません。
店主のおじいさんはやっぱり戦争の本を読んでいました。表紙には日の丸がありました。
わたしは新聞配達でもするみたいに、さっと目の前に置いて、小走りで原稿用紙の棚に行きました。今日は二つ折りにしようか。そんな囁くような声で別に意味もないことを呟き、背中でおじいさんの反応をうかがっていました。
いつもならすぐに買って帰ってしまうところを、今日は熱心に選んでいるふりをしました。
「バナナか」
驚いてわたしは振り返りました。
おじいさんは戦争の本を横に置き、わたしの小説を読んでいました。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
