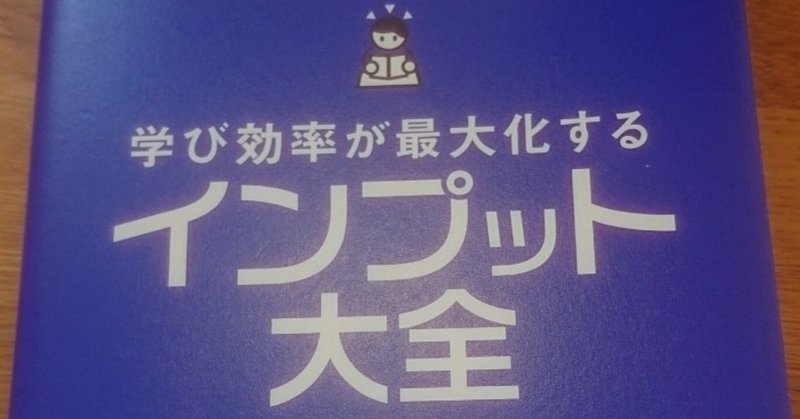
2週間以内に3回ルールで記憶を定着させる
「記憶を定着させるには2週間以内にその事柄を3回繰り返す」という脳科学的アドバイスがありました。昨日が1回目で、今日は2回目です。
(『ITエンジニア本大賞に当選したので読もう【学び効率が最大化するインプット大全】』の振り返り)
1.アウトプット前提でインプットする
例えば★人前で発表する、Slideshareで公開する、noteに書く、など、アウトプット前提でインプットする。適度な心理的プレッシャーがかかり、ノルアドレナリンが分泌される。ノルアドレナリンが分泌されると、集中力が高まり、記憶力、思考力、判断力が高まる。
もっと簡単に★「今度○○さんに会ったときに話す」だけでも良い。
ロンドン大学の研究で、Aグループには「これが終わったらテストをするから暗記しておいてください」Bグループには「これが終わったら他の人に教えてもらうので暗記しておいてください」と言い、同じ時間をかけて同じテストをしたところ、Bグループの方が点数が高かったらしい。
これは継続的にやっている。あ、そうそう。今度、久しぶりに会う友達にこの話をしようっと。
2.インプットと目標設定はセットで
勉強する場合、本を読む場合、何かをインプットする前に、「なんのためにするのか」を10秒考える。
次に読む本は・・・サブスクリプションの本。今後、顧客やチームメンバと一緒にサブスクリプションモデルビジネスについて、
1.サブスクリプションとはなにか
2.従来ビジネスとの違い
3.実現の難しさ
4.自分や自組織で実施する場合の問題と課題
を議論できるようになろう。そのためにはここでまとめるか。
3.2週間に3回アウトプットすると記憶に残る
例えば、★同じテーマを2週間かけて3回のnoteの記事にする。
これはいまやっている。
4.月1冊~+アウトプット
ただ読んでもほとんど頭に残らない。読んでアウトプットすることで定着する。★月1冊読んで、読んだ内容を他の人に話す。
サブスクリプションの本を読んだら、早速、チームメンバや上司に聞いてもらおう。そのためには多少まとめた資料が必要だ。★インプット大全と同じ用にnoteにメモしていこう。
5.自然音を聴く
単純作業には音楽は効果的だが、頭を使う場合は良くない。頭を使う仕事の際には自然音や環境音を聴く。You Tubeなどで★「頭を使う仕事用」のプレイリストを作っておく。
流行りのASMRの曲を2つ見つけた。これをプレイリストにしよう。これから徐々に増やす。
6.観察+なぜ?の繰り返しで頭のトレーニング
ふとしたタイミングで、物事や人の行動をよく観察してみる。不思議に思ったことを「なぜ?」と考えてみる。想像(妄想?)して色々と考えてみる。そのことをすぐに調べてみる。
この繰り返しで知識や脳の働きが深まる。
観察+なぜ が豊富にあるのは「街歩き」「旅行」「美術鑑賞」。特に、★美術鑑賞は自分がどこに興味を覚えたかを他人に伝える。
これは・・まだできていない。が、美術鑑賞には今年行く。
7.興味のある分野の情報が自動的に入ってくるようにする
★情報収集したいテーマを決め、RSS、キュレーションサイトのフォローなどで情報を自動取得する。また、見る時間は限定する。ネットサーフィンはインプット最大の愚行。情報を探しに行くのではなく、情報を届けてもらう。
8.情報アンテナチャート
★マンダラチャートを作成して、自分の目の届く場所(GoogleDriveなど)に置いておく。チャートを見て、収集したい情報に対するアンテナを高くしておく。
これは★今日これから作成してみる。
9.寝る前15分にインセンティブを与える
寝る前15分は最も記憶に定着しやすい時間帯。なぜならそのまま睡眠に入ると記憶の定着を妨害する因子である「記憶の衝突」が起きないから。気持ちよく眠る快楽を取りたいところだが、平日はここをインプット時間にあてる。また、インプット時間を1日1時間としたとして、★寝る前の15分は日中の60分に相当するというインセンティブを与える。(つまり日中1時間せずとも寝る前15分すればOKというルール)
昨日寝る前の15分でインプットの時間を設けました。
10.運動で記憶力を高める
★週に合計2時間以上の有酸素運動を行うことで、脳が活性化することがわかっている。ウォーキング、ランニング、水泳など。自分の場合は、ランニング30分+ウォーキング30分×2。
また、運動中は脳が活性化することから、★デュアルタスクトレーニングを行う。具体的には、ランニングにオーディオブックを聴く。
昨日、audiobookの会員登録した!そして寝る前に聞きました。(スティーブ・ジョブズの名言集)これから夜寝る前に聞く。または移動時。
★ランニングはこれから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
