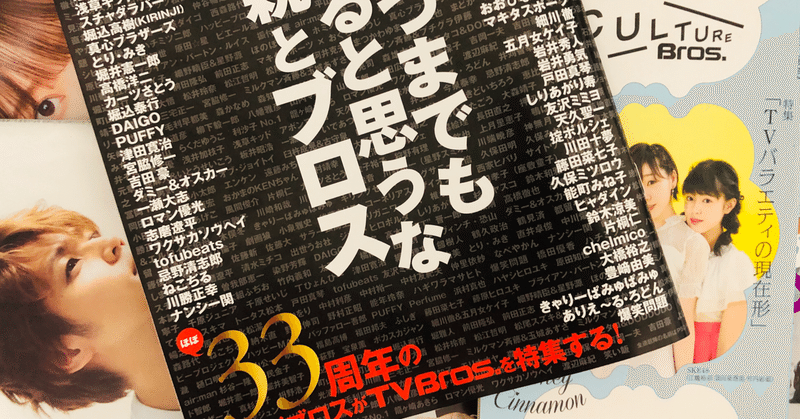
『テレビブロス』定期刊行終了についてと、バラエティを制作者で追うということについて。
『テレビブロス』(以下、『ブロス』)の紙での定期刊行が終了した。これからはnoteに場を移すらしい。
ついこの間まで高田馬場の孤独な大学生だったのだが、刊行日に必ず書店に足を運んだ。「雑誌エリア」の「テレビ棚」からそれを引っ張り出すときちょっと誇らしい気持ちだった。「こんな言葉を読みたいんだろ」と言いたげ雑誌ばかりの棚にあって、凛とした佇まいでいるブロスが好きだった。
買ったあとは必ずひとつ下のフロアの定食屋さんでお刺身定食を食べた。マグロだけ解凍があまい刺身定食。シャリシャリして嫌だから醤油で溶かして食べた。2時間くらい長居して『ブロス』を読んでたから、トントン。でも、最終刊な今回に限って定食屋はコロナでおやすみ。あの頃とは本当にさよなら。
私は、おそらく愛が強いブロス読者であっただろうが、そんな私でもブロスが形態を変えざるを得なくなったのは半ば必然であると考えている。それは「テレビ的」というシーンを括る概念自体が雲散霧消したからだ。もちろん『ブロス』側もその現状を取り込み番組表の掲載をやめるなどのリニューアルを行なったが、それ以上に「”テレビ”ブロス」という語り口自体が存立不可能な時代になったということだ。
「テレビ的」といえるシーンはどこにあるのか。そして、note版『ブロス』にどのような切り口を行なって欲しいかについて考えてみた。
心に残っている号がある。『テレビブロス』本誌のスピンオフ誌、『CULTURE BROS.』での「TVバラエティの現在形」という特集。2016年に発売されたもの。当時『人生のパイセンTV』(フジテレビ)の総合演出であった萩原啓太(愛称:マイアミ・ケータ )と『しくじり先生』(テレビ朝日)の総合演出であった北野貴章(テレビ朝日)を「型破りな新たな才能」と紹介し、対談を組んでいた。
そこでは以下のような言葉が交わされていた。
北野 僕はテレビ朝日には映画に携われるかなって思った入りました。でも先輩方の中にドラマや映画のプロデューサーはいても、監督はほとんどいない。だったら、バラエティでディレクターをしたいと。(略)ウチにはコント番組の文化がないので、フジテレビさんのコント番組の文化が羨ましいですね。
マイアミ コントはやりたいですね! 僕、『リチャードホール』が大好きで、特に「汗のマークの引っ越しセンター」が。友達と集まってゲラゲラ笑って見てましたから、「スゲーな、ヤベーよ」と言いながら。
北野 佐久間(宣之)さんがやってた『SICKS 〜みんながみんな、何かの病気〜』(テレビ東京系)は、自分がいつかやりたいと思っていた形式で、めちゃくちゃ悔しかったです。
マイアミ 強い思いを制作者がもっていないと、どんどんテレビがつまらなくなりますよ。絶対。僕がチャラく振る舞う様子をガンガン放送にのせるのは、テレビ局って楽しんだな、って若い世代のみなさんに感じて欲しいから。
「次世代のテレビを担う」とされていた作り手たちが2016年に「何に憧れ」「何を夢見ているのか」がありありと伝わってくる。
その後、マイアミ・ケータはフジテレビを退社。
【ご報告】
— マイアミ啓太 (@miami_beach5577) December 2, 2019
先月いっぱいでフジテレビを退社致しました。
今後はテレビだけに留まらず、Youtube/映画/PV/MV/CMと幅広く映像制作をしていきます。
そして夢であったクリエーターの育成事業、就活生のサポートもしていきます。宜しくお願い致します!
対して、北野貴章は『しくじり先生』というパッケージの中で「お笑い研究部」という”出島”をつくり、最近はそれがSNSのお笑いファン周りを中心に評価されている。地上波のブランド力を借りながらあくまでも主戦場はABEMA。コント番組はつくれなかったが、「しくじり学園」というテーマが決められたある種の演劇空間をつくることでコント性を担保している。例えばある回の『しくじり学園お笑い研究部』で行われた「ロケ番組で爪痕を残そう」なんていうテーマは、「『テレビ的』を”出島”から臨む」そんなスタンスを感じる。
「コント番組の文化が羨ましい」「テレビ局って楽しいんだな、って若い世代の皆さんに感じて欲しい」という、上の対談は今読み返すと字面以上の読み込みを禁じを得ない。ここ3〜4年の若手ディレクターのポジショニングから「『テレビ的』なものの融解」が見られる。
先日、『佐久間宣之のオールナイトニッポン0』の藤井健太郎(TBS)ゲスト回で以下のような会話があった。
佐久間 テレビって志したのっていつですか?
藤井 なんとなく志したのは、中高生、早めだと思うんですけど。中高生くらいで『電波少年』。裏方が面白いことを考えて、面白いことできそうだなって感じが。薄っすらとですけど。
佐久間 そうだよね。あの、やっぱりそこが全く。年齢は5個離れてるんですけど藤井さんと僕が全く違うのは、僕が『夢で逢えたら』と『めちゃイケ』だから演者側が面白いという番組を観てたのね。
藤井 そうですよね。
佐久間 それで藤井さんくらいから下の世代になると『電波少年』があって、制作がこれを仕掛けるというのにすごく喜びを見出すクリエイターがすごい増えるよね。
佐久間宣之が手掛ける『ゴッドタン』や『キングちゃん』などは、その番組のレギュラーを務めるタレントのイメージ形成に大きく貢献した。(『ゴッドタン』であれば劇団ひとり、おぎやはぎ。『キングちゃん』であれば千鳥。)
しかし、藤井健太郎が手掛けた『水曜日のダウンタウン』や『クイズ!タレント名鑑』などはそのレギュラーを務めるタレントのイメージを新しくはしていない。
そして、藤井の下の世代のマイアミ・ケータと北野貴章がそれぞれの番組(『人生のパイセンTV』、『しくじり先生)で起用したのは若林正恭(オードリー)だった。その若林について、上で引用したインタビューで以下のように語ってる。
マイアミ 僕はおバカなので、作るVTR は必然的に「ボケ」要素が高くなる。だから、的確にツッコんでくれる若林さんが必要だと思って。
北野 『しくじり』の企画が通ったときに、MCなしの番組にしたかったんですよ。会社に企画書を通しても、「MCが弱い」って理由でボツになることが多くて。(略)『しくじりに関してはメインはあくまでもメインは先生ですから。なので、特番のときは若林さんも生徒の一人という形でした。誰よりも楽しんで授業を受けてくれるのが若林さん。だから今もMCっぽいことはしてもらってないです、わざと。
若林の便利使いのされっぷりが愛らしいが(笑)。上のように藤井健太郎世代以降のテレビディレクターたちはイニシアチブを持ちたがる傾向にある。これはおそらく芸能界というものの変遷と表裏であろう。
(そして、これに対して佐久間が手掛ける『あちこちオードリー』はオードリーの「ラジオパーソナリティーとしての一面をテレビ化する」という点で、彼らのイメージを刷新している)
以上のように「テレビ的」なものそれ自体がスクラップ(&ビルド...??)されている今、芸能人のインタビューを主軸に据えてアジェンダ設定をすることに価値はあるのだろうかと考える。
このようにテレビ制作者のスタンスが大きく変わってきている今だからこそ『ブロス』のリニューアルに期待したい。なぜなら、タレントサイドに諂い切らない編集スタンスこそが武器であったはずだから。これからも読む時に誇らしい気持ちになれるような雑誌であって欲しい。
(了)
サポートは執筆の勉強用の資料や、編集会議時のコーヒー代に充てさせていただきます
