
村上春樹が記録したレストランの風景
1999年に発表された「スプートニクの恋人」は超絶技巧の比喩を散りばめた文体と、「こちら側」と「あちら側」を行き来する幻想性で知られるが、同時に世紀末の東京の日常を凍結保存した描写が、作品を際立たせている。
例えば、ミュウとすみれは、食事の際にこんな会話をする。39歳のミュウが22歳のすみれをレストランに連れていくシーンである。
ミュウはいつも白身の魚を食べ(たまにチキンを注文して半分残した)デザートをパスした。ワイン・リストを子細に検討し、ボトルを選んでとったが、本人はグラスに一杯しか飲まなかった。
「あなたは好きなだけ飲みなさい」とミュウは言ったが、すみれにしても、いくらなんでも一人でそんなには飲めない。だから高価なワインのボトルはいつも半分以上残ったが、ミュウはとくに気にしなかった。
「二人でボトルを一本取るのはもったいないんじゃない、半分も飲めないのに」とすみれはあるときミュウに言ってみた。
「いいのよ、それは」とミュウは笑って言った。
「ワインというのはね、たくさん残せば残すほど、多くのお店の人たちが味見できるの。ソムリエ、ヘッドウェイターから、いちばん下の水を注ぐだけの人までね。そうやってみんなでワインの味を覚えていくわけ。だから上等なワインを注文して残していくのは、むだじゃないのよ」
1990年代中期、メドックの格付ワインが三千円前後、ムートン・ロートシルトなどの一級シャトーでも若い年代なら一万円前後で買え、焼き鳥屋でDRCのワインが飲めた時代、年上の方からこう言われたことを鮮明に覚えている。
安いワインは飲み干しても良いが、良いワインを頼んだ際は、ボトルの3分の1くらいを残して店を出ること。
残したワインは、店の中の誰かが飲み、それが東京のレストランシーンを循環させて新たな才能を育て、我々は十数年後にどこかの店でその恩恵を受けることができる。
但し、ワインを残す際には、店の人に何も言わず、次に訪れた際も全く触れないこと。あくまでも「自然に」残していくこと。
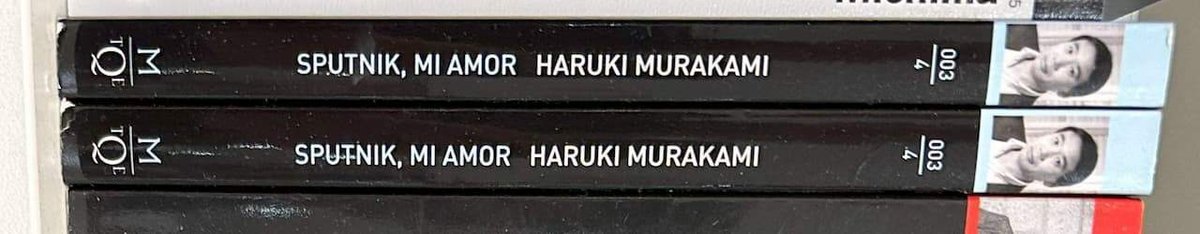
村上春樹は、スプートニクの恋人を「楽しんで書いた小説」であると記している。村上の周囲の光景が取り込まれ、フィクションと絶妙に絡み合う。作者はその過程を楽しみながら作品世界を構築していったのではないだろうか。
もし僕の書いた小説群を「比較的楽しんで書いた小説」と「比較的苦しんで書いた小説」にわけるとすれば、この『スプートニクの恋人』は楽しんで書いた小説の最右翼に位置するのではないかと思う
世の中には、幻想的なシーンを含む小説は数多あるが、村上作品が際立っているのは、こういった日常描写の解像度の高さである。
単なる身辺描写ではなく、実生活で時々生じるエアポケットのような瞬間を美しく捉え、何気なくフィクションに挿入する。その技巧が、作品に独自の息吹を与える。

2023年の冬、東京の街は世界各国の観光客で溢れている。質が高くバラエティに富んだレストランが、世界中の人を魅了し、食の都としての東京の地位は確立されているかのように見える。
しかしながら、一昔前の状況は異なっていた。1980年代後半から90年代にかけて海外で多くの時間を過ごした村上春樹は、1994年のインタビューで下記のように述べている。
たまに日本に帰ると『なんでこんなにお金がかかるんだろう』と愕然としちゃいますよ。レストランがそれほどおいしくないんで、外食をあまりしないというメリットもありますね。日本に住みたくないとか、外国がいいとかいうんじゃなくて、ひとつの別の可能性として外国に住んでいるという感じですね」
実際、当時の東京のレストランはそんな感じだった。例外はあったが、全体としてはそんなに大したことはなかった。だから村上作品の主人公のように、パスタを家で調理する必然性もあった。
前世紀末から今世紀にかけて、東京のレストランシーンは著しく発展した。その背景には、レストラン側の努力に加えて、生態系を育てた顧客側の貢献があった。そんな何気ない風景の一端が、小説の一場面という形で後世に伝えられるのは、とても素敵なことだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
