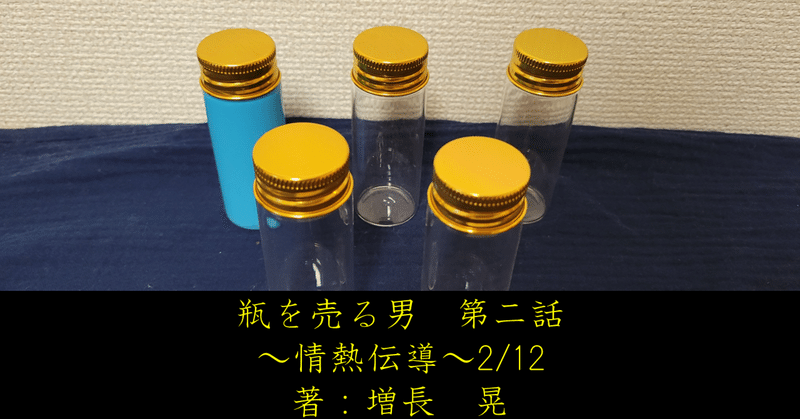
瓶を売る男 第二話 ~情熱伝導~ 2/12
K市は毎年八月、K夏祭という夏祭りがある。祭りの時期は警察の仕事が多い、交通課はもちろん、祭りの現場は窃盗犯罪が通常より起きやすい。祭りはまだ先だが、これから忙しくなるため今抱えている仕事を減らしておく必要がある。
中村が退勤したのは深夜十一時を回るころだ。明日も朝八時から仕事があるというのに、家に帰らず署に泊った方がいいような気がしてきた。しかし腹が減ってしまった。とりあえず中村は署を出て最寄りのコンビニに足を運んだ。
同じ店でも深夜のコンビニは日中とまるで違った顔を見せる。そこにいる人間が違うからだ。夜勤の店員も、この時間に利用する客も日中とはタイプが異なる。店員は一人、商品の補充をしている。客は自分の他に女子高生一人と、小さい子を連れた不良夫婦が一組。
刑事の勘というのは、無いようで、ある。犯行を起こしやすい条件が揃った場に出くわすと、無意識に警戒してしまうのだ。
「こんばんは」
一人の女子高生に、中村は背後から声をかけた。返事は無い。しかし彼女の手は止まった。その手に握られた板ガムは、かごに入れるふりをして左手の袖に入れようとしていた。
「それを戻せば誰にも言わない」
中村に言われ、少女は右手に持っていた板ガムを棚に戻した。夜とはいえ、七月下旬だというのに長袖のパーカーを着ている。棚に向かうのではなく横に立っていた。防犯カメラに背を向ける立ち方だ。
「よし、それでいい」
少女は何も言わず、微かに震えていた。
歩き方からして怪しかった。人の視線に敏感な素振りで、空のかごを提げて同じ場所にずっと立っている。手は動いているが、かごの中身が増えない。ただの買い物客の立ち居振る舞いではない。刑事課の目から見ればなおさら訝しい。
「その制服、K西高か?」
中村が問うと、少女は頷いた。しかし中村は小さく笑って言った。
「君の丈に合っていない。それに鞄と制服が違う学校の物だ。他人の制服だろう?」
少女は答えない。中村はため息をついて口を開いた。
「すぐに店を出よう。ご両親を呼んでここに来てもらうんだ。それまで一緒に待ってやる」
「お願い、親には言わないで」
微かに震える声で少女は言った。しかしその声は震えていたものの、一切の温度を感じない。
「わかったよ。店の外にタクシーを呼ぶ。その前にちょっとだけ買い物をするからな」
お茶とプリンを二つ買い、レジ袋を提げて店を出た。駐車場の隅、街灯も店の照明も届かない闇の中に彼女はいた。
「ちょっと待ってくれ、タクシーを呼ぶ」
中村は携帯を取り出し、タクシー会社に電話をかけた。その間この少女について考えていた。下手な万引きだ。初犯ではないが、慣れていない。周囲に同学年と思しき者はいなかった。誰かに命令されてやったわけではない。気になるのは他校の制服で偽装したことだ。服の丈が大きすぎる。その不自然に自分で気づかなかったのか。それとも何か理由があったのか。
「あと十分で来るそうだ。ほら、食いな」
そう言って中村はプリンを差し出した。少女はこちらに一瞥もしない。先ほどのように怯えてもいない。闇の中でも無表情が分かる。呼吸をしているのかも怪しいほど静かだ。
「なんでこんな時間に外に出ていたんだ?君は未成年だろう」
「別に」
「どこの学校の子だ?」
「なんでそれ言うの?」
「防犯のためだ」
「警察みたい」
「警察なんだよ。警部補の中村だ」
中村は名刺を渡した。名刺を受け取った少女が一瞬だけそれに目を落とし、ポケットにしまって再び闇を見つめ始めた。
「君がここや他の店に迷惑をかけないために学校に連絡をしなきゃならん。何より、君みたいな若者を犯罪者にしないために、話を聞きたいんだ。青少年の深夜俳諧は犯罪に繋がりやすいからな」
「…佐々木」
「ん?」
「佐々木小夏」
少女は小夏と名乗った。着ている制服は本人の物ではないのだろう。どこの生徒なのか分からない。
「そうか。この辺に住んでるのか?」
「さぁ」
「こんな時間に出歩いていた理由は?」
煙草に火を点けながら中村は聞いた。ケント6ミリの最後の一本だ。さっきのコンビニで買っておくべきだった。
「退屈だったから」
「退屈なら寝てろ。あるいはネットかゲームでもしとけ。その方が万引きよりずっと健全だ」
「それにも飽きたの。全然楽しくない」
「万引きは楽しかったか?」
言うと、小夏は黙った。
「夏休みなのはお前たち高校生だけじゃない。他県の大学生が帰省したり、あらゆる問題児が活発になるからトラブルも起きやすい。特に夏の夜は涼しいから外出する連中も多い。君が巻き込まれないために、深夜はおとなしくしてほしいんだ」
小夏は相変わらず無言だ。年上の説教に納得した様子は無い。
ふと中村はさっきのコンビニに目をやった。子連れの不良夫婦が騒がしく店から出てくる。小夏はその家族を一瞥し、すぐに目をそらした。興味がなさそうだ。
近年、非行少年は減少傾向にあると言われているが、そんなものは見え方の問題だ。青少年の問題行動に気付きづらくなっただけで、SNSやソーシャルコミュニティでは少年たちの蛮行が蔓延っている。
情報化社会の負の影響だ。有害な情報に触れやすくなったり、そう言った人間と接しやすくなったこと、またネット上であれば罪の意識が軽くなること。たしかに刑法に触れる非行は減っているが、それは決して、青少年の精神の成熟度が上がったからではない。
ネットやゲームには飽きた。もう楽しくない。先ほど小夏はそう言った。彼女が重度のネットユーザーである可能性は十二分にある。そういった人間は時として、自分を構成する要素を他者に依存することがある。細胞の代わりに、他人の情報で自分を作るのだ。
自分の血肉より他人から借りた要素を武器にする。中村はそう言った人間に嫌悪がある。なぜ自分の強さを信じない。なぜ返しもしないくせに他人の力を頼り続ける。借りたものに依存する。そんな人間は、弱く見える。
お前のことだぞ。遠藤。
「お、タクシー着いたな」
中村が言うと、小夏は目を上げた。眩しいヘッドライトが駐車場に入り込み、二人の側で止まる。ドアが開き、小夏が中に入る。
「すみません、これでお願いします。お釣りはその子にあげて下さい」
中村が運転手に二万円を渡しながら言った。
そのまま小夏と何も言わず、タクシーは発車した。運転手に行き先を伝えているようだが、相手の目を見ず、窓の外の暗闇を見つめていた。そこで違和感を覚えた。スマートフォンを持っていないのか?
中村は小夏が重度のネットユーザーであると思っていたが、彼女は一度もスマートフォンを見ていない。それどころか、渡した名刺も一瞬だけ見てそれ以外はずっと暗闇を見ていた。膨大な情報の海に汚染されたのではない。むしろその逆で、虚無だ。
虚無の少年。TWENTYでのことを思い出した。この少女は他人に依り続け混沌に溺れる遠藤というより、どこまでも虚無な小林という少年に近いのではないか。
気付けばタクシーは光の尾を残して遠くへ消えていた。音も光もない、静かで冷たい闇の中に身を投じられた気分だ。
これが現代の若者のいる世界、その一つか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
