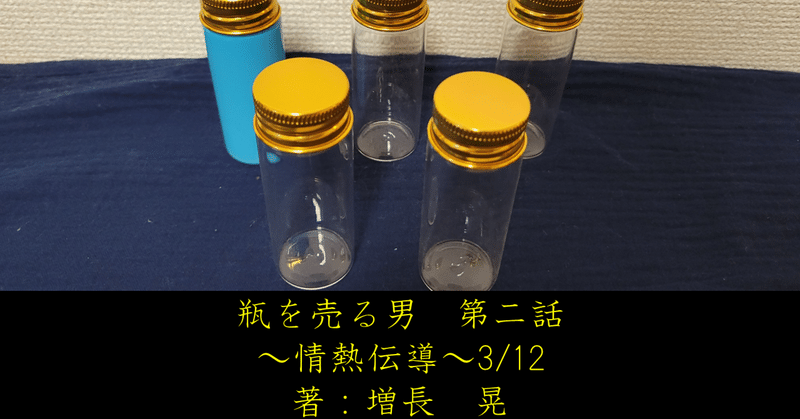
瓶を売る男 第二話 ~情熱伝導~3/12
この店は十一時開店、夜八時閉店だ。小林は普段、夕方五時から八時までのシフトに入っているが、夏休みに入ったことで小林はフルタイムで働けるようになった。最近知ったことだが、中学生のアルバイトは労基で禁じられているらしい。その点この店は監査で一発不合格になるのではなかろうか。
そして今小林が何をしているかというと、女性用の浴衣を着せられ、そして女性用のメイクを施され、写真を撮られてネットで晒されている。
「よしよし、いい感じだ」
満面の笑みを浮かべるのは遠藤だ。どうやらこの夏の期間中、紳士服だけでなく浴衣も仕立てるらしい。その宣伝のため、小林をモデルとするようだ。小林は線が細く少年の割に顔が整っている—と遠藤が言っていた—ので、女子学生向けのモデルに最適なのだという。色とりどりの浴衣を何着も着せられ、顔を何度も変えられた。異性の格好をさせられる不快感は無かった。メンズの浴衣の写真も撮られたが、レディースと同じ気持ちだった。
ちなみに大人用のメンズとレディースの浴衣は遠藤本人がモデルとなり、小林が写真を撮った。遠藤は普通の男性より少し背が高く肩幅も広い。それなのに女性の浴衣を着てメイクをした途端、その佇まいは女性の物となる。加えて自分の線を細く見せるカメラの角度や、帯の結び方に工夫があるのだという。遠藤の元々の体格と浴衣を着た際の線の細さを比較する写真を撮り、それも宣伝した。たちまちホームページに女性客の予約が殺到したという。
浴衣はオーダーメイドとレンタルの二種類あり、レンタルは学生でも手を付けやすい値段である。そのため、同級生も何人か客として来た。ゆえに遠藤は、小林の身元がばれないように小林を変装させた。
「中学生が働くのは労基違反なんだ。だからお前を変装させるし、俺の親戚ってことにするぞ」
「それは分かりますが、なんで僕が女装なんですか?」
「宣伝になるからだ」
「じゃあなんで遠藤さんは紳士服なんですか?」
「宣伝になるからだ」
小林は藤色の浴衣を着てロングのウィッグを被り、簪まで着けられた。対して遠藤は半袖の白シャツにベスト、首からメジャーを垂らすいつものテーラースタイルだ。
生きた看板となった小林は女性客の注目の的となった。中にはツーショットをせがまれ、SNSに上げたいと言い出す客もいた。遠藤の承諾を得て小林は了承したが、なんど写真を撮られても、小林は笑顔になれなかった。「人形みたいでミステリアスなのが良い」という感想を貰ったが、それなら人形に服を着せて立たせればいいのではないかと小林は思った。
その日は看板だけでなく客の案内や予約の受付などあらゆる業務をこなした。浴衣は重い。一日中浴衣で仕事をしていれば額に汗が浮かび、それを拭うとメイクが崩れる、ということが何度もあった。そのたびに遠藤が直すのだ
そんな忙しい一日の夕方、客足が減ってきたころに休憩に入った。小林はいつものスーツに着替え、メイクも落とした。
これから遠藤から、特別授業がある。貰った指輪の使い方と、“霊素”の理解を深めるものだ。
霊素、それは霊魂を形成すると言われている物質で、生き物の体の外では結晶として存在する。その結晶を材料に瓶を作り、取り扱うのがこの店TWENTYである。
「霊素が観測されたことは無い。電子顕微鏡やx線でもその姿を捉えることはできない。ただ霊的な世界に繋がりを持つ太古の特殊な能力者のみがその存在を知覚できる。平成の日本では関係ない話だ」
遠藤はそう言いながら第二客室の瓶の作業をしていた。大小様々な瓶の中身を移し替え、漂着瓶を消費している。あれは誰かから買った感情を漂着瓶に移し、その漂着瓶に対応する持ち主の心を満たしているのだ。
「霊素に対する解釈はいろいろあるが、俺たち結晶協会の人間は霊素を粒子の一種だと解釈している。その粒子による結晶格子—つまり結晶の立体構造—の形に応じてそこに刻まれる霊情報—記憶とか感情みたいなやつだな—を記録する。ここまでついてこれるか?」
「粒子って何ですか?」
「あー、目に見えないほど小さい粒だ。今は使い方だけ理解できればいい」
霊素や瓶については何度説明されても理解できない。ひとまず霊素がたくさん集まれば生き物の内部で霊魂として形成されることが分かった。それが生き物の外に出たら物体になる。その物体を瓶の形にして人の記憶や感情を封入できるらしい。
「霊素が霊魂を作るなら、この瓶は誰かの命から作られてるってことですか?」
「いや、霊素は自然界にいくらでも存在する。というより常に生き物から出たり入ったりしているんだ。人体でいうと、常に新しい水分と古い水分が入れ替わるようにな。生きた人間から取り出すようなことは決してしない。不可能だしな」
遠藤は瓶を棚に戻すと椅子に座り、コーヒーを一口含んだ。遠藤によって中身を満たされた霊素瓶は少し小さくなった。遠藤曰く、ある程度漂着瓶を小さくすれば—つまりある程度その人の心の空白を埋めれば—自分でそれをケアできるケースが多いらしい。現に遠藤によって小さくされた漂着瓶は、みるみる小さくなっていき、もう無くなりそうである。
「だから小林。くれぐれもその指輪や瓶を使うときは慎重にな」
珍しく遠藤が真剣な顔でこちらを見た。
「どうしてですか?」
小林が問い返すと、遠藤は同じ表情で答えた。
「本来なら人の記憶やそれについての心情は見えないし、触れられないものだ。だがうちの店の瓶はそれを可能にする。他人の心に触れるし、この目で見れるし、なんなら他の誰かに譲ることもできる。人の心が本来何であるのかを見失いがちだ。そういった意識が希薄になるのがこの仕事だ。だから覚えておけ小林。心は物じゃない」
そう思うならなぜ心の売り買いをしているのだろう。小林はそう思った。たった今目の前で誰かから買った心の一部を他の誰かの瓶に移し、その人の空白を埋めたではないか。人の心を物として処理したではないか。言っていることとやっていることが伴っていない。そう考えていたら、遠藤が椅子から立ち上がってこちらに小瓶を手渡してきた。
「まぁお前は分別のある子だから特に問題は無いだろう。人の心云々はどうせお前には難しい。それよりこれをやる」
「何ですか?」
「俺の記憶のコピーだ。霊素結晶があれば記憶の複製を瓶に入れることもできる。この瓶に霊素瓶の扱い方の記憶を入れた。最初はこの瓶で指輪の使い方を覚えろ」
「それって貴方の一部を物扱いしてませんか?」
「手続き記憶に人格があるか?自転車の乗り方なんてみんな同じだろ。それと一緒だ」
技術や能力に関する記憶は手続き記憶という分類に入るらしく、霊素瓶にはこういった記憶を入れられるらしい。小林が受け取ったこの小瓶には、遠藤がもつ霊素瓶の扱い方の記憶が入っており、この瓶を開ければその記憶が手に入るのだそうだ。
つまり遠藤の霊素瓶の扱い方の記憶はそこまで遠藤の人格の含有量が多くない。データをUSBに入れて他の端末に覚えさせるのと同じだ。
学ばずに覚える。賢い人の記憶を盗めば学校の試験で楽ができそうだなと思った。それを見透かされたように、遠藤は言葉を継いだ。
「言っておくが“覚えること”と“身に付ける”ことは別だ。俺の技量は“貸す”。お前自身にその技量を馴染ませるには実戦経験が要るぞ」
遠藤はそう言って、こっちを向いて左手でコップを掴む形を作り、それを飲むふりをした。小瓶の中身を飲めと言っているようだ。小林は小瓶の蓋を開け、遠藤の記憶を飲んだ。
まるで目覚める前の夢を思い出すように、見たことが無いはずのあらゆる“理解”が頭に入ってきた。人間社会の空白を満たす霊的な粒子を掴む感覚と、それを人の心に共鳴させて瓶を作る記憶。左手の指輪の異物感が少しだけ軽くなる。
「感想は?」
薄ら笑みを浮かべる遠藤が尋ねた。
「はやく試したい」
言うと、遠藤は小さく笑った。
「節度は守れよ。行ってこい」
小林は小夏の漂着瓶を持ってロッカーに行った。早く着替えて、彼女を見つけたい。それは覚えた技術を実践したい焦燥に似て、逆に突然覚えたばかりの技能に対する恐怖を和らげようとする防衛意識にも思えた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
