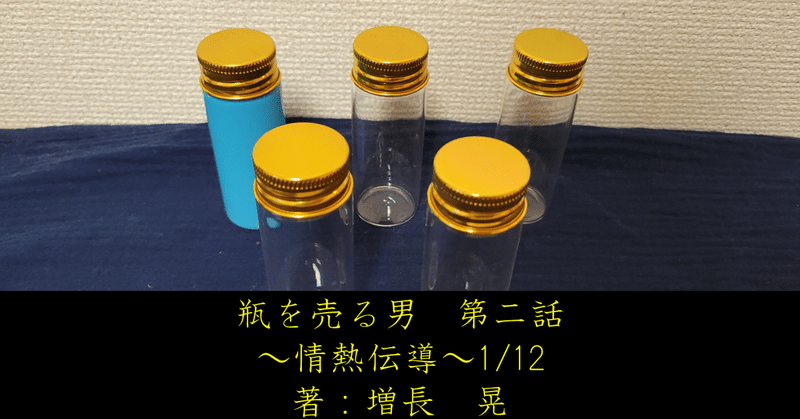
瓶を売る男 第二話 ~情熱伝導~ 1/12
七月の今日は終業式だった。つまり明日から夏休みである。夏休み期間中も小林はこの店でバイトをすることになっている。TWENTYで着る制服も夏服となり、半袖シャツにノーネクタイといった格好である。学校の制服の夏服とまるで変わらない。
服を着替えなければ気分が混在してしまう。学校にいるときは学校の制服を、バイト中はバイトの制服を着なければ、自分がこの世界の異物になってしまったような錯覚をするのだ。だから小林は店主の遠藤の許しのもと、ベストを着用している。喫茶店のウェイターみたいな格好だ。
ひとまず気分はバイトモードにしっかり切り替わった。ロッカーを出て第二客室に入る。
「遠藤さんおはようございます」
第二客室は相変わらず現実から切り離された別世界感のある部屋だった。9畳ほどの限られた空間の四方を背の高い棚が占め、その全てを大小色とりどりの瓶が、溢れんばかりに収まっている。壁に窓や時計は無く、外の音も一切入ってこない。耳に入るのは呼吸や衣擦れだけだ。
部屋の中央に応接用のテーブルがあり、紺色のテーブルクロスと応接セット。普段は遠藤がそこにいるが、今回はどうやら他の人物がいる。テーブルに汗をかいたカップが二つ、どちらもアイスコーヒーだ。
「おう、来たか小林」
振り返ってこちらを見たのは店主の遠藤だ。ネイビーの半袖シャツを着て、ワックスで短く切った黒髪を整えている。夏仕様の遠藤を見るのは初めてだが、相変わらずフォーマルで清潔感のある着こなしだ。そんな彼と向かい合って座る男が一人、中年の男がテーブルをはさんで向こう側に座っている。
「そうそう中村さん、この子がうちのバイト二号だよ。小林っていうんだ。よろしくな」
中村と呼ばれた男は「どうも」と一言発してこちらに頭を下げた。小林も会釈を返す。中村は四十半ばに見えるが、まっすぐな座り方や肩幅の広さ、何より真一文字に結ばれた口元と強い目力から、芯の強さを感じ取った。生きることに疲れくたびれた大人とは違う、自分の中に確たる強さを有する人だ。
「アルバイトの小林です」
「K県警察本部、刑事課、盗犯係、中村警部補だ」
中村はそう言って名刺を差し出した。小林はそれを受け取ると—正しい受け取り方が分からなかったが—、遠藤が横から口をはさんだ。
「中村さんは表向きは警察の方なんだが、今日は別の仕事なんだよ。この人は“結晶協会”の一員でもあるからな」
“結晶協会”とは、遠藤のように霊素結晶を扱う専門業者が加入を義務づけられる団体である。遠藤は霊素結晶で瓶を作り、人の心を売り買いする。そういった店には結晶協会の管理が必要なのだ。
「で、中村さんはこの店の監査に来られたってわけだ」
「カンサ?」
「うちの店でルール違反が無いか調べるってことだ。つまり、穏便に済む話だろ」
「たわけたことを。遠藤ともあろう男が規約違反の一つも犯さん方が異常だ。叩けば、いや、叩かなくても埃が出る」
中村がため息交じりにそう言った。調べなくても遠藤の規約違反を確信するあたり、遠藤は誰が相手でも“いつもの姿勢”を崩さないらしい。
「おおなんてひどいことを言うんだ、親愛なる中村警部補。貴方がこのK市の管轄になってから俺は一切の振る舞いに節度を持たせ、慎ましく真摯にこの仕事をしているというのに、いったい何が貴方の貴重な信頼を損なったというのか」
「先月だったかな。瓶を持った少年二人が土砂降りの中走っていたところを目撃してな。あの瓶はどう見ても霊素結晶の瓶だったし、蓋を開けた瞬間瓶が消えた。お前の店の商品だろう?」
先月の瓶——。かつての客である坂上と小林が瓶を抱えて走っていた時のことだろうか。(第一話参照)あれを目撃されていたのか。中村がこちらを見つめている。しかし中村は一瞬だけ訝しく首を傾げ、視線を遠藤に戻した。
「新しいバイト君は、表情が変わらんのだな。お前がこの子の感性を盗んだのか?表情が無ければ、隠し事もし易かろう」
「そんなひどい。俺は人から性格や人格の一部を不当に盗んだことなど一度もない。ましてやこの店の都合のために人様の大切なものを盗もうだなんて」
遠藤は声に悲壮感を含ませて言った。遠藤は人の記憶や感情を盗み、あまつさえ飲んだり飲ませたりしたことがある。しかもそれを旨いと言って愉しんでいた。まさに叩かなくても埃が出る男である。中村はそのような遠藤の人柄を知っているのだろう。それにしても、小林の表情の乏しさをこのような形で心配されるとは、遠藤の悪評のすさまじさというべきか、それとも小林の人間味の薄さというべきか。
「とにかく貴方の証言だけじゃあ当店の不正を証明できまい」
「では、この動画を見てもらおう」
そう言うと中村はスマートフォンを取り出し、二人に動画を見せた。ひどい土砂降りの映像だ。奥から二人の少年が走る様子が撮られている。前の少年が抱える瓶を後ろの少年に投げて渡し、前にいた少年は画格から消える。そして三人目の少年が映り込み、ややあって瓶の蓋が開かれた。やがて瓶は空気に溶けるように消え、片方の少年が突然頭を下げた。
「この映像は?」
「先月中旬、場所はこの店のすぐ近くだ。三人の少年の内一人は背格好がこのバイト君に相当する。そして映っていた瓶は見たところ、霊素瓶。この店の瓶だ」
「土砂降りのせいで音も顔も不明瞭だし、背格好だけで人を判断するなんて警察らしくない。それに霊素瓶の取り扱いは結晶規約に従っているだろう?どこが違反だというのか」
遠藤が冷静に反論する。対する中村もまた冷静だ。
「霊素瓶の扱いの規約は、霊情報の取引に双方の同意が必要であること。片方でも同意せずお前が無断で心や人格を瓶に詰め、盗み出そうとすれば規約違反だ。この動画にはその疑いが示されている」
「規約内容は知っている。俺はそんなことしてないし、その動画の証拠能力は不十分だろう?」
「だから、監査するんだ」
そこまで言うと中村はアイスコーヒーを一口含んだ。そして再びこちらを一瞥する。
「それにしても、この坊やはまるで動揺しないな。まるでお前のようだ」
遠藤みたいだなと言われた。心外だ。すごく心外だ。
「おい小林、お前さっきから馬鹿にされてばかりだが、ようやく褒められたぞ」
「御冗談を。僕なんか貴方の足元にも及びたくもないので」
「それを聞いて安心した。君はまだまともなようだ」
中村がそう言うものの、表情は険しいまま変わらない。微笑を浮かべているのは遠藤だけだ。
「ひとまず監査の件は了承したよ。日時が決まったら連絡してくれるんでしょう?」
「ああ、今回も俺が担当だ。前回はごまかされたからな。今回は徹底的に洗わせてもらう。あのバイトの少女はもういないからな」
中村はそう言ってコーヒーを飲み干すと、遠藤は微笑んで肩をすくめた。バイトの少女とは誰のことだろう?そういえば小林はバイト二号と呼ばれていたから、小林の前にバイトをしていた人がいるのだろうか。
「では失礼する。見送りは結構だ。監査は遅くても今月中になるだろう。君もあまり無理をするなよ。この男に悪い影響を受けるな」
そう言って中村は立ち上がった。普段は警察であり、片や結晶協会の監査官。人を取り締まるという仕事柄か、他人に厳しくなりがちだが彼個人は温情を重んじる一面もあるようだ。二人に一礼して踵を返すとき、遠藤が口を開いた。
「中村さん、その靴は古そうだ。よろしければうちで新しく買っていきませんか?」
この店TWENTYは表向きは仕立屋だ。無論、靴も扱っている。中村が履いている革靴は、この店で見たことのあるものだ。
遠藤は立ち上がって中村に歩み寄り、一通の封筒を差し出した。黒地に金の表記でTWENTYと書かれている。
「当店の無料利用券だ。初回限定一名様限り。だが貴方は次のご来店を初回にカウントしよう」
「賄賂か?くだらん。貰っておくが、約束はせんぞ」
遠藤から封筒を受け取り、鞄に仕舞って中村は背を向けて言った。
「靴はまだ履ける。この店が食い扶持を失った頃に、仕立屋の客として来よう」
中村は背中で答え、そのまま部屋を出た。
「あーあ、監査かぁ」
遠藤が椅子に座って背伸びしながら言った。
「で、どうする小林」
「何をですか」
「監査対策だよ。もちろん何もしなくてもこの店は法律を遵守しているが、念のため、あのオヤジが悪意を持ってこの店を潰しに来ないとも限らない。少しぐらいこっちが有利に傾くことをしなきゃならん」
この国の法律に、人の心を瓶に詰めて売ってはならないという法律は無い。しかし法律で定めるまでもない善悪はある。
「おう小林、選ばせてやる。中村の弱みを握って黙らせるか、恩を売って黙らせるか」
「どっちにせよ中村さんを黙らせる方向なんですね。不憫だなぁ」
「そうだな。ちなみに俺は前者がいい」
遠藤が笑って言った。もはや逃げも隠れも、しらばっくれるのも面倒になったという風だ。
「後者がいいです」
小林が答えると、遠藤が立ち上がり、瓶の棚に歩み寄った。
「こっちに来い」
温もりも冷たさもない声で遠藤はこちらを呼んだ。小林が近づくと、小さなリングケースをこちらに差し出した。黒地に、金の印字でDear TWENTYと書かれている。
「やるよ」
遠藤が微笑んでそう言った。ケースを開けると、中には小さな赤い宝石が埋め込まれた銀の指輪があった。
「赤い霊素結晶はレアだぜ。最初の持ち主の魂に共鳴する。つまりお前専用の指輪だ。人前で着けるなよ」
そう言うと、遠藤はこちらに左手を見せた。その中指に、先ほどは無かった指輪があった。小林が受け取ったものと同じ、赤い霊素結晶の指輪だ。この店の瓶もまた、霊素という同じ素材でできている。小林も同じ位置に指輪をはめてみた。少し重くて固い異物感がある。
「じゃ、今日も仕事だ」
「中村さんのことはいいんですか?」
「それもあるし、通常業務もあるだろ。今日のお客様はこれだ」
そう言って遠藤は一本の瓶を棚から取り出した。この町のどこかに住んでいる誰かの、行く当てのない心の空洞が、瓶の形になってこの店に流れ着く。それも満たし、心の持ち主に返すのがこの店の仕事だ。その手段として人の心を売り買いすることもあるが、今回はどうなるだろう。
「その指輪があれば瓶を通じて瓶の持ち主の情報を読み取ったり、その人の霊情報を入れる瓶を作れる。試しにその瓶の持ち主を見てこい」
受け取った瓶は見た目より軽く、傷も濁りも見当たらない。不気味なほど綺麗だ。瓶のラベルには、“佐々木小夏”と書かれてある。
この瓶が持ち主の心を表しているとすれば、彼女は心に傷も汚れも抱かず、しかし満たされぬまま正体の分からぬ苦しみを抱いているという事だ。
心に痛みも感じず、何の苦しみも知らない。なんだか自分に似ているなと思ったが、そこに一切の感慨は無かった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
