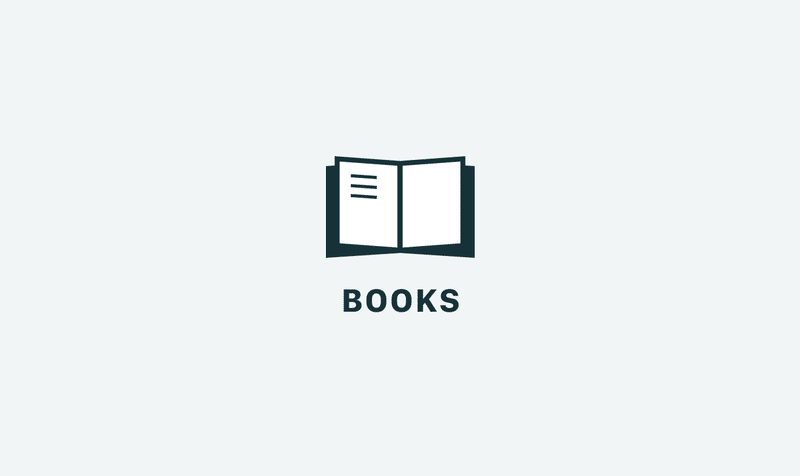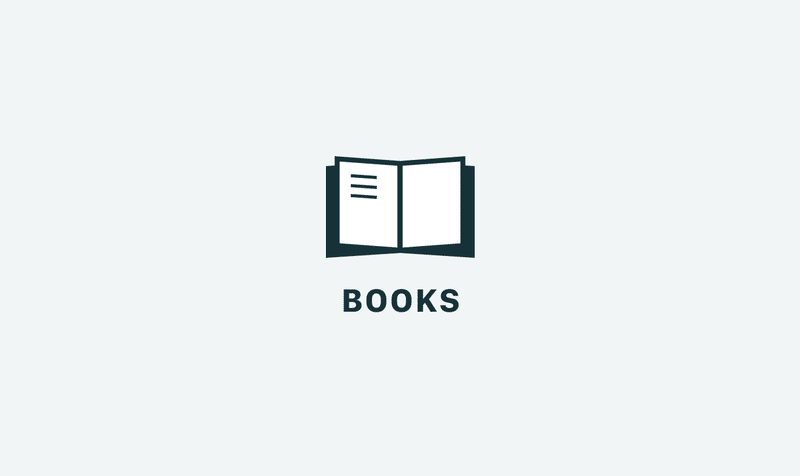同じ言葉と知識を持たなければ、対等な関係は作れないし、アイデアも生まれない
使う言葉と知識の量が違うのって何が駄目なんだろう、を考えてみた。で、いわゆる言葉遣いだったり知識の立場の非対等性が強まっちゃうと、嫌でも上下関係が発生してしまい、結果としていいアイデアが出づらくなるよね、ということなんじゃないか。
デザイナーなら、デザインスプリントという言葉を耳にしたり、実践したりした人は多いかもしれない。上記に紹介した本は、個々人が持つたくさんの情報を発散し、まとめ、最適解を選択していくものづくりの手法について言及している本だが、実際に中を見てみると思っ