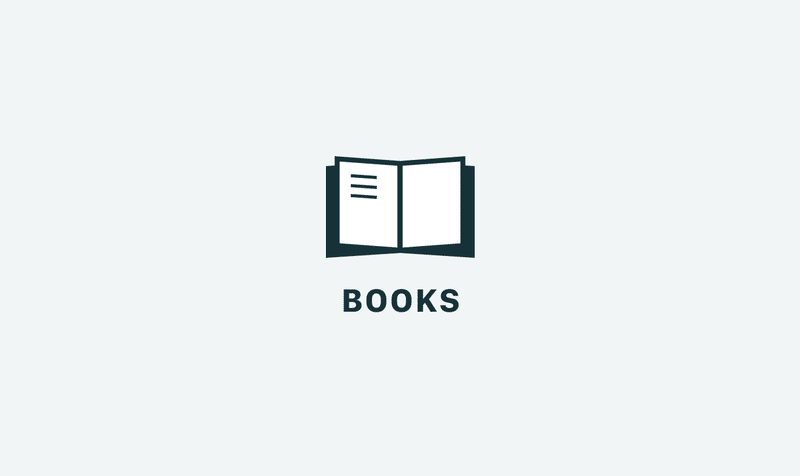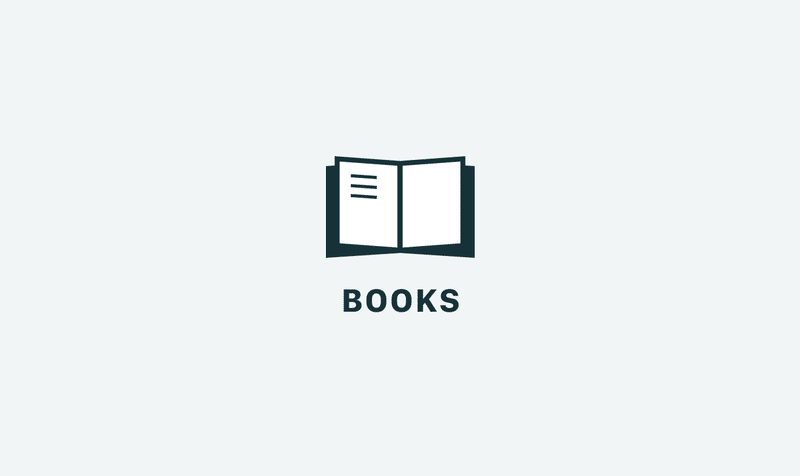舌打ちとひとり言が多いとき、その体はカチコチかもしれない
トゥレット症候群はチックという一群の神経精神疾患のうち、音声や行動の無意識な運動がとまらない症状のことである。例えば、汚い言葉を発することが止められない、鼻を鳴らしたり、指をたてたり、震えが止まらない、といった症状が挙げられる。
トゥレットであると診断されたわけではないが、私にも独り言をいったり、夜中に汚い言葉を叫んだりする癖がある。仕事や公共の場でそれらを行うことは無いため深い問題として捉えているわけではないものの(自覚してないだけかもしれないが)、それらがどんなときに起