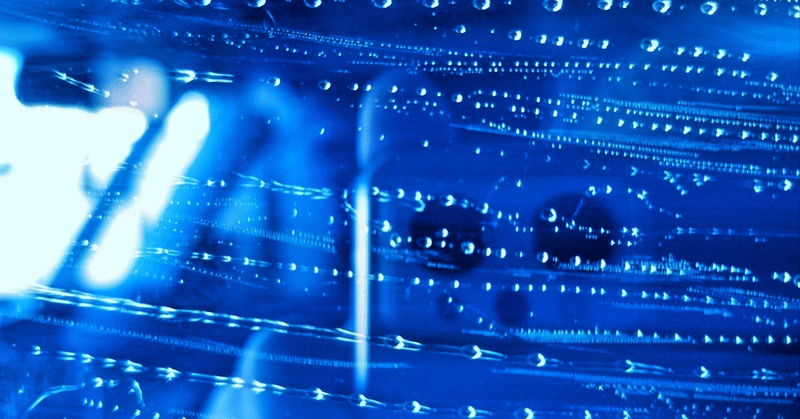
連載小説『エフェメラル』#5
第5話 再会
ユーヒは二重扉で仕切られたクリーンルームの中にいた。ユーヒの意識が戻ったとの連絡を受け全力で駆けてきたジルは、ユーヒの姿をガラス越しに確認する。ボンヤリとした目つきだが、ユーヒの目はしっかりと周囲を認識しているようだ。ユーヒの治療にあたった担当医師の説明では、身体機能、脳波とも異常なく、数日後には話せるようになるとのことだ。その言葉を聞いたジルは安堵した。まずは一つ峠を越えた。現状を月の本部に伝えなければならない。気を引き締めなおし、施設の通信機器を使って本部のレニー中将にユーヒの状況を報告する。
「ユーヒ様は無事に意識を取り戻しました。はい。そうです。少年はまだ意識が戻っていません。はい……了解しました」
レニー中将は、ユーヒの状況をゲンソウを経由でミジュに伝えるとのことだった。そして、少年の命があるうちに、身体から得られる情報を全て手に入れておけとの指示。ジルは別の部屋で治療を受けている少年の元へ向かう。
「少年のデータ、解析できましたか?」
ジルは少年の担当医師に問いかける。
「解析は終わりました。詳細はこちらにまとめていますのでご覧ください」
ジルは担当医師から手渡された端末にまとめられた報告書に目を通す。しかし、数ページめくっただけで報告書は最終ページになってしまった。
「あの、ちょっと、情報が少なすぎませんか?」
ジルに問われた担当医師は、眉間にしわを寄せ、私に聞かれても困る、と顔で示す。
「その少年の身体には、情報へのアクセス制限がかかっています。分かったことと言えば、彼の名前、出身地など公的な情報だけです」
「アクセス制限。どのようなタイプの?」
「報告書にも記載していますが、少年の身体は四肢を中心に、約45%が人工身体、いわゆるモールドと呼ばれるものに換装されています。おそらく換装施術の際に、その後の行動に関するデータはモールドの一部を記録媒体としているものと考えられます。頭部は換装されていないので、意識が戻れば、少年自身は記憶にアクセスできると思われますが」
「モールドの製造元は分かりますか?」
「はい。グルーム社です」
グルーム社。ジルの恩師、ドクターエノウラからの情報と関連しているのかもしれない。しかし、全宇宙におけるモールドのシェアで考えれば、その約70%を占めているグルーム社の製品を身体の一部としている傭兵は珍しいものではない。ただ、身体情報へのアクセス制限をかけているという事実の裏を返せば、この少年はユーヒを襲った集団、もしくはその背後にいる黒幕に関する何らかの情報を持っていること示している、とジルは考える。身体情報へのアクセス制限を解除するには技術的な労力と時間を要する。そうであれば、少年の意識が戻るのを待って尋問を行うほうが効率が良いだろう。
ジルは現時点で分かっている少年の情報を確認する。名は『ラジャン』。年齢は15歳。出身はかつて地球でエイジアと呼ばれていた地域の山岳地帯。現在は管理上『Eー6』と表記される場所だ。ジルは地球の地理について詳しくはないが、その地域は古くから山岳信仰に起源を持つ、歴史ある宗教団体の総本山が存在する場所であるということは知っていた。人類が宇宙に進出する際、その地域の人々はその信仰に従い、総人口の90%以上が宇宙への移住を拒んだ。『Eー6』以外の地域では、ほぼ全ての人々が宇宙への移住を受け入れた。つまり、地球に残った人類は、この『Eー6』に集中しているということだ。そんな地域出身の少年がどういった経緯で宇宙に出てきたのか?ジルはその点が気になったが、一人の少年が宇宙に出てきた理由がユーヒを襲うためだとは考えにくい。ユーヒを襲った人物の一人が地球出身というだけで、その二つを結びつける必要はないのかもしれない。いずれにしても、少年が意識を取り戻してから少しずつ解き明かすしかない。少年の部屋を出てユーヒの部屋に戻る途中、ジルはもう一つ、何か大事なことを忘れているような気がした。
「あ、そうだ。エマたちに連絡しないと」
誰もいない廊下で自分に言い聞かせるように声を出したジルは、歩きながらエマの携帯に連絡を入れた。
☆
ユーヒの意識が戻った日、ジルから連絡を受けたエマはすぐにユーヒに会おうと、居候していたセリーナの家から飛び出さんばかりの勢いだったが、ジルから「会話ができるようになるまで待て」と釘を刺され、その日のうちにユーヒに会うことは叶わなかった。それからエマはユーヒの回復状況を毎日ジルから聞いていたが、実際会ってみないとユーヒが元の状態に戻っているかどうかの確信を得られないと思っていた。身体も記憶も元通りとの話だが、その二つが揃ったとしても、その人物が以前のユーヒと全く同一であるとの確証はない。早く会って話したい。ユーヒが目覚めたその日から、エマの頭の中はその事だけに支配されていた。
ユーヒが会話できるようになったとの連絡を受けたエマは、ジルが指定した集合時間の1時間前にはユーヒがいる施設の入り口で待機していた。
「結局、ユーヒが目覚めてから一週間だぞ?待たされる身になってみろっつーんだよ!」
ユーヒの部屋に向かうエマは鼻息が荒い。
「仕方がないでしょう。ちゃんと話せるようになってからじゃないと、ユーヒちゃんだってストレスになるんだから」
施設のエントランスまで迎えに来たジルはエマをなだめる。
「リン、お前も何か言ってやれよ」
エマに振られたリンは、いつもどおり無言をもって回答とする。
「エマ、もういいでしょ。もうすぐ会えるんだから」
「おいメガネ。お前の意見は聞いてない」
「はいはい。もう黙りますよ」
斜め後ろ方向のエマと振り返り気味に話をしていたジルは、進行方向に顔を向け直し、赤いフレームのメガネを右手の中指でクイッと押し上げる。
会話ができるようになったユーヒは特殊治療を行う病棟から一般病棟に移り、エマ達の到着を待っていた。まだ外出は許可されていなかったが、病棟内であれば、食事や買い物など、通常の生活を送る上での制限はほとんどなかった。ただ、会話の相手は病院関係者に限られていたため、ユーヒが最も望んでいる他愛もない会話は実現していなかった。意識が戻ってから自由に動けなかったこともストレスだったが、それ以上に親しい人たちと会話できないことがユーヒには耐えがたかった。ジルからエマたちの訪問を知らされていたその日、ユーヒは病室の窓から、宇宙空間との間にある壁に映し出された青い空の映像を見つめながら一人考え事をしていた。
「あの男の子はどうなったんだろう?」
意識を失う直前に自分に銃口を向けていた少年のことをユーヒは想う。ジルの話では、この施設で治療を受けているとのことだったが、少年と話をすることができるだろうか?そう思ったユーヒは、巡回に来た担当医師に少年の事を尋ねる。
「ああ、あの少年ね。意識は取り戻したよ。もう少ししたら会話もできるようになると思う。でもねえ……」
担当医師は言葉を濁してユーヒから目を逸らしたが、再びユーヒを見つめなおすと、少年の処遇について話した。施設を退院後、彼はテロ実行犯として治安当局に引き渡される。極刑は免れないだろう、とのことだ。襲撃を受けた施設の被害は甚大だった。それ故、少年の処遇は仕方のないことだとユーヒも思う。しかし、彼はユーヒを殺さなかった。ユーヒと目が合った後、少年は銃口を下げた。あのときのことを、ユーヒは少年に直接聞きたいと思っていた。
病室のベットに寝転がり、天井を眺めながら考えに耽っていると、病室のドアに人の気配を感じた。ノックの後に、聞きなれた声がする。ジルだ。
「ユーヒちゃん、入って良いかな?」
「どうぞー」
ドアが開き、ジルを先頭にエマとリンが部屋に入ってくる。その後ろから、知らない女性が一人。部屋に入るや否や、エマはジルを追い越し、ユーヒに近づく。
「ユーヒ、良かった。元気そうで……」
「エマ、もう大丈夫。心配してくれてたってジルから聞いてた。ありが……」
ユーヒが話し終わる前に、エマはユーヒに抱きつく。
「エマ……」
ユーヒはエマの体の震えを感じ取った。そして、エマの体から伝わる温かさをとても懐かしく思った。火星で出会って、月まで二人で旅をしていたことが、遥か昔のように感じらる。エマの肩越しにジルたちの優しげな視線を確認する。いつもは無機質なリンの目が微かに揺らいでいるように見えた。揺らいでいるのは、リンを見つめるユーヒ自身の目なのかもしれない。抱き合う二人にジルが歩み寄り声をかける。
「エマ、あんまり強く抱きしめないでね。ユーヒちゃんも全快ではないから」
「悪い、勢いあまって抱きついちまった。でも、ちゃんと戻ってきてくれたんだな。本当に嬉しいよ」
「うん。みんなのおかげ。現代の医療技術ってすごいんだなって実感してる。病院の人たちにも感謝しなきゃね」
「そうだな。あ、お前に紹介しないとな」
そう言うとエマは、部屋の隅にいたユーヒの知らない女性を手招きする。
「はじめましてユーヒさん。エマの友人のセリーナです。いろいろ大変だったね。無事で本当に良かった」
「ありがとうございます。でも意外です。エマにこんな綺麗で素敵なお友達がいるなんて」
「あら、ありがとう!いやあ、エマ、あなたが言っていたとおり、ユーヒさんってほんとに素直で可愛らしい子ね!」
「ユーヒ、『意外』ってなんだよ?あたしには女友達がいないとでも思ってたのか?」
エマは鋭い眼光でユーヒに詰め寄る。
「え?ああ、そんなことないんだけどね。これまで会ったエマの知り合いにはいないタイプだなーとか思ってさ。セリーナさんは、ドライブインで会った優男さんとかマッチョさんとは全然違うから」
「まあ、そうか。それはそうかもな。でも、セリーナだって見てくれは良さげだけど、性格はあたしよりずっとガサツだから」
「エマ、余計なこと吹き込まないの。ガサツなところ見せるのは、親しくなった男とあなたに対してぐらいだから」
エマとセリーナのやりとりを見て、ユーヒはやっと元の世界に戻ってきたことを確信できた。この広い宇宙において、こんな些細なやりとりはどうでも良いことなのかもしれない。けれど、私にとってはこれこそが生きていることの証なんだ。そう、ユーヒは思う。
「そうそう、リンくんも渡すものがあるんだよね?」
セリーナの言葉に反応したリンがユーヒに近づく。そして、手に持っていた小さな紙袋を無言でユーヒに手渡す。
「開けて良いの?」
リンは小さく頷く。袋を開けて覗き込むと、中には小さな木箱があった。ユーヒは木箱を取り出し、ゆっくりと開ける。木箱に入っていたのは、青く光る小さな石だった。
「綺麗な石……」
ユーヒはその石を手に取って、窓から差し込む光にかざす。光を屈折させた石が微かに赤く輝く。
「地球ではブルーガーネットと呼ばれている鉱石。たぶん、それは人工的に作られたものだけど。ユーヒさんが目覚めるのを待っている間に、リンくんと私たちで選んだの」
セリーナは、リンの代わりに説明する。ユーヒはリンの顔をジッと見つめるが、リンは目を合わそうとしない。
「そうなんだ。リン、どうもありがとう。でも、どうしてこの石を私にくれるの?」
リンはユーヒから目を逸らしたまま答える。
「記念だから……」
「え、何の?」
ユーヒにはリンの言葉の真意が分からない。分かろうと努めてみるが、答えが出ないまま沈黙が続く。その沈黙に耐え切れず、エマが口を開く。
「誕生日だよ!ジルから聞いたぞ。お前、自分の本当の誕生日を知らないって。だから、あたしたちで話し合って決めたんだ。再会したその日を、ユーヒの誕生日にしたらいいんじゃないかって。だからこれは、誕生日プレゼントだ」
それを聞いたユーヒはポカンと口を開けたままエマたちの顔を交互に見つめていたが、徐々に表情が崩れ、目から大粒の涙が流れる。
「ふふふ。そんな、大げさだな。私、誕生日なんていつだって構わないし。ジルだって言ってたじゃん。生まれた日が分からないからって、人生困ったことなんて一度もないって。でも、やっぱりこうして誰かに祝ってもらえるのって嬉しいことなんだね。この世界に戻ってきて、生きていて良かったって思えるよ!」
会話を聞いていたジルも目を潤ます。ミジュ様はどうしてこんなどこにでもいるような普通の少女を地球へ送り込むのか。その理由が知りたいと思った。理由が何であれ、ジルは組織の歯車として、上からの命令に従うしかないのだが。
「じゃあリンくん。言いたいことを言わないと。ちゃんとユーヒさんの目を見て!」
セリーナに促されたリンは、エマに腕を引かれユーヒの前に立たされる。まるで何かの罰ゲームのように。
「自分で引っ張ってきて言うのもなんだが、なんか気の毒になってきたわ。じゃあ、あたしたちも一緒に言ってやるよ。はい、せーのっ」
『ハッピーバースデイ!』
みんなの声に紛れてしまい、リンの小さな声はかき消されてしまった。それでもユーヒは手の中にある小さな石の輝きに、リンの想いを感じ取れた気がした。
☆
月の本部、ユーヒの回復の報告を受けたレニー中将は一人執務室のデスクに座り、目を閉じて脳内の情報と向き合っていた。レニーが部下に集めさせたのは、通信記録や映像、音声データだ。膨大なデータを解析し、内部情報が怪しい経路を伝っていないかを調べる。人類が宇宙に進出してからの急激な科学技術の発展は、地球時代に人々が『直観』と呼んでいた脳内の処理方法を、AIの情報処理能力により意図的に再現することを可能にしていた。親衛隊に所属するレニーは、マイルス商会が所有する最先端のAIと自らの脳を直結させる権限を有していた。情報を解析したAIが、レニーの脳に一つの答えを送り込む。
AIの導き出した答えは、親衛隊に所属する人物とミジュ・マイルスとの関連についてだった。レニーはその答えに対して疑念を抱く。これまでの経験上、AIの情報処理は信頼できるものだった。しかし、今回はレニーの人としての直観がそれを否定しようとする。こういう場合、その疑念も含めて上司であるゲンソウに報告すべきなのだ。そうすることが、軍人としてのレニーの本能でもあった。
レニーはゲンソウの部屋に向かう。
「ゲンソウ様、よろしいでしょうか?」
ゲンソウの執務室の扉をノックしたレニーはゲンソウに入室の許可を求める。
「入れ」
ゲンソウの許可を受け、部屋に入る。
「ゲンソウ様。内通者の情報について、現時点の報告をいたします」
ゲンソウはレニーを執務室内のソファーに座るよう促し、自分もレニーの座ったソファーの左側に配置された一人掛けのソファーに座る。
「虫は見つかったか?」
ゲンソウから問われたレニーの目がわずかに震えたのをゲンソウは見逃さない。
「あまり良い報告ではないのだな」
見透かされたと感じたレニーは、深く息を吐いてから答える。
「良いか悪いかの判断は私にはできません。これはあくまで調査結果の報告です」
「もちろん分かっている。結果をそのまま話してくれれば良い」
「はい」
レニーはAIの解析結果について、ありのままを話す。自身の感じた違和感については、ゲンソウの反応を待ってからで良い。
「なるほど。ミジュ様と直接会い、プロジェクトに関する情報を得た人物でしか、その情報を外部に伝えることができない。そのとおりだ。ユーヒ様の行動詳細をリアルタイムで知ることができるという点でも、合理的な説明が可能だな」
レニーは自身の疑念を述べるかどうか迷った。が、ゲンソウの言葉でその迷いは無意味なものとなった。
「レニー。お前は信じたくないのではないか?もしかしたら、これは誰かが仕組んだ意図的な誤情報ではないかと疑っているのだろう」
レニーの顔から血の気が引く。
「申し訳ございません。恥ずかしながら、おっしゃるとおりです。膨大な情報を集めました。その中でも、AIが判断根拠としたその情報は軽微なものでしたが、我々親衛隊の行動規範に照らしても、その者の行動には違和感を感じざるを得ない。おそらく、AIの判断は妥当なものと理解いたします。しかし自分の心は、根拠となった情報がフェイクではないか、もしくはAIの判断が間違っているのではないかと訴えてきます」
「レニー、それは私情だ。人間は事実を解釈で捻じ曲げる。だが、情報自体は嘘をつかない。仮に情報がフェイクであれば、AIが判断して切り捨てる。だから、ミジュ様とリンが秘密裡に会っていたことは事実と認めなければならないだろう。そして、リンが内通者であることを前提として、我々はこれからの行動を決めなければならない」
「しかし、これを誰に、どう報告すべきなのでしょうか?」
「レニー中将。このことについては他言無用だ。ミジュ様には私からタイミングを見て切り出す。その時は、事前にお前に伝えてからにしよう。もしその後に私に何かあった場合は、お前はこのことをジル少佐に伝えるのだ。良いな」
ゲンソウの言葉に、レニーは目礼で応じる。リンが内通者であることが事実であれば、そこから派生し得る事実、つまり、情報の漏洩についてミジュ・マイルスの意思が介入していることになれば、親衛隊のみならず、マイルス商会という組織の根本を揺るがすことになる。レニーはそれ以上考える事を諦める。もはや、自分の手に負える話ではない。
部屋を去ろうとするレニーの背後から、ゲンソウの独り言のような声が聞こえる。
「ミジュ様は、マイルス商会の総帥という立場をとうの昔に捨て去っておられたのかもしれないな」
思考を諦め、返す言葉の無いレニーは、その巨体を丸めるようにしてゲンソウの部屋を後にした。
☆
エマの船は火星区のフォボスから月に戻る途中だった。船に乗っているのはエマのほか、ユーヒ、リン、ジル、そして、施設を襲撃した組織に所属していた地球出身のラジャンという名の少年。マイルス商会の総帥であるミジュ・マイルスが、当局へ直接働きかけ、少年の身柄を引き取ったのだ。被害を受けた施設の所有者であるとは言え、特別待遇であることは間違いない。それだけ、宇宙におけるミジュ・マイルスの影響力が大きいということだった。
「気分はどう?何か話す気になった?」
エマの船の一室にて、ジルはラジャンに問いかける。ジルは毎日ラジャンと向き合っていた。ユーヒを襲った組織のこと、ラジャンがその組織に入った理由、地球から出てきた経緯などの尋問を行っていたが、ラジャンは黙秘を続ける。
「もう一か月。何も話さないのも辛くない?この際、世間話でもなんでもいいわ。おねえさんに話したいこと、話してみてよ」
尋問を行う側のジルもかなり疲弊していた。一方的な会話がこれ程までに心身を疲れさせるものだとは思っていなかった。そもそもジルは医師であり、尋問に関して専門外だ。かと言って、リンに尋問させることはできない。そんなことをしたら、この一か月間、お互いが黙秘を貫いたことだろう。そのことを想像するだけでジルは息が詰まった。
ラジャンの体に組み込まれていたモールドは、念のため全て新品に入れ替えてある。ラジャンはもう、以前所属していた組織から、形式的にも物理的にも完全に切り離されたのだ。ジルはそのことをラジャンに伝えているが、それでもこの少年は自らのことを何も話そうとしない。ジルは休憩するために部屋から出て船のリビングに向かった。
リビングでは、エマとユーヒが何か言い争いをしている。ジルはリンの姿を探したが、リビングには見当たらない。おそらく、二人の争いに巻き込まれるのを避けたのだろう。ジルがリビングに来たことに気が付かないのか、エマが声を荒げる。
「だから、なんであんな奴をかばうんだよ!お前を殺そうとしたんだぞ!」
またその話か。ジルはここ数日繰り広げられるこの話題に辟易していた。エマとユーヒ、それぞれの言い分はどちらも理解できる。ジルが口を挟めば話が拗れるのは明らか。ラジャンへの尋問と同じくらい、こちらの議論も行き詰っている。
「エマ、何度も言うけど、私はあの男の子のことを知りたいだけ。罪を犯した者が裁かれなければならないことは分かってる。だからといって、罪を犯した理由を確かめなければ、人は同じ過ちを繰り返すだけでしょう!」
ユーヒの言うことを、エマは頭では理解している。しかし、ドライブインの時とは違い、今回ユーヒは命を落としかけているのだ。命に関わる事柄を軽視することなんてできない。ただ、襲われた張本人であるユーヒが少年との対話を望んでいることが、エマを混乱させる。対話をしたからって、そこに何が生まれるというのだ?
「エマだってこれまでの人生、過ちの一つや二つはあったでしょう?そのことを誰にも打ち明けられないって、すごく苦しいことだと思わない?」
罪の意識に関わることは、そんなに簡単には他人に打ち明けられない。そうエマは言いかけたが、声に出す前にグッと飲み込む。
「それはそうかしれない。でも、あいつの話を被害者のお前が聞くのは筋違いも甚だしい。ああ、もう疲れた。話はやめだ!」
会話を終えて大きなため息をついたエマは、髪を一つにまとめていたゴムを外し、肩の下まで伸びた赤い髪を降ろすと、ドンドンと大きな足音をたてながらリビングから去っていった。
エマの足音が聞こえなくなったことを確認したジルがユーヒに話しかける。
「ユーヒちゃん、今日もお疲れ。エマとの言い争いにも飽きたと思うから、気分転換にラジャンと話をしてみない?」
「え、良いの?本部は私が彼に会うのを禁止しているんでしょ?」
「まあ、そうなんだけどさ。あの子、本当に一言も発しないのよ。元々無口なのかな。いや、あれは信念を持った黙秘だね。私には分かる。無口な人間を長年見てきたから。その違いは明らかだよ」
ジルの話を聞いていたかのように、リンがリビングに入ってきた。
「ほれ、噂をすれば。そうだ、リンを護衛につけることを条件にユーヒちゃんとラジャンを会わせる。これなら本部も了解するんじゃないかな。早速、本部に聞いてみる」
ジルは運転席に備え付けてある通信機器を使って本部と連絡を取る。数分で話を終えたジルがリビングに戻る。
「ユーヒちゃん、オッケーだってさ。リン、話聞いてたでしょ?一緒に来て」
ジルはユーヒとリンを連れてラジャンの居る部屋に入る。窓際の椅子に座っていたラジャンは、入室してきたユーヒの姿を確認すると、「あ……」と声を漏らした。ジルも初めて聞いたラジャンの肉声だった。
「ラジャン、ユーヒちゃんが話をしたいって。二人きりにはさせられないから、護衛つきだけどさ。私はリビングで休むから。リン、あとはよろしくね」
ジルは三人を残して部屋から出て行った。ユーヒはラジャンの前に置かれた机を挟んで、ラジャンの真向かいに座る。その動きに同調して、リンはラジャンとユーヒの間にある机の隣に立った。新たなモールドに換装されたラジャンの両手両足は、自由が利かないよう、ジルによって機能を停止させられている。リンの護衛は本部を説得するための口実でしかない。
「はじめまして、ではないね。お久ぶり、っていうのも変か。まあいいや。私の名前はユーヒ。あのね、私はあなたの事を知りたいと思ってここに来たの。話してもらえるかな?」
ラジャンは返事をする代わりに、何かを確認するかのようにジッとユーヒの目を見つめている。ユーヒもその視線から目を逸らさない。ユーヒが次の言葉を発しようと息を吸い込んだそのとき、ラジャンが口を開いた。力強い声だった。
「失礼を承知で申し上げます。あなたは『ラウラ様』なのではないでしょうか?」
ラジャンの発したその言葉は、ユーヒの心中に広がる無意識の湖に大きな波紋を生じさせた。その意味を、ユーヒは理解できなかった。ただ、その波紋により乱された感情が、ユーヒの胸を強く締め付けている。
その様子を、リンはいつもにも増して真剣な眼差しで見つめていた。
つづく
