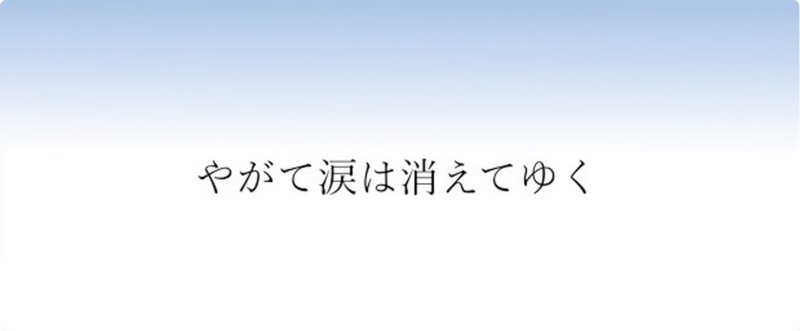
やがて涙は消えてゆく 第2章
翌日、僕は近所の公園のブランコで一人揺られていた。 ときどき、ポケットに入っているくしゃにくしゃになったチラシを眺めては大きなため息をつく。チラシは急きょ、昨日の晩に作ったものだ。
「佐野君の思い出探してます!」、「どうかあなたの話を聞かせてください」。
これ以上ないほどにデカデカと紙面に敷き詰められた文字が、今では情けなくなるほど滑稽に見える。
![]()
今日の朝、僕は学校の校門でこのビラ配りをしていた。クラスメイトの他にも佐野君のことを知っているかもしれないし、より多くの人から思い出を集められた方が文集は作りやすい。そう考えて昨日の晩、僕は無我夢中でチラシを作り、早起きして学校に向かったのだった。
しかし、結果はさんざんなものだった。誰もビラを受け取ってくれないのだ。みんな目を反らして僕を避けるようにして校門へ入っていく。
「なんか、あの人アブナイよね」
「あいつ、どうかしてるぜ、朝っぱらから」
そんな囁き声があちこちから聞こえてきた。それでも僕はなんとか一枚でもチラシをくばろうと必死だった。
「お願いします」、「これ、見るだけでもいいんで」
必死に食い下がる僕にあきれて、何人かはしぶしぶチラシを受け取ってくれた。僕はさらに声を張り上げて、チラシを配り続けた。なんとかイケるんじゃないか、そう思った矢先に、教頭先生が慌ててやってきた。
「ああ、ダメダメ、きみ、何やってんの。許可とってないでしょ、それ。」教頭先生は迷惑そうにそう言った。
「許可って? 何ですか。」
「いいから、すぐ来て」教頭先生は嫌がる僕を無理矢理引っ張って校舎裏まで連れていった。
「あのさ、君自分のやってること、分かってるの?」教頭先生は早口で言った。
「はあ」僕は何のことを言われているのか分からなかった。
「君のチラシを見ることで、嫌な思いをする人だっているってことだよ。」教頭先生はさらに早口で言った。「佐野君のお母さんだって、本当に喜んでくれんのかね。」
「・・・・・・」僕は突然のことで何も言い返せなかった。
「ちょっと、言いにくいんだけどさ。君のためでもあるから、一応言っておくよ。」教頭先生はくしゃくしゃになった僕のチラシを広げて言った。「そういうのって、君の自己満足なんじゃないの。」
![]()
教室に行くと、もうみんなは席について1時間目の準備をしていた。僕は急いで席について、鞄から教科書を取り出した。そしてそれを机の中に入れようとしてしたとき、何かが机の中にぎっしりと敷き詰められていることに気づいてギョッとした。
恐る恐るゆっくりと取り出すと、それは今朝、僕が配っていたチラシだった。どれも無残にも小さく丸められている。僕が驚いて固まっていると、周りからクスクスと笑い声が聞こえてきた。僕は黙って机に入れようとしていた教科書やノート類を黙って鞄の中に戻した。そしてそのまま何事もなかったように授業を受けた。
![]()
もうすっかりと日は暮れていた。そろそろ帰らなければならなかったけれど、もう動く元気すらなかった。僕は公園のベンチに座りながら、もう一度しわくちゃになったチラシを見つめる。
「佐野君の思い出探してます!」、「どうかあなたの話を聞かせてください」。
何度見ても、僕が手書きで書いた文字はぶかっこうでダサイ。「思い出」という言葉ももう使い古された言葉で、何のインパクトもないのだろう。彼らの心には僕の切実な叫びは何も聞こえない。
このチラシを見ながら、「自己満足じゃないか」と教頭先生は言った。たしかに僕のやっていることは、自分の欲望を満たすだけのものなのかもしれない。すでに亡くなった人の思い出を呼びさます行為は、時として大きな苦痛を強いるものになる。僕はこのチラシをばらまくことで、多くの人を傷つけたかもしれないのだ。
佐野君はもうこの世にはいない。誰かの心の中に彼の思い出が眠っているにせよ、それはそっとそのままにしてあげた方がいいのかもしれない。亡くなった人のことなんてもう忘れてしまって、何事もなかったように過ごした方がいい。佐野君のことなんて、もう忘れてしまって・・・・・・。
気がついたら、僕は泣いていた。佐野君のあのあっけらかんとした笑顔を思い出してしまったからだ。そしてそれはやがて、葬式で絞るような声で語りかけていた佐野君のお母さんに変わっていった。
「何でもいいから健太郎のことを思い出したら、教えてください。本当に何でもいいんです。」
佐野君のお母さんがどうしてそんなことを言ったのかは僕には分からない。一人息子が原因不明のまま亡くなって多少混乱していたのかもしれない。だけど、佐野君のお母さんにとっては、「思い出」は宝もののはずだ。少なくても、心を傷つけるようなものじゃない。きっと、バラバラになった心と心の隙間を埋めて、冷め切った心を温めてくれるものだと思う。
人は誰でも強く前向きに生きているわけじゃない。ときどきつまずいて、誰かの助けを必要とするときだってある。そういうときに、誰かが手を差し伸べなければ、人は生きていけないんじゃないかって思う。
僕はくしゃくしゃになったチラシをぎゅっと握りしめた。そして、涙と鼻水でぐちゃぐちゃになった顔を制服のシャツで何度もぬぐった。
泣いてる場合じゃない。泣いてる暇なんかないんだ。
そう思って、立ち上がろうとしたら、目の前に見知らぬ少女が突っ立っていた。制服から同じ中学校であることが分かった。だけど、全く見覚えがない顔だ。
「これ、良かったら使って。」
少女が差し出したのは花柄模様の白いレースのハンカチだった。僕はそのハンカチを受け取った。すぐに「ありがとう」と言いたかったが言葉がうまく出ない。僕は金魚のように口をパクパクと動かしながら、少女の顔をぽかんと見上げていた。
続きはこちら
![]()
前回の話
<エッセイ>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
