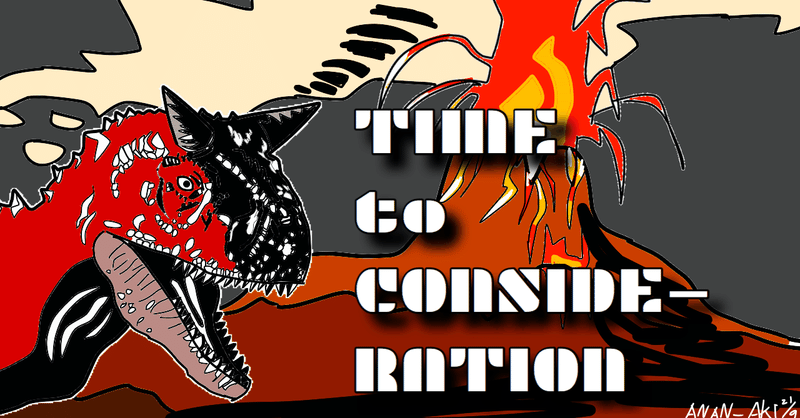
第一回 考察の時間 ゴジラ 1954
1、始めに
今回から始めることになりました、キャラクター、ストーリー考察です。私自身考察と言いますか、この物語の本質とはなんぞやこのキャラクターの心理はなんぞやと言った話が大好物でして、ついには二次創作の一環として、自分自身も筆をとった次第です。
記念すべき第一回目は、日本の映画史みならず世界の映画史、SF史、創作の歴史に多大な影響を及ぼした、我らが怪獣王ゴジラについて考察していこうと思います。
*当然の如くネタバレ全開ですので、閲覧される際はお気をつけください!
2、ゴジラ制作の背景
まず始めに、ゴジラのことを語る際には必ずと言ってもいいほど、戦争と核というテーマがついて回ります。
これはゴジラが制作されるに至った背景に、第五福竜丸事件という出来事と、制作に関わった人々が戦火に巻き込まれた際に抱いた感情や思いを映画にぶつけようとした、という事実があります。
第五福竜丸事件は昭和29年(1954年)に起きた、日本の漁船がビキニ環礁で行われた水爆実験に巻き込まれ、船員の方々が被爆してしまった事件です。この事件が起きたことで、日本は原爆、水爆の被害を被った唯一の国となりました。戦争が終わって十年と経たずに再び同胞が、忌まわしい殺戮と破壊をもたらしたあの原爆よりも、遙かに強力な水爆という核兵器の犠牲になってしまったという衝撃は、核兵器の恐怖を忘れつつある私たち現代人には想像も出来ないことなのかも知れません。
更には、監督の本多猪四郎氏や特技監督の円谷英二氏といった制作陣たちも戦争によって大なり小なり人生を変えられた人たちでした。特に、円谷英二氏が軍人教育用の教材映画や戦意高揚映画を撮影したことで、GHQから公職追放処分を受けてしまったエピソードは有名なものとして知られています。
このように戦争という途方もない暴力と抑圧を経験し、あまつさえ核兵器という文明の怪物によって人としての尊厳すらも踏みにじられた人々が、ゴジラという作品、ひいては存在に自分たちの思いをふんだんに注ぎ込んだからこそ、ゴジラという怪獣王はうわべだけの存在ではなく、ある種のリアリティーと寓話性を持って、この世に生を得ることになったのだと思います。
3、ゴジラとは何か
ジュラ紀に生息していた海棲は虫類と陸上獣類の中間にあたる生物が、現代まで種として生存し、ビキニ環礁の水爆実験(キャッスル作戦)に始まる、度重なる水爆実験によって変異を起こしてしまい、身長50メートル、体重二万トン、焼けただれたかのような皮膚と背びれを持ち、不死身とも思える生命力と放射線を含んだ白熱光を放つ怪物と化した―これが作品上におけるゴジラという存在です。
改めて文章にしてみると、ゴジラは常識の外にいる存在であると同時に、その存在は、おぞましいファンタジーであると言うことが分かると思います。生物として理解の及ぶ骨格や外見を有していながら、高熱に晒されたことが原因と思われる表皮の変異や、口から吐く白熱光からは放射線という不可視の毒をまき散らす―この、生物にあるまじき矛盾した性質は、まさしく混沌、カオスの具現化に他なりません。
そもそものゴジラの初期イメージが「キノコ雲のような頭部を有する怪獣」であったことは、ゴジラのデザインそのものが戦争による大量破壊の落とし子としての意匠を有していたことを表わしています。つまりゴジラの設定や外見は、凄まじい暴力や圧倒的な破壊によって、本来の有り様から大きく乖離させられてしまったありとあらゆるものの象徴であるといえるのです。
爆弾や銃火器によって失われる命はもちろんのこと、大量破壊兵器によって生活基盤をも破壊されてしまった市民、さらには時の権力やイデオロギーによって自身の意志に反する行いを強要されてしまった人々―
このような暴力は物質的なものだけで無く、人間関係や精神をも変質させてしまいます。無思慮に振るわれた力は痛みと苦しみを生み、苦痛は恐怖と屈辱に、恐怖と屈辱は容易に憎しみや怒り、悲しみに変異していきます。これらを鎮めることが出来なければ、それらは燎原の火の如く近しいものから他者へと広がっていくのです。
ゴジラとは、まさしくそういったトラウマ、恐怖や憎しみ、怒り、そして悲しみの代弁者に他ならないのです。
悠久とも思われた安寧は恐ろしい閃光と熱によって失われ、後に残ったのはおぞましい姿となった己と、破壊された安住の地―
ゴジラが光り輝くネオン街を目指して東京湾から上陸し、東京に破壊をもたらしたのは、そういった文明の光と自身に苦しみをもたらした科学の光が同様の存在だと認識したからなのかも知れません。ゴジラは内に抱える怒りや憎しみ、そして悲しみを、あの憎い憎い光を放つものへとぶつけることしか頭になかったと考えるのは、人間的な解釈に過ぎるでしょうか。
なんにせよ、ゴジラは文明の破壊者、怒りと恐怖と悲しみの拡散者として銀幕で暴れることになりました。そしてその背景には、暴力と破壊によってもたらされる歪みと負の感情の化身であると言う側面と、無辜の人々に圧倒的な破滅をもたらす怪物という側面が両立して存在しているのです。
ゴジラの行動や容姿は、およそ自身に対して一切の理解や共感を求めることのないものであり、彼は絶対的な拒絶の表情を浮かべ、人間の住処を焼き払い、押しつぶしていきます。それ故に、ゴジラは人々にとって恐怖と畏怖の象徴、あるいは荒ぶる力の奔流として捉えられ、共感できる過去を持ちながらも他を寄せ付けないという一種の神々しさを持って受け入れられるようになったのだと思います。
4、芹沢博士とゴジラ
物語の中盤から終盤にかけてゴジラは、東京を火の海に変えおびただしい被害をもたらし、その後東京湾に潜伏することになります。
ゴジラが引き起こした惨状を見、登場人物の一人である河内桃子さん演じる恵美子は、恋人である尾形(宝田明)にある告白をします。それは旧知の仲である隻眼の科学者、芹沢博士(平田昭彦)がゴジラを抹殺しうる何かを研究している、というものでした。
そのことを知った尾形は芹沢博士の下へ赴き、彼にそれを使わせようとします。ですが芹沢博士は自身が生み出してしまったもの、オキシジェン・デストロイヤーの使用を拒みます。
水中の酸素を一瞬にして奪い、そこにいる生命を例外なく溶解せしめる薬品であるオキシジェン・デストロイヤーは、砲丸ほどの大きさで東京湾一帯を死の海に変えてしまうほどの威力を持ちます。それ故にオキシジェン・デストロイヤーが世間の目に触れてしまえば、良からぬ結果を生むことになりかねない。それこそ、あの原水爆以上の恐怖を世界にもたらすことになりかねないと、芹沢博士は恐怖しています。
物語というものは対比的な手法でもって描かれるのが常で、ゴジラが科学と戦争が産む凄まじい破壊と混沌の被害者であると同時に、それをもたらすものとして描かれているように、芹沢博士もまた見方は違えど同様の存在、あるいは同様の存在のなりかけとして描かれているように思います。
物語上で詳しく描かれることはありませんでしたが、彼は戦争に行ったことよって片目を失いました。そのことは、彼が戦争によって人間性を変えられてしまったことに対する一種の象徴表現なのでしょう。
芹沢博士が戦場でどのような経験をしたのか、あるいはしてしまったのかは想像することしか出来ません。戦場から戻った彼は、師である山根博士(志村喬)の下へ戻ることを拒み、更には愛していた女性である恵美子からも身を遠ざけ、一人で暗い研究室に籠もって研究に没頭するようになり、そして生み出したものは大量破壊の種子―。
そんな彼の姿は、戦争に加担し、あるいは加担させられた科学者達の姿と重なって見えるのは制作者達の狙いでしょう。いつの時代でも、科学は戦争によって発展し、戦争もまた科学によって発展する―このことは歴史が証明している悲しい現実の一つです。
芹沢博士は、そういった歴史の教訓からオキシジェン・デストロイヤーを平和利用にかなうものにすることに固執しています。戦争の被害者である彼が自身の創造物を、戦争と破壊と暴力の落とし子にさせたくないと考えたのは人情として当然のことでしょう。だからこそ、オキシジェン・デストロイヤーを現段階で使用することは世界に怪物を解き放つことと同義だと捉え、芹沢博士は使用を拒みます。ですがゴジラがもたらした被害は、芹沢博士の考えを変えてしまうほどのもでした。
ゴジラが東京にもたらした惨事は筆舌に尽くしがたいもので、映画の中で描かれる人々の有様は、今の日本映画ではとてもではありませんが表現できないものでした。エキストラの方々も実際に戦争の被害を被った人々だったからこそ、表現できたことなのでしょう。
この惨事を見た芹沢博士は、オキシジェン・デストロイヤーの使用を決意します。芹沢博士はゴジラの所業に一体何を見たのでしょうか。
一ついえることは、彼はゴジラと運命を共にすることを決意するほど、科学者としてはロマンチストであり模範的な倫理観と道徳心を持った人間だったと言うことです。
物語の最終幕にて、ゴジラという怪獣は、オキシジェン・デストロイヤーという怪物と芹沢博士というフランケンシュタインによって葬られます。芹沢博士もまた、フランケンシュタイン博士と同じように自らの創造物と共に死を迎えることを選びます。
ゴジラという荒ぶる神を、芹沢博士とオキシジェン・デストロイヤーというある意味においてゴジラと同じ怪物達が鎮めることで、両者共にゼロへと帰る。まさしく神話のような構造でもって一連の事件は締めくくられるのです。
5、終わりに
ゴジラという作品は七十年近くが過ぎた今でも、優れた娯楽作品としてだけでなく鋭い社会批判、文明批判のテーマを有した作品として評価され、ゴジラの存在は普遍的なものとして受け入れられるに至りました。特に、科学という現代を支配している概念に対する批判的アプローチは特筆すべきものがあるのではないでしょうか。それは、山根博士の最後の独白に集約されています。
「あのゴジラが最後の一匹だとは思えない。もし、水爆実験が続けられるとしたら、あのゴジラの同類が、また世界のどこかへ現れてくるかもしれない…」
この独白は、「人の世の続く限り、同じことの繰り返し」と言う無常観と、山根博士自身が内心、抱いていたかも知れない「再びゴジラに見えたい」と言う複雑な心情を述べているのだと私は解釈しています。
現代科学が生まれてから400年がたち、人は科学という力にすがり、信仰し、おおいにその威力をふるいこそするものの、人としての進歩を科学は与えてはくれませんでした。かといって今更、快適さや力、救済を与えてくれる科学を捨てられるはずはなく、人は科学を信仰し、愛することで今を生きています。
果たしてそれでいいのか?人類が滅ぶそのときまで、人類はそうあり続けるのか?
ゴジラは、私たちにそう言っているのかも知れません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
