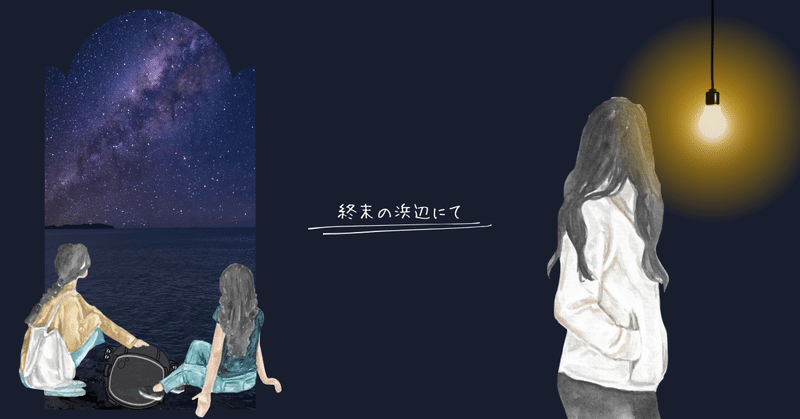
或る日の夢の話① 終末の浜辺にて
昔から私はよく夢を見る。
まだまだ修行が足りないせいか、夢の中で夢を夢と認識するのは、なかなか難しい。私の夢の世界は、夢の中だけにしか存在しないし、すぐに揮発する。
だが、時々、捨て難い夢を見る。ここにそういう夢を少しずつおいていこうと思う。
昔見た夢の話をしよう。
夢のままだと雑味が多いので、すこし、脚色を加えることとする。
目が覚めると──
始まりはこんな感じでいいだろうか。
目が覚めると、私はほったて小屋の中にいた。
オレンジ色の蛍光灯が真ん中に一つだけぶら下がり、小屋の中を柔らかく照らしている。8畳ほどの広さの中に、簡素な木の机が蛍光灯の真下でくたびれた木目を晒している。その上には、先ほどまで食事をしていたのか、汚れた皿と、食べカスが散乱している。窓際には破れて綿が抜けた緑のソファ、その対面には、魚を捌くのには困らない程度の台所がある。
歩くと、床の板が軋んで嫌な音をたてた。今し方人がいたような気配はあるが、どこかへ行ってしまったようだ。
窓の外は暗くてよく見えない。どうやら夜らしい。外に出てみることにする。
扉を開ける。やや蒸し暑く、風はない。呼吸をするたびに、体が湿度を帯びた夏の匂いに満たされていく。ウマオイの鳴く音と共に、微かに波の音も聞き取れた。
足を踏み出すと、思いの外足元が柔らかくて驚いた。砂っぽい。何歩か歩いてその感覚を確かめる。どうやら、浜辺らしかった。
小屋の窓からもれる淡い蛍光灯の光が外を照らしている他は、あまりよく見えない。小屋を背にして、海の音の方に足を運んでみる。
見上げると無数の星が空を覆っている。仰々しいまでにびっしりと、くっきりと他所の星が見える。その割に、月明かりはない。
体が重く、思うように動かない。”これは、私がこの世界の住人ではないからなのだろうか”。いや、もともと、私はこの世界の住人だったか?
よくわからなくなったので考えるのをやめる。
しばらく無心で歩くと、地面に異変がある箇所を見つけた。急ぎ近寄ってみると、直径10メートルほどのクレーターができていた。まるで何かが墜落してきたかのようだ。穴の中央に何かが横たわっているのが見えた。恐る恐るクレーターを覗いてみる。
それは、宇宙服を着た何者かだった。
頭の装備は取れ、痩せ細った顔が息も絶え絶えに地面を見つめている。話しかけたが、返事はない。もう声も届かないようだ。
その人を放っておいて、私は海を見に行くことにした。
波打ち際にたどり着く。左右に伸びる、圧倒的に広大な水たまりが、遥か彼方まで延々と続いている。ずっと水平線を見続ける。夥しい数の星に空が支配されている一方、海は絶望的に真っ暗で底がしれず、いつまでも大きな力に揺り動かされて波打っている。どこまでも終わりがない。
私は恐怖を感じて後ずさった。このままここで世界を見つめていると、闇に飲み込まれてしまいそうだ。
振り返って小屋まで走った。重たい体を懸命に動かし、上がらない足をなんとか持ち上げた。節々が悲鳴を上げてもなお、砂の上を全力で走った。
小屋を視界にとらえた。すると、さっきまで誰もいなかった小屋の前に、女の子が二人座って、アイスクリームを食べていた。
人がいることにホッとした私は、二人に近づいた。小屋からもれる灯りで、その顔はよく見えた。
綺麗な顔をした、アンドロイドたちだった。
ここで何をしているのか、問う。
「自殺についてかんがえているの」と一人が言った。
アンドロイドも自殺を考える時代になったのか。しかし、なぜ今?
「もうここには誰もいないから」もう一人が言った。
でも、さっき海辺に一人いたよ、と言うと、二人は寂しそうに笑って首を振った。なんとなく、この世界にはもう人類が住めないことは、察しがついた。
「あなたは、ずっとここにいたいの?」と問われた。
私は押し黙った。私は──ここにいたい、のか? ”ここはそもそもどこなのだろう”。
ウマオイが静かになり、鈴虫の声が聞こえるようになる。星は相変わらず鬱陶しいくらいに輝いている。静かに差し出されたアイスクリームを受け取って食べる。味がしない、と、首を傾げると、女の子たちは笑った。
「あなたもアンドロイドでしょ」
海はどこまでも闇深く、星は輝き、虫と波の音が飽和した。大自然の中に取り残されたアンドロイドたちは、静かに終わりがくるのを待った。
目が覚めると、布団の中だった。
タオルケットが妙に蒸し暑く足に絡みついているのを解いて、麦茶を飲んだ。寝起きのせいか、口の端からこぼれてしまう。
いつもの部屋から窓の外を覗く。まだ外は暗く、街灯と信号だけが瞬いていた。こちらの世界は星なんて一つも見えない。あの女の子たちはどうしているのか……などと考えても意味がないことはわかっているが、せめて、並行世界のどこかで、アイスクリームを嗜むくらいの生活を送っていて欲しいとは思う。
さて、おぼつかない足取りで布団に戻り、もう一眠りする。
体がなんだか言うことをきかないが、気のせいだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
