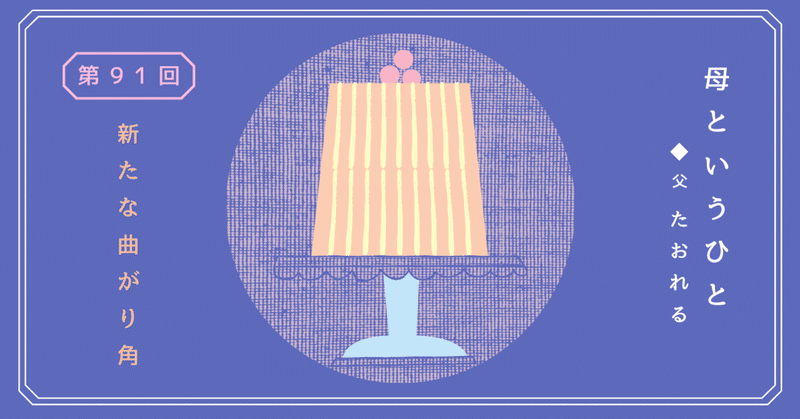
母というひと-091話
前の話を書いている最中のこと。
母が路上で倒れて救急搬送された。熱中症だった。
が、本人は「ただ転けただけ」と言い張ってきかない。「熱中症なんか起こしとらんのに、ケイサツが勝手に決めつけて勝手に病院呼んだんじゃわ。あれは病院からおカネをもらっとる」と。
助けてくれた恩人にそんな失礼なことをといさめてみたけれど、どうたしなめたって止められるもんじゃない。
1週間の入院がそれはそれは辛かったと愚痴が止まらない母を、父と2人で慰め続けた。
しかしその前に、実家ではもうひとつ大変なことが起きていた。父の緊急入院だ。
一年と少し前の出来事だった。
これこそ私が最も恐れていたことだ。
母でなく父が倒れる。
それは、両親の生活だけでなく私の生活も根底から覆すだろう最悪のシチュエーション。
(どうかそれだけは避けられますように)と、何度苦しいほど願ったか分からない。
不謹慎とか親不孝者と誰かからなじられるかもしれない。でも、そう願うしかない。
しかし現実は容赦なかった。
昨年6月の夕方頃。仕事中に、母の、いつもの少しのんびりとした声で電話が掛かってきた。特に深刻さはなく、「アンタどうしとるかね、元気ね?」の呼びかけに、私も笑ってハイハイと答えた直後。
「あんな(あのね)、うちの(父のこと)がね、F大病院に入院したんじゃけどな、大したことないけんアンタ来んでもいいけんな」と言い出した。
F大病院には、母が悪性リンパ腫を患って以来、退院後の定期検診でずっとお世話になっている。私達家族にとって馴染みの場所ではあるのだが、これまで何の病気もしたことがない父がいきなり大学病院に入院するなんて、「大したことない」状況のはずがなかった。
作成途中だったWordファイルを保存&終了させて、いつも手元に置いているスケジュール帳を急いで開く。とにかくメモを取らなければ。
「それがな、あんまり便秘がひどいんで近くの胃腸科に行ったらな、これは大変なことになってますって言われてすぐ紹介状出されてな、それ持って大学病院に行きなさいって。それでタクシーで行ったらそのまま帰れんごとなってなあ」
アハハハハ、と笑う。
「そのまま帰れんってどういうこと?」
「なんかな、癌が見つかったらしくてな、すぐ手術するんと。説明は私がもう全部聞いてきたけん、今コロナで会えんし、アンタ来んでいいけんね。一応教えとこうと思っただけやけん気にせんでな」
母の声は、まるで普通だった。
気軽な感じで出かけたら、あれよあれよと大学病院へ回されて帰宅できなかった流れを、ちょっとした笑い話だとでも思っているようだ。
とりあえず母のペースに合わせて軽めに返事をし、一度電話を切ってメモを見つめた。
〈近所の胃腸科へ〉〈すぐ紹介状〉〈タクシーを呼んで大学病院へ今から行けと言われ〉〈着いてすぐ検査〉〈そのまま入院〉〈帰れず〉
大したことない?そんなわけない。
(大学病院に聞くしかないか……)
不要不急の電話連絡は、忙しい大学病院にとっては迷惑でしかない。しかしこのまま放っておいて良いとも思えなかった。
母に電話をかけ直し、入院した病棟が外科で間違いないか聞いてみると、なぜか少し機嫌を損ねて「連絡やらせんでいいっちゃ。着替えは私が届けよるけん」と反発する様子を見せた。いらん(余計な)ことするな、の意思表示だ。
こういう時はゴリ押しせずに少し話を逸らすのがいい。
それで父が大学病院へ行くまでの流れをもう一度尋ねてみると、さっきの電話では癌が見つかったのは大学病院だと言っていたのに、今度は最初のクリニックで見つかったという話になっている。
(やっぱり病院に直接確認しなきゃダメだ)
「電話やらせんでいいけんな」と繰り返す母に「確認したいことがあるから」と言うと「何を確認するんかえ」と呆れたように笑われたが、うんうんと流して電話を切り、すぐに大学病院のナンバーを押した。
電話交換手が出て、病棟へ繋いでくれる。
そのほんの短い待ち時間に、母が闘病していたあの日々の匂いが鼻腔をかすめた。
(あの時も夏だったな…)
エアコンもまともに効かないオンボロの中古車で汗が噴き出すような暑さの中を毎日毎日、通った。
その時に嗅いでいた病棟の匂いの記憶が、電話の保留音が流れる束の間にうわーっと蘇ったのだ。
消毒液のような匂いではなく、例えば薬っぽい匂いがほのかに漂うトイレとか、思いのほか人の気配が濃いロビーの熱気とか、古い建物ゆえの天井の低さ、天井の隅にいつも消えないでいる影、そういうものが匂いの記憶として脳にこびりついている。
「はい、外科病棟です」
声が聞こえて現実に引き戻された。
そう言えば何と言って切り出すか考えていなかった……。
慌てて「◯日に入院した三崎の娘ですが、母が少々認知症を患っていて要領を得ないもので」と、直接電話を掛けた言い訳をしたうえで、できれば今後の説明を母に代わって受けたいのですがと申し入れると、女性の看護師が「ああ!」と明るい声を出した。
「助かります!明日とか来られますか?」
おや?
慌ててスケジュール帳をめくると、打ち合わせと仕事の納期が続いている。行けるとしても3日後だ。
それを伝えると、「先生に確認して来ます」と電話が保留になった。
(何か急ぎで家族が行く必要があるの?)母の「来なくていい」からは予想できなかった反応だ。
数分して戻ってきた看護師は、担当医がすぐにつかまらないから折り返させてくれと言って、私が訪問する日を再度確認して慌ただしく電話を切った。
(助かりますって何だろう)
スケジュール帳に目を落とすと、保留音を聞きながら書いた「癌が見つかったのはクリニック?大学病院?」の文字が斜めに走っている。
健康な人なら単なる記憶違いで済むかもしれないけど、母の場合は認知の変化がふとした拍子に現れるので、こういう事実のズレが見過ごせない。
病院から折り返しが入ったのは30分ほど後。担当医の空き時間に合わせて来て欲しいということと、「申し訳ないんですが」と前置きされて「入院の同意書にサインをいただきたいので、印鑑を持ってきて頂けますか」と丁寧に頼まれた。
そうだ、同意書!
なぜ私もそれをすぐに思い出せないのか。すっかり入院の手順を忘れてしまっている。
「助かります」の意味はおそらくこれだろう。
母が入院した際も、「生計を同一にしていない保証人」のサインを求められて、私が書いた。
今回も、同様の説明があったはずなのに。
母に再び電話を掛けて、同意書のサインが必要だから3日後に病院へ行ってくるねと伝えると、さっきの不機嫌はどこへやら、
「アンタわざわざ電話してくれたんかね!うわーすまんねえ。ありがとうねえ。忙しいのに悪かったねえ」とひたすらに謝られた。
ついさっき「いらんことせんでいい」と反対した病院への確認連絡をした私に、今度は感謝し恐縮している。
ああ、
母さんは、たった今目の前で起こることしか見えなくなってるのか。
時間を隔てて起こる物事や会話を結びつける力が、思っていた以上に弱くなっているんだとこのとき感じた。
日常会話では複雑な話をしないから、変化を見過ごしてしまっていたんだろう……。
「来なくていい」は、単にいつものように遠慮が出ただけ。
そして感謝は、私が「何かをわざわざしてくれた」ことに出てきた言葉で、そこに同意書の存在はこれっぽっちも入っていなかった。
(こんなに思考力が落ちたのか)
背中の力がストンと抜けるような脱力感が湧き、咄嗟に
「明後日の夜はそっちに泊まっていい?」と考えるより先に聞いていた。
私が実家を出てからこれまで、20年近く一度も泊まったことはなかった。これからもないだろうとこの瞬間まで思っていたのに。
「いいがえぇ(いいよ)。待っとるけんな」
意外にも母の声のトーンが一段上がった。
あれ?もしかして嬉しいのかな?と思えるくらい。
頭の中を少し整理してからリビングにいる夫の元へ行き、ことの顛末を話して不在の間の猫たちの世話を頼む。
まさかの父の緊急入院に対して、
「お母さんも不安だろう。何日か泊まってきたら?」と母を労る言葉を彼が口にしてくれて、やっと、さっきの母の声が安心から出てきたのかもと思い至った。
私もずいぶん鈍いもんだ。というか、両親との間で、互いの不安を慰め合うような経験が今まであっただろうか?
気持ちを寄せ合う経験が圧倒的に不足している家庭だったからか、こんな時にも心に浮かぶ心配は現実面に対するものしか出てこない。
私の「冷たさ」は健在だと思わず苦笑した。
私が母に泊まっていいかと聞いたのは、彼女の食事が気になったからだ。
料理も掃除も自分ではできなくなっている母が、世話役の父が急にいなくなって何を食べているのか見当も付かなかった。
生協に入っているので、何かしら食べるものはあるはずだが、包丁をまともに扱えるかどうかもあやしい。
帰ってくるつもりで出掛けた父がそのまま入院したのなら、その日の食事の用意もなかっただろう。
泊まりに行くまで、母の食生活や火の扱いがどうなっているのかずっとヒヤヒヤしていた。
と同時に、父の癌のステージがどれくらいなのかも母からの伝え聞きでははっきりしなくて、わずか3日の時間がもどかしく、仕事に集中するために意識して頭を切り替える必要があった。
あの日から、年末年始の2日間と体調不良でダウンした数日間以外、休みのない状況が一年以上続いている。
仕事が詰まっていたのもあるが、将来へ向けてのスイッチを切り替えるべきタイミングが重なったからだ。
人生でここまで密度の高い時期を過ごしたことはない。
人間、何歳になっても新しいことが訪れるし、自分から踏み出すこともできるんだなあと感動すらしている。この辺の話はいずれまた。
*** ***
地下鉄の構内からエスカレーターで大学病院の新館ロビーへ上がる途中に、スターバックスができていた。
母が入院していた頃には無かった棟だ。
6月とはいえ十分に暑い日で、(帰りに寄ろう)と横目で見ながら早足で上る。新型コロナ対策でテイクアウトのみになっていると看板に書かれているのがチラリと見えた。
父が入院している病棟は旧館なので、一度新館から出て、出入り制限のため旧館の端にある夜間専用の入り口へ回るようにと警備員に指示される。
体温チェックを受け、重い扉を全身を使って押し開けた。
旧館の薄暗い廊下。
まさかここに、母でなく父の見舞いで訪れることになるなんて。
奥まったエレベーターの場所へ、案内を見ずともスイスイ進める。その斜め向かいにトイレがあるのも、角を曲がる前に思い出していた。
母が水を流すボタンと間違えて緊急ボタンを何度も押して、看護師が飛んできたトイレだ。ひたすら謝る私に、看護師は「何もなくて良かったです」と笑ってくれた。
そこここに、3日前、病院に電話を掛けた時に蘇ったあの匂いが漂う。
(何も変わってないんだな)
それが私に、故郷へ帰ってきたような妙な懐かしさと安堵を感じさせた。
病院なのにホッとするなんて変な気分だ……。
「父さん」
看護師に教えられた病室へ入ると、父は横になっていた。
病院から呼び出しがあるような場合を除いて一切面会禁止のため、他の患者の家族は誰も来ていない。向かいのベッドの高齢の男性が、ん?とこちらを向いたので軽く頭を下げて挨拶をする。
「えー、お前さん来てくれたのか」
むくりと起き上がる腕に点滴の管が繋がっていた。
「絶食なんでずっと点滴打ってんだよ」
「絶食?」
「腸が詰まってたらしくてな」
さらりと言われたが、えっと思わず息を飲んだ。
腸閉塞を起こしていたのだとしたら、あまり良い状態じゃない。
驚きを顔に出さないようにしながら「母さんから少し聞いたよ」と言うと、「ああ、聞いたか。どうやら癌らしいな」なんてサラッと続ける。
(強がっているのかな)と顔色を見たが、いつもの表情とあまり変わらない。
こんな形で娘に弱い姿を見せるなんて、多分、父とすればあまりにも想定外のはずだ。
私もつとめて普通に話すことにした。
「あとで先生から説明があるみたいだから、それまでに入院の同意書書いてって言われたんだけど、ある?」と聞くと、ああそれかと言いながら雑誌の下から同意書を引っ張り出した。
「いやお前さんを呼びつけてまで書かせるのも悪いと思ってな」と、これまた母レベルののんびりさで書類を開く。
「いや、これは必要でしょ。すぐに呼んでよ」と返すと、大きな声でとんでもないことを言い出した。
「必要なもんか。こんなもなぁ書かなくてもいいんだよ。病院の都合なだけだ」
母との喧嘩で鼓膜を破られて聞こえが悪くなってから、会話はいつも大声だ。
非常識なことをこんな堂々と病室で言わないで、と静止しようとしたところへ、まるで聞いていたかのように事務の女性が来た。
「やっと出してもらえるんですね。良かった!」と言われるものだから私は慌ててすいませんと頭を下げる。
(何が「来なくていい」よ、病院の人を困らせてるんじゃん!)
うちは徹底した封建主義の家だった。
「親の言うことは絶対」で逆らうことは許されず、仮に親が間違ったことを言っても「子供は黙って従うべし」、そんなことを2人とも本気で言っていた(彼らがそう育てられたのがそもそもの原因だけど)。
私はもちろん反発したから家を飛び出したのだけど、父に対しては常識ある人間だと信じていたのに。
頭の中にチラリと(老害)という言葉が浮かんで、打ち消した。
これまで母のことは父に任せれば良いと思っていたが、それもちょっとあやしくなってきたのかもしれない。
体力気力がしっかりしている父だけに、私も頼りすぎていたなと反省した瞬間だった。
いや、違う。
心の声が安易な反省を打ち消した。
母の手を離したあの時は、それがベストだった。
簡単に自分を責めてその場の問題に目を塞ぐのは良くないことだ。
自分の正直な感情を抑え込み続けたせいで爆発して分裂しかけ、頭の声で「別の自分」が叫び出した瞬間のことが思い出される。
あの出来事は、自分をこれ以上潰さないためのストッパーのように、自分を後回しにしようとすると脳裏に浮かぶようになっていた。
父に全てを任せたのは、私の出る幕が一旦終了したからだ。
デメリットよりもメリットがわずかでも上回ると感じたからそうした。それはそれで、良かったと思うべきだと考え直した。
ただ、父が倒れたからには。
(またサポートを始めよう)
同意書を読み、サインをしながら、両親との距離感を変えなければならない瞬間の訪れを私は痛いほど感じていた。
もう、今までみたいな手放しではいられない。
親子の関係がもう一段変化する、新しい曲がり角に差し掛かったのだ。
自分は普通だと言い張る母の、どう見ても普通とは言い難い人生を書いています。
000〜047話は、母の人生の前提部。
051話からが、本題です。
※文中の人名はすべて仮名です。
読んでくださった皆さまに心から感謝を。 電子書籍「我が家のお墓」、Amazon等で発売中です! 知ってるようで情報が少ないお墓の選び方。親子で話し合うきっかけにどうぞ^^ ※当サイト内の文章・画像の無断転載はご遠慮します。引用する際には引用の要件を守って下さい。
