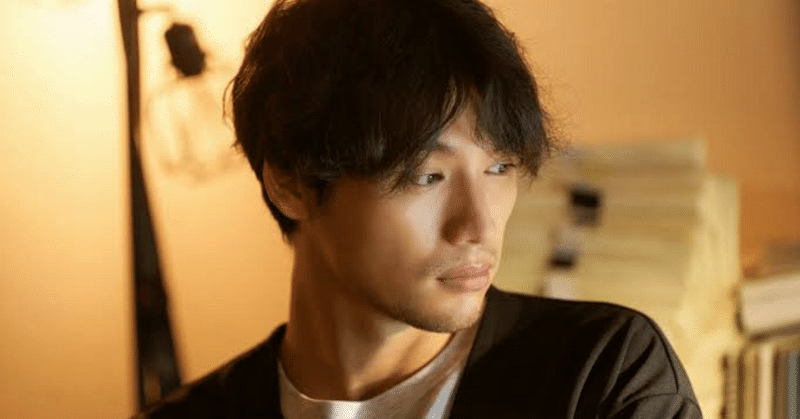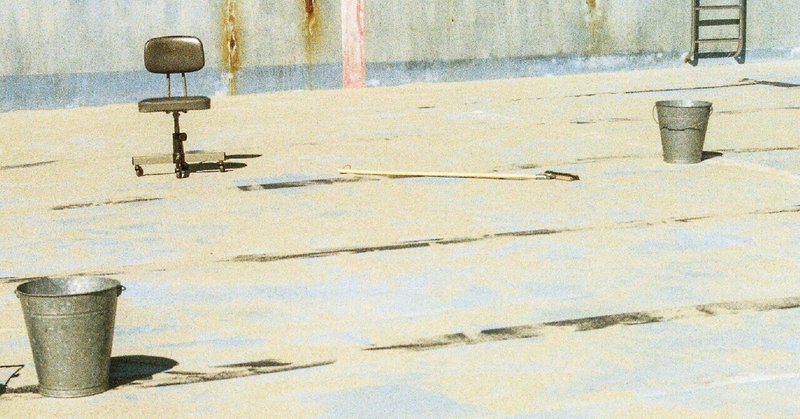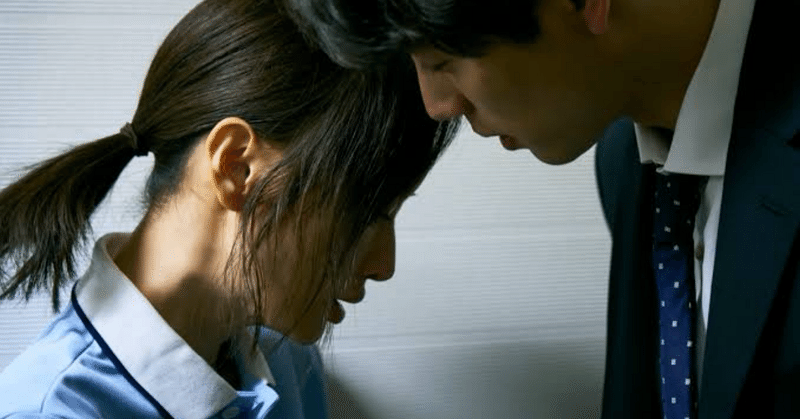最近の記事

【日時変更】女の子、男の子。12.7こどもが主人公のちいさな映画祭を開催。『泳ぎすぎた夜』『わたしは元気』屈指の名作2本を伊豆・松崎町にて上映。
お誘いをいただき、伊豆・松崎町にて、相田冬二セレクト上映会をおこないます。 わたし自身、上映会は初めてで、主催の方々と一緒に奮闘中ですが、上映作品には絶対の自信があります。 こどもが主人公の映画を二本選びました。いずれも相田がその年のベストワンに選んだ傑作中の傑作。世界映画史に残る逸品です。 たまたまですが、男の子の映画、女の子の映画になりました。また、カラーとモノクロームという対比の妙もあります。入れ替え制ですが、ぜひ二本ご覧いただけますと、映画芸術の風格と可能性を同
マガジン
記事

【アーカイブ受付中】『蛇の道』『Chime』『Cloud』そして“2020年代の黒沢清”を黒沢清監督が語り下ろすzoom公開スペシャルインタビュー6.22開催。
2024.6.22土曜日 1830開場1900開演 zoomトークイベント 【contact】featuring黒沢清 柴咲コウ主演『蛇の道』(6.14公開)、吉岡睦雄主演『Chime』(8月劇場公開。https://roadstead.io/にてレンタル視聴可能)、菅田将暉主演『Cloud クラウド』(9.27公開)。2024年、わずか4か月に3本もの新作が公開される黒沢清監督。 フランスでの自作リメイク、前例のない映画フォーマットでの45分、菅田将暉らフレッシュな顔