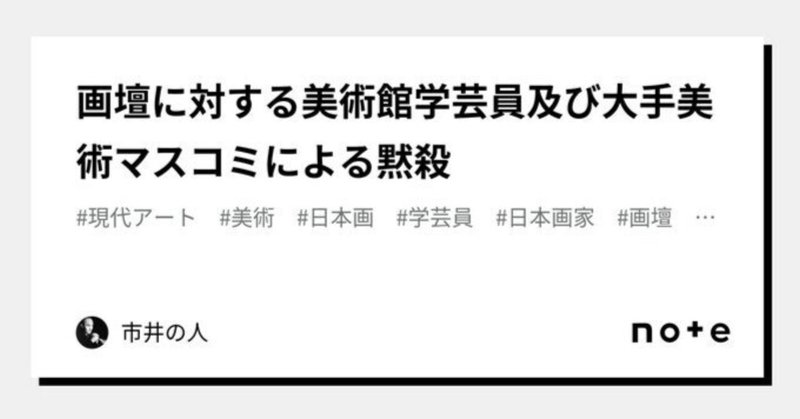
画壇に対する美術館学芸員及び大手美術マスコミによる黙殺
昨今の日本美術界を見渡しますと、都市部にある大手公立美術館では現代アート系だと学芸員から認められれば若手でも個展が開催できますが、画壇系だと絹谷幸二氏や田渕俊夫氏、野見山暁治氏、遠藤彰子氏など、余程の大物でない限り個展が開催されることはありません。ただし、地方の公立美術館だと画壇系でそれほど大物でなくても郷土の画家なら個展を開催してくれるケースもありますが。
私が思うに、公立美術館(私立は美術館のオーナーの方針によってコレクションや企画展の性質がそれぞれ異なるので除外します)の学芸員の大半は基本的に現代美術家しか眼中に無く、団体展や百貨店画廊、日動画廊を始めとする一般画廊を見回って無名ではあるものの才能がある洋画家・日本画家を発掘すると言った地道な作業はしていないものと思われます。これは無所属でも同じでしょう。
大新聞の文化部(学芸部)美術記者にも同じことが言え、現代アート系だったら記者が気に入れば無名の若手でも記事になりますが、画壇系だと余程の大物でない限り記事にされることはありません。特に『朝日新聞』の文化部にその傾向が顕著です。
テレビでも画壇系は写実絵画が「まるで写真のようで凄い」という視点から主にバラエティ番組・情報番組で取り上げられるくらいで、『日曜美術館』などの美術番組で取り上げられるのは大半が現代アート系です。
また、現代アート系だったら注目されれば若手でも大手出版社から画集を出せますが(注1)、画壇系は余程の大物でない限り、求龍堂や芸術新聞社などの美術専門出版社からしか画集を出せません。
それから、平松礼二氏のようにフランスで評価されて芸術文化勲章シュヴァリエを受章する日本画家もいれば古吉弘氏のように作品がクリスティーズで高額落札されたり智内兄助氏のようにヨーロッパで高い人気を誇り作品がロスチャイルド家に所蔵される洋画家もいるのですが、何故か日本の大手美術マスコミはそういうケースは取り上げようとしません。海外で評価される美術家は権威に弱い日本の美術マスコミの大好物のはずなのに、現代アート系だったら大袈裟に持ち上げて、画壇系だとこの有様です。
結局、画壇系の美術家をきちんと取り上げるのは『月刊美術』や『美術の窓』、『新美術新聞』といった多くの人が読まない業界誌(紙)や求龍堂・芸術新聞社などの美術専門出版社、百貨店画廊、日動画廊を始めとする一般画廊及びホキ美術館(写実絵画)、成川美術館(現代日本画)、郷さくら美術館(現代日本画)といった画壇系に特化した私立美術館のみであり、それ故に画才があっても不当に知名度が低い洋画家・日本画家がゴロゴロいます(注2)。
この記事をご覧になっている方はこのような日本美術界の現状、つまり美術館学芸員や大手美術マスコミによる画壇に対するあからさまな黙殺についてどう思われますか?よろしければ率直な御意見をお寄せ下さい。
【追記】
私は画壇及び団体展の現状を肯定する訳ではありません。現在の団体展は体質的に問題が多いのも事実ですし、洋画家・日本画家のレベルは明治〜昭和期に比べて明らかに落ちています。ただ、大手美術マスコミや美術館学芸員の極端な現代アート偏重の姿勢により一部の才能ある洋画家・日本画家が日本美術史の闇に葬り去られるのを黙って見過ごす訳には行かないのです。そういう思いからこの記事を書きました。
(注1)堀江栞氏(1992〜)という若手の現代アート系日本画家がいますが、この人は2022年3月に『堀江栞 声よりも近い位置』という画集を小学館から出版しており、『日曜美術館』で司会を務める小説家・小野正嗣氏と神奈川県立近代美術館館長の水沢勉氏が寄稿しています。これはあくまでも一例です。
(注2)象徴的なのは日本画家・村上裕二氏(1964〜)です。若くして院展の同人に選ばれもともと才能のある画家ですが、近年、ゴジラやウルトラマン、仮面ライダーをモチーフとした作品を発表して以降は百貨店画廊を中心とする日本画市場で絶大な人気を誇り、2022年からは雑誌『文藝春秋』の表紙絵を任されるまでに至りましたが、大新聞の美術面で取り上げられることも無ければ大手公立美術館で個展が開催されることも無いため一般的な美術ファンの間では殆ど知られていない存在だと思われます。
※記事に関する御意見・情報提供は連携しているツイッターアカウントのDMか、下記のメールアドレスにお願い致します。
dyi58h74@yahoo.co.jp
【最終加筆:2023年5月29日】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
