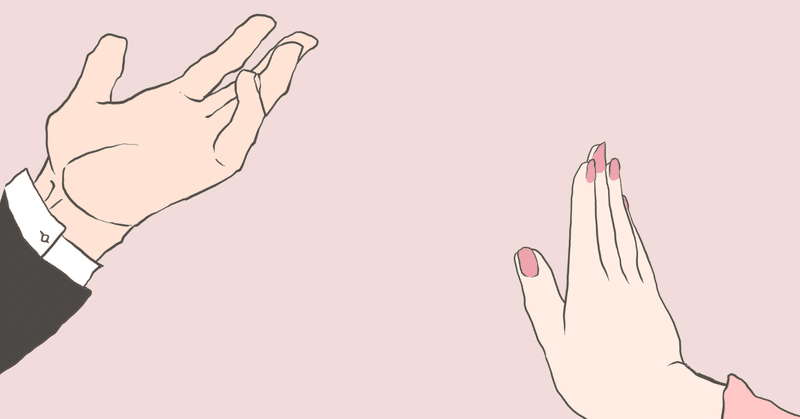
父とわたしを結ぶユーミンの歌
父との思い出があまりない。全くないというわけではないけれど、「思い出」と語るくらいの何かは圧倒的に少ない。書き手のわたしは今年28歳になるが、幼いころの父との記憶を思い返すと、のどの奥がすこしツンとする。父は転勤族だったから、一緒に住むというのはあまりなかった。半年から一年間とか短期間こちらにいることはあったけれど、長い間一緒にいることはなかった。
*
全く愛されていないんじゃないかと思うくらい、わたしは父親に厳しく育てられた。3つ上の兄がいるのだけれど、父は兄にはわたしよりも少し優しかった。兄には怒ることはあまりなかったし、心配や気遣いもあったようにみえた。
それなのにわたしに対しては、とても厳しかった。一応人間だから、わたしにも思春期というものがあり反抗期があって、母と喧嘩をしていた時期があった。
父が家にいるときにわたしが母と喧嘩をすると父が出てきて戦争になり、結局わたしは怒鳴られ時には手を出されて黙るしかなかった。そのおかげか、わたしの反抗期はあまりに短く終わり、反抗しきれなかった気持ちはくすぶったまま転がっていった。顔に痣ができたこともあったし、首に手の跡がついたこともある。男性がふりかざす拳がこんなに痛いんだと知った日、わたしのなかで「結婚」というものへの憧れがなにもかも砕け散ってしまったように思える。母性と父性を学ぶことが、多分うまくできなかった。
会話の少ない父との日常と、対面で逢えない日々の中。わかりあうための時間をつくるなんてことはできなかった。
ただ、旅行なんてめったにしたがらない父が、唯一連れて行ってくれたのが、小さいころに住んでいた福島の家だった。父の母、わたしにとっての祖母が住んでいた家は、祖母が亡くなっても二年間あまりは福島にあった。地震の影響もあって今はもうわたしたちの手元から離れてしまったのだけれど、しばらく手放さなかったのは、父が残していたかったからなんだろう。その一心だ。
家というのは、人が住んでいないとだめになってしまうらしい。たまに帰ると嬉しそうにみしみしと音をたてて、まるでそれは「おかえり」と言ってくれているみたいだった。帰らなければ帰らないほど、どんどん老朽化が進んで、かびが増えていって、でも父は思い出を消したくないから必死に手入れをしていたんだと思う。たまに家族そろって帰るときにはお家は久しぶりに訪れたとは思えないくらい綺麗で、きっとこっそり父が掃除をしていたからなんだなと悟った。だからこそなんだか暖かくて、居心地がよくて、今は亡き祖母の笑い声が聞こえてくるみたいだった。
父の父、わたしの祖父は、父がまだ成人する前に亡くなったらしい。その頃から一緒にいた母は、ある日突然聞かされたそうだ。「親父が、死んだ」。その言葉を、何気ない会話をするようにしたもんだから、母もどう反応したか覚えていないらしい。
ミスタードーナツのアルバイトで出会った父と母は、性格が真逆のくせになぜか結婚した。喧嘩が絶えず、母が泣く姿をたくさん見てきたけれど、なんだかんだ父のそばにいれるのは母しかいなかったと思うくらい、ふたりは運命を背負っている気がしている(のはわたしだけかもしれない)。
*
家族そろって福島に帰るときの車の中。必ず流れていたのは、松任谷由実さんの歌だった。特に流れていたのは「やさしさに包まれたら」と「恋人がサンタクロース」。後部座席の右側で、父の真後ろでわたしは何度も同じ曲を聴いていた。どうしてだか思い出される景色は夕焼けで、福島から東京に帰ってくる車の中で流れるユーミンの歌を思い出す。
兄や母が寝ていてもずっと運転を続ける父の頭を、なんともいえない気持ちで眺めていたあの頃。
今思えば、ずっと悲しそうだった。ユーミンの声がささやくように車内に蔓延するあの時間。父は何を思っていたんだろう。どうしてあんなに悲しそうだったのか。何を思って、聴いていたんだろう。何を思って、何を思い出して、家族4人が揃う車の中で流していたんだろう。
父のことを知るためには、あまりにも過ごした時間が少ない。知ろうとすると、悲しい気持ちと怒りの方が先行してしまっていたから、本当の意味で父のことを知ろうとできたのは、最近だ。実家を出てひとりぐらしをして5年。父も会社を定年退職する歳になって、やっと。やっときちんと話せるようになった。過去を話すなんて野暮ったいことはしないけれど、たまに実家に帰るとわたしの好きなごはんをつくろうと準備をしてくれている(ちなみに父の料理は味付けが濃く、母は極端に薄い。真逆だ)。
社会人になって自分が壊れるほどに働いて倒れて、やっとわかった。
父も母も、すごい。どんな時でも働いて、わたしたちのことを養ってくれて、本当にすごい。逃げたくなる日だってさぼりたい日だってあっただろうに、それを極力みせないようにして働いてここまでわたしを育ててくれた。会社でどんなことがあろうと、家庭を持つ大人として、兄とわたしに愛をくれた。自分の時間をわたしたちに、くれた。まずそのことに気づくのがとても遅かった。
一緒に住んでいた福島の家を手放した時の父は、どんな気持ちだったのか。早くにして失くした祖父と、誰よりも大事にしていた祖母との思い出が詰まった家を売る決意をしたその気持ちを想像すると、泣けてくる。できることなら守りたかった。わたしにできることがあるなら、助けたかった。それを求めるほど、父親は「子供」じゃなかった。それが正解だったんだろう。
*
気持ちを言葉にするのがとても苦手な父の心を代弁していたのがユーミンだとしたら、父は意外とピュアなのかもしれない。車の中の曲はいつも同じような順番で流れてきていたけれど、ひょっとしてプレイリストとか作っていたのかな。だとしたら、父はそのときどんなことを思っていたんだろう。
もしかしたら父は、ユーミンが紡ぐ言葉に救われていたのかもしれない。若くして自分の父親を亡くした寂しさ、転勤を繰り返しひとりで知らない土地で暮らすことが多かった父。ユーミンが届けてくれる曲のひとつひとつで涙を流す日々があったのかもしれない。
ユーミンの曲を聴くと、父の顔が思い浮かぶ。
わたしにとってのユーミンは父。父を思うときに聴く曲は、ユーミン。
わたしと父を繫いでくれたのは、ユーミンなのだ。
*
きっと、父はわたしよりも早くに亡くなる。どんなに望んだって、どんなに願ったって、会えなくなる日が来る。それでいい。早くにわたしが死んだって、多分今の彼は悲しむから。それがいい。
こうやって会えなくなる時のことを考えて書いているだけで涙が出るから、
わたしはどうしたって、父が好きなんだと思う。ずっと、愛されたかったんだと思う。
父とうまく向き合えないこと。痛くて苦しくて、モヤモヤする日々。嫌いになれば楽なのに、それができなかったのはなぜなのか。情なのか、切なさからなのか、悲しさからくるものなのか。今まではわからなかったけれど。
今ならわかる。
この痛みの正体は、「寂しさ」だったんだろう。わたしはずっと、父のことが好きだった。父のことを知りたかった。
実家に帰るたびに弱っていく父の姿。そのくせ変わらない気の強さ。でも昔よりも何倍も優しくわたしを見る目。ちょっとだけ娘の恋愛事情が気になっていそうなあのソワソワした感じ。可愛くて、愛おしくて、そんな日々がきたことに情けないほど、わたしは嬉しくて泣いてしまう。
これまでの父のすべてはどうやったって理解できない。そんな父の心を思いっきり鷲づかんだ母と。
ユーミンは。
わたしにとって、偉人だ。
*
「そろそろ帰って来い」って言ってるらしい。母から聞く便りに、「忙しいから確認するね」なんて言いながら、少し嬉しかったりもする。素直に会いたいって連絡してくればいいのに、そうしたらわたしも素直になるのに、お互いに出方をうかがっているあたり、似た者同士だなぁなんて思ったり。
次にもし会えたら、聞いてみようかな。「どうしてユーミンが好きなの」って、聞いてみようかな。どうせ酔っぱらった時にしか聞けないし、あっちも酔ってるだろうし、その答えはわからないんだろうな。
父が好きな松任谷由実さんが、ユーミンが。これからも、この先も、どんな時代になっても。誰かにとっての英雄でありますように。ずっとずっと、語り継がれているアーティストでありますように。そんなことを思いながら聞く「ひこうき雲」。
ぽろぽろと溢れてくる涙は、父とわたしがいなくなってもこの世の中にあってほしい、そんな想いからくるもの。お互いが死んでも、わたしと父の思い出になるんだろう。そして誰かの思い出の曲に、なっていくんだろう。そうあってほしい。
*
おばあちゃん、父のお母さん。
おじいちゃん、会ったことのない父のお父さん。
父を産んでくれて、ありがとう。きっともう、大丈夫。
寂しさを感じた分、父に愛を注いでいこうと思います。
父は、ちゃんとわたしの父です。父なんだ。
わたしと父を繫いでくれた、松任谷由実さんに敬意をこめて。
#思い出の曲
いつも応援ありがとうございます。
