
【ACT SDGs】 TOKYO x SDGs 都市における美しい資源循環を考える イベントレポート
都市における資源循環の美しいモデルとは、どんなものでしょう?
食品ロス問題(食べられるのに捨てられてしまう食品)が叫ばれていますが、食料の供給システムを最適化し、そもそも出てしまう食料廃棄を減らさなければ、根本解決には至りません。
世界の飢餓人口は、約8億人(出典:国連2018)。
しかし人類は、すでに全人口をまかなうだけの食料を作ることができているということをご存知でしょうか?(出典:FAO)
分配方法がうまくいっていないばかりに、飢餓や栄養不足の人を生んでしまっています。私たちは、いかにして食料を調達・分配し、資源を循環させればいいのでしょうか?
すべての人の人権を守りながら世界と調和する世界とは

持続可能な世界の実現を誓ったグローバル目標「SDGs(Sustainable Development Goals)」では、全人類の人権を守り、地球と世界が調和する世界を目指すことが掲げられています。
しかし日本の現状は、まだまだ大量生産・大量消費・大量廃棄社会。日本人の消費をまかなうのに必要な土地面積は、なんと「日本 7.7個分(2018)」。東京都においては、「東京都125個分(2000)」も必要とのデータもあります(出典:WWF)。

今後アフリカをはじめとする途上国が発展することを考慮すると、日本はまず、現状の資源の扱い方を改めて考える必要があるのではないでしょうか。
さらに、今後悪化することが予測されている気候変動の影響で、農作物の収量が減ることや、土地が劣化してしまうことを考慮すると、なおさら資源を無駄にはできません。
「経済」 「社会」 「環境」 にまつわる食の問題

SDGs が記載されている「2030 アジェンダ」の冒頭にあるのは、「Transforming our world(私たちの世界を変革する)」。ここで必要とされているのは、政策や教育制度、産業構造などの抜本的な改革です。
今の社会の延長線上に持続可能な未来はない。根本原因を見つめた上で、根本解決となるエコシステムを構築することが、今もっとも必要なことと言えます。
そこで今回、そもそものサプライチェーンのあり方を見直す、食料廃棄全体をなくすといった視点からイベントを企画しました。根本的な解決とエコシステム構築を目指すために、まずは「経済」「社会」「環境」それぞれにまつわる食の問題を考えました。
資源がうまく分配される循環システムとはどんなもの?

「経済 x 食」の問題では、過体重人口19億人(出典:WHO)に対し、飢餓人口は8億人も存在(出典:国連)、アンバランスが起きています。さらに人類は、すべての人を養うだけの食料を作ることができるにもかかわらず、生産量の3分の1にあたる約13億トンの食料を廃棄してしまっています。
ここ日本でも、年間8,088万トンの食料を生産しているうちの約3割にあたる2,759万トンの食品廃棄物(2016)を出しており、世界の食料援助量の2倍にあたる643万トンの食品ロス(出典:農水省)を出しています。
飢餓に苦しむ人は東京都人口の半分にあたる612万人もいるといったデータ(出典:Newsweek)もあり、日本でも同じようなアンバランスが起きています。
世界全体の食料廃棄量を減らす第一歩として、どんな資源循環モデルがあればいいでしょうか?
人権が守られる労働環境とはどんなもの?

出典:農水省
食業界では、働き方改革においても課題が多いことが挙げられます。営業時間が長いことからシフト制を採用し、パート・非正規雇用に頼る食業界、人も辞めやすいことから改革が進みにくいのが現状です。
また、食業界は特に外国人労働者の受け入れが進んでいますが、人口減少が進むに連れて人材確保も難しくなっています。
関わる人の幸せを実現する働き方や長く働ける雇用環境とは、どんなものなのでしょうか?
誰も取り残さない食、誰も取り残さないコミュニティはどんなもの?

「社会 x 食」の問題には、遺伝子組み換え種子や化学農薬・化学肥料など、食してきた歴史の浅いもの、今後どのような影響があるかわからないものが多く流通しているといった食料安全の問題があります。
特に殺虫剤をはじめとした化学物質は、子どもへの健康被害や認知症との関連を疑う論文や土壌水質汚染、生態系破壊の問題もあるので、改めて向き合い方を考える必要がありそうです。
それに加え、宗教やアレルギーにまつわる表示やメニューバリエーションへの対応の遅れ、8つのこ食(孤、子、固、個、粉、濃、戸)の問題などもあります。
SDGs が掲げる「誰ひとり取り残さない食」、そして「誰ひとり取り残さないコミュニティ」は、どうあればいいのでしょうか?
生物多様性を実現する農業、最適なビジネスサイズは?

出典:農水省
「環境 x 食」の問題では、日本の自給率の低さの問題から、様々な問題へと繋がっていることが挙げられます。
過去最低37%(カロリーベース)の自給率は、「フードマイレージ(輸送距離)」を引き上げ、輸送する際の二酸化炭素排出量やエネルギーの消費量を増やしています。
また、気候変動や汚染による水不足が懸念され、将来水戦争が起こるとの予測がなされているなか、「バーチャルウォーター(生産の際に使用される水量)」の輸入量を高めていることも問題です。
途上国から調達をしているものの中には、森林伐採による生態系破壊や児童労働に関わっているものもあります。
インスタント食品に多く使われているパーム油は、日本も多くを輸入に頼っています。これを利用することは、開発を推し進め環境を破壊をすることに間接的に加担していることに他なりません(出典:認定NPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン)。
ゴミを出さない最適なデリバリーは?

さらに、これまで大量生産・大量消費が進められてきたことで、使い捨ての包装パッケージのゴミも増えています。
ほとんどのパッケージの素材となっているプラスチックは、現状100% 回収する仕組みができておらず(出典:環境省)、一部は海に流れ出し、海洋生物を傷つけ汚染にも繋がっていることから、世界的に大きな問題に発展しています。
2050年には、魚の総量よりもプラスチックゴミの総量の方が多くなる予測(出典:WWF)があることに加え、脱石油から気候変動対策に繋がることもあり、多くの国が規制を進めています。
プラスチックゴミは海に漂う汚染物質(農薬や潤滑油など)を吸着することがわかっていますが、それを魚が食べ、それを食べた人間の身体に蓄積される可能性もゼロとは言えず、研究者から健康被害の警告が出ています(出典:日経ビジネス/東京農工大高田教授)。
その対策のなかには、微生物によって生分解できる植物性バイオプラスチックが出てきていますが、現状のバイオプラスチックは石油が混入され海で分解できないものもあり、冒頭の資源不足の問題、気候変動問題、さらなる廃棄が増えることも懸念されており、問題視する声も多く存在します。
持続可能な食、未来に残したい食ってどんなものだろう?

ここで一度、参加者のみなさんと「どんな食を実現したいか?」「どんな食が持続可能か?」キーワードを出すワークを行いました。
どんなところで、どんな人が、どんな風に作っていて、それがどんな風に流通するのか、SDGs 17ゴールも意識しながら、細かく言葉に落とし込んでいきます。

「美味しい」「オーガニック」「地産地消」「顔が見える」「アーバンファーミング」「コミュニティ食」「栄養価が高い」…たくさんのキーワードが出てきました!
これを読んでいるみなさんは、どんな食がいいでしょう・・・?
根本解決のためのさまざまなソリューション

貧困層にも安全な食を届けるプロジェクトを紹介した映画「エディブルシティ」(出典:EDIBLE MEDIA)
食の問題を説明した後は、これらの問題を解決するさまざまな事例を、3人のゲストにご紹介いただきました。
環境作家であり大学講師でもある谷崎テトラさんは、富が偏りがちな中央集権型のビジネスモデルから、協同組合型のビジネスモデルへのシフトを提案。そもそもの経済のあり方を問い直し、新しい経済圏を創出する「Next Commons Lab」のお米を通貨にした経済実験についてご紹介いただきました。
続いて、IBM FOOD TRUST 担当である水上賢さんのお話では、ブロックチェーンで食物の経路を記録していき、蓄積されたデータを分析、資源量や流通方法を最適化できるソリューションをご紹介いただきました。
このテクノロジーを使うことで食物の安全性を向上、病気や異物混入など何か問題が見つかったとしても、その経路が特定できることから、膨大なロスを出さなくて済むといったことまで実現できるそう。
また、資源分配の方法も、最適な量、最適な場所、最適なタイミングで行いやすくなるので、無駄なく資源循環させることに貢献します。証明書の発効もできるので、それを元にお客さんとコミュニケーションをすることも可能になります。

左から:農水省食品産業環境対策室 室長 野島昌浩さん、IBM 水上賢さん、ボングー代表 坂巻達也さん、環境放送作家 谷崎テトラさん
続いてご登壇いただいたのは、埼玉県川口市で完全予約制のパン屋さん「Ocalan」を営む、坂巻達也さん。
ほとんどのパン屋さんでは、販売見込みから小麦粉を発注するため、売れ残りが出てしまいます。そこでOcalanでは、まず商品ラインナップから発注を受付、必要量がわかってから材料発注をかけるため、最低限の量でまかなうことができます。まさしくファッションブランドの受注発注制にも近い仕組み。
さらに、購入者が食品ロスにしないパンの開発(冷凍しても美味しいパン)や、豆腐屋さんで出るおからを活用した焼き菓子の発明なども行っているそうです。
最後はACT SDGs 松尾から、調達・物流・加工/販売・廃棄、それぞれの国内外のソリューションをご紹介しました。その一部をご紹介します。

フランス/市民による市民のための会員制スーパーマーケット(出典:greenz)

アメリカ/日本の出前をアップデートした「LOOP」。専用バックでパッケージを回収できるソリューション。(出典:ITmedia)

アムステルダム/有機性廃棄物を、焼却せずその場でグリーンエネルギーや天然肥料や水に変換する仕組み(出典:井出留美さん記事)
いよいよ本番!みんなで資源循環モデルをデザイン

さまざまなソリューションを紹介したあと、いよいよグループごとに食の循環モデルをデザインしていきます。
調達/物流/加工・販売/廃棄の4つを意識しながら、個人ワークで循環図を描きます。そこからグループ内で意見をすり合わせ、最適なものを ひとつ選んでいきます。
これはSDGsの進め方でも採用されている「バックキャスティング」のアプローチ。ありたい姿を描いたあと、自分たちの行動計画へと落とし込んでいく方法です。
つい目の前の利益に集中しがちのところ、高い視座を持って問題を捉えることができるので、本質的な方法を見出しやすく、このプロセスを踏むことでみなさんとビジョンを共有することができるので、よりSDGsの実現性を高めることもできます。

およそ 1 時間かけて個人ワークからみなさんの意見を統合、グラフィックレコーダーさんにひとつの絵にまとめていただきました。みなさんお疲れ様でした!
民産官協働で持続可能な食の実現を目指す
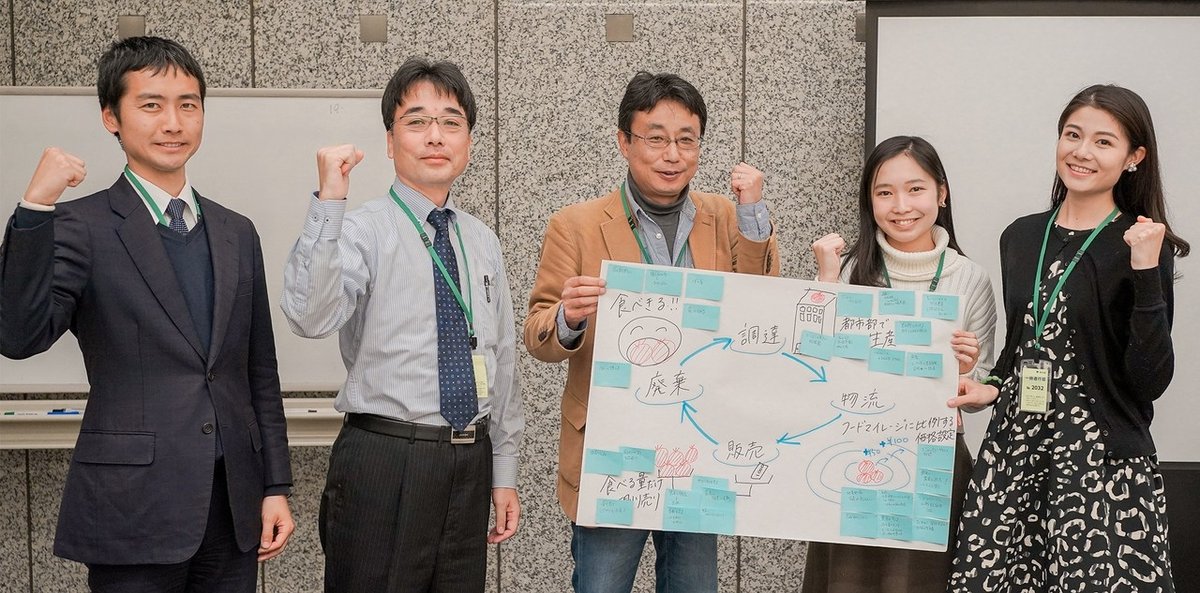
東京都は先日、持続可能な食糧政策宣言「C40 Good Food Cities Declaration」にも署名をし、食品ロスをはじめとした食料問題にコミットすることを宣言しました。
ここでは次のことが掲げられています。
・健康的な植物性食品の消費へのシフト
・食品ロスや食品廃棄物を 2015年比50%削減
・食品調達ポリシーを「Planetary Health Diet」に準拠
・市民、企業、政府機関等が共同で上記目標達成のための戦略を策定
ここにある「Planetary Health Diet」では、①大人の毎日の摂取カロリー2,500カロリー以下に、②肉消費を1週間で300g未満 & 乳製品を1日で250g未満に、③ファーストフードやソフトドリンクなど極力抑えるといった内容が盛り込まれていますが、
これを実現することで、人口100億人時代にもバランスの取れた栄養素が提供でき、年間1,100万人の命を救うと書かれています。
紛争の原因にもなりうる資源問題に向き合うことは、SDGsの実現、平和の実現にも欠かせません。
また、SDGsでも言われているのが「マルチステークホルダー」による共創。SDGs策定でも多様なオンライン意見を反映していますが、さまざまな人が参加することで、より多角的な視点から出たアイディアや強靭な仕組みづくりへと繋がり、多くの人が自分ごとにすることができるのではないかと考えています。

最後に、参加者のみなさんにそれぞれ個人でできること、組織でできることをシェアいただいて、無事イベントは終了しました。
ご参加いただいたみなさま、東京都環境局のみなさま、本当にありがとうございました!今回出たアイディアは環境局に提出、今後に繋げていきたいと思います。
Special Thanks photo by kenta jufuku
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このイベントパッケージは、より良い方法を一緒に模索できるよう、そして早く平和が実現できるように! みなさんにご自由に使っていただこうと思っています。
一緒にやってみたい!サポートしてほしい!相談したい!という方は、どうぞお気軽にご連絡くださいね。
ACT SDGs 管理人 松尾
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
