
BtoB事業 利益の源泉(3)「ソフトの罠」
前回の記事はこちら。
すっかり更新を忘れていました。すいません。
前回は、ZEBを事例にとって具体的なBtoBビジネスのポイントを解説しました。この解説では「ソフト」が重要になりそうな結論に至りました。今回はこの「ソフト」の力について、問い直していきます。
2つの落とし穴「ソフトの機能」「ソフトへの接続」
「ソフト」には大きな落とし穴が2つあります。
1つはこんなイメージです。
あなたが電気屋さんでパソコンを探しているときに、店員が横に来て「このコンピューターにはなんとワードというソフトが入ってます!入ってるソフトが優秀でしょ!」と言ってきたらどうでしょうか?
確かにワードは「ソフト」です。嘘ではありません。文書が作れる優秀な「ソフト」であり、パソコンには欠かせない大事な機能です。
しかしながら、今時、当たり前についてる「ソフト」ですね。

これと同じです。建物のエネルギーを管理する「ソフト」は、欠かせないものではありますが、正直なところ、差別化できるポイントとは言い難いのが実情です。
もう一つの落とし穴は、ワードをお客様が使いこなせるか?という問題です。
多くの人がワードを使うことはできます。では、建物エネルギー専用のコンピューターを動かす「ソフト」をオーナーが使いこなせるかと言えば、ワード並みに多くの人が使える前提を想定すべきではないでしょう。
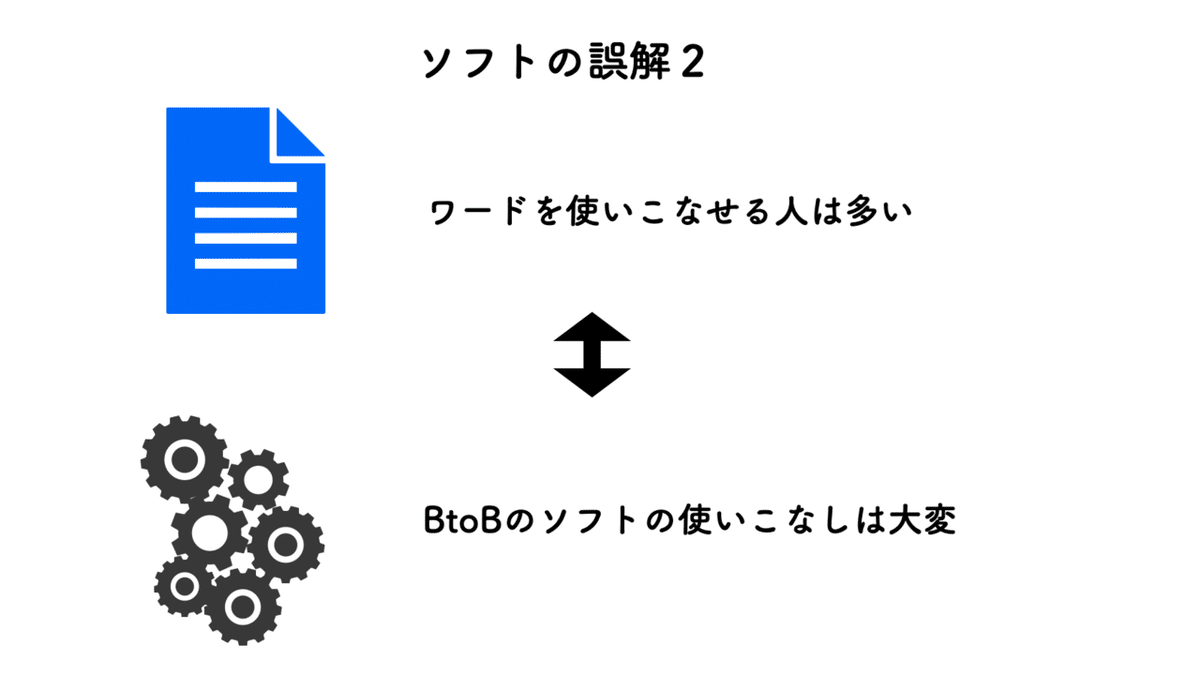
どう頑張っても、この「ソフト」は複雑になり、専門的になってきます。ワードに写真を挿入したい、段落をいれたい、ページ番号を入れたい・・・ワードならできる人も多いと思いますが、これが建物エネルギー専用のコンピューターだと話は変わります。
照明と接続したい、空調と接続したいとなれば、かなりの専門性を要することになります。このときに、照明メーカーは照明のことは説明できても、コンピューターのことはよく知らないということになってきます。
前回の3つのピースで言えば、①、②、③を提案する側は、それぞれ個別に存在してしまっています。
もちろん、ここにはコンサルや設計事務所といった「総取り纏め役」は存在しますが、得意な領域と苦手な領域はやはり存在しますので、全てをいってに引き受けることができるプレイヤーを探すのは容易ではありません。

そうなると、今回の場合でいえば、ZEBという横串で対応できる窓口があった方が、有利になります。すでに感動できる「コト」が何かも、それを実現するために必要な「ソフト」も顧客は分かっています。そして、それを①、②、③と個別には揃えることもできました。
しかし、ものごとは簡単には進まなかったりします。各パーツが繋がらないこと、否、繋がるはずだけど、繋げるのが大変だからです。
大変⇄ラク
「大変である」の反対語は明確です。「簡単である」「ラクである」ことです。BtoBにおいては将来必要なテーマは、提案者も、お客様も、エンドユーザーも分かっています。そのテーマよりも実際上で重要なのは、そのテーマをいかに簡単にラクに実現できるかが肝なのです。
なので「ラク消費」の意識が必要なのです。
BtoBのほとんどの人は、エンドユーザーを感動せるために必要な「コト」を知っています。いちばん注力するのはその実現方法です。実現が「ラク」であればあるほど価値があるわけです。
それではこの「ラク消費」をお客様に提案していくために我々がすべきことはなんでしょうか?次回はこの辺りを考えていきたいと思っています。
ということでまた。
現在サポートは受け付けておりません。
