
インスリンとアブラの話【糖尿病④】
現代では主食として炭水化物を摂取しているが、それは膵臓を疲弊させる。
絶食時にはカロリー源として、まず糖質が消費され、次に脂質、最後にたんぱく質が消費される。
身体は上手くできてきて、大切なものほど後に使うんだ。
これは昔のヒトの生活を考えると、次はいつ手に入るかわからない糖質に頼って生きていなかったということだ。
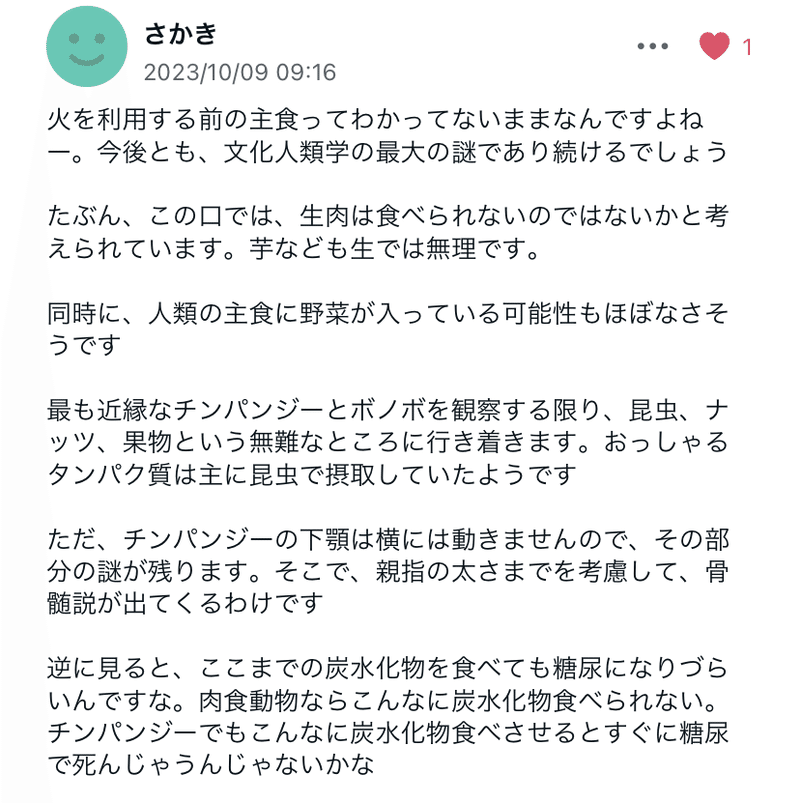

炭水化物を食べないことを徹底するだけで、ヒトの消化機能として備わっている膵臓のインスリン分泌を休ませてあげることができる。
ちなみに「島」を示すラテン語(insula) から「インスリン」と名付けられた。そのインスリンはランゲルハンス島から出ているんだよ。
毎日あなたの身体の島から、島がうまれてる。
けれど、島を生み出すのは負担がかかる。
今日はそんな話。
人はブドウ糖の炎で脂肪を燃やして生きている
炭水化物は糖だ。その糖は即エネルギーになる。
その力でヒトは脂肪を燃やして生きるようデザインされているんだ。
糖質は肝臓、および筋肉中にグリコーゲンとして貯蔵されている。
しかしグリコーゲンだけ使うとすれば人はごく短時間でエネルギーが切れてしまうことになる。
通常1日、運動してたら1〜2時間しかもたないんだ。
そんなエネルギー源を"主食"にしてしまうと、狩猟採集する時の狩りは成功するだろうか?
タラウマラ族というメキシコ原住民がいる。
彼らは「走る」ことに長けており、1日で200km走る。彼らの中のマラソンチャンピオンは700Kmを続けて走ったとされる。
日本の24時間テレビのチャリティーマラソンでも間寛平さんが1日で200Km、1週間で600Kmを走った記録があるので実際に可能なのであろう。
そして思うのは、糖質だけを燃料として走り切ることはできない、ということだ。
長距離を走ることができるのは脂肪をうまく活用しているからであり、彼らと同じように私たちの身体も作られているんだ。
脂肪をうまく使えば水だけで一カ月や二カ月は生きられるのは周知されているだろう。
ヒトは糖質ではなく、脂肪を燃料にして活動する仕組みなんだ。
脂質で生きる穀断ちと即身仏
現代人は主食を炭水化物という糖で賄っている。
糖質を身体が使い切らないかぎり次に蓄えている脂質を使わないんだ。
だから糖質から脂肪を燃料にするスイッチがスムーズに切り替わる人は、驚異的な力を発揮することができたりもする。
ナチュラルに糖質制限している人は居ないだろうか?
僧侶の修行の穀断ちというものがある。
それはもしかしたら、糖質から脂質への代謝スイッチを切り替えているのかもしれない。
だから調べてみようと思うんだ。
五穀または十穀を食べずに修行すること。
その修行者を古くは穀断聖(ひじり)といったが,中世・近世には十穀聖とか木食(もくじき)行者とよぶようになった。
五穀,十穀の種類はかならずしも一定していない。
五穀は普通米・麦・ヒエ・大豆・小豆といわれるが,アワやキビをかぞえる場合もあり,ソバも十穀の中に入るので,ソバ食即木食というわけにはゆかない。
要するに人間の栽培食物を食べないで,アワ・シイ・松実・クルミ・カヤ・トチなどの木の実や草根を食べることによって,人間の穢れから遠ざかろうという思想から出たものである。
即身仏の話となるが、江戸時代には疫病や飢饉に苦しむ衆生を救うべく、多くの高僧が土中に埋められて入定した。
死後に肉体が腐敗しないよう整え、ミイラの状態に体を近づけるために、1000日~5000日かけ木食修行をする。
木食修行とは、山にこもり火の入った食物をとらず、木の実や果実のみを食す。
肉類、米穀、野菜を常用しない修行のことだ。
1960年代に新潟大学医学部が実施した現地調査で、ほとんどの即身仏には死後人工的に乾燥させるなどの加工が施されていたことが判明した。
日本の温暖湿潤な気候環境においてはエジプトのような自然ミイラは生まれようがなく、即身仏となる前に人の手が加えられたのである。
おそらく木の実の脂質で生きている。
肉や大豆、つまりタンパク質すらも拒否するのは、自分の筋肉をも分解して糖として使用し、即身仏としての完成度が高くなると予想されたからだろう。
穀断ちを行うと、最も腐敗の原因となる脂肪が燃焼され、皮下脂肪が落ちていき水分も少なくなるんだ。
もちろんタンパク質を抜くのは危険だ。
死を前提とした修行を除いては一定期間をもって満了としているようだ。
しかし炭水化物とタンパク質を積極的に摂取しなくても、修行僧は3年以上も山に籠って生きる事ができるのだ。
アワ:367kcal、たんぱく質11.2g、脂質4.4g、糖質66.4g、GI 65
シイの実:244kcal、たんぱく質3.2g、脂質0.8g、糖質54.3g、GI不明
松の実:669kcal、たんぱく質 15.8g、脂質 68.2g、糖質6.5g、GI 10
クルミ: 713kcal、たんぱく質 14.6g、脂質 68.8g、糖質4.2g、GI 18
カヤの実: 629kcal、たんぱく質8.7 g、脂質64.9 g、糖質4.4g GI不明
(カヤの実は縄文時代に食されていたナッツ)
トチ(蒸し):161kcal、たんぱく質1.7g、脂質1.9g、糖質27.6g 、水分58.0 g、GI不明
ソバ(ゆで):114kcal、たんぱく質4.8 g、脂質0.7 g、糖質18.4 g、GI 54
アワとシイの実は糖質が多いが、低GIで脂質が多い木の実の消化に役立っただろう。
脂質やタンパク質の消化にはエネルギーが多く必要なんだ。
ホルモン
血糖値を上げるホルモンはグルカゴン、コルチゾール、アドレナリン/ノルアドレナリン、成長ホルモンなど多岐にわたる。
けれど血糖値を下げるホルモンはインスリンしかない。
これは何を意味しているだろうか?
高血糖よりも低血糖の方が生命に対して非常に危険だからだ。
そのため身体がより注意を働かせていくつもの対策をしているんだ。
グルカゴンは低血糖に対するシグナルで、糖を肝臓から出させるために働く。
コルチゾールやアドレナリンなどは、ストレスが与えられると逃走か闘争かという状況下の中、血糖値をあげて筋肉に対して素早い行動ができるように備えているのだろう。
成長ホルモンは、成長を促進するホルモンでもあるが、基本的には夜の間に脂肪を分解して、翌日血糖値が低い状態でも動けるようにするというホルモンだ。
だから、夜中に何も食べていなくてもヒトは生きているし、朝はそこまでお腹が空いていない。
ヒトの体は長い歴史の中で飢餓に対しては対策していた。
しかし糖質を常に摂取できる飽食の時代が来たのはつい最近のことだ。
だから糖質を多量に摂取して急激に上がった血糖値を処理する能力が、たった一つのインスリンに頼って、そして過剰に働かせて疲れてしまうんだ。
グルコース・スパイクが体を蝕む
空腹時血糖値と食後血糖値の差が大きいことを、グルコース・スパイクという。
下の図は糖尿病になった彼の波形だ。

24時間糖質を測るフリースタイルリブレという測定器を二の腕に刺しているため、興味本位で測定値を監視している。
身体とデータは食べたものを素直に表していて本当ウケる。
では何故このスパイク(トゲ状の波形)が危険なのだろうか?
糖尿病のラットのうち、二四時間少しずつエサを食べて、ずっと250から300の高血糖を持続したものと、一日に二度だけエサを食べて、空腹時には100少しの血糖値で食後だけ250ほどの高血糖になるものとを、比較した研究があります。
その結果、驚くべきことに、高血糖がずっと持続しているラットよりも、食後だけ高血糖になるラットのほうが、大血管の障害がずっと多かったのです
"血糖"が問題なのであれば、高血糖である時間が長いラットの方が体調が悪くなるはずである。
しかし、明確な理由が未だわかっていないんだ。
ホメオスタシス(恒常性)が関係しているのではないかと言われる。
ホメオスタシスってなんだろう。
《同一の状態の意》生体が外的および内的環境の変化を受けても、生理状態などを常に一定範囲内に調整し、恒常性を保つこと。
また、その能力。
神経やホルモンの働きによる。米国の生理学者キャノンが提唱。ホメオスタシス。
私たち人間の体は、37兆個の細胞からなっていて、それが営みを続けていられるのは、常に身体の内部の環境が一定に保たれるからだ。
たとえば、私たちの体温は外気温に関わらず約36℃程度に保たれている。
もし体温が高くなった時にホメオスタシスが働かないと、体に熱がこもり死んでしまうだろう。
たとえば牛乳を飲んだら、カルシウム含有量の割に大きく足りないマグネシウムを自分の骨髄から捻出して骨がもろくなるように。
たとえば、遭難した時に雪や海水を飲んではいけないように。
身体の中の物質や温度を一定に保つには負担がかかる。
だからこの急激に上がった血糖値を元に戻すことで起こるスパイクは身体にとても負担をかけることとなるんだ。
なるべくならスパイクを起こさない方がいい。
スパイクを起こすくらいなら、高血糖の方がいい。
もちろん正常値が1番良い。
脂質
脂質は血糖値を一切上げない。
なぜなら糖質が含まれていないからだ。

ただし、ヒトの消化をもってしても利用できない油があるらしいよ。たとえばマーガリンとか。
ガイトン臨床生理学によると、脂質のみで生活すると、通常ブドウ糖しかエネルギー源にしない脳も、50~70%を脂質代謝産物のケトン体からエネルギーを得る。と記載されている。
血糖値は糖分を補給しなくても一定に保たれているし、足りないと人体が勝手に生成する仕組みを備えてる。そして脳でさえも、糖が使えなくなったら脂肪を使えるようにデザインされているんだ。
まとめ
アブラは血糖値を上げないけど、どんなアブラでも良いというわけではない。
脂質を上手く利用しながら、生きることを考えてみてもいいと思うよ
高たんぱくで高脂質の食事が正常の腎臓に悪いと明らかにするような研究結果はないが、すでに腎機能障害を生じている人が高たんぱく食を摂ると腎機能障害が進行しやすい可能性があるから注意してね。
本が欲しい
