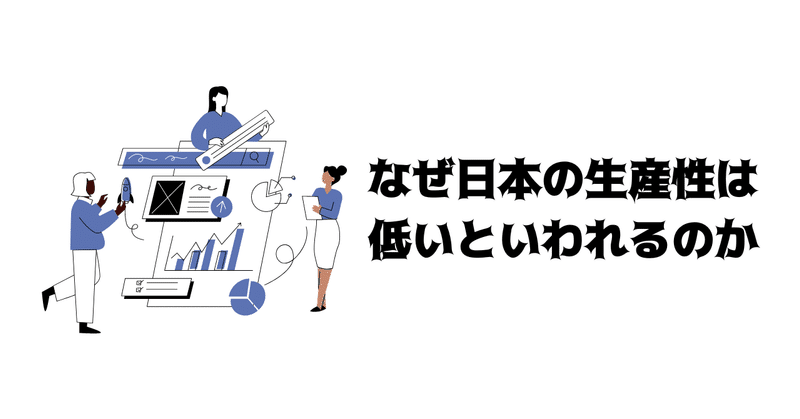
なぜ日本の生産性は低いといわれるのか
自己紹介
ご覧頂きありがとうございます。新卒で食品会社に就職し、営業職を経験したのちにアメリカの子会社に赴任。約10年間海外駐在しています。
自分自身への備忘録も兼ねてアメリカでの体験や自身の考えをnoteに残していきたいと思います。同じ境遇やこれから海外に挑戦したいという方にとって少しでも参考になれば幸いです。
はじめに
「日本(人)は生産性が低い」ということを近年よく耳にしますが、アメリカで働いていて、日本人が生産性で劣っているとは感覚的に納得し難い部分があります。むしろ基礎能力は世界的にみても高い水準にあるとさえ感じます。
人類史の中で世界レベルで生産性が上がったということを考えると、イギリスの産業革命ではないでしょうか。産業革命下では機械という主役を中心とした分業システムが構築されました。
現代では機械は当たり前で、AIという強力なツールも出てきていますので、それらを活用した「分業」が生産性向上にとって重要だと感じます。
そしてその分業に影響を与える要素として、以下項目の日米における違いを見ていきたいと思います。
雇用形態(ジョブ型 vs メンバーシップ型)
システム ⇔ 人の関係性(標準化 vs 属人化)
意思決定プロセス(トップダウン vs ボトムアップ)
ジョブ型 vs メンバーシップ型
まず雇用形態から見ていきたいと思いますが、日本は会社に所属することを許可するメンバーシップ型であるのに対して、アメリカは特定の業務に従事することを前提としたジョブ型が基本となります。
メンバーシップ型ではいろんな業務に従事することが求められるためジェネラリスト適正が求められ、逆にジョブ型ではスペシャリスト適性が求められます。
メンバーシップ型雇用では、時には営業からWebマーケティング担当と全く畑違いのアサインをされることもあるでしょう。異動により数年かけて蓄積した専門性をリセットされることすらあるということです。そうするとまたゼロから専門性を積み上げていかねばなりません。
私自身、日本でルート営業を経験したのちにアメリカに来て営業企画に加えSCMという全く異なる役割を与えられました。仕組みも前任者もない状態でほぼゼロからのスタートでした。
仕組みもなければ前任もいないということに加えて、環境の変化(言葉の壁)という三重苦で相当に苦労しました。
日本ではこのような職務の変更というのは当たり前ですが、ジョブ型雇用のアメリカではまずありえません。今までになかった新しい職務が生まれるならその職務経験者を雇い入れます。他部門からアサインして習得させていくという発想はまずありません。
どちらがより早くアウトプットにつなげられるかは明白でしょう。
職務の変更を伴わない場合でも転勤のように労働環境や人脈を強制的にリセットされるということもあります。例えば営業で転勤をするとまた新たに得意先との信頼関係を構築していく必要が出てきます。
もちろん異動や転勤は人材育成やガバナンスの一環という側面もありますが、前提の変化により一時的に付加価値(=アウトプット)を生み出す能力が下がってしまいます。
逆にジョブ型雇用のアメリカでは転職をしても職務は変わらないため、キャリアチェンジをしない限りはキャリアを通じて同じ職務を担う(階層は変わっていく)というケースが主流です。
また職務自体の細分化が日本の比ではなく、例えば日本のセールスなら一人でカバーする範囲に一般事務を担うアシスタントがいたり、見込み客をつなぐインサイドセールスがいたり、データアナライザーがいたりトレードマーケターがいたり、販売費担当がいたりします。
当然、経験年数x職務範囲の濃度のかけ合わせが高くなり、少ないインプットでより大きなアウトプットが期待できます。個々人としては非常に偏ったスキルですが、配置/登用を工夫することにより全体としてのバランスを取ろうとしている印象です。
ただジョブ型も良い点ばかりでもなく、マンネリ化、思考の硬直化によりかえって生産性や創造性が落ちてしまうという側面もあります。
標準化 vs 属人化
最近は日本のニュースなどでもよく取り上げられているので、ご存知の方も多いと思いますがアメリカの給与水準は日本のそれと比較すると相当に高いです。
感覚的には同じ職務でアメリカの方が日本より1.5~2倍の給与相場という印象です(それも1/2~2/3くらいの実労働時間で…)。
そしてその乖離はコロナ後さらに広がってきているのを感じます。
いずれにせよアメリカでは人材要件を低減せねば、人件費負担が事業運営を圧迫します。加えて人材が流動的な環境下では、日本の新入社員に言われるような「3年間は給与泥棒」という状態だと、給与とノウハウを盗まれて付加価値を生み出せるようになる前に転職されてしまいます。
そして多人種が共存して社会を形作っているアメリカにおいては、それぞれの思想/常識に基づいた属人的な判断をさせない仕組みが必要です。そういう意味で性悪説(人は間違いを犯すもの)という想定の下あらゆるシステムが設計及び運用されているように感じます。
ERPやセールスフォース始め多くのITシステムが米国発というのもそういう背景からなのかもしれません。
(汎用性の高い)システムに人を合わせるということがしっかりと根付いていると感じます。
逆に日本では基礎能力が高い割には人件費が安い、加えて単一民族で思想の均一性も高いということもあり多額のITシステムに投資せずとも事業運営が出来てしまう部分があります。
また人材流動性が低いので、どうしても独自進化(ガラパゴス化)が起きやすい環境となります。そうなると社内や部門独自のルールができてしまい、汎用性の高いシステム(=柔軟性がない)の導入がさらに困難になるという悪循環も発生します。
専門性や経験を買われて転職しても、社内の独自ルールのためになかなかパフォーマンスを発揮できないということもあるのではないでしょうか。
トップダウン vs ボトムアップ
最後に意思決定に関してですが、日本は稟議書に代表されるようなボトムアップの意思決定が主流かと思います。ボトムから階層を上がっていくには承認を取っていくための準備が必要です。時には正攻法だけでは足りず、キーパーソンへの”根回し”も必要になってくるでしょう(むしろ根回しの方が重要だったりします)。
当然、上層部を納得させるには判断に足る情報や根拠が必要です。それを集めるだけでも相当な負担が発生します。たいていのプロジェクトの場合は上層部からの承認を得るまでに相当な時間がかかり、精神力も削られてしまうのではないでしょうか。
逆に欧米のトップダウンの場合は、既に意思決定がなされた状態で降りてくるので、準備期間を大幅に省くことが可能です。そしてそのエネルギーを実行や修正に向けることができます。
むしろ意思決定の段階では60-70%くらいの確度で、プロジェクトを進める中で100%に持って行くような進め方をしているように感じます。
リソースが限定的な状況で100%を目指さず、まずは方向性を定め、新たに見えてきた景色の中で走りながら考えるケースが多いように感じます。
アメリカで働いていて、ここの部分が日米間の最も大きな違いだと感じる場面が多々あります。アメリカのスピード感に慣れてしまうと日本の意思決定の遅さにイライラしてしまうこともあります。
最後に
私自身が日本とアメリカでの就労を経験し、感覚的に感じてきたこと考察してまいりましたが、雇用形態により一つの企業に勤めながら分業における役割が変更になってしまうこと、役割が変更するたびに属人的な業務に習得期間を要してしまうこと、習得をしても意思決定に多大な負担を要すること、それらが日本人の生産性が低いといわれる理由の一つとなっているのではないでしょうか。
しかしながら、ここまで読んで頂いた方はお気づきになったかもしれませんが、良し悪しは置いておいて、日本のビジネスパーソンの方が「分業」という意味合いにおいては、相当に厳しい環境に置かれているということはあると思います。
その中で鍛えられることにより、ビジネスパーソンとしての基礎能力が上がっているのではないでしょうか。それが冒頭のような日本を形作っている日本人という構成員レベルで見た時に、アメリカ人と比較して生産性が劣っているとは思えないという感覚につながっているように感じます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
