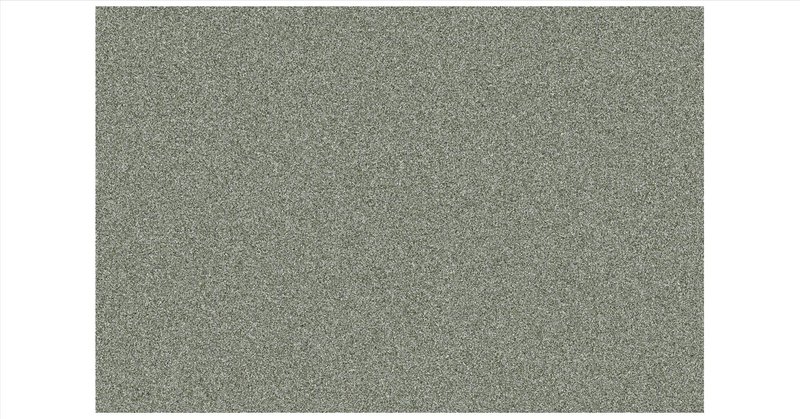
【絶対写真論】Chapter2 オリジナリティ
この章で着目したのは、オリジナル性である。
アートにおいて、いまやありとあらゆる表現はやりつくされている、という前提がある。それでもなお、アートにおいてオリジナリティ(独創性)が問われてはいるが、現代においてのオリジナリティとは同様の表現(方法)であったとしても、アーティストの「解釈」が独創的かどうかが問われている。
キー・パーソンはやはり、マルセル・デュシャンであろう。美術から芸術へとシフトさせたのはデュシャンの功績といっても過言ではない。
では、写真におけるオリジナリティとは何であろうか。
一般的な写真は撮りさえすれば、写ってしまう。フレーミングや絞り、シャッタースピードといった各種パラメータは、写真である画像を生成するために設定するためのものであり、どう切り取ったかは重要ではない。どう切り取ろうが、シャッターを押しさえすれば、「写真になる」のである。
たとえば、ある有名な写真家と全く同一なフレーミングで写真を撮影したとしても、その写真は同等の価値があるかというと、ないに等しい。
その写真的価値は、写されたイメージにあるのではなく、「誰が」「どのような意図」で生成されたのかによって決定付けられているのである。
そんな中、本章では昨年から賑わいをみせているNFTに着目した。NFTではこれまでの「作品」という物質的な価値から、画像データの非物質的なものに価値付けがなされたことが大きい。
ただし、現時点において問題点は多く残されているため、やや引いた位置から見るにとどめている。
では、写真である画像データの「オリジナル」とはなにかについて読み解くため、有機化学の「構造異性体」からみていった。
なお、本書の特徴として、写真の本質を読み解くうえで、科学的(主に数学的、物理学的)なアプローチによって展開している。これは、私が大学の学部時(約20年前)の専攻は地球科学(地学)であったが、趣味で物理学科や数学科の講義を受けていた点が大きい。おそらく、いや、確実に入る学科は見誤っていたのであろう、と今となっては思ってはいる。
化学式は同じであっても示性式は異なる
たとえば化学式 C2H6O で表されるものには、エタノール(C2H5OH)とジメチルエーテル(CH3OCH3)という性質が異なる 2 つの示性式が存在する
同じ成分から、異なる物質が生成される。写真もまた、各pixelにおいて同じ色情報であったとしても、その配置が異なることによって、表象するイメージは異なって「みえる」のである。
画像データにおいて求められているのは位置(配置)の「正確さ」であって、データそのものがオリジナルかどうかは、本質的な問題ではない。仮にデータがオリジナルであったとしても、複製されたデータであったとしても、最終的に「写真となる」ことに何ら変わりはない。
マスターデータが破損し、コピーデータが残っていたとしたら、その後はコピーデータがマスターデータへと昇格するのである。
NFT同様、デジタルデータそのものに物質的なオリジナル性を求めること自体が、そもそも間違いなのである。
フィルム写真からデジタル写真へと変わったとき、一般的にはフィルムからデジタルという記録媒体が変更されたのみで、写真となるシステムそのものは同様であるという見方がなされてきた。
これは、デジタル写真もまたカメラとレンズといった撮影システムに準じている点が大きい。しかし本質的にはデータの取り扱い方が全くの別物なのである。
いつまでもフィルム写真の延長線上としてデジタル写真を読み解こうと努めたところで、その本質的な違いはみえてはこない。
フィルム写真とデジタル写真は同じ化学式=写真であったとしても、示性式が異なる=性質の異なる写真が生成されているのである。
よろしければサポートお願いします!今後の制作活動費として利用させていただきます。
