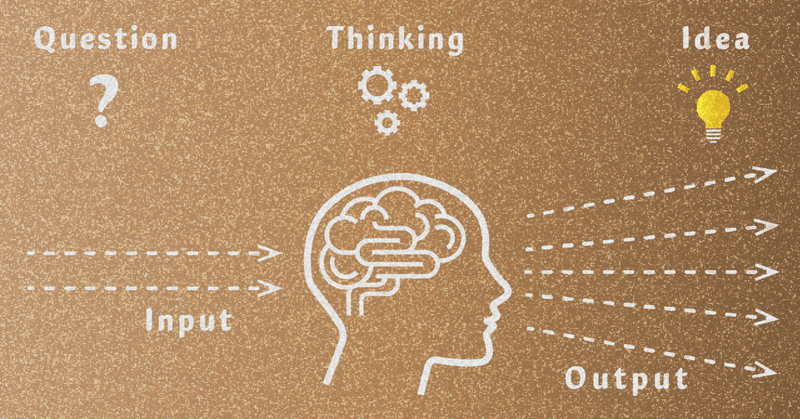
【コンセプチュアル・アート】他者への眼差し
現代美術研究家であるトニー・ゴドフリー著『コンセプチュアル・アート』木幡和枝訳、岩波書店、2001年。コンセプチュアル・アートの観念について果敢に挑んだ本書を読み解いていく。
内容が多岐に渡る(全448ページ!)ため、章立てごとに区切って進めていく。
かつて順を追って書いていたが、内容的にこちらを先に抑えないといけないため、第9章『他者への眼差し 写真を使うアーティストたち』を展開。この章で副題にもあるように、写真を用いた表現に触れている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メル・ボフナーが1970年に刊行した≪誤解(写真の理論)≫で提示したように、写真を用いたコンセプチュアル・アートの大半が、写真そのものではなく、写真と、写真の使い方について考えることであった。
写真は、その仕組みと使い方を分析するべき対象として存在していた。なぜなら、写真は必ずなんらかのイデオロギーが貼り付いた表象方法であるからである。
1960年代におけるコンセプチュアル・アートの核心は「言語的であると同時に、視覚的、その両方を成就すること」にあった。このことから、文字と写真の組み合わせこそがコンセプチュアル・アートの原点だ!という作品が増加傾向にあった。
しかしながら、ロバート・スミッソンが「写真は作品から精神を盗み取る」とランド・アートを巡る議論の中で述べているように、写真は写真は人を疎外する装置であるとの不安が広がっていた。この不安が表面化したのは、ヴェトナム戦争の報道カメラマンたちに浴びせられた質問である。
ロラン・バルトが指摘したように、写真は自己のそのままの描像であったことは一度もなく、それは常に「他者としての自己」の描像に過ぎなかったのだ。
これは、写真は自身の思いをそのまま表現したものではなく、世界をファインダーを通して四角のフレームに切り取る行為、すなわち客観的な自己表現であることだといえよう。
そもそも、コンセプチュアル・アートにおける写真の役割は、行為や記録として用いられていた。1970年に、ドナルド・カーシャンが述べた、「カメラは意見を持たない複写装置」であるという言葉の域を、このときのアーティストたちはまだ超越していなかった。
だが、次第に写真のもつイデオロギー的な意味合いを察知するアーティストたちがあらわれ、こうした考えが通用しなくなっていった。
ダグラス・ヒュプラー、ジェフ・ウォール、ジョン・ヒリヤードなどなど。社会的な空間→日常性への関心へと向けられることにつながっていく。
しかし、ヒリヤードのような美術家でも、「写真家」と呼ばれることには嫌悪感を示していた。理由は以下の通りである。
・最終的な発表物(=写真)よりも、写真を撮り発表するもとになった思考の方を重要視していたこと
・「芸術写真」と関連付けて埋め止められることを嫌ったこと
1点目はコンセプチュアル・アートそのものの理由によるところである。2点目については、当時芸術写真として扱われていたのが、エドワード・ウェストン、アンセル・アダムス、アンリ・カルティエ=ブレッソンといった、巨匠たちの作品が主流であったことに起因する。とりわけ、ブレッソンの「決定的瞬間」にみてとれるように、芸術写真は窃視=覗き見を連想させるものであったのだ。
この流れが次第に、「写真と社会という文脈で認識したうえでの、写真の使われ方の検証」へと移行していく。撮影することよりも、収集・分析することに重点が置かれるようになった。
たとえば、ダン・グレアムの≪アメリカのための家≫(1966-1967年)にみてとれる。1枚1枚のカラー写真には、彼自身の思いが込められた写真である。しかし、作品全体を通してみると、アイロニー(皮肉)が散りばめられているのだ。理由は以下の通り。
・カラー写真は一般的なスナップ写真や「ナショナル・ジオグラフィック」のようなものに用いられていたこと
・当時の芸術作品はほとんどすべてがモノクロ写真であったこと
そういった芸術写真から享受される現実との乖離、すなわち、純粋な「芸術的な」質をさらに浮き彫りにすることになる。
こうしてグレアムが取り上げられるようになったのは、ジェフ・ウォールが「コンセプチュアル・アートの自己言及性を脱して、写真の構築的でしかも批判的な活用へといたる道を確立するのに不可欠であった」と主張した、すなわちジェフ・ウォールの主張のための作品として写真が取り上げられたからにほかならない。
事実、この作品を制作した当時のグレアムは美術家としては認知されておらず、せいぜい詩人、もしくはたまに批評を書くライターとしてしか認知されていなかった。
初期のコンセプチュアル・アートの展覧会にも顔を連ね、重要な人物として挙げられるのが、ベルント&ヒラ・ベッヒャーである。タイポロジーで知られる彼らは、「ノイエ・ザハリヒカイト(新即物主義)」の系譜を自負し、アウグスト・ザンダーの影響を受けていた、、。
と、書いてはみたものの、私もかつて(今も若干?)ベッヒャー派を継承していると自称していたため、彼らの仕事についてはよく知っている。そのため、ここでは割愛。
1970年初期以降、コンセプチュアル・アートの多くが学術的な傾向を強めていくことになる。さらに、1973年にギャラリストのジョン・ギブソンが「ストーリー」という展覧会を開催して以降、「ナラティヴ・アート(物語美術)」という運動が起こったが、長続きはしなかった。
物語の傾向としてはクイズ的なものや逸話的なものが多く、テクストとイメージが自然に融合するようなものは極めて稀であったという。
フォルマリストによって美術界から排除されてきた物語性の流れがあったからこそ、「日常性への回帰」というところにつながっていったのであろう。
また、時代は広告写真全盛期である。広告によって過激に演出・構成された写真が、プロバカンダのように人の行動規範や趣味・思考といったものを印象操作するものとして、写真が使われていたのだ。
一方、1980年代に入ると、絵画の模倣や作品の大型化といった傾向があらわれる。1960年代のピューリタン的な批判姿勢から、快楽と美学の補強へと変貌している。
このことはロラン・バルトによる1961年と1980年の『カメラ・ルシダ』でも変化が見えてくる。
それまで写真と言葉が組み合わされ、日々消費される写真もまた、言葉につながり、写真が言葉のレッテルを貼られている、ということを念頭においた場合。ジェフ・ウォールやトーマス・シュトルートらは視覚に特権を与え、イメージからテクストを切り離しにかかった。
やや急に時代を飛び越えていった感はあるが、1960年代〜1980年代の写真における表現は大きく変わる頃であるので、別途詳細に整理しておきたいところではある。
つまるところ、写真を使うことでコンセプチュアル・アートが生んだ最大の効用は、自明のことを表明するのではなく、問いを発する機能を写真に与えたことだった。コンセプチュアル・アートが写真を変質させるわけではないが、写真というものに対する考え方は変わった。見る側の、見る行為に対する自覚を高めた。
アートとは、少し遅れてやってくる時代の代弁者、であるといってもいいかもしれない。
よろしければサポートお願いします!今後の制作活動費として利用させていただきます。
