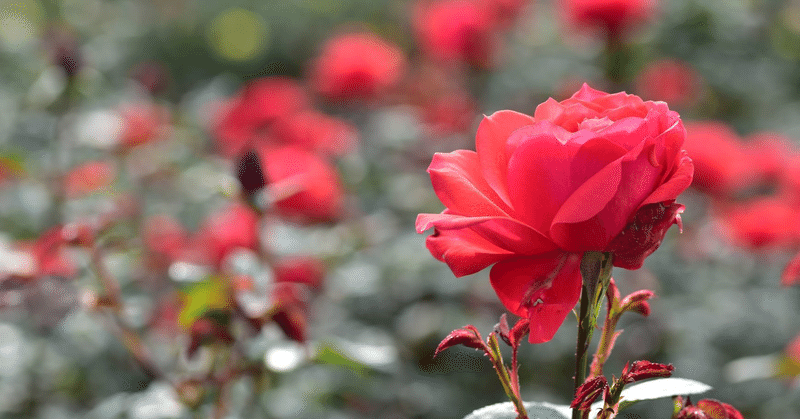
ミカちゃんとの思い出(上)--赤く染まったぬいぐるみ
わたしには小学2年生の頃、ミカちゃんという仲のいい女の子の友だちがいた。それまではいろんな子と仲良くしていた気がする。小学校で特別仲良くなったのは、ミカちゃんが初めてだった。
ミカちゃんは学校という集団の中では、あまり自己主張をしない子だった。口数もそんなに多いほうではなかった。けれど、二人きりになると饒舌だった。言葉遣いも少し荒々しくて、わたしには新鮮に映った。
子どもの頃のわたしは来るもの拒まず状態で、あまりどういう人物かわかっていなくても好意を向けられたら仲良くしていた。
自分の周りにいる人たちがみんなやさしかったから、それが当然だと思って疑わなかった。人のことを故意に傷つけたりすることが信じられない子どもだった。何の意味があってそんなことをするのか理解できないという感じだった。恵まれていたと思う。
だからミカちゃんがわたしに対して攻撃的なことを言っても、わたしはその意味がよくわかっていなかった。でもあの日から少しだけ異変を感じていた。
ある日、ミカちゃんがわたしの家に遊びにやってきた。
わたしはぬいぐるみが大好きな子どもで、数えきれないほどのぬいぐるみを持っていた。
わたしの枕元にはハムスターのぬいぐるみが置いてあった。それは、その当時のお気に入りの一つだった。
ミカちゃんはハムスターのぬいぐるみを見てこう言った。
「ねぇカモネちゃん、このハムスターのぬいぐるみ、ホラーの人形みたいにしたら面白いと思うよ」
ミカちゃんは赤の油性マジックでぬいぐるみを書き殴った。布のような素材でできていたハムスターのぬいぐるみは、あっという間に赤く染まっていた。
ミカちゃんは「こわいね」と言ってケラケラ笑っていた。わたしは体がフリーズしたみたいに動かなかった。そんなわたしを見てミカちゃんは、「カモネちゃんもやったらいいよ。たのしいよ」と言って、油性マジックを渡した。わたしは頭が真っ白だった。何も考えられず、言われるままにぬいぐるみを汚した。
ミカちゃんを玄関まで見送る。
ミカちゃんは「たのしかったね」と言って笑っていたけれど、わたしはいま自分がどんな顔をしているのかがわからなかった。
彼女がわたしの家から帰った後、わたしは一人、部屋で変わり果てたぬいぐるみを見つめてた。真っ赤に染まったハムスターのぬいぐるみが「どうしてこんなことするの、カモネちゃん」と言ってる気がして、悲しそうに見えた。
彼女を止めるどころかわたしも同調してぬいぐるみを汚した。ぬいぐるみにごめんなさいも言えない。わたしもミカちゃんと同じことをした。
あの時どうしてわたしは同調して「面白いかもしれないね」と言ったんだろう。何も面白くなかった。だが、後悔してもぬいぐるみが元通りになることはない。
わたしは後ろめたくて、ぬいぐるみの視線から逃れるように、ぬいぐるみをクローゼットの見えないところに隠した。
なんでミカちゃんがわたしにこんなことをさせたのか、わたしは理解できないでいた。
この頃から胸がジクジクと痛むようになっていた。
つづく(1/3)
この話を書いていたら涙がポロポロと溢れてきて、当時、心の奥底にしまっていたかなしい気持ちがよみがえってくるようだった。
昨日の記事でも書いたが、小学校低学年の頃は言葉を知らなくて自分の感情を表現することができない子どもだった。知っている言葉を当てはめて伝えることはしなかった(それができたらきっと楽だったのにね)。
書くなかで、この話を親にしたことがないことにも気がついた。
ミカちゃんの話はあと2回ほど投稿する予定です。
よければまた読んでください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
