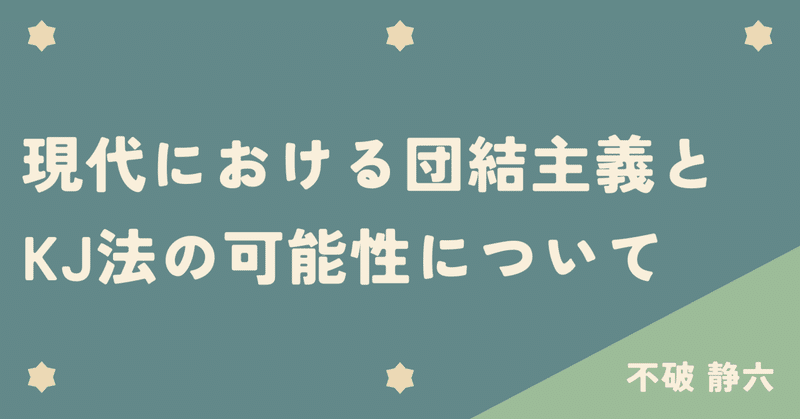
現代における団結主義とKJ法の可能性について/不破静六
頭山統一『筑前玄洋社』、千坂恭二『思想としてのファシズム』『歴史からの黙示』を参考に、現代の団結主義とKJ法が持つ可能性について論じる。
(1) 衆知の集め方
(1)-1. 東洋君子としての政治を中国で作り上げようと無償で行った荒尾精の試みは結局、帝国日本の侵略を助長し、理想は現実の野心に呑み込まれてしまった。
荒尾 精(あらお せい、安政6年6月25日(1859年7月24日) - 1896年(明治29年)10月30日)は、日本の陸軍軍人、日清貿易研究所の設立者。日清戦争の最中、「対清意見」「対清弁妄」を著し、清国に対する領土割譲要求に反対した。日中提携によるアジア保全を唱えた明治の先覚者である。
荒尾精たちの楽善堂は、全地球を救う志のもと、中国全土の情況調査に無償であたった。荒尾精の行動は、道徳的なオブラートで包んであったとしても、結果として日清戦争における帝国日本の侵略を助けた。荒尾精の狙いは、西欧列強の野蛮な侵略に対して、東洋君子としての政治を中国にて作り上げることであった。
こうした、荒尾精の試みは、東洋の伝統的な君子政治を復活させるという高貴な目的を持っていた。彼の行動は、真に道徳的であり、結果的に帝国日本の政策に利用されたとしても、その意図は尊重されるべきだ。偉大な理想は常に困難に直面するものだ。しかし、その理想が現実の野心に呑み込まれたことを無視するわけにはいかない。彼の行動は、結局、日本の侵略を助長する結果になった。道徳的な意図があっても、それが現実にどれだけ害をもたらしたかを見過ごしてはいけない。荒尾精の理想も、結局は権力と支配の裏に隠された偽善に過ぎなかったのであろうか。彼の行動は、名ばかりの道徳で覆われた侵略の一部であり、無償で行ったという美談も、実際には帝国主義の手先に過ぎなかったのか。理想はいつも権力側の手段に収斂していくに過ぎないのであろうか。
(1)-2. 名もなき人々の純粋な思いを大切にした玄洋社は、個人ではなく家族単位の選挙権を主張し、日本土着の民主主義思想を訴えた。
玄洋社の源流ともなった地方自治組織「筑前共愛会」は、「家」ごとに参政権を与える選挙制度を明治の初め頃に起案した。
家族成員の意見をまとめて政治意見を表明すべき主体として「家」ごとに選挙権を与える日本土着の民主主義思想を訴えた。この考えは、時代が下って大正デモクラシー期において、個人の参政権を求める運動に反対し戸主に参政権を与えるべきだとする「純正普選運動」につながっていった。

玄洋社の思想は、日本の伝統的な家族制度を尊重し、個人主義に対抗するものだ。家族全体の意見を一つにまとめ、家を単位とした参政権を主張することは、家族の絆を強め、社会全体の安定をもたらす。伝統を守ることが、未来を築く基盤になる。しかしその考え方は、個人の自由と権利を無視するものでもある。家族単位での選挙権は、特に女性や若者の声を抑圧する結果になる。大正デモクラシーが求めた個人の参政権こそが、真の民主主義を実現するために必要であった。ただし家族単位の選挙権というのは、結局は家父長制の強化に他ならない。個人の声を無視し、家という名の下に抑圧を正当化する構図が透けて見える。玄洋社の主張も、名もなき人々の純粋な思いを利用して権力を集中させるための手段に過ぎないとも言える。家族の絆という美名の裏に隠された支配と抑圧の実態を直視する必要がある。
この議論を通じて見えてくるのは、理想と現実の間にある複雑な関係だ。荒尾精の行動が持つ道徳的な意図と、その結果としての侵略行為の間には深い矛盾が存在する。理想が現実の中でどのように形を変え、権力の手段として利用されるかを見逃してはならない。同様に、玄洋社の家族を重視する思想も一見すると美しいが、実際には個人の自由と権利を抑圧する結果を招く可能性もある。このような矛盾を直視し、理想がどのように現実に影響を与えるかを常に問い続けることが重要だ。
結局、私たちが目指すべきは、理想と現実のバランスを見極め、個人の自由と権利を認めつつも、助け合いを尊重する社会だ。個人的権利の素晴らしさに心を奪われることも大切だが、それが家族の絆や文化の尊さを侵害するものであってはならない。理想が現実の中でどのように形を変え、どのように利用されるかを常に見極めることで、より公正で自由な社会を築くことができるだろう。現代日本の低迷する選挙投票率を省みると、多くの人々が現行の選挙制度に何の希望も見出せていないのではないかと推測できる。衆知を集め決断するための新しい方法を検討すべきだ。その一つの手段として、KJ法は一顧に値するだろう。創案者の川喜田二郎が、学生運動へのアンサーとして東工大の職を辞して、その普及のために「移動大学」を始め、そのことが現在に至るKJ法の源流を形作った経緯がある。当時の全共闘運動が、プレファシズム的だと評されることを示し合わせると、団結主義とKJ法とのつながりに思いを馳せずにいられない。
(2) 血肉の通った革命
左翼も右翼も悠久の歴史に自らの存在意義を見出すことができずに、近現代の栄光に縋るだけで、現実的な革命を実現できないまま力を失っている。
左翼にとっての啓蒙突破が労働運動だとすると、右翼にとってのそれは軍隊である。
戦前の左翼にとって啓蒙を突破するものは労働運動だったとすれば、右翼においては軍隊だろう。労働運動における労働者と、軍隊における兵士には共通項があり、それはともすれば同じ人物の違った現れ方であるといえる。[p.75]
たとえば一九二〇年代から三〇年代にかけてのドイツにおける左翼の「労働者・兵士評議会」や、右翼革命派のエルンスト・ユンガーがいうような「兵士=労働者」論などは、労働者と兵士の関係の運動的、思想的な消息を示していよう。[p.75]
ナショナル・ボルシェヴィキ(民族派ボルシェヴィキ)のエルンスト・ニーキッシュと交流のあったユンガーが注目していたボルシェヴィキ政権初期のトロツキーの「労働軍」構想も数えられよう。[p.75]
戦後の右翼も左翼も、自らの存在意義を見失い、無意味な啓蒙活動に終始して具体的な革命の彼方へ飛翔できないでいる。
世間がイメージする右翼といえば街宣車による情宣活動があるが、あれは何をしているのだろうか。その時々により「日教組打倒」とか「北方領土奪還」その他、様々なテーマがあるが、やっていることは要するに啓蒙活動である。[p.75]
つまり真実はこうなのだと、ここのテーマに応じて右翼が真実であると認識し確信していることを世間に啓蒙(告知)しているのだ。[p.75]
むろん啓蒙は重要な活動であり、すべての活動は啓蒙から始まる。しかし、啓蒙には固有の限界がある。それは正しさや真実しか伝えないため、現実からすれば抽象の域を越えず、しかも自らの正しさや真実に自足しているため、最悪の場合は空疎な正義のお題目にしかならないということだ。[p.75]
私は戦後の右翼は総じてこのような限界を持っており、それは今なお克服されていないと考えている。かりに右翼の一部が実力行動に走ったとしても、それはかつてエリコ・マラテスタなどをリーダーとしたイタリアのアナキストが「行為による啓蒙」として爆弾闘争やテロをやったように、やはり啓蒙の域を出ないだろう。[p.75]
戦前の右翼も多くは啓蒙の域を出ることはなく、それは左翼とて例外ではなかった。[p.75]
戦前の右翼は、軍隊に啓蒙レベルを超えた現実に対する活動の組織基盤を持ち、それは左翼の労働運動に対応するものだった。ところがそれに対応するものが戦後の右翼にはない。[p.76]
むろん似たような状況は左翼にもある。左翼の労働運動は社民的な体制内の既得権維持の運動と化し、現代の「ルンペン・プロレタリアート」とされる昨今の失業や格差問題を運動化する力量を喪失してしまっている。かくして現在においては変革の希望はなく、現状肯定を前提とした様々なベーシックインカム論ばかりが蔓延するようになってしまった。[p.76]
右翼は保守の傭兵に、左翼は社民の別働隊と化しているのが現在ならば、もはや左翼や右翼などは用済みだろう。[p.76]
社会弱者の側に立つことが反体制的な意義を持たない現在、革命の根拠は歴史に求めるしかなく、それができるのはもはや右翼しかいない
かつて革命の正しさの根拠は虐げられた民衆の側に立つところに求められた。しかし、虐げられた民衆という社会的な場面に正しさの根拠が求められなくなった場合、革命の根拠はどこに求められるのか。[p.77]
それは社会に対する歴史の場であり、革命の根拠は歴史に求める以外にはないだろう。この時、革命は社会的な正義から歴史的正統性へと変容するが、革命という問題について右翼に出番があるのはここである。[p.77]
すなわち現在、革命を肯定することが出来るのは右翼以外にはないとさえいえるのである。誤解を恐れずにいえば、極左よりもさらに左に位置する右翼のみが革命を肯定できるのであり、また右翼が保守に埋没することなく右翼自身の可能性を求めるならば「右からの革命」にしかないといえなくもないだろう。[p.77]
右翼の思想は、我々の国の悠久の歴史と伝統に根ざしている。近現代の栄光に縋ることなく、我々は歴史の深みから力を引き出し、国家と社会の安定を図る。軍隊や国家への忠誠は、我々の存在意義を強固にするものであり、現実的な革命の唯一の道だ。一方で、右翼が歴史に根拠を求めるのは、現実的な解決策を見つけられない面もある。労働運動や社会運動こそが、現実の問題解決に直結する手段であり、啓蒙活動もその一環だ。
近現代の栄光に縋るだけでは、真の社会変革は実現しない。右翼も左翼も、結局は現実の問題から目を逸らしているだけだ。右翼は延々とした形ばかりのお題目に逃げ込み、左翼は無意味な啓蒙活動に終始する。現実の社会は、経済格差や環境問題、労働者の権利など、具体的な問題に満ちている。革命を言葉遊びに終わらせてはいけない。現実的、具体的な行動を取らなければ、何も変わらない。その手段が左翼にとっては労働運動であり、右翼にとっては軍隊だ。日本史の根本に根付いた軍隊が革命のために求められる。
(3) 絶望からの再生
矛盾を超えた運命的共感や自己超越を指向することで、虚無と混乱の中から新たな宇宙的社会構造が現出する。
平等と自由を犠牲にし、内在的批判を試みた結果、ファシズムと極左の矛盾した革命的な共感が生まれる。
あえて図式化して言えば、ファシズムは一体なんなんだと言えば、ファシズムは自由はないんです。平等もないです。その変わり適度に自由があり適度に平等がある。[p.237]
ファシズムは自由・平等・博愛の博愛なんです。友愛でもいいです。[p.237]
ファシズムは友達を大事にしましょうという思想です。友達が困っていたら介抱してあげるということ、とにかく飯でも食えよと。お互い金を出し合うお助け講の世界なんです。[p.237]
千坂恭二2015『思想としてのファシズム——「大東亜戦争」と1968』彩流社、p.237
生と死の矛盾を抱えるアナキズムは、自己否定と現実からの断絶を通じて虚無へと突き進む。
ネチャーエフはいかなる革命論を持っていたのか。私たちは未だその全貌を知ることはできぬが、「ネチャーエフ・プラン」と呼ばれたものによるならば、「農民の不安を組織的に煽り立てて、革命の口火を切る」というものであった。[p.62]
このナロードニキと全く背反せる思想の中にネチャーエフの革命論は凝縮されているといえる。[p.62]
革命家は大衆と断絶することなくしては、本質的に結合しえないのだ。[p.62]
革命家は意識的に革命を目ざし、その意味を体現せしめる存在として、革命の内容たる大衆とは現実レベルで交わることは不可能なのである。[p.62]
しかも革命の意味は、存在論的に<神>を否定せるものにほかならず、したがって、<神>が万能であるごとく、革命の意味もまた、すなわちその体現者たる革命家もまた万能であり、「すべてが許されている」のでなければならない。[pp.62-63]
ネチャーエフは人間の背理を喝破することにより、革命を絶対的真理にまで高めたのである。[p.66]
自ら「革命家はあらかじめ死刑を宣告された存在である」と、その人間的存在を否定し、革命の絶対性の化身とせしむることにより、彼はマキャベリズムの最たる戦術を唱え、かつ部分的に実行したにもかかわらず、断じてマキャベリストの一員ではなかった。[p.66]
すでに述べた<目的>と<手段>に関していえば、ネチャーエフは一つの明確な解答を私たちに与えているのである。すなわち<神>に叛逆せるもう一方の絶対者——<神-人間>の関係を超越せる存在者=超人——は、神瞰図的視点を有するがゆえに、絶対性の勝利のため「目的のために手段は選ばぬ」ものであっても、それは人間的視点においては「目的と手段の一致」に合致しているということである。[p.66]
人間は人間を超えねば、人間たりえぬのである。[p.67]
かかる背理をネチャーエフは鋭くも嗅ぎとったに違いない。しかもそれが人間を超えて存するがゆえに、個はかかる人間の背理を対自的に凝視する者と、それを即自的に埋める者とに分かたれる。[p.67]
この背理の対自-即自の回路の中にこそ、私はこれまでの革命における<政治>と<実存>の分裂による革命の悲劇を止揚する原基が存すると考える。[p.67]
セルゲイ・ゲンナジエヴィチ・ネチャーエフ(ロシア語: Сергей Геннадиевич Нечаев, ラテン文字転写: Sergei Gennadievich Nechaev, 1847年10月2日 - 1882年11月21日)は、ロシアの革命家。ロシアのニヒリズム運動のオルガナイザー。
非革命の時期におけるとある犯罪が革命かどうかは、革命それ自身が決定する。
革命は決してヘーゲルやマルクスのように史的決定論ではありえず、(史的決定論は、広義の<革命=回転>をその内容とするのであり、歴史の内に存在する革命〔未だ革命としては具現化されていない〕は、なべて、歴史の恣意性にゆだねられてしまう)、あくまでも革命決定論でなければならない。[p.228]
何故なら革命は可能性として存在するのではなく、必然性として、しかも歴史的必然性ではなくして革命自身の必然性として存在するからである。[p.229]
すなわち、それは<非革命>の時間を超越しつつ、<非革命>の時間の内に存在するのであり、革命の時間においては、それはまさに革命として存在する。[p.229]
しかし革命はまだ、自らの時間を、この歴史-世界の中に獲得し、具現化していない。だからして、革命は、<非革命>の時間にある、この歴史-世界においては、犯罪としてしか現れないのである。[p.229]
犯罪が、革命的なのではなくして、革命が犯罪としてしか存在しえないのだ。[p.229]
ファシズムのような強い国家主義的思想は、混乱と虚無の中で新たな秩序を提供する手段だ。自己超越を目指すことで、個人は国家と一体となり、強固な社会構造を形成することができる。現代の混沌とした社会において、ファシズムは一つの救いの道となりうる。しかし、これは危険な考え方でもある。ファシズムは平等と自由を犠牲にすることでしか成り立たないし、その過程で多くの犠牲者を生むことになる。共感や自己超越は美しい言葉だが、それを利用して抑圧と支配を正当化するのは誤りだ。私たちは多様性と個人の自由を尊重すべきである。さらに、ファシズムやアナキズムの議論にしても、結局は現実から遊離した理想のお話でしかない。ファシズムは一部の権力者が自分たちの利益を守るために使う道具でしかない。平等や自由を犠牲にしたその先にあるのは、抑圧と暴力の連鎖だ。
私の心はこの議論の中で揺れ動いている。強固な国家のもとで、社会の秩序が保たれることには魅力がある。しかし、過去の歴史が教えてくれるのは、ファシズムがもたらすのは必ずしも安定とは限らない、ということだ。未来の技術や都市の夢を見ることで、現実の辛さから一時的に逃れることもできる。しかし、現実を直視しなければならないのも確かだ。私たちの社会が直面している問題は、決して簡単には解決しない。
重要なのは、ファシズムやアナキズムという極端な思想に頼るのではなく、もっと現実的で具体的な解決策を見つけるべきだ、というのでは決して終われないということだ。結局のところ、人間は人間を超えねば、人間たりえぬのである[千坂2018,p.67]。そして、ファシズムは友達を大事にしようという思想である。友達が困っていたら介抱してあげる、飯を食わせてあげる。そうしたお助け講の世界だ。[千坂2015,p.237]
技術の進化や未来の都市の理想を語ることは悪くないが、その一方で現実の問題に対する解決策を見つける努力を怠ってはいけない。ファシズムのような先鋭な思想を実際の行動で示し、博愛の精神を尊重しながら、持続可能な社会を築くために、私たち一人ひとりが何をすべきなのか。それを考え続けることが大切である。
(4) スパゲッティと超国家
革命を持続するには、スパゲティを食べるローマの大衆の風景に超国家の風景を見出す必要がある
私たちは<革命空間>を<国家性時間>の中には求めることができない。それは<国家性時間>の外に、<国家性時間>を超えたところにしか存在しないのだ。[p.219]
すなわち歴史を、その時間質において超越した地点にしか存在しないのである。[p.219]
しかし私はニーチェのように楽観主義者ではない。ニーチェは、たんに歴史の時間質でしかない存在である<国家性時間>の歴史と、歴史一般をとり違えたのであり、いわばここにニーチェの<超人>が瞬時に意志により実現されえても、それを持続させうることができない所以がある。[p.219]
私たちは持続させねばならないのだ。したがってそれは、たんに意志のみで解決されうる問題ではないのである。[p.219]
私たちは<国家性時間>の真っただ中で、何の変哲もない風景をながめつつ、そこで時間質の逆転をはからねばならぬのだ。国家の風景のなかに、超国家の風景をみるのである。[p.219]
『フェリーニのローマ』には国家がないのだ。それは場末の劇場、そして第二次世界大戦の初めてのローマ空襲、そしてファシストの青年団のフィルムなどで、ほんのわずかに顔をのぞかせるにすぎない。[p.220]
しかし逆に考えてみるならば、野卑でバイタリティに満ち、スパゲティをもりもり食べるローマの大衆そのもののなかに、国家をみるならば構図は逆転してしまう。[p.220]
そして必要なのは、この構図の逆転ではないだろうか。[p.220]
ファシズムのような強い国家主義的思想は、混乱と虚無の中で新たな秩序を提供する手段だ。スパゲティを食べるローマの大衆が国家の一部となり、共通の目標を持つことで、持続可能な革命が可能となる。ファシズムは国家の力を結集し、社会の安定を図るための道具である。でも、それは個人の自由と多様性を犠牲にするだけではない。ローマの大衆がスパゲティを楽しむ風景は、個々の自由な選択の結果であって、国家の管理下に置かれるべきではない。確かにそうだ。ファシズムが持続可能な革命をもたらすというのは幻想で、その実態は権力者による労働者の搾取と抑圧の連鎖だ、というのも理解できる。しかし、そこに友愛の精神が見出される時、国家主義的思想によって真の社会正義を実現する可能性が開かれるのだ。
このやり取りを通じて感じるのは、私たちがどんなに異なる視点を持っていても、共通の経験や文化が人々を結びつける力を持っているということだ。強権的な政治というのは、一見秩序を提供するように見えるかもしれないが、それだけでは個々の自由と多様性を犠牲にする危険性を孕んでいる。例えばスパゲティを通じてイタリアの文化を享受することは、私たちが個々の選択を尊重し、楽しむことの重要性を示している。ファシズムや強い国家主義的思想がもたらすものは、結局のところ、民衆の助け合いの精神を高揚させることに他ならない。私たちが求めるべきは、個々の自由と多様性を尊重し、共に成長し、真の社会正義を実現することだ。消費社会の一部であるスパゲティを楽しむことすら、私たちの選択の自由を象徴していると感じる。だからこそ、私たちは真のファシズム思想によって異なる視点を受け入れ、共に議論し、より良い未来を創造していくべきなのだ。
総括
確かに、荒尾精の試みは確かに東洋の君子政治を復活させる高貴な目的を持っていた。しかし、その理想が現実の野心に呑み込まれた結果、日本の侵略が助長されたのだということも否定できない。道徳的な意図があっても、その結果がどれだけの害をもたらしたかを見過ごすわけにはいかない。それは、理想と現実の間にある複雑な関係を暗示している。
理想はしばしば権力の手段として利用されるものであり、現実を直視する必要があるのだ。玄洋社の家族の絆を重視する思想は、確かに個人の自由と権利を抑圧する懸念がある。家族単位の選挙権が家父長制を強化し、真の民主主義にはならないとも言える。個人の声を無視することは支配と抑圧を正当化する手段に過ぎないのだ。一方、現実を直視して理想と現実のバランスを見極め、個人の自由と権利を尊重する社会を築くために、具体的な行動が求められている。下降線をたどる選挙の投票率を省みると、衆知を集めて皆で決断するためのオルタナティブな手段を検討すべきである。60年代の学生運動と問題意識を共にするKJ法は、現在においても参照すべき技法と言える。
私たちが目指すべきは、多様な視点を持ち、バランスを保ちながら前に進むことだ。技術の進化や未来の都市の夢を見ることは悪くないが、現実の問題に対する解決策を見つける努力を怠ってはいけない。ファシズムを単なる極端な思想に終わらせることなく、博愛精神を尊重しながら、多様性に満ちた持続可能な社会を築くために、私たち一人ひとりが何をすべきなのかを考え続けることが大切だ。
真のファシズム思想には、異なる視点を持ちながらも、共通の経験や文化によって人々を結びつける力がある。私たちは自由と多様性を尊重し、真の社会正義を追求すべきだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
