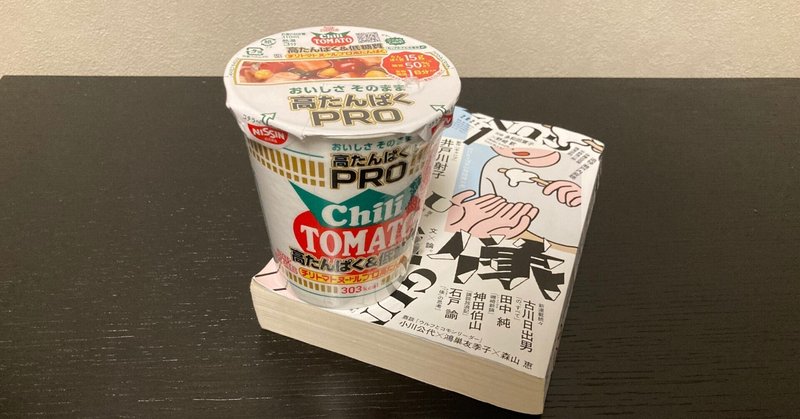
【読書録】高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』
今回読んだ作品:高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』
作品を食べ物に例えると”ふき味噌”

ストーリー:2
芦川という人物と通して揺れ動く人間関係は、読んでいてハラハラさせられる。いつか人間関係が崩壊することを匂わせる不穏なストーリー展開は、とても惹きつけられた。
描写・演出:3
タイトルからも推測できる通り、この作品は食べ物・食事の描写が定期的に登場する。それらの描写は私の五感を刺激し、読み手を飽きさせない。
キャラクター:3
二谷という人物のクズ加減が良かった。彼女のことを嫌いな女性と寝て、陰で彼女の悪口を言う。そのような言動をとりながらも、自分自身は危険に晒されないよう立ち回る。しかし、そのような二谷的側面は、私たちが誰しも少しばかり持ち合わせているのではないかと感じた。
世界観:2
舞台は、現代日本の首都圏にある営業所。作品から読み取れる営業所内の雰囲気は、私の日常生活の近くにある風景なのではないかと思わされた。
思想:1
現代人が抱えがちなコミュニケーションに関する悩み。それを作者が意図的に発信しようとしていたのかはわからない。しかし、少なくとも私はこの作品を通して、自分自身の認識や行動を見直すきっかけを持つことができた。
平均:2.4
<あらすじ(ネタバレ含む)>
この作品は、二人の一人称が交互に繰り返されることで進行する。一人は男性の二谷、もう一人は女性の押尾。二人は同じ会社、同じ事業所に務めており、押尾は二谷のことが好きだ。しかし、二谷は、同じく同僚の芦川という女性と付き合っており、押尾は二谷のことを嫌っている。つまり、この作品は、三人の三角関係を軸として物語が進行する。
押尾が芦川のことを嫌っている理由は、二谷と付き合っているからというだけではない。根本的には、芦川が事業所内で「弱い人間」として守られていることにも起因する。ここにおける「弱い人間」とは、身体的弱さと精神的弱さの両方を指す。芦川は時々頭痛を訴え、会社を早い時間で退社する。そして、その尻拭いをしているのは自分だと押尾は主張する。芦川は、高圧的に接してくる取引先が苦手だ。そして、その尻拭いをしているのは自分だと押尾は主張する。つまり、押尾は芦川と比べて、自分が会社の中で大切にされていないと感じている。認められていないと感じている。だから、芦川のことを妬み、愚痴を吐いたり嫌がらせをするようになる。
そして、その愚痴を聞くのが二谷だ。押尾は二谷が芦川の交際相手であることを知ってからも、二谷に向けて芦川の愚痴を言い続ける。そのような押尾の行動を二谷が受け入れるのは、二谷も押尾と同じように芦川に対して不満があり、その思いを共有したいからである。二谷は芦川のことが好きだ。しかし、二谷と芦川の生き方にはいくつか相違があり、それが二谷の抱く不満の原因となっている。芦川の生き方は丁寧である。料理は毎回しっかりと作り、それを二谷に対して振る舞う。また、趣味はケーキ作りであり、これは二谷だけでなく会社の同僚たちにも振る舞う。一方で二谷は、そのような芦川の厚意をしんどく思っている。芦川が作った料理を食べた後、芦川から隠れるようにカップラーメンを食べる。芦川からもらったケーキをぐしゃぐしゃにして会社のゴミ箱に捨てるなど、二谷は芦川の行為に対してある種「反抗」と捉えられる行動をとっている。
やがて、押尾は会社を辞めることとなる。押尾が芦川に対して行っていた嫌がらせが発覚したためだ。ただ、それが露見するきっかけとなった嫌がらせを行っていたのは、二谷だった。押尾は自分の罪と、二谷の罪を肩代わりする形で会社を退職する。そして、二谷は芦川と結婚する流れを匂わせながら、物語は終わる。
<感想>
芦川は、自分が周りにどう思われているのかということに対して、おそらく客観的な認識ができていない。なぜなら、恋人である二谷から自分が嫌がらせをされていることにすら気づいていないためである。そして、芦川の言動を内心よく思っていないのは、二谷と押尾だけではない。なぜなら、二谷と押尾以外の人間が、芦川の作ったカップケーキを食べずに捨てていたためである(それも定期的に)。つまり、二谷と押尾以外の人間も、芦川のことを内心よく思っていない可能性が高いのである。しかし、会社の中で芦川のことを悪くいう人はいない。なぜなら、「芦川のような弱い人間は守らなければならない。尊重しなければならない」という共通認識が事業所内で一般化しており、それに背くような考え方を社内で口にすることは許されないためである。そして、それを口にしたり行動で表す人間(押尾)が現れた時、人々はそれを弾劾する。
「多種多様な人間を尊重する。そのような理想や常識だけが人々の中に先行し、彼らの本心はそれに追いついていない」このような人間関係の形式は、現代日本においてはとても一般的なものなのだろうと私は思った。だからこそ、この作品は多くの人に支持されているのかもしれない。少なくとも、私はとても共感することができた。
理想が先行しすぎた常識が組織の中で蔓延った時、私たちの取れる行動は大きく二つに分類される。一つはそのコミュニティを抜けること。作中において、押尾がとった行動である。もう一つは、その矛盾の抱えながら生き続けること。作中において、二谷が取った行動である。もちろん、「組織内の認識を一新(あるいは破壊)する」という行動も考えられるが、それは現実的でないし、作中でも語られていない。そして、私たちが二谷や押尾のような状況に立たされた時、たいていの場合は二谷のような行動をとる(と私は思う)。作中でも、事業所内の大半は二谷と同じ行動をとっている。ケーキを食べずに捨てた真犯人も、おそらく会社を辞めてはいない。
誰も芦川と本音で向き合おうとしないことを、あるいは芦川が周りにどう思われているのか客観的に理解してないことを、批判することは簡単だろう。この本を読んでいる最中、私は作中に登場する人物全員を批判したくてしょうがなかった。しかし、自分を振り返ってみれば、自分も登場人物たちと大して変わらないことに気づく。(おそらく)自分には、芦川のように無頓着なところもあるし、二谷や押尾のように正面切って人と向き合わないこともある。この作品は自分を内省するきっかけを、私に与えてくれたように感じる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
