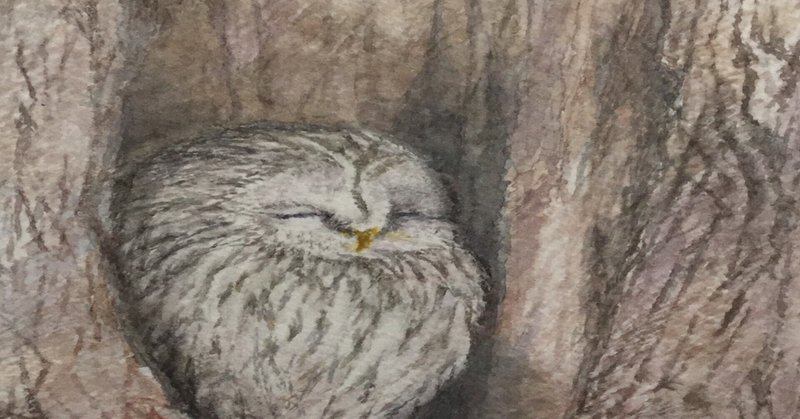
幸田露伴・支那(中国)の話「仙人呂洞賓①」
仙人呂洞賓
仙人は歌って云う、
名声と富と 二ツとも何の価値ある。
首(こうべ)を廻らせて山に帰れば、味わい転(うたた)甘し。
世間のものを数えるに 心に適(かな)うものなし。
誰が更に 道に適おう。
寸に到らずして尺を談じ 一もなお明らめ難きに強いて三を説かんや。
経巻と瓢箪と 並びに杖と 担(にな)いて入らん 仙人の地に。
まことに一も分からないのに三を説くのは醜(みにくい)と云うべきで、首を廻らせて山に帰るも情無しとは云えない。仙人歌ってまた云う、
中(ちゅう)を守り学を絶って 正に奥(おう)を知らん、
一を抱いて言無くして 始めて佳(か)を見ん。
成程、成程。学問をするのは知識を深める為である。であるのに、多く俗智を蓄える人を観れば、これまた妄想をほしいままにするだけである。言(ことば)を発するのは意(おもい)を伝える為である。であるのに、妄りに我意を述べる者を観れば、これまたいたずらに煩わしい問題を生むだけである。中正を守れば役立たなくても他を煩わさず、一を堅持すれば節操によって自己を全(まっとう)できる。狂言綺語は讃仏乗(さんぶつじょう・仏の教えをたたえる)の縁(えにし)であると詩人は云うが、狂言も不要、綺語も不要、春の日には鳥の声が花の紅(くれない)に、秋の夜には鹿の音が月に白く、讃仏乗は随所に有り随時に有る。雕虫篆刻(ちょうちゅうてんこく)は道の華(はな)だと仙人も吟じたが、雕虫も役には立たず篆刻も役に立たない。司馬相如の文才でも実際の山の色さえ写せず、杜甫の詩の力をしても結局は水の容(すがた)さえ現わし難くて苦しむ。道の華はむしろ寒暑の往来や季節の変遷にこそある。自然は何を語る、面白いのは自然である、大いなるは自然である。人よ反省せよ、拙(つたな)いものは人である、小さいものは人である、花も折るが善い、硯も抛(なげう)つが善い。これゆえに仙人は歌ってまた云う、
緑酒に酔って眠る 日月閑(のどか)に、
白い水草に風は定まって 江湖に釣る。
長(とこし)しえに気度を将(も)って 天道に随い、
言詞を取って 世徒に問わず。
言葉を用いて世間の人に問いて何の益があろう、気度を将って天道に随えば妙趣があるだけである。しかしながら、旧債を未だ償(つぐな)われなければ人の求めも断り難く、宿業が猶残れば自分のことも完全には出来ず、努めて筆を執って妄りに白紙に向う。白紙に臨んで何の字を書こうか、筆を執って誰の伝を綴ろうか。アアまた煩わしいではないか。仙人の詩の句に、
四海皆忙(せわ)しく 幾個か閑ならむ、
詩人口内に 塵縁を説く。
知る 君が道有って山上に来(きた)るを、
何ぞ似かむ 無名にして世間に住するに。
という。忙しく落ち着かない世間に在って、ゴタゴタと煩わしい関係を説くのも、また恥ずかしい。早く旧債を果して宿業を了(お)える他(ほか)は無い。筆が禿げてもまだ足りず、紙は猶終わりに至らず、墨汁一点の下(もと)、思いつくまま筆をやたらと走らす。
謡曲は面白いものである。その中でも一見して佳作とするものも少なくはない。絢爛の色彩や琴や楽器の音の響きは、時に幽玄の趣きを含んで忠厚の志(こころざし)を刺激する。衰世の時代に出たものではあるが棄て去ることはできない。時に観るに足りないものもあるが、深く咎めるほどのことも無い。謡曲の中に漢土(中国)のことを伝えるもの、ただ五六に止まらない。「昭君」「鐘馗」「東方朔」「慈童」「合浦」「玄宗」「項羽」「三笑」「楊貴妃」「西王母」「咸陽宮」「白楽天」「張良」「邯鄲」等がある。このうち「白楽天」は、白楽天と我が国の漁翁との詩歌の問答を叙述する。勿論その事は実際に在った事では無く、作者の作った創作である。「張良」は、張良が下邳(かひ)の地で黄石公に会ったことを叙述する。張良が翁のために沓(くつ)を取ろうとすると、大蛇が出て来て張良をおびやかす。張良は恐れずに大蛇を叱ると記す。この事は「史記」や「漢書」には載っていない。それでは妄作か俗伝か、その根拠はハッキリしない。しかしながら、足利末期から徳川初期にかけての俗書に張良を樊噲(はんかい)同様の勇猛な士とするものがあるのは、謡曲の「張良」にもとづくように、謡曲の叙述する漢土によって、漢土に対する当時の人の知識のほどを推知することができる。
同じ謡曲の「邯鄲」は元清(もときよ)の作という。盧生(ろせい)の一夢の事を叙述しているが理解し難いところが多い。曲に云う、
「浮世の旅に迷い来て、夢路をいつと定めけん。これは蜀の国のかたわらに、盧生といえる者なり、われ人間でありながら、仏道をも願わず、ただ茫然と明かし暮らすばかりなり。まことや楚国のヨウヒ山に、貴き智識(賢者)の居られるよし承(うけたまわ)り候ほどに、身の一大事(人生問題)をも尋ねばやと思い、ただヨウヒ山へと急ぎ候。」
これを記の始めとして、盧生の旅程を叙述し、
「野暮れ山暮れ里暮れて、名にのみ聞きし邯鄲の、里にもはやく着きにけり。」
と云い、やがて間(あい)の狂言があって、盧生は邯鄲の枕を借りて、
「一(ひと)村雨(むらさめ)のあまやどり、日はまだ残る中宿(なかやど)に、仮寝の夢を見るやと、邯鄲の枕に臥(ふ)しにけり。」
と叙述して、第二段の夢の中の境地に入る。
盧生は夢に楚帝の使いを受けて、迎えられて位を譲られて一書生が突然、帝になる。宮殿は玉を磨いたように輝き、妃嬪は花をあざむくほどに美しい。かくて栄華に飽きるほど歓楽に耽ること五十年、忽然として夢が覚めれば、
「ただ茫然と起き上がり、あれはど多くの女御更衣の声と聞きしは松風の音となり、宮殿楼閣はただ邯鄲の仮の宿、栄華のほどは五十年、サテ夢の間(ま)は粟飯の一炊(いっすい・炊飯)の間(あいだ)なり。」
という段になり、曲の地は人の詞(ことば)と交互に錯落して、人生の真相を簡潔に喝破し、この曲のクライマックスに達する。ここにおいて盧生は、
「まことに何事も一炊の夢、南無三宝、南無三宝、よくよく思えば、出離を求める智識はこの枕なり。げにありがたや邯鄲の、夢の世ぞよと悟り得て、望み叶えて帰りけり。」
と曲は終る。
謡曲はただ一齣(ひとこま)のものなので、その体裁の上からも自然と簡単素朴にならざるを得ない。なので、この一曲に多く望むのは無理なのは云うまでも無いが、盧生の夢の状態は余りにも淡々として、ただ夢を続けただけで何等の曲折も無く、夢が覚める時も覚める原因も無く、忽然として夢が覚め、茫然として心迷い、終(つい)に飄然と大悟するところ、甚だ興趣が無い。ことに最初から身の一大事を尋ねようとヨウヒ山に行くと云うのは、趣旨を通すことに心が有り過ぎて却って妙趣に欠ける。しかし夢が覚めた後の、地の謡(うた)と盧生の詞(ことば)と、一ツの「は」の語を境にして、女御更衣の声と聞いたものは松風の音であり、宮殿楼閣はただ邯鄲の仮の宿というあたりは、まことにおもしろく、般若心経の即是の二字も生ぬるく感じられるほどである。「邯鄲」もまた佳曲と云うべきではないか。
筆たまたま邯鄲の一夜におよぶ、ならばこれからは此の一点を基として物語を進めよう。
曲の中にヨウヒ山という地名がある。前後の文勢を考えると邯鄲の近くの山の名のように思える。ある書に羊飛山という文字さえ見える。しかし、邯鄲辺りは云うに及ばず、羊飛山という山があるということは聞かない。少しばかり所持する地誌の類を調べてもその名は出て来ない。作者が作り出した山なのか、それほど必要のない山の名を何故点出したのかと長い間考えていたが、たまたまある人が、「邯鄲の事は太平記にも出ている」と教えてくれたので、同書を読み返すと、巻二十五に黄梁(こうりょう)夢の事という條(くだり)があった。昔の人の書いたものは謡曲とも違って面白い。記して云う、
昔漢朝に才能も無いのに富貴を願う客いて、楚国の国王が賢才の臣を求め玉うと 聞いて、厚く待遇されたいと早速楚国へと赴(おもむ)いた。道に歩き疲れて邯鄲の旅亭に休んでいると、呂洞賓という仙術の人が、この客の願うところをそれとなく悟って、富貴の夢を見ることができる一ツの枕を貸した。客がこの枕で寝て一ト眠りした夢の中で、楚国の王が勅使を派遣して客を招かれた。その礼を尽くした贈物は甚だ厚く、客が悦んで早速楚国に参上すると、楚王は席を近づけて政道についれ質問し軍事について問われた。客が答える度に諸卿は皆首を曲げて傾聴すると楚王は喜んで、此の客を尊んで大臣の位に昇進させ給われた。後に楚王が隠れ給う時に、第一の姫君を客に妻(めあわ)せ給われたことにより、従官・使令・好衣・珍膳、心に適わないということ無く、目を悦ばさないということが無い。座上には客が常に満ち樽の中には酒が満ちて、楽しみは身に余り、遊び尽して五十一年、夫人はひとりの王子を産み給われる。楚王には位を継ぐ御子は無く、この孫が生まれたので、公卿大臣は相談の上この孫を楚国の王に成し奉(たてまつ)る。蛮夷も従い来朝すること、秦の始皇帝が六国を併せ、漢の文恵が九夷を随えたのと異ならず。王子が三才に成り給われた時に、洞庭湖の波の上に三千余艘の船を並べ、数百万人の好客を集めて、三年三月の遊びを仕給う。紫髯の老将は錦の纜(ともづな)を解き、青蛾の女御は棹の歌を唱う。かの有名な大梵高台の月や喜見城宮の花も看るに足らず楽しむに足らずと、遊び戯れ舞い歌って、三年三月の歓楽すでに終わりし時、夫人は三才の太子を懐いて船端に立ちておられたが踏み外し、太子は夫人諸共海底に落ち入り給われた。数万の侍臣は慌てて、一同に「あれやあれや」と云う声に、客の夢は忽ち覚める。ツラツラ夢の中の楽しみを数えれば、遥かに天子の位五十年を経たと云えども、覚めて枕上の眠りを思えば、僅かに午睡は一黄梁(いちこうりょう・炊飯時の睡り)の間に過ぎない。客はここに人間百年の楽しみも枕頭一時の夢でしかないと悟り、これよりは楚国には行かず身を捨て世を去る人となって、遂に名利に繫がる心は無くなった。これを楊亀山が日月を謝するの詩を作って云う、
少年力学して志(こころざし)須(すべか)らく張るべし、
得失由来 一夢(いちむ)長し。
試みに問え邯鄲に枕を欹(そばだ)つる客に、
人間幾度か黄梁(こうりょう)熟するやと。
これを、邯鄲午炊(かんたんごすい)の夢と申すなり。
謡曲の中の夢の状態を太平記の夢の状態に比べると、簡単か詳細かの差はあるが凡(およそ)は似ている。即ち当時このような伝説が有って、太平記もこのように記し、謡曲もこのように作られたことが分かる。サテまた太平記が楊亀山の詩をここに引用したのは、いささか適当でない。詩の心は月日の過ぎやすいことを言って、少年の時期に学業に勉めることの大切さを詠んだものである。「黄梁一炊の夢」と人世を軽く視て、不執無着の境涯に遊ぼうとするような意(こころ)を詠んだものではなく、却って世に云い伝えられている邯鄲一夢の話を面白く打ち返して、反対に日月を空費してはいけないと云うもので、いわゆる翻案の効果を発揮したものである。亀山先生は名を時と云い、程子の門人で儒学の人なので、道教や仏教めいた解悟などを悦ぶはずがない。学問思弁の功を積んで、仁義道徳の真(まこと)を得ることを期待する心雄々しい儒者である。身を捨てて世を去るような思想などを抱く人では無い。しかし亀山先生の詩の本意は兎に角として、邯鄲一夢の事を引用したことは、似合わない詩を引用したと云うだけで、縁のない詩を引用したと云うことではない。この詩もまたこの事に就いて当時の話題となっていたものであろう。しかしながら、この詩やこの物語が転々と伝わるうちに、語って語り歪め、聞いて聞き僻めるのが、心忙しく学愚かな輩(やから)の常で、根拠もない羊飛山などと云う字面(じづら)も生じたのだろう。謡曲の中にはこれだけでなく時々納得しがたいことがある。余りにも推測が過ぎるが、こうとでも解釈しなければ羊飛山の事は解釈することが出来ない。
羊飛山の事は深く論じる価値はない。ただし謡曲を「太平記」に比べて調べると、別に注意に値するものがある。それは謡曲に盧生の名が有って「太平記」には盧生の名は無い。「太平記」には呂洞賓の名が有って謡曲には呂洞賓の名が無いことがこれである。盧生と呂洞賓は何れの世界から来て、我が謡曲に上り「太平記」に上るのか。
邯鄲一夢の物語は、ソモソモ最初は何の書に出たのか。云う。「経に無く、史に無く、荘列諸家の書に無く、屈・賈・司馬相如・東方大中諸賢等の集にも無い」。では何の書に出たのか。云う。「その出たのは甚だ遅い、唐になって初めてこれ有り、唐の李泌が撰する「枕中記」一巻が即ちこれである(注・別に沈既済の撰するものがある)」と、邯鄲一夢の事はその中に記されている。「枕中記」は唐の李公佐の著わす「南柯記」の類であって、内容は各自が夢を借りて懐(おもい)を述べるだけである。若しそれが本当にその人が居てその事が有ってその夢があると云えば、これは人間のようなものが夢に弄ばれているだけのことで、達人は笑い出すであろう。しかし「枕中記」は文が妙で事が妙で夢もまた妙であり、しかもなおこれを撰する人もまた妙なので、夢が滅びないこと一千年、その生じた夢の夢子・夢孫・夢曽孫・夢玄孫・支流庶出・末孫遠系が今なお存在する。夢の寿命もまた今では金石に勝ろうとする。盛んなるかな夢や。「枕中記」は勿論珍しい本とは云えないが、謡曲や「太平記」等に比べ遥かに内容が多意多趣なので、私はノンビリと閑筆を運んで古談の風貌を伝えたいと思う。忙しい人は休みなく働く、君が名声と富を図るのは君の随意に任せる。「枕中記」は次のように記す。(②につづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
