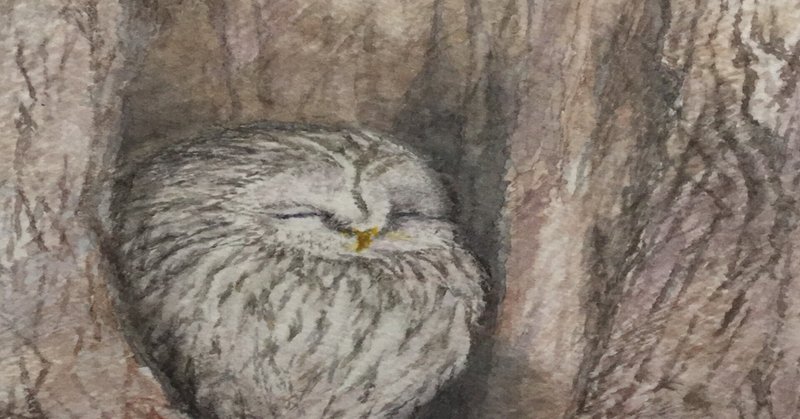
幸田露伴・支那(中国)の話「笋を焼く」
笋を焼く
白楽天の「笋を食う」の詩に云う、
紫籜(したく) 故錦を析(さ)き、
素肌 新玉を擘(つんざ)く。
と。笋(タケノコ)の皮が剝(む)かれて身が現れた潔さを巧みに言い取っている。笋の愛賞すべきものであることは云うまでも無いが、富貴の白楽天が次句で、
毎食 遂に加飧し、
時を経て 肉を思わず。
と云うのは少し装飾が過ぎるようだ。しかし春夏の境にあって笋はまことに好い食べ物である。その時に当っては寒土に光を生じ、飢えた腹も潤うような思いがする。ただし笋も彼の地と我が国とでは異なっていて、我が国では煮て食うだけだが、支那(中国)では焼いて食うことが有ると見えて、黄山谷の「簫巽と葛敏修の二学士が私の食笋の詩に和す、次韻して之に答えるの詩」に、
根に就いて 煨柮(いとつ)するの美、
豈(あに)念(おも)わんや 炮格の債。
の句が有る。柮(とつ)は木の切れはし、榾(ほた)である、焚き木である。煨は「懶残和尚芋を煨く」の煨である。焼くのである。であれば根の処で榾焼きをすることが有って、その味は甚だ美味であると云う意味である。金の郝天挺の詩の頭の句に、
煨柮 旧開く 山谷(黄山谷)の語、
と云うのも、まさに此の句を指して云うのである。郝天挺の詩は題して既に食焼笋と云う。
未だ放たず 錦綳 束縛を開き、
己に看る 玉版の 荼毘を証するを。
の一聯は明快にその状(さま)を云う。玉版は笋の 身を云い、荼毘は火花を云い、錦綳は籜(たく・筍の皮)を云う。佳句ではないが実際を伝えることは伝えている。また楊万里の唐徳明から笋を恵まれるを謝するの詩に、
錦紋猶帯ぶ 落花の泥、
論ぜず 焼煮を 両(ふた)つながら皆奇なり。
とあり、唐庚の食笋行の詩に、
野人は惜しまず 蒼苔の古りたるを、
掘り得て 嘉餐 自ずから焼煮す。
とある。楊と唐の詩に優劣はあっても、焼字があるのは同じである。焼笋を食って、陳惟寅の竹間を詠んだ明の楊基の、
春雷 一声 万簪(ばんさん)の玉、
参差(しんし) 乱れ迸りて 莓苔(ばいたい)緑なり。
斬り来たって 葉を払い 当境に焼く、
何ぞ異ならん 萁(き・豆殻)を燃やして 秋菽(しゅうしゅく・秋の豆)を煮るに。
盤に登る 査牙として 玉版肥ゆ、
尾を焦し砕破す 蒼龍の皮。
山人 大嚼 以て報ゆる無し、
写し作す 林間 笋を焼くの時。
の一篇になどは野気横溢して人を微笑ませる。その場で焼いて敢えて大食いをして、竹林の主人の顰蹙を買うことは無かったか。蘇東坡の猫兒頭笋を恵まれるを謝すの詩に、
長沙 一日 籩笋を煨く、
鸚鵡 洲前 人未だ知らず。
走送 煩わす公の湯餅を助くるを、
猫兒 突兀 鼠 籬を穿つ。
の一絶がある。煨の一字が有ることで、明らかに煮るのでないことが分かる。ただ猫兒頭笋の一語は、推測できるが明解は出来ない。籩笋の二字も籩は竹の器のことなので理解し難い。且つ転結の二句も戯謔が過ぎて品格無く、しかも此の詩は私の蔵本している蘇東坡集には載っていない。疑わしいところがある。同じく蘇東坡の作るところの戯謔の一篇に、「劉噐之は好んで禅を語るが、山に遊ぶことを喜ばない。山中に筍が出る、戯れに噐之に語る、同じく(一緒に)玉版長老(筍)に参ずべし」と、この詩を作ると題したものがある。査初白の註は苕渓叢話を引用して云う、「蘇東坡は嘗て劉噐之と共に玉版和尚(筍)に参禅する。噐之は喜んで此れに従う、廉泉に着いて、筍を焼いて食う、噐之は筍の美味を感じて、之は何と云うものかと問う、之は玉版と云う名のものである、この老僧は法要を説いて人に禅悦の味を得させると答える。噐之はここにおいて、その冗談であることを悟る」と。詩は禅家の語を用いて善く冗談を楽しむ。苕渓叢話の中に焼筍而食(筍を焼いて食う)の語があるのに照らせば、東坡もまた焼いて食ったことは確かで、思うに当時は普通に行われていたのであろう。蘇東坡や黄山谷の清雅な人柄は、葷羶(くんせん・匂いの強い野菜や生臭い肉)なものよりも寧ろ淡泊なものを愛す。笋の話が伝わるようになったのも自然なことであろう。特に山谷は食笋十韻に詩が二篇有るだけでなく、苦笋賦を作って蜀の人が食うべからずと云う苦笋を称えて、「苦にして味あるは、忠義の士の諫言が国を活かすように、多過ぎる害が無ければ、士を挙げて賢を得るようなことだ」と云う。笋を嗜むのも極まると云える。
宋の時代の人が笋を焼いて食べたことは前述のようである。ただし、唐の時代の人では白楽天に食笋の五言古詩がある。韓昌黎に侯協律が笋を詠ずるに和す排律の長篇があるが、皆一言も焼笋を云わない。なぜ唐人は焼くことを知らず、宋人は焼くことを覚えたか。飲膳の道を平安朝は唐に学び、足利期は宋から受ける。しかし笋を焼くことは之を耳にしない。思うに彼の国の筍は繊(ほそ)く小さいので、そのため小説の文に美人の指を形容して、繊々春笋の如しと云うのがある。我が国の賞食する笋は孟宗竹や真竹や淡竹などで、美人の玉の指とはかけ離れた巨大なものである。であれば、巨大な笋は無論焼いて食すべきでなく、篠竹等の細い笋は焼いて食うべきであるか。思うに笋は巨細の別なく、海草やワカメと共に煮て羹(あつもの)として食うのが最も佳い。何で焼く焼かないを論じる必要があろう。
(昭和十五年三月)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
