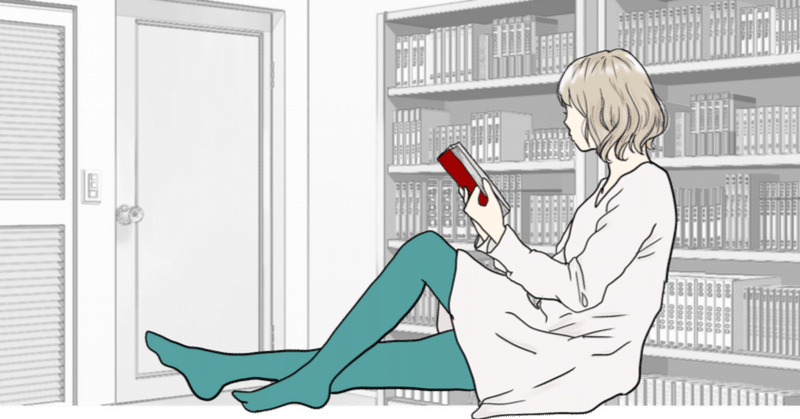
【短編小説】日記ちゃん
私は小学生の頃日記を書いていた。日記ちゃんと名前を付け、友達と会話をしているかのように文字を並べていた。友達がいなかった訳ではないのだけれど、お母さんを亡くしてしまった悲しさを話せるのは日記ちゃんにだけだった。
お父さんは毎日朝早くから遅くまで仕事だったけれど、朝ごはんと夕飯は必ず手作りで用意してあった。私はお姉ちゃんと二人で食べながら、お父さんに心配かけまいと幼いながら話したのを覚えている。
優しいお父さんとお姉ちゃんと一緒にいればいるほど、お母さんが恋しくなっていた私。
そんな私は日記ちゃんに毎日話しかけていた。
「きょうはお父さんがハンバーグをつくってくれたよ おいしかったよ お母さんも食べにきてね」
「きょうはお父さんとおねえちゃんとすいぞくかんにいったよ お母さんはでっかいさかなさんみたことある?」
「きょうはおねえちゃんとおやつにケーキをたべたよ
大好きないちごのケーキおいしかったよ お母さんもたべる?」
初めはお母さんに問いかけてばかりの私の日記。日記ちゃんがお母さんに伝えてくれているんだと私は思いたかったのだろう。もしかしたら返事がくるかもと淡い期待、いやそのときは本気でそう願っていた。
だけど、そんなことは起こるはずもなく日記ちゃんへの会話は段々変化していった。
中学生になれば、好きなアイドルのことや友達と遊びにいったこと。恋の話やお父さんとお姉ちゃんへの愚痴。
高校生になれば、部活のことやお洒落なお店を見つけたこと。背伸びした化粧の仕方や将来の進路。
日記を書き始めたきっかけは悲しみだったけれど、日記ちゃんへの会話は成長するに連れ前向きなものになっていった。
だけど短大を卒業し、社会人になった私は慣れない一人暮らしと多忙な仕事に終われて日記ちゃんとの会話は無くなっていた。色々とうまくいかないことで私のことを支えてくれていた彼のことも邪険に扱うようになっていた。
そんな生活が一年ほど続いたある日、私は朝起きなくてはいけない時間に起きあがることができなかった。意識はあるけど、ベッドから出れない。いつも乗る電車が出発する時間を指している時計を見てると妙に冷静になった。
今日は休もう。
ただただぼーっとしている私はふいにクローゼットをあさり、奥にしまってあった日記を取り出した。最初に書き始めた日記から10冊ほどになっていた。
我ながらよく書いたと思いながら、パラパラと見直してく。ひらがなの多い文から短い文、漢字が増え長い文になったと思えば一言で終わる日。
色々な日があったこと思い出させてくれる日記ちゃん。
今日は久しぶりに日記ちゃんとの会話をした気がする。私は会社を休んだことを日記に書いた。
会社から連絡があり体調不良だと伝えると、いつも遅くまで頑張ってて心配だったから二、三日ゆっくり休みなと上司が言ってくれた。
私は久しぶりに実家に帰ることにした。日記を見返して懐かしくなり急に実家が恋しくなった。
実家に帰ると赤ちゃんを抱いたお姉ちゃんが出迎えてくれた。去年実家を増築リフォームし、今はお父さんとお姉ちゃん夫婦が住んでいる。
「おかえりー めずらしいね 連休取れたんだ」
「そう たまたまね」
何気無い姉妹の会話をしながらリビングへとあがる。
「たまにはお父さんに連絡してる?心配してるし寂しがってるよー」
「あー ちょっと忙しくてさ」
確かに一人暮らしを始めてからはあまりお父さんに連絡してなかった。今日はゆっくり話してあげようかなんて思いながら帰りを待っていた。
「お姉ちゃん 今日の夕飯どうするー? 」
「今日はお父さんが作るってー」
「えー?お姉ちゃんじゃないの?お父さん仕事でしょ?」
「もう買い物終わって帰り道だってさ それにだったらあんたが作ってあげなよ」
「わたしー? じゃあお父さんでいいよ」
正直私が作るよりお父さんのほうが料理がうまいのは知っている。それにお父さんの料理久しぶりに食べる気がするな。何作ってくれるんだろう。一人じゃない食卓が楽しみだった。
お父さんは帰ってくるなりキッチンで準備を始めた。作ってくれたのはハンバーグだった。お父さんのハンバーグは絶品でお姉ちゃんの旦那さんもそのハンバーグが大好きなようだった。
夕飯を終えると、私はモノが無くなり広く感じる自分の部屋へいき、また懐かしいアルバムや漫画本を眺めていた。
コンコンと扉をノックする音。
「なにー?」
「まな、ちょっといいか?」
「うん」
お父さんが部屋に入ってきた。
「仕事はどうだ?一人暮らしは大丈夫か?」
「あー うん まぁ大変っちゃ大変だけどなんとか大丈夫かな」
私は半分ほんとで半分嘘をついた。
「そうか いつでも帰ってきていいからな それとこれ」
そういうと一冊のピンク色に星のシールがデコレーションされた分厚いノートを私に差し出した。私がノートを受け取るとお父さんは部屋を出ていった。
ノートをめくると
「愛する真愛《まな》ちゃんへ」
と書かれていた。ピンク色に星のシールは私が小さい頃大好きだったものだ。
お母さんの字…
私はもう一枚ページをめくる。
「小学生の真愛《まな》ちゃんはお母さんがいなくなってきっととても悲しんじゃうね。ごめんね。でもね、大丈夫だよ。真愛ちゃんには優しいお父さんとお姉ちゃんがいるから、それにまだお母さんも少しだけ時間があるみたいだから、少しでも長く真愛ちゃんといれるように日記を書いとくね。」
「今日はみんなの大好きなハンバーグを作りました。真愛ちゃんはあっという間に食べちゃったね。いっぱい食べて健康に育ってね。お父さんにハンバーグの作り方教えておくからね」
「今日はみんなで水族館に出掛けたね。真愛《まな》ちゃんは大きなお魚さんにびっくりしてたけど、楽しかったね。真愛ちゃんが大きくなったら素敵な彼とでもいくのかな?」
「今日のおやつはいちごのケーキだよ。真愛《まな》ちゃんの好きなケーキ。お父さんに教えておくからね。」
お母さんはまるで一緒に時間を過ごしたかのように日記を綴っていた。それは何日も何日も書かれていた。特別なことじゃない日常の一コマが私の記憶を蘇らせる。その中にはお父さんが実現させてくれたことが何個もあった。
「お母さんずっといるじゃん…」
私は涙でぼやける視界の中で一文字一文字が、映像へと変換されていくのがわかった。
「大人の素敵な女性になった真愛《まな》ちゃんへ」
「ここまではお母さんが思い描いた未来を日記に書いてみました。ここからは真愛《まな》ちゃんが思い描く希望に満ちた未来を描いてね。きっとそれは必ず叶うから。お母さんはずっとずっと見守ってるから。」
「愛してる。ありがとう。」
それが最後の言葉だった。
私は泣いてるのも忘れてみんながいるリビングへとかけ降りていった。
「お父さん! お姉ちゃん!」
ソファーに座っていたお姉ちゃんがシーっと口の前に指を一本添えながら振り向く。
「子どもが起きちゃうでしょ!ってあんた泣いてる?」
お父さんはダイニングテーブルで缶ビールを飲んでいる。私の顔を見ると優しく頷いた。その雰囲気を感じとったお姉ちゃんは優しく私にこういった。
「あんたが全然連絡くれなかったから今日になっちゃったんだからね」
それから三人で思い出話をした。初めて知ったお父さんとお姉ちゃんの思いもあったけど、私は未来を見ていた。
私はお母さんの日記の続きに一言だけ書き加えた。
「お母さん ありがとう」
それから数年
私は日記ちゃんと会話している。私の愛する子供の成長の話を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
