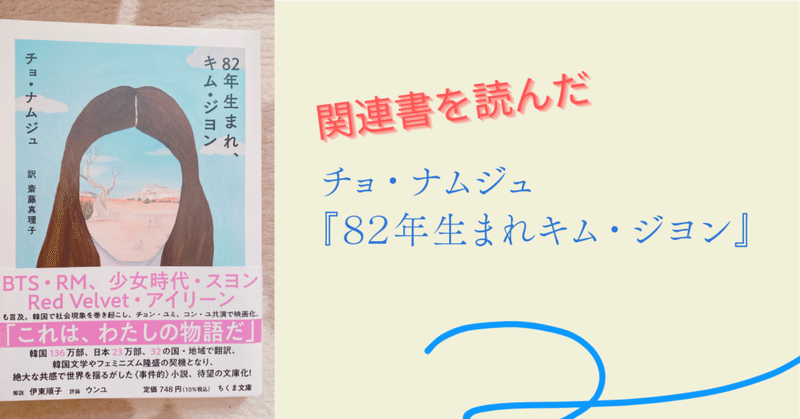
無知識だったのでさらに本を読んだ
以前、本の感想を記事にした。(下記記事)
『82年生まれ、キム・ジヨン』は近年話題になった韓国のフェミニズム文学だ。わたしの感想は作品と解説を読んだ中で感じたことを書いたまでだった。しかしその文章の中で
「女性には不人気とされる分野で話題性を押し出したい際、扱いやすいようカテゴライズするための「カープ女子」「森ガール」「ソロ活女子」、似たタイプの語として「歴女」「リケジョ」などの言葉が生まれている。新規顧客獲得のためマーケティングをおこなった結果とは思うが、そもそもその分野において女性が積極的に好まないものであると、誰が決めたのだろうか。少数派であることを証明する調査でも行ったのか。」
ということを書き 本当になぜこのような認識がされるようになったのかという疑問が湧き、さらに関連本を読んで少しでもその中身を知りたくなった。
大井 浩二 著『ヴィクトリアン・アメリカのミソジニー タブーに挑んだ新しい女性たち』小鳥遊書房 (2021年5月刊行)

上記の書籍では19Cアメリカで活躍した
■ジュリア・ウォード・ハウ(奴隷制度廃止活動家)
■メアリー・パットナム・ジャコービ(医師)
■シャーロット・パーキンズ・ギルマン(作家)
三人の女性に焦点を当てアメリカのフェミニズム初期について考察されている。なおミソジニーとは女性に対する憎悪や嫌悪することをいい、女性蔑視のことである。
こんな箇所がある。
(……中略)したがって、男性の社会的な公的領域に越境して、詩人や医学研究者や評論家として多方面で活躍するハウやジャーコービやギルマンは「反自然的」な「半女性」あるいは「精神的両性具有者」にほかならず、彼女たちの仕事は、「真の女性」は閉じ込められるべき家庭的な私的領域の枠からはみ出た、女性には許されていない行為、身の程をわきまえていない行為と認識された。彼女たちは女性には不向きと考えられていた知的職業に携わっているだけの理由で、男性だけに認められた公的なマーケットプレイスへの歓迎されざる侵入者として避難された。【P.12】
もうすでに19世紀アメリカで現代と変わらない扱いを彼女たちは受けていた。さらにこうまとめられている。
ヴィクトリアン・アメリカの家父長制社会においては、「男性にコード化されたプレステージの高い領域」に入り込もうとした女性たちは「悪い女性」で「家父長制の敵」と見なされ、「ミソジニー的敵意」を向けられた。【P.13】
このように長く深い隔たりはまるで因縁めいた何かがあるとしか思えない。…と思わずにはいられない。性別が異なるということはこれほどまでに難しいことなのだろうか。しかしある地位や名誉を欲している男性に限るのではという考えも浮かぶ。さらに別の本に当たり根源的な点に関する仮説があったので紹介する。
赤坂 俊一 著『ヨーロッパ中世のジェンダー問題 異性装・セクシャリティ・男性性』世界人権問題叢書115 明石書店 (2023年8月10日刊行)

(以下は本文の要約)
ジェンダー構造についての一つの仮説。セクシャリティとしてのメス、オスではなくジェンダーとしての女と男というくくりは、つまりは社会的な存在であり価値意識を伴うものである。その価値とは有史以来、強いか弱いかで決まっていたといわれる。しかし、メスとオスは同じ体格で同じように強かったのではという検討はされてきていない。
だが、直立歩行になりメスは乳房が垂れ下がる、定期的に生理がくる……など生きる、生活する上でオスより不利になってしまう。そこで集団から阻害されないためにメスは居住地を守り採取した食べものの調理などを担い、オスに自分を保護すべき存在だと思わせた……というものだ。
(このほかにリーアン・アイスラーの、ジェンダー構造が存在しないかまたは希薄だった時代があったと主張する考えもある)
この仮説がすべてではないだろうし、著者は上記の仮説が「一直線に」現代まで続いてきたかどうかはまた別の問題だと疑問を呈しているが、こんな文化も希薄なただ生きるというだけの時代から役割が存在し、その認識が少なからず現代に引きずられているのだから、女性と男性は「人間」という皮をまとった別の生きものだと思わざるを得ない。しかしだからといって進まなければ停滞してしまうばかりだ。人類がこの先どのような進化を続けるのかは先のわたしの記事に記したように、異なる他者をどのように許容するのかという意識に拠るのではとあらためて思う。

今は生活と絵をがんばっています。 「スキ」してくれるとアルパカが出てくるので、ぜひ。 サポートはすべて画材に当てております。 いつも応援本当にありがとうございます。
