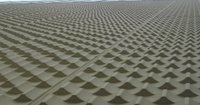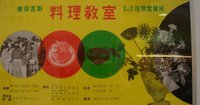2020年10月の記事一覧

再生
音楽のレシピ(その6) ー聴取者と演奏者ー
『誰もいない森の真ん中で木が倒れたとき、その音は存在したことになるのか』 今夜、サッカーJ1リーグ 浦和レッズ×セレッソ大阪の試合をちらりとTVでみたのだが、攻撃に転じたとみるやそのプレーのテンポに合った四つ打ちの手拍子を送り出し始める浦和サポーター達の様子を見て、「やっぱサッカー観戦ってライヴ並みにイイもんだよなぁ。オンガクだよなぁ」と思ったのであった。 そう。“お客さん”の存在って、音楽にとって必要なもの? そりゃ必要でしょう! だけど、オレはかつて中坊だった頃に恩師がいったこんな言葉を未だに憶えている。とあるチェロ演奏家が「私は聴衆との交感を演奏動機の一番のエネルギーとしています」とTVで語っていたのを見ての一言。「この人、世界でただ独りの人間になってしまっても、まだ演奏するのかなあ」‼‼‼‼!!‼‼!‼‼! 「たとえそうなっても演奏する人になってやるぞ」と心に決めたオレだったが、何のことはない。演奏者は常に自身の一番の聴衆でもあるのだから、そうなったって全然大丈夫! でも、やはり、お客さんがいれば嬉しい。貼り付けた画像は、最早主客一体となったライヴの好例として参照されたい。