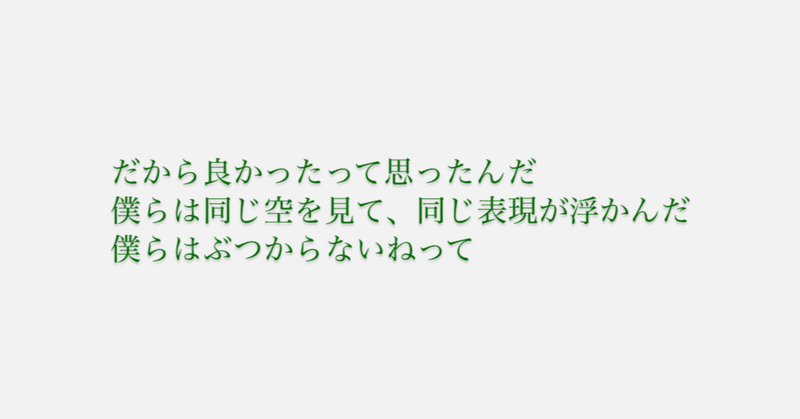
骨朽ちるまで 前
春人君が死んだ。
彼にぴったりな名前だったなと、死んでから思った。
毎年必ず訪れるけれど、それは本当に瞬きの様な一瞬で。例えば桜を観なければ感じ取れない程で、しかし確かに在るのだというその不安定さは、まさに彼の様だった。
私たちは付き合っていたのだと思う。
まだ学生の私達は、大人の様に自分の感情を恋だとか、愛だとかを確かめたり迷ったりする事なんてなく、只毎日登下校を繰り返し、帰り道にプリクラを取ったり、お互いの家でゲームをしたり、キスをしたり。
それだけが本当の事で、それだけで満たされていた。
彼は学校の屋上から飛び降りたのだと聞かされた。
「自身で死を選ぶ人の気持ちが僕にはよくわかる。この世界は不条理だよ。不条理だと言ったら己の努力不足だ、環境を変えれば、なんて外から言われる点が不条理だ。だけどね灯里ちゃん。だからこそ僕はそんな選択は選びたくないんだ。屈服したくないんだ。だからみっともなく生きて、何かを残そうと思うんだ」
彼はよくそんな話を私にした。
彼は小説を書いているのだと言っていた。私はまだ一度も、読んだことが無い。
私には彼の話が、良く分からなかったのだと思う。
それは春人君が、あまりにも楽しそうだったから。生徒会の副委員長としてはきはきと良く喋っていたし、彼は友達が多かった。
うん、私とは正反対なほどに、環境に良く馴染んでいた。
春人君の体が燃やされていくのを見ながら、私は彼との思い出を反芻していた。
そうしてなぜだか、涙が出ない自分が、ひどく虚しかった。
私は春人君のどれだけを、知らなかったのだろう。
―――体は勝手に動いていた。
彼の遺骨と呼ばれるそれを前に、私はスマートフォンを取り出していた。
かしゃり。
スマートフォンのカメラを内側に向け、しっかりと顔の横に入るように。
私とそれとの、ツーショット。
腕を誰かに引っ張られていた。大人が何人か大きな声を出していた気がした。
不謹慎だと言われている様な気がした。
知るか、そんなもの。
これは私と春人君の中で許し合ってきたコミュニケーションだ。
火葬場から追い出された私は、骨になった春人君とのツーショットを待ち受け画面に登録した。
「春人君、あなたどうして死んだのよ」
「えー、非常に悔やまれる事態であります。私達教職員一同、なぜもっと早くに彼の悩みに気づいてあげられなかったのかと思うと、本当に情けなく思います。2年A組の羽野木春人君は、私達の心の中で生き続けるのであります」
全校集会が開かれた。なんだか偉い大人達が外からも来て、相談窓口だとかの説明をしたりしていなかったり。皆黒いスーツを着て、顔はしかめて。
壇上の男の、心の中で生き続けるという言葉が頭の中に靄の様に広がった。
生きるとはなんだろう。
生きるって、変化していく事ではないのだろうか。
それは成長であれ、劣化であれ、静止する事をやめない事なのかもしれない。背が伸びたり、髪が伸びたり、忘れたり、そうして衰えていく。
ふと、言葉通りの想像をしてみた。
春人君の事を心の中で思い浮かべてみる。
白い空間に、彼一人。
スラっと背の高く色白な彼の姿は、輪郭をうっすらとぼやかしている。
春人君は笑っている?左頬だけに浮かぶえくぼを指でなぞると、彼は気恥ずかしそうに目を逸らす。
これは記憶。
この彼は、私の心の中で、変化していくはずがないだろう。
想像の中で髪の伸びた、スーツなんかを着るようになった彼を作り上げることは、彼の変化ではなく私の作りものだ。
春人君が死ぬまで、こんな事考えた事も無かった。
人が死ぬニュースを見て、人が死んだのだと理解する。死ぬという事がこの世界では起きて、私もいずれそれを迎えるという事を知っている。
そういう事で、それだけの事だったから。
心の中で生き続けるなんて、良く分からない。
彼を浮かべた時の白い空間は、羽ばたく事を許さない鳥かごの様に思えた。
春人君が籠から動かないのは、彼が静止しているのか、私が閉じ込めているのか。
動悸がして、スマホを開いた。
そういえばこの骨は、彼のどの部分なんだっけ。
「灯里、大丈夫?」
放課後。
教室の空気は息がしづらくて、窓の近くで外を眺めていた。
いつもの様にふざけている男の子達がいたり、不謹慎だよと怒っている学級委員長がいたり、あぁ、彼はどこの誰とも似ていなかったなと考えていた。
ん、
「あ、ごめん、なんか言った?」
「…ううん、私もここにいて良い?」
「うん」
栞の声は、とてもクリアに聞こえる。
彼女は生徒会長をしていて、とてもまじめで、優しい。
人の温度感にすごく敏感で、特に会話をしなくても居心地が良い。私の唯一の友達。
「春人君さ」
「ん」
「良い人だったよね」
「…そうだね」
良い人。春人君は、良い人だった。
優しい人とか、真面目な人とか、そんな言葉は似合わない、良い人という言葉が当てはまる。
私のくだらない悩み事を聞いてくれている時の彼は、私が言葉の後ろに隠した何かを見つけようとしている目をしていた。
それなのに、多くを話さない。
全てを解ったうえで、私が話さなかった部分には触れないように、ただただ包み込むように聞いてくれていたのだと思う。
言葉以上に仕草や目線で、理解しようとしてくれる。
私が落ち着いたのを感じ取ると、彼は散歩に連れ出してくれて、全然違う話をしはじめる。
その彼の話に私はさっきの会話のヒントを見つけ出して、勝手に解決することが良くあった。
今になればそれは、春人君なりのアドバイスだったのかもしれない。
自らが話さない強さを、彼は持っていた。
「そういえば、春人君、栞に何か言ってた?」
「何かっていうのは…原因がなんだったのかに関連するような何かって事かな。そういう意味では、私たちは只の生徒会仲間だっただけだから特に何も言ってなかったよ。ただ」
「ただ?」
「灯里の事を良く話してた」
「―――」
「話してたって言うより、聞かされてたって言った方が良かったかな。春人君、すごく嬉しそうに灯里の話するのよ」
「なんかすごく意外、なんて言ってた?」
「惚気話ー、ってわけじゃなかったのかな。なんだろう、灯里は僕とは違う、凄いんだって。ただひたすらにあなたを褒めてた」
栞はふふふと笑いながら、悲しさも混じっているのが私にわかる程ぎこちなく、楽しそうに話してくれた。
「褒めてたって、私にはそんな事全然してくれなかったけど」
「そういうのって本人には言いづらいじゃない、気恥ずかしくて。そうだな、灯里はすごく自分に正直なんだって、何度も聞かされてた。自分の気持ちにまっすぐで、迷ってる時も迷ってるって言える。表情もたくさんあって何でもすぐわかるって。人間っぽくて好きなんだってさ」
「人間っぽくって何よ…。私そんな風?」
「ううん、私は正直、灯里にそんな事思った事ないわ。気難しいったらありゃしない」
「それもそれでよ」
「でも、あなたが春人君の前ではそうで、そう映ってたって事よ」
「…」
「私にも見せない姿を見せられたのが春人君だったのね。それをちゃんと感じ取ってくれてた」
初めて聞かされた話に戸惑ってしまった。窓の外の雲の動きを眺めたりしながら、春人君との事を振り返っていると、時間はとても、ひどく長く感じた。
「灯里」
「ん」
私が呆けている間、どれだけ時間がたっただろう。教室の皆はいつの間にかいなくなっていて、私と栞二人だけになっていた。
「またね。今度カフェでも行こう」
待っていてくれたのか。
栞は気持ちの良い友人だ。誰かが一人になりたいときに察して身を引く。
私は周りに恵まれていたのだと、空を見ていた。
夏の暑さが終わるのか、涼しい風が吹いたのを素肌に感じ、捲っていたワイシャツの裾を下す。
空は既に青空からピンク色に変わっていた。
ふと、去年の同じ季節の春人君との会話が浮かび上がった。
「見て春人君、綺麗なピンク色」
「本当だ、確かにピンク色。僕も同じように思えるよ」
「思えるってなあに?ひっかかる言い方ね」
「んー」
彼は時々、しまったという顔をした。そんな時は決まって何かを考えている。
彼は色々と自分の考えている事を進んで話したがらない。
「また何か考えてるのね。私はそれを聞くのが好きで春人君が好きなのよ」
それじゃあ、と彼は話し始めた。
「僕はさ、人が言い争ったりするのが嫌なんだ。どうしてだろうってずっと考えてる。いや、どうしてかって言われたら、人はみんな違うからだろうって事はわかってるんだけどね」
「うん」
「でもそうじゃない事もあると思うんだ。例えばだけど、僕と灯里はこの空の色を見てピンク色だって言ったろ?けれどこの空の色を桃色だっていう人もいると思うんだ」
「うん」
「同じ色を見て、同じ事が浮かんだとしても、知っている言葉や表現の違いでぶつかる事ってあるんだろうなって。本当は胸に浮かべている事は同じなのに、言葉数や伝え方で誤解が生まれる事がたくさんある。言葉じゃない胸の内で感じている事はどうだろうって目線をもって、人と話し合いたいんだよ」
「なんとなくだけど、わかるかもそういう事」
「だから良かったって思ったんだ。僕らは同じ空を見て、同じ表現が浮かんだ。僕らはぶつからないねって」
ピンク色に染まった彼の頬はどこか照れくさそうで、同時に私も照れくさくなって、えいっとえくぼに指を刺した。
彼はくしゃくしゃっと笑っていた。
「今日もピンク色だよ、春人君」
家に着いて、ご飯を食べて、お風呂に入った。
私は生活を出来ている。
テスト期間に連絡を取っていないような、喧嘩をしてしまって顔を合わせていないような。
たったそれだけなんじゃないかって。
心が これまでに置いて行かれたまま、どこか落ち着いている。
彼の遺骨との写真を私はなぜ撮ったのだろう。
重い体を布団に沈めたまま、スマホの待ち受け画面を唯々眺めた。
骨となって静止した春人君。
この骨は、彼の体の一部で、共に生きていた一部で、彼自身であったもので。
この骨は、彼の考えていた事や、話してくれた事、小説を書いていたという事を知っているのだろうか。
春人君の心と呼ばれている物が死んで空に解き放たれたとして、固く無機的な物体になったこの骨に、彼の暖かさを感じられない。
あなたは彼の体の中にいたんでしょう。
どうしてあなたから、彼を感じられないのかしら。
私は春人君の何をもって、彼を感じていたのだろうか。
後半
https://note.com/5minute_stories/n/n2f556184544c
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
