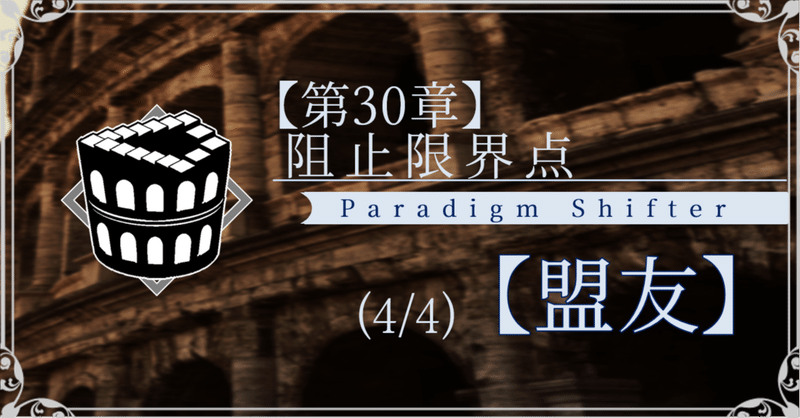
【第2部30章】阻止限界点 (4/4)【盟友】
【確証】←
「なんとなればすなわち、これほどの速度で増殖するとは……レールガンを駆動させていた多脚戦車の電力を、吸収したかナ? あれだけの莫大なエネルギーを供給していたとなると、核熱球を搭載していたのだろう……」
『おじいちゃん! 冷静に分析している場合じゃないということね!?』
「いや、ララ……窮地にあってこそ、沈着であるべきではないかナ……?」
ダムが決壊するように隔壁が破れ、スライムの濁流があふれ出してくる。天井にひびが入り、崩落し、いくつかの瓦礫が落下してくる。館内放送から、少女の悲鳴が反響する。
ドクター・ビッグバンの双眸にはめこまれた精密義眼が、赤い光を放ちながら、小さな駆動音を立てる。ひるむことなく、津波のごとく迫る粘菌を見すえる。
「なんとなればすなわち、ララ。心配することはないかな……このワタシはすでに、先ほどから『状況再現<T.A.S.>』を起動している……ッ!」
粘液の水しぶきは老科学者の白衣を汚すことはなく、スライム本体の濁流も老人を避けるように間隙ができている。
ドクター・ビッグバンは通路をさらう粘菌の急流から、余裕を持って避難するように、先刻、落下してきたばかりの瓦礫のうえに登る。
「この粘液体が、どの程度の知能を持っているのかは不明だが……すでに、安全地帯と脱出路は算出済みかナ!」
『でも、おじいちゃん……演算のための導子力は……ッ!?』
「無論、このワタシの生体活動を維持するために、タイトなエネルギー配分が要求されているが……必要なリスクというものではないかナ!!」
白衣の老科学者を呑みこもうと、スライムの濁流の水面が上昇してくる。ドクター・ビッグバンは、瓦礫群を飛び石のように渡ると、おあつらえ向きに壁面の崩壊に伴ってできたつかみと足場を使って、上階へ向かって登攀していく。
この世のものならざる粘液は、擬腕を作りだし、白衣の老科学者を捉えようとする。粘菌の触手は、ドクター・ビッグバンの背中をかすめるも、接触には至らない。
「ふうぅぅ……この歳になって、全力疾走のみならず、ボルダリングまで経験することになるとは思わなかったかナ……人生とは、わからないものだ……」
白衣の老科学者は、天井に開いた穴を抜けて、上部区画へと転がりこむ。階下の通路は、すでに半ほどまでスライムの濁流によって満たされている。
『もう、おじいちゃんったら……見ているこっちの心臓が持たないということね!』
個人用の導子通信機に切り替えて、何度めかわからないララの抗議の声が聞こえてくる。中央制御室がある区画以外は電力が途絶したままで、館内放送を初めとした設備は使えない。
「なんとなればすなわち、ララ……結果オーライ、としてはもらえないかナ? それはそうと……このワタシの回収を、手配してもらいたい。適当な航空機を自力で奪取しようかと思っていたが……その余力は、なさそうだ」
照明の落ちた暗い通路のなかで、尻餅をついたドクター・ビッグバンは、荒い呼吸を繰りかえす。
『了解ということね、おじいちゃん。いまは、身の安全の確保を最優先して? いまから回収ポイントを算出するから……』
導子通信越しに、ララの足音が聞こえる。メディカルルームから、ブリッジに向かっているのだろう。白衣の老科学者は、若干の酸欠症状を自覚しながら、立ちあがる。
「このワタシが、『シルバーブレイン』に戻り次第……艦の演算機能を使って、帝国の機密データを精査する。どうにかして、現状の打開策を見いださねば……」
『たたっよたったた……いったい、どうすればいいのかしら……』
「なんとなればすなわち、少なくとも、この『塔』を破壊する必要はあるかナ。自爆装置でも仕込んであれば、話は早いのだが……」
おそらく期待できないだろう、という言葉をドクター・ビッグバンは呑みこむ。通信を交わす父娘の声音は暗く、重い。規格外の天才ふたりがかりとは言え、完全に把握し切れてすらいない命題の解答を、ごくわずかな時間で導き出さねばならない。
(なんとなればすなわち……できるかナ?)
導子理論の提唱者にして、セフィロト社の隆盛を支えた、多元宇宙全体を見まわしても希代の碩学の額に、冷や汗が伝う。
『──ふむ、取りこみ中だったかね。こちら、『伯爵』。たったいま、『塔』に到着したところだ。途中からだが、話は聞かせてもらった。ドクの回収は、我輩が請け負ってもかまわないが?』
鬱屈とした沈黙を吹き飛ばすように、朗々とした、それでいて明確な意志を宿した声音が、導子学者父娘のホットラインに割りこんでくる。帝国軍の追撃部隊からの陽動をみずから買って出て、別働隊となっていた『伯爵』だ。
「デズモンドかナ! なんとなればすなわち、どうやって『塔』までたどりついた!?」
『周辺は、極高温環境に包まれていて、まともに接近できる状態じゃなかったということね!?』
『ふむ。無論……徒歩かね。こういうときのために、足腰は鍛えている』
壮年の男は、こともなげに言ってのける。天を突く威容を誇る『塔』、その根本の正門まえ、下草が焼け焦げ赤茶色になった大地に、伊達男は立っている。
勝負着である燕尾服は燃えつき、お気に入りのシルクハットはひしゃげ、自慢のカイゼル髭も焦げ乱れている。ワックスで入念にセットした頭髪も、ゲリラ豪雨に叩きつけられて、ぐしゃぐしゃだ。
ぼろぼろの『伯爵』は、それでも、ひょうひょうとした態度を崩さない。
「いや、さすがに少しばかり、のどが渇いた……カフェか、給水所はどこだろうか。ドクと合流すれば、案内してもらえるかね?」
カイゼル髭の伊達男は、少しばかり冗談めかしつつ、導子通信機に向かって尋ねる。すぐにドクター・ビッグバンからの応答が返ってくる。
『なんとなればすなわち、そのまえに……もう一仕事、頼みたい……『塔』の解体。可能かナ?』
「やれやれ、相変わらずドクの仕事は無茶ぶりばかりだ。だが、ふむ……やってみよう。我輩にも、ユグドラシルの管理者としての矜持がある……仕事あがりに、よく冷えたエールを期待させてもらうかね」
シルクハットを手で抑えながら、『伯爵』は頭上をあおぐ。『塔』の天頂は、雲と空のうえにかすんで見通すことはかなわない。カイゼル髭の伊達男は、両目を細める。
アストランという名の次元世界<パラダイム>で、似た大規模建造物を見た。どことなく故郷の世界樹とも似たシルエットだが、母なる大樹のような包容力はみじんもなく、万物を侮蔑するような威容で見下ろしている。
「『塔』の解体。朝飯まえというには、少しばかり大事だが……ふむ、ちょうどいいかね。この構造物は、我輩の美的感覚に照らしあわせても……悪趣味に、過ぎるッ!」
カイゼル髭の伊達男は、左手に握りしめた呪符の束から、右人差し指と中指で1枚のカードをつかみ、引き抜く。
「『世界騎士団<ワールド・オーダー>』、『塔<タワー>』……我が故郷の受けた屈辱と破滅を味わうがいい……解き放て、『重力獄<グラヴィトン・ウェル>』ッ!!」
超巨大建造物に挑むように、『伯爵』は呪符を掲げる。『塔<タワー>』のカードには、カイゼル髭の伊達男の故郷である次元世界<パラダイム>、ユグドラシルが経験した厄災を再現する力を持つ。
ずん、と周囲の空気の重さが増す。『伯爵』を中心に広がっていく漆黒の染み──重力フィールドが、グラトニアの中心に鎮座する『塔』の土台を揺さぶりはじめた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
