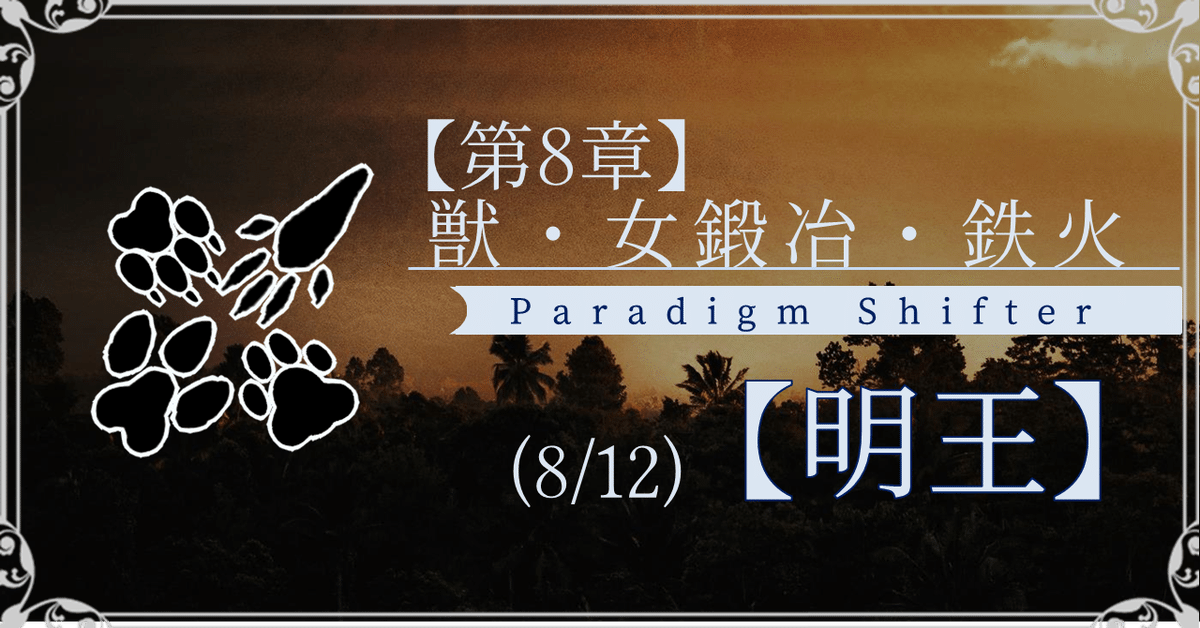
【第8章】獣・女鍛冶・鉄火 (8/12)【明王】
【土塊】←
「チィ……ッ!」
リンカは、手にした刀を振るい、無数の赤焔の筋を飛ばす。炎熱の爪牙が、住居の壁を、柱を斬り裂きながら、土の巨人へと殺到する。
だが、女鍛冶の放った超常の火は、人型の土塊の表面に、黒い焦げ跡をわずかに残すだけだった。
「……まあ、効かないのよな」
リンカは、荒い吐息をこぼしながら、つぶやく。炎で土を焼けないことなど、鍛冶職人である自身が、一番よくわかっている。
獣人の東屋をなぎ払いながら、土の巨人は、リンカへと迫り来る。巨岩のような拳が屋根を叩き壊し、石柱のごとき脚が寝床を踏みつぶす。
「これなら……どうだッ!」
大振りな巨人の攻撃をかいくぐり、女鍛冶は土塊の足下へとすべりこむ。両手で握りしめた刀を肩にかつぎ、眼前の脚部を力任せに斬りつける。
両断……とまではいかないが、業物の刃が、大柱のごとき脚をおよそ半分ほど斬り裂く。巨人であっても、生物ならば、間違いなくひざをついただろう。
しかし、相手は命を持たない土の塊だ。泥に向かって、斬りかかるようなものだ。決死の一撃を気にとめる様子もなく、巨人は獲物をつぶそうと地団駄を踏む。
女鍛冶は、機敏に飛び退き、人型の土塊から距離をとる。
「はあッ、はあー……ッ」
リンカは、何度も荒く息をつく。艶やかな黒髪は、汗に濡れて、てらてらと輝く。対する巨人は、相対したときから、動きが鈍くなる気配すらない。
「まあ、生き物じゃないんだから……疲れたりなんか、するわけないのよな」
女鍛冶は、黒髪を揺らしながら、さらに人型の土塊から間合いを離す。手にした刀で正中の構えをとりながら、呼吸を整える。
「長丁場は、不利。かといって、アタシに他の取り柄もなし」
野牛の獣人の集落を破壊しながら、土の巨人がリンカのもとへと迫り来る。女鍛冶は、目を細めて、化け物の異様を見つめる。
相手から意識をそらさず、己の丹田に集中する。『気』を汲みあげ、収束し、『龍剣』の刀身へと流しこむ。
「たあアァァァ──ッ!!」
女鍛冶が握る刀の切っ先が、半月を描くように地面をかすめる。刹那の間を置いて、刃の軌跡から白熱する焔の壁が燃え上がる。
まばゆい輝きが、リンカと巨人のあいだの視界をふさぐ。土を焼いて、消し炭にすることはできない。だが、土器や陶器は、土を焼き締めて作られる。
「……どうだッ!?」
己が産み出せる、もっとも高温の炎を前にして、女鍛冶は叫ぶ。『気』を振り絞ったため、虚脱感とともにめまいを覚える。
リンカは、いまにも砕けそうなひざを叱咤して、白く輝く焔の壁を見つめ続ける。
突然、白熱の障壁が揺らぐ。黒く変色した腕型の土塊が、炎のなかを無理矢理に突き抜けて、女鍛冶に向かって伸びる。
「んぐ……ッ!!」
もはや、回避する余力は残っていない。リンカの身体が、土の手に捕まれ、宙に吊りあげる。巨人の胴体が、炎の壁を突っ切って、姿を現す。
「だめ……か……ッ」
女鍛冶は、悔しげにうめく。単純に、リンカの炎の熱量が、化け物の動きを妨げるに至らなかった。ただ、それだけだ。
それでも、握りしめた刀は手放さない。せめてもの抵抗だ。稚拙な泥人形のような目鼻もない巨人の頭部が、眼前に見える。
「すまない……のよな……」
リンカの双眸から、涙が流れ落ちる。女鍛冶の胸中を満たしたのは、己自信のふがいなさと、友を助けられなかった無念だった。
「げほッ、がぼ……ッ!」
化け物の加減を知らない握力に、女鍛冶は苦しげにせきこむ。『気』を絞り尽くしたリンカの視界は、そのまま、暗転していく。
───────────────
(──走馬燈、ってやつか?)
女鍛冶は、漠然と思う。絶命する刹那、人は、一生の記憶を想起するという。にしては、妙だ。リンカがいま立っているのは、見た記憶のない空間だ。
窓のない屋内だった。故郷の建築様式だ。鍛冶の作業場か、禅寺の仏堂か、あるいはそれらを足しあわせたような、巨大な広間に見える。
──ガァンッ、ガァンッ。
女鍛冶の眼前から、鉄を鍛えあげるけたたましい打擲音が反響する。リンカには、不思議と、不快には感じない。
ゆっくりと顔をあげ女鍛冶は、山のように巨大な何者かが、自分に背を向けているのを見る。先ほどまで相対していた化け物と、同じほどの身の丈はあるか。
この巨人のごとき何者かが、鉄を鍛えあげているのだろう。光の案配から、巨体の向こう側に煌々と輝く鍛冶炉の存在が見て取れる。
(アンタは、誰なのよな──)
リンカは、見上げる背に向かって誰何しようとする。大いなる存在の手が、止まる。女鍛冶の意図を察したかのように、ゆっくりとこちらを振り返る。
巨人が、息を呑むリンカを見下ろす。右手には、燃えさかる鎚を握りしめている。よく見れば、山のような体躯もまた、炎のように燃えている。
背後の炉の輝きが、後光を背負っているように見える。大いなる存在は、顔に憤怒の形相を浮かべている。リンカは、不思議と畏れを覚えない。
「──……」
女鍛冶の見上げる巨人が、口元を動かす。怒気がこもった相貌にもかかわらず、その唇の動きは、優しく、教え諭すようだった。
───────────────
「──ごぶッ」
土塊の巨腕に握りしめられたリンカの意識が、嗚咽をこぼしつつ、現実に戻る。全身の痛みも、息苦しさも、どこか遠くに感じられる。
視界がかすみ、焦点があわない。手足の感覚もない。リンカは、指先に意識を集中する。刀は、ある。まるで自分の身の一部であるように、手のひらに吸いついている。
震える腕に力をこめて、柄を握る右腕を引きあげる。刀身から、赤白の火花が飛び散っている。
リンカは、前方──土塊の化け物に向かって、自身の刀を掲げる。
「我は炉、刀は焔、そして、鎚持ち打ち鍛えるは──」
女鍛冶ののどから、朗々と言葉が読みあげられる。自分でしゃべっている感覚は、ない。己の深いところから、自然に文言が滑り出てくるような感覚だ。
「──龍剣解放、『炉座明王<ろざみょうおう>』」
その名をリンカが口にすると、刀を中心にして時計回りに炎の渦が、人型の土塊すらも呑みこむように、巻きあがる。
やがて、まばゆい焔は、燃える鎚を携えた魔神の姿を形作り、巨大な化け物の背後に現れる。目鼻もない土塊の顔が、一瞬、狼狽したかのように見える。
──グォォォオオッ!
咆哮するような音を立てて、燃ゆる鎚が、人型の化け物に向かって振り下ろされる。凝縮された熱量を持つ打擲が、不浄な土塊を叩き潰す。
『炉座明王<ろざみょうおう>』の炎熱が、土砂のなかに潜りこんだ『屍兵化弾<ホロウ・ポイント>』を、一瞬で融解させる。
いびつな人型をとり続けていた土塊は、己の形を保ち続けることができずに、崩れ落ちていく。リンカの身は解放され、その場に投げ出された。
→【屍化】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
