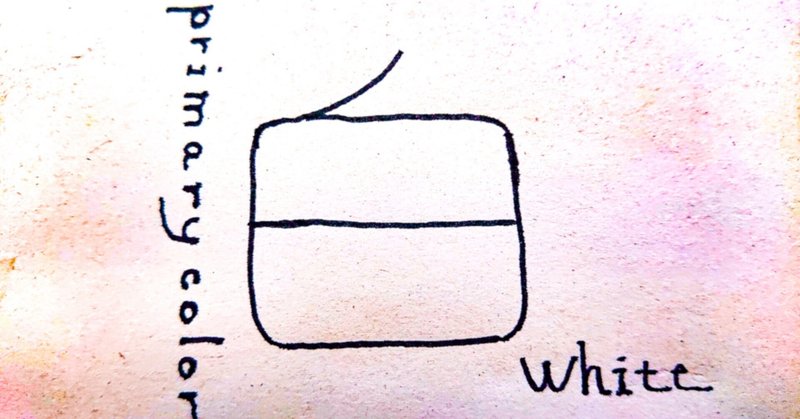
プライマリー・カラー 〈Wの章〉
彼は都内の飲食店でバイトをしているらしい。確かにと透香が思ったのは、体を撫でる指先がひどくかさついていたからだ。透香の両腕を押さえつけ、貪るように、あるいは今夜の居所を探るように、彼は柔肌に顔を埋める。30過ぎの熟れかけの身体でも需要がある。それは単純に嬉しかった。頬のニキビ跡が気になったものの、そこそこ顔立ちも整っていた。だがエサになったような気分がずっとあり、透香は行為に集中できずにいた。
対する彼は透香の身体に溺れていた。会話の中で同年代にはない落ち着きと色気を感じ、彼は犬のように鼻先に神経を集中させた。すると肌の奥には、シロツメクサの蜜のような、素朴だが惹きつける薫りがあった。
花畑の中で彼は夢中で駆け回る。
卒業論文と、壮年層だらけの焼き肉屋バイトを行き来する毎日。とうに性欲も涸れたと思っていたが、気付けば彼は花弁をそこら中にまき散らしながら戯れ、貪っていた。
そうやって果てたあと、彼の眼下には透香がいた。そこで彼は言いかけて、躊躇った。今ではないと思ったからだ。
ホテルを出ると朝陽がふたりの瞼を痺れさせた。同じように太陽を見上げていることに気づくと彼はつい、告白してしまった。
「ありがとう」
それだけ言って透香は歩き始め、二人はあっという間に駅に着く。改札を抜けて振り返った彼を見つめながら透香はもう一度、胸の前で手を振った。
わたしは誰かに色を付けて欲しかった。その色に染まれば、少なくとも透明じゃないから。誰の目にも焼き付くこともなく、最初から存在しなかったように消えるのがただ怖かった。
だから、相手に合わせ、受け入れてきた。わたしは、自ら色を発することをずっと怠ってきたんだ。
それに気付いた瞬間、透香は自分がひどく滑稽に見え、笑ってしまった。
改札の前で独りで笑っている女を通行人は異物のように見ている。それでいいと透香は思う。
帰り道、ワルツが踊れそうなほど、足取りは軽く、透香は純白を身に纏うその日に向かって、歩き出した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
