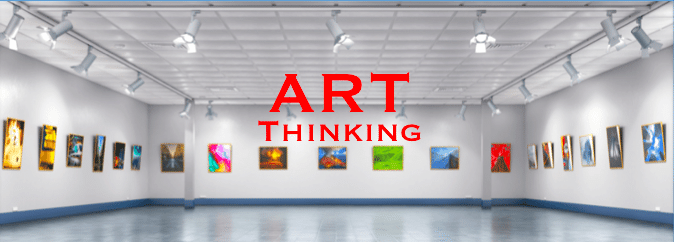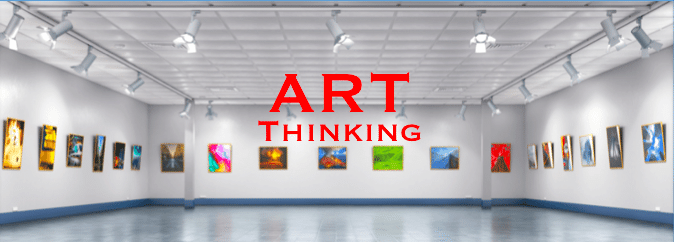【クリエイティブ解体新書】
SUPER DOMMUNE 2022/03/29 DOMMUNE SPECIAL PROGRAM「クリエイティブ解体新書」〜脳から生まれる創造性の原風景
perfumeや坂本龍一さんとのコラボやリオ五輪2016大会閉会式での東京五輪2020へのフラッグハンドオーバーセレモニーのAR映像などでもお馴染みの真鍋大度さん。脳の創造性を音楽の視点から探究する東京大学の医学博士 大黒達也さん、音の対話型鑑賞開発者モジュラーシンセの女神galcidこと斎藤レナさんと私で「クリエイティブ