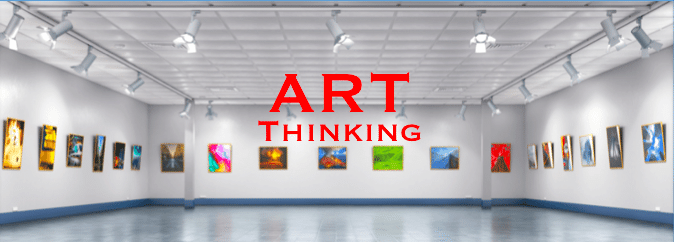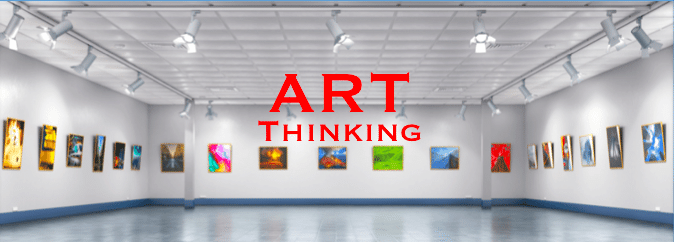「invisible cinema まだ見ぬ君へ」
メディア芸術の総合フェスティバル「第24回文化庁メディア芸術祭 受賞作品展」spiralで開催された「invisible cinema まだ見ぬ君へ」を体験して来ました。(すでに公演は終わっています)
サウンドアーティストevala氏による音だけの“耳で視る映画”です。
暗闇という非日常はジェームズ・タレルの「南寺」でも経験しましたが、暗黒の70分間というのはかなり長いです。暗闇の中から雨や波の自然音に混じって電子音がサラウンドで聞こえてきます。最初は暗闇の中で音を意識を集